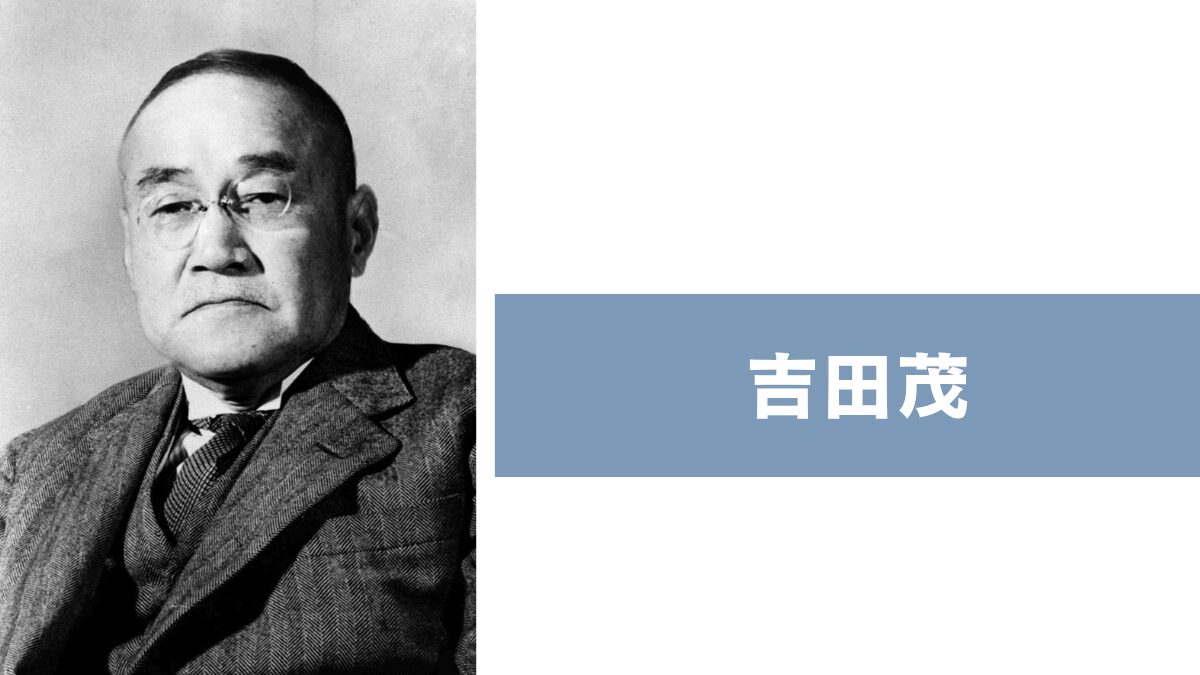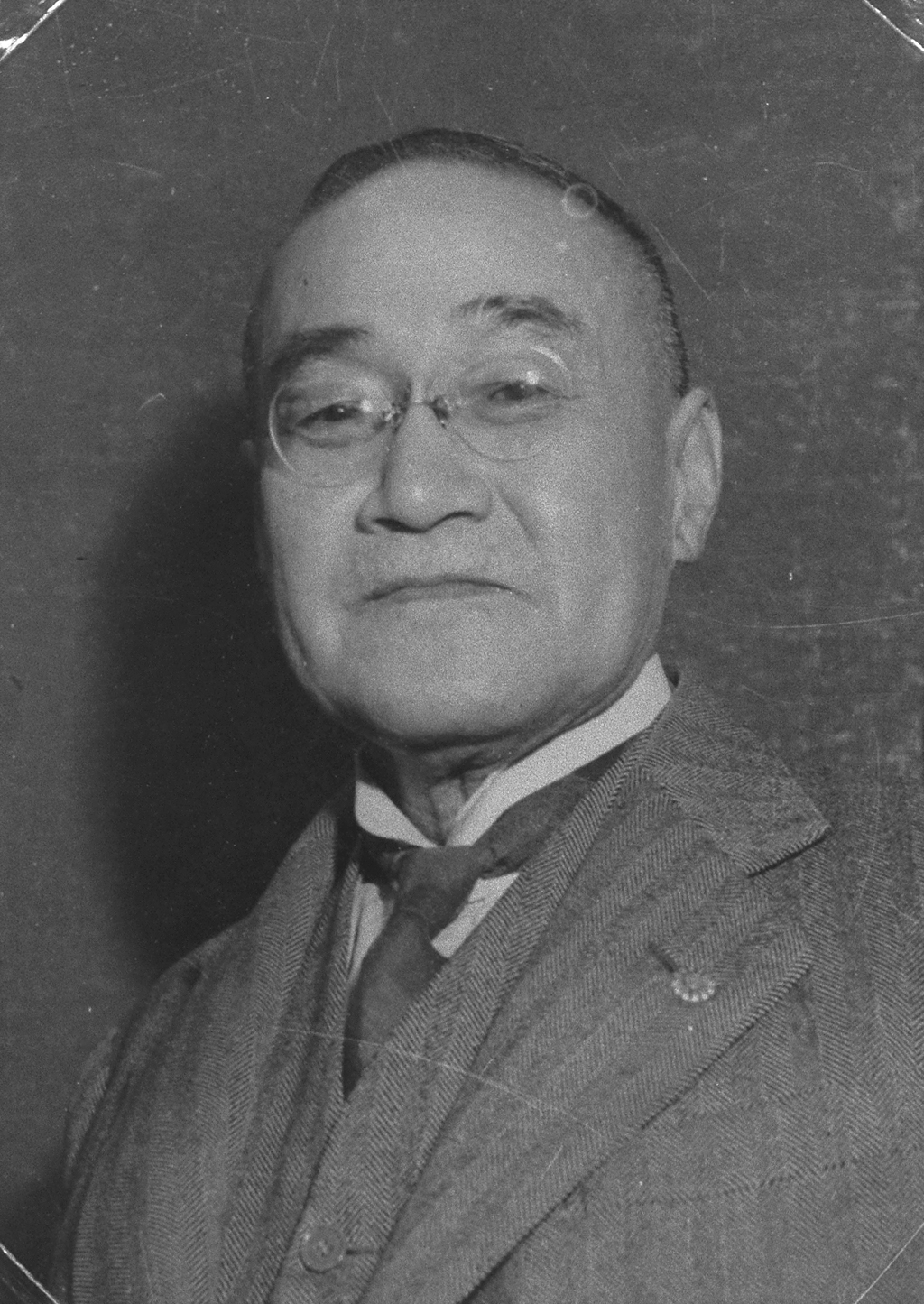戦後の日本を復興に導いた総理大臣、吉田茂。
葉巻をくわえた姿は有名ですが、彼が具体的に「何をやった人」なのか、はっきりと説明できる人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、吉田茂が外交官からいかにして総理大臣に上り詰めたのか、そして日本の独立回復という最大の功績から、日本国憲法の制定、日米安保条約の締結、さらには有名な「バカヤロー解散」に至るまで、彼の「やったこと」を時系列に沿ってわかりやすく徹底解説します。
この記事を読むと、以下の点について理解できます。
- 吉田茂が外交官から首相になるまでの経緯
- 日本の独立回復と日米安保条約の締結
- 経済復興(吉田ドクトリン)と自衛隊の礎
- 「ワンマン宰相」と呼ばれた個性的な人物像
吉田茂がやったこと:戦後日本の基礎

- 首相になる前の経歴:外交官時代
- 反軍部的な和平工作と戦後の台頭
- 日本国憲法の制定と施行
- サンフランシスコ平和条約での独立回復
- 日米安全保障条約の締結
首相になる前の経歴:外交官時代
吉田茂は、内閣総理大臣として戦後日本を率いる以前、外交官として豊富な経験を積んだ人物です。
彼は1878年(明治11年)に土佐(現在の高知県)出身の自由民権運動家・竹内綱の五男として東京で生まれましたが、生後まもなく横浜の貿易商・吉田健三の養子となりました。
養父・健三が早くに亡くなったため、吉田は11歳という若さで莫大な遺産を相続することになります。
彼の学生時代は、必ずしも順風満帆ではありませんでした。
神奈川県の耕余義塾を卒業した後、日本中学、高等商業学校(現在の一橋大学)、正則尋常中学校、慶應義塾、東京物理学校(現在の東京理科大学)など、多くの学校を渡り歩いています。
高等商業学校を「商売人は性が合わない」という理由でわずか2カ月で退校するなど、自分の進むべき道を見つけるまでに時間がかかった様子がうかがえます。
最終的に学習院に入学したことで、ようやく外交官になるという目標が定まりました。
学習院大学科が閉鎖されたことに伴い、東京帝国大学法科大学に移り、1906年(明治39年)に卒業します。
同年、外交官および領事官試験に合格し、外務省に入省しました。
同期には、後に同じく総理大臣となる広田弘毅がいます。
当時の外交官の出世コースは欧米勤務とされていましたが、吉田はキャリアの多くを中国大陸で過ごしました。
天津や奉天(現在の瀋陽)などで勤務し、奉天総領事時代には東方会議に参加しています。
この頃の吉田は、満州における日本の合法的な権益を守るためには実力行使も辞さないという強硬な意見を持つこともあり、時として軍部よりも強気な姿勢を見せたと言われています。
1928年(昭和3年)には田中義一内閣で外務次官に就任しました。
その後、駐イタリア大使を経て、1936年(昭和11年)には駐イギリス大使という要職に就きます。
彼は一貫してイギリスやアメリカとの協調関係を重視する「親英米派」と見なされていました。
そのため、急速に台頭するドイツとの接近や、日独伊三国同盟の締結には強く反対する立場を取ります。
しかし、日英親善を目指した彼の努力もむなしく、極東情勢の悪化を防ぐことはできませんでした。
1939年(昭和14年)、外交の第一線から退くことになります。
反軍部的な和平工作と戦後の台頭
吉田茂が戦後日本のリーダーとして急速に台頭した背景には、彼が戦時中に見せた「反軍部」的な姿勢と、それに伴う出来事が大きく関係しています。
彼は太平洋戦争の開戦前から、軍部の独走とドイツ・イタリアとの同盟に批判的でした。
外交の第一線を退いた後も、その姿勢は変わりませんでした。
戦時中、吉田は岳父である牧野伸顕(まきののぶあき)や、元首相の近衛文麿(このえふみまろ)ら重臣グループと連絡を取り合い、水面下で戦争を終わらせるための和平工作に従事していました。
これは「ヨハンセングループ」とも呼ばれる動きです。
特に1942年(昭和17年)のミッドウェー海戦での大敗北を知ると、これを和平交渉開始の好機と捉え、近衛と共にスイスへ赴いて交渉に導く計画を立てたこともあったとされています。
しかし、この計画は実現しませんでした。
吉田の運命を決定づけたのは、終戦直前の1945年(昭和20年)2月の出来事です。
日本の敗色が日に日に濃くなる中、彼は近衛文麿が昭和天皇に戦争終結を促す上奏(近衛上奏文)を行うための準備に協力しました。
しかし、吉田邸に書生として潜入していたスパイ(東輝次)によって、この和平工作の動きが憲兵隊に露見してしまいます。
結果、吉田は反政府陰謀の疑いで憲兵隊に逮捕され、拘束されることになりました。
この投獄は40日あまり続きましたが、不思議なことに、彼は他の拘束者とは異なり、独房で差し入れも自由という比較的良い待遇を受けていたとされます。
これは、当時の陸軍大臣であった阿南惟幾(あなみこれちか)など、軍部の中にも吉田と親交のある人物がいたための配慮ではないかと言われています。
最終的に吉田は不起訴となり釈放されました。
この戦時中の「投獄」という経歴が、戦後は一転して吉田にとって非常に有利に働くことになります。
終戦後、日本を占領下に置いたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、軍国主義に協力した人物を厳しく排除(公職追放)しようとしました。
そのような状況下で、軍部に逮捕された経歴を持つ吉田茂は、GHQから「反軍部的」であり「平和主義者」であると見なされました。
これがGHQの信頼を得る大きな要因となり、彼は終戦直後の東久邇宮内閣、続く幣原内閣で外務大臣として起用されます。
そして、この信頼を足掛かりに、やがて内閣総理大臣として戦後日本の舵取りを任される道が開かれていったのです。
日本国憲法の制定と施行
吉田茂は、戦後日本のあり方を根本から変えた「日本国憲法」の制定と施行のプロセスに、中心的な立場で深く関わりました。
彼の役割は、時期によって二つに分けられます。
一つは憲法改正草案が作成された時期の「外務大臣」としての立場、もう一つは憲法が国会で審議され、公布・施行された時期の「内閣総理大臣」としての立場です。
終戦後、GHQの最高司令官マッカーサーは、幣原喜重郎首相に対し、大日本帝国憲法の改正を示唆しました。
これを受けて、幣原内閣は松本烝治(まつもとじょうじ)国務大臣を主任とする憲法問題調査委員会(松本委員会)を設置します。
しかし、松本委員会が作成した改正案(松本試案)は、天皇が統治権を持つという従来の原則を維持するなど、保守的な内容でした。
GHQはこの案を拒否します。
1946年(昭和21年)2月、マッカーサーは自ら指示した「マッカーサー・ノート」に基づき、GHQ民政局が作成した草案(GHQ草案)を日本政府に提示しました。
この草案には、天皇の象徴化、戦争の放棄、封建制度の廃止といった、それまでの日本とは全く異なる原則が盛り込まれていました。
当時、外務大臣としてこの歴史的な会談に同席していた吉田茂は、その急進的な内容に驚愕した一人です。
日本政府は最終的に、天皇制を守るためにはこのGHQ草案を受け入れるしかないと判断し、これを基に憲法改正案を作成することになりました。
その直後の1946年5月、事態が動きます。
総選挙で第一党となった日本自由党の総裁・鳩山一郎が、GHQの指令によって公職追放となってしまったのです。
後任の総裁として白羽の矢が立ったのが、貴族院議員であった吉田茂でした。
彼はこれを受諾し、内閣総理大臣に就任します(第1次吉田内閣)。
吉田は、大日本帝国憲法下で天皇から組閣の大命を受けた、最後の総理大臣となりました。
憲法改正案の審議は、この第1次吉田内閣の下で帝国議会(衆議院および貴族院)にて行われました。
この審議の過程で、吉田首相は憲法第9条(戦争放棄)について、歴史に残る答弁を行っています。
1946年6月の衆議院本会議で、彼は「自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄した」と述べ、国家の正当防衛権としての戦争さえも否定するという見解を示しました。
この答弁は、当時の日本が徹底した平和国家として生まれ変わることを国際社会に強くアピールするための、政治的な判断であったと解釈されています。
議会での修正(芦田修正など)を経て可決された日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
吉田は、戦後日本の法的な枠組みが根本から作り変えられるという歴史的な転換点において、最高責任者としてその中心にいたのです。
サンフランシスコ平和条約での独立回復
吉田茂が内閣総理大臣として成し遂げた最大の功績として広く認められているのが、サンフランシスコ平和条約の締結です。
この条約は、1951年(昭和26年)9月8日に調印されました。
これにより、1945年(昭和20年)の敗戦から約7年間にわたって続いたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による占領状態が終わり、日本はついに主権を回復し、独立国家として国際社会に復帰することになりました。
この独立回復への道のりは、決して平坦なものではありませんでした。
1950年(昭和25年)に朝鮮戦争が勃発すると、アメリカは日本を共産主義陣営に対する「防波堤」として重視するようになり、講和への動きが加速します。
しかし、講和条約の結び方をめぐって、日本国内の世論は真っ二つに割れました。
一つは、ソ連や中国共産党政府など、戦争状態にあった全ての国々と同時に条約を結ぶべきだとする「全面講和論」です。
これは主に革新勢力や多くの知識人たちが主張しました。
もう一つは、まずはアメリカを中心とする西側諸国(自由主義陣営)とだけでも先に条約を結び、早期の独立を優先すべきだとする「単独講和論」です。
吉田茂首相は、現実的な政治判断として、この「単独講和」の道を選択しました。
東西冷戦が激化する国際情勢の中で、日本が西側陣営の一員として経済復興を目指すためには、早期の独立が不可欠だと考えたからです。
この決断は、国内の反対派から「アメリカへの従属を招く」「再び戦争に巻き込まれる」と激しい批判を浴びるものであり、吉田にとってはまさに政治生命を賭けたものでした。
1951年、吉田は首席全権としてサンフランシスコ講和会議に出席します。
会議では、あえて伝統的な巻物に書かれた演説原稿を読み上げるというパフォーマンスを見せ、日本の主権回復を印象付けようとしました。
(この巻物原稿について、当時の現地メディアからは「巨大なトイレットペーパー状のものを読み上げた」と揶揄されたという逸話も残っています。)
条約には、日本を含む49カ国が署名しました。
ソ連などは署名を拒否しましたが、吉田の目的であった西側諸国との講和は達成されました。
日本国内では講和条約への賛否が渦巻いていましたが、いざ独立回復が現実のものとなると、国民の多くは占領の終わりを歓迎しました。
帰国後の吉田内閣の支持率は、戦後最高となる58%(朝日新聞調査)に達したと言われています。
この瞬間が、吉田茂の政治家としての頂点であったとされています。
日米安全保障条約の締結
吉田茂は、サンフランシスコ平和条約に署名したのと全く同じ日、1951年(昭和26年)9月8日に、もう一つの重要な条約を結びました。
それが、旧「日米安全保障条約」(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)です。
この二つの条約は、戦後日本の進路を決定づける「セット」として扱われました。
平和条約によって日本は独立を回復しましたが、同時に日米安全保障条約によって、独立後もアメリカ軍が引き続き日本国内の基地に駐留し続けることが法的に認められました。
これが、現在まで続く日米同盟関係の出発点となります。
吉田がこの条約を結んだ理由は、当時の日本の安全保障環境にありました。
独立を果たしても、日本国憲法第9条の下、日本には自国を本格的に守るための軍備がありませんでした。
一方で、すぐ近くの朝鮮半島では戦争が続いており、アジア全体で共産主義勢力の脅威が高まっていると認識されていました。
吉田は、日本の安全と経済復興のためには、アメリカの軍事力に防衛を依存することが、最も現実的で合理的な選択であると考えました。
この条約の締結に際しては、吉田の強い決意と覚悟を示す有名な逸話が残されています。
平和条約の調印式には、池田勇人蔵相(後の首相)ら他の全権委員も吉田と共に署名しました。
しかし、その直後に行われた日米安全保障条約の調印式には、吉田は池田らに対し「君はついてくるな」と命じ、随行員を室外に出して、ほぼ一人で署名に臨んだとされています。
これは、国内で必ずや激しい批判を浴びるであろう安全保障条約の締結に関する全責任を、自分一身で背負い、他の政治家たちを批判の矢面から守るためだったと言われています。
実際、この旧安保条約は、多くの問題を抱えていました。
例えば、アメリカが日本を防衛する義務は明確に書かれていない一方で、日本はアメリカに基地を提供する義務を負うという「片務的(一方的)」な性格が強いものでした。
また、独立後も外国の軍隊が国内に留まり続けることに対し、野党や革新勢力からは「真の独立ではない」「アメリカの植民地化だ」といった厳しい批判が巻き起こりました。
しかし、吉田はあえてこの体制を受け入れました。
防衛をアメリカに任せることで、日本の軍事的な負担を最小限に抑え、国の限りある資源を経済の復興に集中させる道を選んだのです。
この決断が、その後の日本のあり方を大きく方向付けました。
吉田茂がやったことの評価と影響

- 経済復興優先の「吉田ドクトリン」
- 自衛隊の礎:警察予備隊の発足
- 造船疑獄と「バカヤロー解散」
- 「吉田学校」が後世に与えた影響
- ワンマン宰相と呼ばれた人物像
経済復興優先の「吉田ドクトリン」
吉田茂が首相在任中に敷いた戦後日本の基本路線は、彼の名を冠して「吉田ドクトリン」と呼ばれるようになりました。
これは、吉田自身が公式に提唱したものではありませんが、彼の一連の政策が示す国家戦略を後世の研究者らが名付けたものです。
その中核となる考え方は、「軽武装・経済重視」という言葉に集約されます。
具体的には、日本の安全保障(防衛)は日米安全保障条約に基づきアメリカに依存し、軍事的な負担(防衛費)は最小限に抑えます。
そして、それによって生み出された国力(予算や人材)を、全て経済の復興と発展に最優先で振り分けるという戦略でした。
吉田は、敗戦によって徹底的に破壊され、疲弊した日本を「痩せ馬」に例えました。
彼は「このひょろひょろの痩せ馬に、独立したからといって過度の重荷(=本格的な再軍備)を負わせると、馬自体が参ってしまう」と述べ、国防よりもまず国民の生活再建と経済の立て直しを優先すべきだと強く主張しました。
この考えは、彼が首相に就任した第1次吉田内閣の時から一貫しています。
例えば、大蔵大臣に起用された石橋湛山(いしばしたんざん)が推進した「傾斜生産方式」は、石炭や鉄鋼といった国の基幹産業に、利用可能な資源を集中投下する政策でした。
また、復興金融金庫を設立し、産業界に資金を供給するなど、経済復興を最優先課題として取り組みました。
サンフランシスコ平和条約と日米安保条約の締結も、この吉田ドクトリンの文脈で理解することができます。
アメリカからの強い再軍備要求に対し、吉田は憲法第9条などを盾にしながら抵抗を続けました。
そして、アメリカの軍事力に安全保障を委ねる(安保条約)という選択をすることで、日本の軍事費負担を低く抑えることにある程度成功したのです。
この吉田ドクトリンは、その後の日本に大きな影響を与えました。
この戦略があったからこそ、日本は戦後の荒廃から短期間で奇跡的な経済復興を遂げ、やがて世界有数の経済大国となる「高度経済成長」の礎を築くことができたと高く評価されています。
その一方で、この路線はいくつかの課題も残しました。
安全保障をアメリカに依存する体制が固定化されたことで、日本が自国の防衛について主体的に考える機会が失われたのではないか、という批判です。
また、経済的な利益を最優先する姿勢が、国際社会での政治的な役割や貢献を軽視する傾向を生んだという指摘もあります。
メリットとデメリットの両方を抱えながらも、この吉田ドクトリンが戦後日本の進路を決定づけたことは間違いありません。
自衛隊の礎:警察予備隊の発足
現在の日本の自衛隊は、吉田茂内閣の時代に創設された「警察予備隊」をその直接的な起源としています。
これは、憲法第9条で「戦力」の不保持を定めた日本が、再び武装組織を持つに至った、極めて重大な転換点でした。
この大きな政策転換の引き金となったのは、1950年(昭和25年)6月に勃発した「朝鮮戦争」です。
朝鮮半島で共産主義勢力(北朝鮮)と資本主義勢力(韓国・アメリカ軍中心の国連軍)との間で激しい戦争が始まると、日本の状況は一変しました。
まず、日本を占領していたアメリカ軍の主力部隊が朝鮮半島へ出動したため、日本の国内治安を維持する力が手薄になりました。
同時に、共産主義の脅威が現実のものとなったことで、アメリカ(GHQ)はそれまでの日本の「非軍事化」政策を180度転換させます。
そして、日本を共産主義に対する「アジアの防波堤」と位置づけ、日本自身にある程度の武装(=再軍備)を強く求めるようになりました。
吉田首相は、アメリカからの本格的な「軍隊」の再建要求に対しては、憲法第9条や経済復興の優先を理由に、強い抵抗を続けました。
しかし、国内の治安維持の必要性と、占領下にある日本がアメリカの要求を無下にできないという現実との板挟みになります。
その結果、吉田が下した苦肉の策が、「軍隊ではない、国内の治安維持を目的とした実力組織」を創設するというものでした。
こうして、朝鮮戦争勃発のわずか2カ月後、1950年8月に「警察予備隊」が発足しました。
警察予備隊は、あくまでも日本の警察力を補う組織である、という名目で創設されました。
しかし、その実態は、アメリカ軍から小銃や機関銃などの武器を供与され、軍事的な訓練を受ける部隊であり、従来の警察とは全く異なるものでした。
この組織は、独立回復後の1952年(昭和27年)になると、国内の治安維持だけでなく「間接侵略(国内の騒乱など)」にも対処する組織として「保安隊」へと改組されます(同時に海上警備隊は「警備隊」となりました)。
そして、吉田内閣の末期である1954年(昭和29年)7月、防衛庁設置法と自衛隊法が施行されます。
これにより、保安隊は「陸上自衛隊」に、警備隊は「海上自衛隊」に改編され、新たに「航空自衛隊」が発足しました。
この時初めて、組織の任務として「直接侵略(外国からの武力攻撃)」に対する防衛が明記され、現在の自衛隊の形が整いました。
このように、憲法改正という正面からの議論を避け、「警察力」から「保安力」、そして「自衛力」へと、実態を後追いで法整備していく形で組織を強化していった手法は、後に「なし崩しの再軍備」と呼ばれることになります。
この手法は、憲法第9条と自衛隊の存在をめぐる法的な問題を、現代に至るまで残す原因となりました。
造船疑獄と「バカヤロー解散」
6年以上にわたり5次にわたって内閣を組織し、長期政権を維持した吉田茂ですが、その権勢は永遠には続きませんでした。
彼の長期政権の末期は、「バカヤロー解散」と「造船疑獄」という二つの有名な事件によって大きく揺らぎ、最終的に退陣へと追い込まれます。
これらは、吉田の「ワンマン」とも呼ばれた強引な政治手法や、彼の短気な性格が国民や政界からの強い反発を招いた象徴的な出来事でした。
バカヤロー解散(1953年)
1953年(昭和28年)2月、衆議院の予算委員会で事件は起こりました。
野党・右派社会党の西村栄一議員との質疑応答中、吉田首相は西村議員の質問の仕方に対し、いら立ちを隠せませんでした。
答弁席に戻る際、吉田は非常に小さな声で「バカヤロー」と呟いたのです。
しかし、この発言は運悪くマイクに拾われており、国会審議の場で総理大臣が暴言を吐いたとして、議場は騒然となりました。
野党はもちろん、与党内からも吉田の姿勢を問題視する声が上がります。
この失言をきっかけに、吉田首相に対する懲罰動議が国会で可決されるという異例の事態に発展しました。
さらに、野党側は勢いづき、内閣不信任案を提出します。
吉田と対立していた与党・自由党内の反主流派(鳩山一郎らのグループ)もこの不信任案に同調したため、不信任案は可決されてしまいました。
これに対し、吉田は即座に衆議院を解散して対抗します。
この一連の経緯から、この解散は「バカヤロー解散」という不名誉な名前で呼ばれることになりました。
解散後の総選挙で自由党は議席を減らし、過半数を割り込みます。
吉田は少数与党として第5次吉田内閣を発足させますが、政権基盤は著しく弱体化しました。
造船疑獄と指揮権発動(1954年)
吉田政権の終わりを決定づけたのが、1954年(昭和29年)に発覚した大規模な汚職事件「造船疑獄」です。
これは、海運・造船業界が政府の補助金を得るために、政治家や官僚に大規模な賄賂を贈っていたとされる事件でした。
東京地検特捜部による捜査は政界の中枢に及び、ついには吉田の側近中の側近であり、与党・自由党の幹事長であった佐藤栄作(さとうえいさく、後の総理大臣)にまで逮捕の疑惑が及びます。
検察が佐藤幹事長の逮捕を決定し、国会に逮捕許諾請求を行おうとしたその時、吉田首相は法務大臣の犬養健(いぬかいたける)を通じて、検事総長に対し「佐藤の逮捕を延期し、任意捜査に切り替えるように」という指示を出しました。
これは、内閣が検察の具体的な捜査に介入する「指揮権の発動」と呼ばれるものです。
戦後の日本では、この時にしか行われていない極めて重大な政治介入でした。
吉田は党幹部の逮捕を強引に阻止しましたが、この行動は「法治国家の原則を揺るがす捜査への不当な介入だ」として、新聞や世論から猛烈な批判を浴びせられました。
国民の支持は完全に離れ、政権は末期症状を呈します。
野党が内閣不信任案を提出すると、もはや可決は確実な情勢となり、吉田もついに解散を断念しました。
1954年12月、吉田茂内閣は総辞職し、彼の長期政権は幕を閉じました。
「吉田学校」が後世に与えた影響
吉田茂は、内閣総理大臣を退任した後も、日本の政治に極めて大きな影響力を持ち続けました。
その影響力の源泉となったのが、「吉田学校」と呼ばれる弟子たちの存在です。
吉田茂はもともと外交官出身であり、選挙や党内調整でキャリアを積んできた「党人派」と呼ばれる生粋の政治家たちとは異なり、与党・自由党内での基盤は必ずしも強くありませんでした。
そこで吉田は、自らの政策(特に経済復興や日米協調)を確実に実行し、党内での主導権を握るため、優秀な中央官僚や若手の政治家たちを積極的にスカウトし、自らの側近として重用しました。
特に1949年(昭和24年)の総選挙では、吉田の呼びかけに応じた多くの元官僚たちが立候補し、当選しました。
彼らは師である吉田茂を囲む政治集団を形成し、やがてメディアなどから「吉田学校」と呼ばれるようになります。
この「吉田学校」の「生徒」として最も有名なのが、池田勇人(いけだはやと)、佐藤栄作(さとうえいさく)、大平正芳(おおひらまさよし)といった面々です。
また、官僚出身ではありませんが、若くしてその才能を吉田に見出された田中角栄(たなかかくえい)も、吉田学校の優等生の一人と数えられています。
驚くべきことに、このうち池田、佐藤、大平、田中の4名は、全員が吉田の退任後に内閣総理大臣の座に就いています。
吉田学校の出身者たちは、師である吉田が敷いた「軽武装・経済重視」「日米協調」という現実主義的な政治路線を、基本的に継承しました。
彼らは、1955年(昭和30年)に結成された自由民主党(自民党)の中で、「保守本流」と呼ばれる中核的なグループを形成し、1950年代後半から1970年代にかけての日本政治を長期間にわたり主導していくことになります。
例えば、池田勇人内閣は「所得倍増計画」を掲げて高度経済成長を力強く推進し、佐藤栄作内閣は戦後最長の政権を担い(当時)、沖縄返還という大きな仕事を成し遂げました。
このように、吉田茂が自ら育て上げた人材が、戦後日本の政治エリート層の中核を形成し、彼の政治哲学や国家観が、彼の引退後も長きにわたって日本の進路に受け継がれていくことになったのです。
吉田が引退後も「大長老」あるいは「吉田元老」と呼ばれ、政界に隠然たる影響力を保持し続けた背景には、この吉田学校の存在が非常に大きく関わっていました。
ワンマン宰相と呼ばれた人物像
吉田茂は、その極めて強烈な個性と、妥協を許さない政治手法から、「ワンマン宰相」と呼ばれました。
彼は自らの信念に絶対的な自信を持ち、他人の意見に左右されず、時には世論や野党の反対を押し切ってでも物事を決定することが多かったため、多くの支持を得ると同時に、数多くの敵も作った人物です。
彼の人物像を語る上で欠かせないのが、葉巻をこよなく愛し、ふくよかな体型であったことから、イギリスの宰相ウィンストン・チャーチルになぞらえて「和製チャーチル」と呼ばれたことです。
その性格は「癇癪持ち(かんしゃくもち)の頑固者」として広く知られており、非常に短気であったと伝えられています。
前述の「バカヤロー解散」の原因となった国会での暴言は、彼のそうした短気な性格を象徴する出来事と言えるでしょう。
また、カメラマンにしつこく写真を撮られたことに激怒し、相手にコップの水を浴びせたという有名な逸話もあります。
これは、彼がまだ愛人関係にあった小りん(後の妻・喜代)とのプライベートな姿を、過去に新聞記者に無断で撮影されたという苦い経験があり、カメラマンに対して強い不信感を持っていたためとも言われています。
駐英大使の経験が長かった吉田は、英国流の生活様式を好み、その立ち居振る舞いは「貴族趣味」と評されることもありました。
愛車がロールス・ロイスであったことも、そうしたイメージを強めました。
彼は外交官出身であることに強い誇りを持っており、選挙区の陳情や党内の調整に奔走する「党人政治家」や、イデオロギーを振りかざす共産党員などを見下す傾向があったとされます。
気に入らない相手には痛烈な皮肉を言ったり、会いたくない客に対しては平気で居留守を使ったりすることもあったようです。
ある財界人から長寿の秘訣を尋ねられた際に、「それは君、人を食っているのさ」と答えて笑ったというジョークは、彼の「人を食った」ような洒脱さと辛辣さを同時に表しています。
しかし、こうした傲岸不遜(ごうがんふそん)とも取れる態度の裏には、複雑な側面もありました。
吉田の側近であった白洲次郎は、吉田を「あのくらい純情で、あのくらい涙もろい人はザラにはいない」とも評しています。
また、昭和天皇に対する尊崇の念は人一倍強く、戦後に天皇退位論が出た際には断固として反対しました。
天皇の前では自ら「臣(しん)茂」と名乗り、時代錯誤だと批判された際には「臣は総理大臣の臣だ」と切り返したという逸話は、彼の保守本流としての信念の強さを示しています。
このように、吉田茂は強烈な個性とワンマン体制で、戦後の混乱期にあった日本を強引に牽引した、毀誉褒貶(きよほうへん)の激しいリーダーでした。
吉田茂がやったことの総まとめ
吉田茂は、その強烈な個性とリーダーシップで「ワンマン宰相」と呼ばれながらも、戦後の混乱期にあった日本の進路を決定づけた人物です。 彼が成し遂げた主な功績や、彼に関連する重要な出来事を以下にまとめました。
- 総理大臣になる前は、駐英大使などを歴任した外交官でした。
- 一貫してアメリカやイギリスとの協調を重視する「親英米派」の立場を取りました。
- 太平洋戦争中は軍部の独走に反対し、水面下で和平工作に従事します。
- 和平工作が原因で憲兵隊に逮捕・投獄された経験を持ちます。
- 戦時中の投獄が逆にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の信頼を得る要因となりました。
- 終戦直後に外務大臣として政界に復帰し、その後、内閣総理大臣に就任しました。
- 総理大臣として、日本国憲法の制定と施行という歴史的なプロセスを主導しています。
- 国内の世論が二分する中、「単独講和」という現実的な道を選択しました。
- 1951年にサンフランシスコ平和条約を締結し、日本の主権回復(独立)を果たします。
- 同日、日米安全保障条約にも署名し、その後の日米同盟関係の基礎を築きました。
- 防衛をアメリカに依存し、軍事費を抑えて経済復興を最優先する「吉田ドクトリン」と呼ばれる路線を敷いています。
- 朝鮮戦争の勃発を受け、現在の自衛隊の源流となる「警察予備隊」を創設しました。
- 政権末期には、国会での「バカヤロー」発言が引き金となった「バカヤロー解散」を経験します。
- 汚職事件「造船疑獄」では、側近の逮捕を阻止するために「指揮権発動」を行い、世論から強い批判を浴びました。
- 池田勇人や佐藤栄作など、後の総理大臣となる優秀な官僚たちを育て、「吉田学校」を形成しました。
これらの出来事は、時に大きな批判や対立を生みながらも、現代の日本の政治、経済、そして外交の枠組みに深く影響を与え続けています。
参考サイト