言葉がうまく話せなかった?うなぎ好き?
徳川家重と聞いて、そんなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
「徳川家重がしたこと」を調べている方の多くは、将軍としての実績が分かりにくい、何をした人物なのか明確に知りたい、と感じているかもしれません。
また、「無能」とも言われがちな評価の背景に、実際どんな障害や病気があったのか、そしてその影響でどんな政治体制が築かれていたのかにも関心があるはずです。
この記事では、家重の将軍就任の経緯から、田沼意次・大岡忠光といった側近たちの役割、家族構成(側室や子供)に至るまで、人物像と政権の特徴をやさしく丁寧に解説していきます。
「うなぎ好き」など人間味あふれる逸話にも触れながら、家重という将軍がどのような時代を生き、どのように評価されているのかを総合的にお伝えします。
歴史に詳しくない方でも読みやすく、かつしっかりと理解できる内容になっています。
読むうちに、徳川家重の「知られざる一面」がきっと見えてくるはずです。
この記事を読むとわかること
- 徳川家重が将軍として何をしたか
- 障害や病気が政務にどう影響したのか
- 田沼意次・大岡忠光らの支えと役割
- 側室や子供など家族との関係
徳川家重がしたことを簡単に解説

- 将軍就任の経緯と家督継承の背景
- 家重政権を支えた田沼意次の役割
- 大岡忠光との関係と政治的サポート
- 家重の障害と判断力への影響
- 家重が患っていた病気と当時の状況
- 家重の死因とその時代背景について
将軍就任の経緯と家督継承の背景
徳川家重が将軍に就任した背景には、家系の流れと当時の政治的事情が大きく関係しています。
家重は、八代将軍・徳川吉宗の長男として生まれました。
吉宗は「享保の改革」で知られる名将軍ですが、その治世後半になると後継者問題が取り沙汰されるようになります。
吉宗には複数の子供がいましたが、嫡男である家重が正統な跡継ぎと見なされていました。
しかし、家重は幼少期から言語障害があり、周囲にはそのことを理由に将軍としての適性を疑問視する声もありました。
一部の譜代大名や幕閣は、弟の宗武(むねたけ)を推す動きも見せていたようです。
それでも吉宗はあくまで長子相続を原則とし、家重の後継を譲りませんでした。
この方針は、家康以来の家系維持と統治安定を重視する幕府の基本方針に合致するものでした。
1745年、吉宗は将軍職を家重に譲り、隠居します。
このとき家重は30歳を超えており、すでに成熟した年齢でしたが、公の場に出ることが少なかったためか、江戸市中では「どんな将軍になるのか」と不安視する声もありました。
吉宗は隠居後も大御所として政治に関与し、家重を支えました。
この「大御所政治」によって、家重の将軍就任はスムーズに見える形を取っています。
また、当時の江戸幕府は一応の安定期にあり、大きな戦乱や騒乱がなかったことも家重の将軍就任を後押ししました。
内政的にはまだ吉宗の政策の余波が残っており、急激な変化を望まない空気がありました。
そのため、形式的には家督の継承は順当であり、制度上の問題もありませんでした。
一方で、実務的な政治は側近や老中たちが担う場面が多く、家重は表立って政治的リーダーシップを見せることはあまりなかったと言われています。
このことが、のちに「影の将軍」や「実権は他人が握っていた」といった見方につながる要因にもなりました。
家重政権を支えた田沼意次の役割
徳川家重の政権下で重要な役割を果たした人物のひとりが、田沼意次(たぬま おきつぐ)です。
田沼は家重の側近として抜擢され、将軍の信任を得ながら政務に深く関わっていきました。
彼はのちに家重の子・徳川家治の時代に老中として大きな力を振るうことになりますが、その礎は家重政権期に築かれました。
田沼意次が注目された理由の一つは、実務能力の高さにあります。
彼は書院番という下級武士の出身でしたが、抜きん出た才能と人心掌握術によって家重の信任を得て出世していきました。
家重の言語障害により、政務においては補佐的立場の人物が求められていたため、田沼のような実務家の台頭が自然と進んだのです。
また、田沼は吉宗が進めた質素倹約路線とは異なり、経済的な発展を重視する姿勢を持っていました。
その姿勢は、家重の治世ではまだ目立たなかったものの、彼の政策の片鱗はこの時期から現れ始めます。
例えば、商人との結びつきを強めたり、年貢以外の収入を模索するなどの取り組みがありました。
一方で、田沼の権力拡大には批判的な見方も少なくありませんでした。
特に、既存の幕府官僚や譜代大名からは、「家重が弱い将軍であることを利用している」と捉えられることもあったようです。
ただし、家重自身が田沼に深い信頼を寄せていたことは記録からも明らかであり、その関係性は政務の安定に大きく貢献していたと言えます。
結果として、家重時代の田沼意次は「将来の実力者」としての地盤を築くと同時に、将軍の代弁者として幕政に関与し続けました。
このような背景から、田沼意次の役割は単なる側近ではなく、「影の実力者」としての性格を強く持っていたのです。
大岡忠光との関係と政治的サポート
徳川家重の政権を支えたもう一人の重要人物が、大岡忠光(おおおか ただみつ)です。
彼はあの「大岡越前守忠相」の子にあたり、父親同様に実直な官僚として知られていました。
家重政権においては、特に政務や財政面でのサポート役として活躍しました。
忠光は勘定奉行から出世し、老中格にまで登用されます。
彼の職務は、家重の意思を正確に汲み取り、実務に反映させることにありました。
家重の言語障害により、直接の意思疎通が難しいこともあり、家重に近い家臣たちの読み取り能力と政治感覚が問われる場面が多かったのです。
忠光はそのような中でも冷静かつ堅実な対応を取り、周囲からの信頼も厚かったとされます。
また、忠光は田沼意次とも協調関係を築き、幕政に安定をもたらす役割を果たしました。
表舞台での派手な功績こそ少ないものの、実務を淡々とこなす中間管理職的な存在として、非常に重要な位置にいました。
このような人物がいることで、家重の将軍としての立場が支えられていたとも言えます。
一方で、忠光が進めた政策の一部には保守的な傾向があり、経済拡大を志向する田沼とは方針の違いも見られました。
ただし、その違いが表立って対立になることは少なく、両者は家重政権下でバランスを取りながら幕政を支えていたのです。
このように、大岡忠光は家重の能力不足を補う補佐役として、実直な支えを続けました。
政治の安定には、こうした地味ながら重要な人材の存在が欠かせなかったことがわかります。
家重の障害と判断力への影響
徳川家重が将軍として評価されるうえで、しばしば議論に上がるのが「障害による影響」です。
家重には、生まれつきとされる言語障害がありました。
具体的には、発語が不明瞭で、何を言っているのか周囲には理解しづらい場面が多かったとされています。
このことが、将軍としての指導力や判断力にどのように影響を与えたのかは、歴史的にも関心が高いテーマです。
まず、結論から言えば、家重自身が政策の中心となって主導的に判断する機会は限られていたようです。
彼の言葉が聞き取れなかったため、近臣たちは彼の発言を推測しながら政務を進めざるを得ない状況にありました。
そのため、家重政権では側近の存在が極めて重要でした。
とくに信任されていた人物の一人である田沼意次が実質的な政務の舵取り役となることで、政権の安定が図られたのです。
一方で、家重の言語障害が知的な判断力にまで及んでいたかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれています。
発話に困難があることと、政策判断の能力は必ずしもイコールではありません。
記録によれば、家重自身が政治に強い関心を持っていたわけではないものの、重要な局面では一定の判断を下していたと考えられています。
また、言葉の問題があることで、外部との接触が極端に制限されていた可能性もあります。
将軍としての公務においては、表向きの儀式などが避けられ、実務面も限られた人々とのやりとりの中で進められていました。
そのため、「判断力が弱かった」という評価も、ある意味では環境によって作られた印象とも言えます。
ただし、当時の記録には、家重の言葉を理解できた家臣がいたことや、家重が意思を示す手段を工夫していた様子も記されています。
このことからも、完全に意思疎通が不可能であったわけではないと考えられます。
家重の障害は、将軍という立場にある人間としては大きなハンディであったことは間違いありません。
しかし、それを補う体制が築かれていた点で、江戸幕府の政治体制の柔軟さもうかがえます。
障害のある人物でも将軍職を全うできたという事実は、現代においても一定の示唆を与えるものと言えるでしょう。
家重が患っていた病気と当時の状況
家重の健康状態については、将軍在任中から様々な記録が残されています。
中でも注目されているのが、彼が慢性的な病気を抱えていたという点です。
言語障害とは別に、身体的にも虚弱であったことが知られており、それが政務に大きな影響を与えていました。
具体的には、家重はてんかんのような症状を持っていた可能性が指摘されています。
てんかんとは、突発的な痙攣や意識障害を引き起こす神経の病気であり、当時の医学ではほとんど理解されていませんでした。
このような病状がある中で将軍職を務めるには、日常的な健康管理が欠かせなかったはずです。
実際、記録では、家重がたびたび政務を離れて静養していたことが確認されています。
当時の医療は漢方や民間療法が中心であり、西洋医学の知識はほとんど導入されていませんでした。
そのため、病気の原因を特定したり、効果的な治療を行ったりするのは難しく、体調が優れない将軍に対しては、とにかく安静にさせるという対応が一般的でした。
こうした背景もあり、家重は将軍でありながら、健康上の理由で表舞台に出る機会が非常に少なかったのです。
また、病弱であることは家臣たちの間でも広く知られており、政務の実権が側近に移る一因ともなっていました。
田沼意次や大岡忠光などの側近たちは、家重の体調を考慮しながら政治を進める必要がありました。
このような政治運営の形は「集団指導体制」とも言われ、将軍一人のカリスマに頼らない統治の先駆けとも評価されます。
一方で、将軍が病弱であることは、外敵や反乱分子にとっては「政権が脆弱である」と映るリスクもありました。
そのため、幕府としては家重の病気をあまり公にしないよう注意を払っていたとされます。
表向きは「穏やかな将軍」としてイメージを保ちつつ、実務は側近が担うという二重構造が形成されていたのです。
このように、家重の病気とその対応は、当時の幕府政治が抱える脆さと柔軟さの両面を象徴する事例といえるでしょう。
家重の死因とその時代背景について
徳川家重は、在任から10年ほどで将軍職を退き、隠居生活に入りました。
その後、数年を経て、1761年に亡くなります。
死因は明確に断定されているわけではありませんが、当時の記録や医者の所見などから、脳血管系の疾患や重い持病による衰弱死と考えられています。
家重が亡くなった時代背景として重要なのは、江戸幕府が比較的安定した状態にあったことです。
享保の改革で幕政が整えられ、家重の治世も大きな戦乱や政争がなかったため、彼の死によって政局が混乱することはありませんでした。
家重の子である徳川家治がすでに将軍に就任しており、継承もスムーズに進んでいました。
また、家重の死はその晩年の隠居生活の延長線上で迎えたもので、政務にほとんど関与していない時期の出来事でした。
そのため、家臣団や江戸市中も冷静に対応できたと言われています。
江戸幕府としては、前将軍の死に伴う大規模な儀式や弔意表明が必要でしたが、政治的な影響は最小限にとどまりました。
一方で、家重の死をもって一つの時代の区切りが訪れたとも言えます。
吉宗から続く家系の血統は保たれつつも、田沼意次のような実務型の政治家が本格的に台頭してくる時代に突入していくのです。
この移行期における家重の死は、幕府の権威構造が変化していく象徴的な出来事だったとも解釈されています。
家重の死因についての具体的な記録は少ないものの、死の直前まで大きな混乱がなかったことは、むしろ彼の治世が一定の安定を保っていたことを示しているとも言えるでしょう。
病弱な将軍ではありましたが、その存在が幕政の緩やかな継承を可能にした点は、歴史的に評価されるべき一面です。
徳川家重がしたことを簡単に知るまとめ
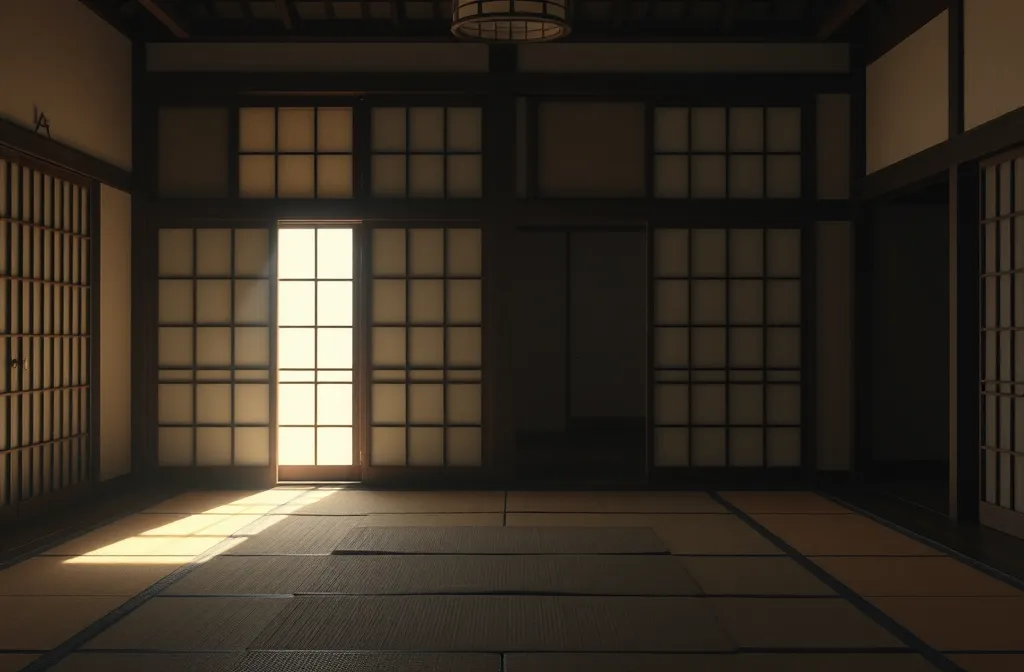
- 将軍として特に目立った出来事とは
- 側室の存在と家重との関係について
- 家重の子供・家治とのつながり
- 家重の人柄がわかるうなぎ好きの逸話
- 歴代将軍の中での家重の評価
- 家重時代の幕府は安定していたのか
将軍として特に目立った出来事とは
徳川家重の将軍在任期間は1745年から1760年までの約15年間です。
この時期における政治的な目立った出来事はあまり多くはないものの、いくつか注目すべき点があります。
特に大きな戦や政変がなかったことから、安定期として位置づけられることもありますが、それでも将軍としての動きが全くなかったわけではありません。
まず一つ目に挙げられるのは、幕政の実権を側近に委ねる体制がより明確になったことです。
家重は身体的な障害や病弱さにより、自らが強く主導するタイプの将軍ではありませんでした。
そのため、信頼できる家臣に政務を委ねることが常態化していきます。
これにより、田沼意次が台頭するきっかけを得ることになります。
田沼の登用は、家重政権における人事面での重要な決定事項と言えるでしょう。
また、経済面では物価や年貢の問題が深刻化しつつあった時期で、幕府の財政運営にも課題が浮かび上がっていました。
家重時代には直接的な抜本改革は行われませんでしたが、田沼意次のような実務家が関与し始めたことが、のちの改革に繋がる下地となります。
その他にも、吉宗時代から続いた享保の改革の「後継路線」として、無理に新政策を打ち出すのではなく、安定維持に重点を置いた政治が特徴でした。
目立った功績といえるような大改革や戦略的施策は少ないですが、その分、無理のない穏健な政治運営が行われていたと評価されています。
このように家重の将軍期は、派手な出来事よりも「次の時代への橋渡し」としての役割が大きかったと言えるでしょう。
それは必ずしも否定的な意味ではなく、混乱を避け、平穏な統治を継続したという点で、歴史的にも一定の意義があります。
側室の存在と家重との関係について
江戸時代の将軍家において、側室の存在は珍しいものではありませんでした。
徳川家重にも数名の側室がいたとされ、その中でとくに有名なのが「お喜世の方(おきよのかた)」です。
この人物は家重との間に、後の第10代将軍・徳川家治を産んだことで知られています。
お喜世の方は、家重の信頼を受けた側室であり、ただ子を産む存在ではなく、精神的な支えともなっていた可能性があります。
当時の将軍は、政治と家庭を厳密に分けるというよりも、家庭内での人間関係が政務にも少なからず影響を及ぼしていました。
特に家重のように体調が不安定で公務から距離を置く時間が多かった将軍にとって、側室との関係は単なる形式的なものではなく、日常の生活にも深く関わっていたと考えられます。
一方で、側室との関係は正室とのバランスが重要であり、将軍家内では微妙な力関係を生むこともありました。
しかし、家重の場合は病弱だったことや政務から距離を置いていたこともあって、政治的な側室争いのような記録はあまり見られません。
これは、側室との関係が比較的穏やかだったことを示しているのかもしれません。
また、お喜世の方が生んだ家治が次の将軍に就任したことで、彼女の立場はさらに高まりました。
将軍の母としての権威を持ち、幕府内でも一定の影響力を持った可能性があります。
このように、家重の側室は単なる歴史上の脇役ではなく、将軍家の安定や継承において重要な役割を果たしていたと言えるでしょう。
家重の子供・家治とのつながり
徳川家重の子供の中で最も重要な人物は、第10代将軍・徳川家治です。
家治は家重と側室・お喜世の方の間に生まれ、父の跡を継いで将軍に就任しました。
この親子関係は、将軍家の継承という視点から非常に注目されます。
家治は幼少期から将軍後継者として教育を受けており、父・家重の体調を考慮して比較的早い段階から政治的な準備が進められていました。
また、家重の引退後すぐに家治が将軍に就任していることからも、継承が円滑に行われたことがわかります。
一方で、父子の直接的な関係性については、詳細な記録が多く残っているわけではありません。
ただし、家重の治世が比較的安定していたことや、側近政治が定着していた状況から考えると、家治もまた「周囲の支えを受けながら統治する」というスタイルを踏襲した可能性が高いです。
家治の時代には田沼意次の積極的な改革が進められていきますが、それは家重政権下での基盤があったからこそ可能となったとも言えます。
つまり、家重と家治の関係は「政治的な連続性」を保つための重要な要素であったのです。
このように見ていくと、家重と家治の親子関係は、感情的なつながり以上に、「将軍職の安定した継承」という面で大きな意味を持っていたことがわかります。
家重の人柄がわかるうなぎ好きの逸話
徳川家重の人柄について語られる際、よく知られている逸話の一つが「うなぎ好き」だったという話です。
将軍という厳粛な立場にありながら、食に対して強いこだわりを見せたというこの話は、家重の人間らしさを感じさせるエピソードとして親しまれています。
特に有名なのは、家重が「うなぎが食べたい」と周囲に頻繁に訴えていたという記録です。
言語障害があり、発言が不明瞭だったとされる家重ですが、「うなぎ」という言葉だけははっきりと発音できたと伝えられています。
このため、家臣たちの間では、「将軍の意思は“うなぎ”で測る」といった冗談めいた話まであったと言われます。
このようなエピソードは、家重が感情を持つ一人の人間であったことを強く印象づけます。
当時の将軍は絶対的な権力者であり、距離のある存在として描かれがちですが、家重のように「好きなものをはっきり主張する」という行動には親しみやすさが感じられます。
もちろん、こうした逸話は事実の一部を強調した伝承である可能性もあります。
しかし、言葉に困難を抱えた将軍が、好物を通じて意思を表明していたという話は、多くの人にとって印象深く映るものです。
うなぎ好きという小さな特徴が、家重の性格や人柄を知る手がかりとなっている点は興味深いものがあります。
形式や儀式に支配された幕府の中で、そうした素朴な一面を持っていたことが、家臣たちにも受け入れられた理由の一つだったのかもしれません。
歴代将軍の中での家重の評価
徳川家重は、歴代の徳川将軍の中でも評価が分かれる人物の一人です。
一部では「無能な将軍」と言われることもありますが、それは家重が抱えていた障害や病弱さに起因する誤解である場合も多く、実際にはもう少し多面的に見る必要があります。
まず、政治的な手腕については、家重本人が積極的に統治を主導したわけではないため、評価は控えめです。
しかしその一方で、田沼意次や大岡忠光など有能な側近を登用し、政務を安定的に任せる体制を築いた点では、一定の成果を挙げたといえるでしょう。
つまり、直接の功績は少ないものの、「信頼できる部下に政務を任せる」という判断力は持ち合わせていたとも考えられます。
また、享保の改革を進めた父・徳川吉宗の存在が非常に大きかったため、どうしても家重は「影の薄い将軍」として比較されがちです。
実際には、吉宗が築いた政治体制を無理なく維持し、混乱なく次代へとバトンを渡したという点では、家重にも一定の評価が与えられるべきです。
歴代将軍の中には、戦や大改革で名を残した人物も多い一方、家重のように「何も起こさなかった」ことで安定を守った将軍もいます。
そのような静かな功績は記録に残りにくく、誤解されやすいという特徴があります。
特に近年では、家重の障害を考慮した上で、「無理に自己を前面に出さず、全体の調和を優先した将軍」として再評価する動きも見られています。
このように、家重の評価は時代によっても変化しており、単純に「できない将軍」と断じることはできません。
歴代将軍の中で目立つ存在ではありませんが、「組織の安定に貢献した人」として、もっと注目されてもよい人物です。
地味ではあっても、確かに必要な役割を果たした将軍だったといえるでしょう。
家重時代の幕府は安定していたのか
徳川家重が将軍を務めた時代、江戸幕府は表面上は安定を保っていたものの、内側では徐々に課題が蓄積していた時期でもありました。
そのため、「安定していた」と断言するのはやや楽観的かもしれませんが、大きな反乱や政変がなかった点では、一定の平和が維持されていたといえます。
まず、家重の将軍期(1745年〜1760年)は、享保の改革が一段落し、幕府が次の方向性を模索していた過渡期でした。
父・吉宗が築いた倹約政策や統制体制は、一定の成果を上げつつも、経済成長や市場の自由化との摩擦を生み出しつつありました。
そのため、庶民の間では物価の上昇や重税への不満が高まりつつあったのです。
一方で、将軍家内部では家重自身の体調や障害の影響により、政治の実務は側近に委ねられるようになります。
このことが一部の有力家臣の権力集中につながる一方で、大きな失策や混乱を招くような事態には発展していません。
田沼意次のような実務派が台頭する土壌が整ったのも、この時期の安定した政務体制の成果といえるでしょう。
また、諸藩の統治状況についても大きな乱れは見られず、江戸の町でも治安は比較的保たれていました。
農村部では天候不順や飢饉の兆候が出始めていましたが、本格的な危機は家治以降に表面化します。
つまり、家重時代はその前兆となる問題を内包しながらも、表立った混乱は起きていなかったのです。
総じて、家重の治世は「静かな安定期」といえるでしょう。
ただし、この安定は一時的なものであり、根本的な改革がなされなかったことが、後の時代の混乱へとつながっていきます。
このことから、「安定していたが、潜在的な課題を多く抱えていた時期」として、バランスの取れた評価が必要です。
徳川家重がしたことを簡単に総括
ここでは、徳川家重が将軍として行ったことを簡単に整理してお伝えします。
病弱で目立った業績が少ないとされる家重ですが、時代の移り変わりを支えた重要な存在でもありました。
以下に、彼の将軍在任中の動きや関連人物との関係を、分かりやすく箇条書きでまとめました。
- 徳川吉宗の長男として生まれ、将軍の座を順当に継承しました
- 幼い頃から言語障害があり、将軍就任には不安視される声もありました
- それでも吉宗の「長子相続」方針により、家督を受け継ぐことになります
- 実際の政務では、田沼意次や大岡忠光などの側近に大きく支えられました
- 田沼意次は実務能力に優れ、後の政権基盤をこの時期に築いています
- 大岡忠光もまた、穏健で堅実な対応を取り続けた重要なサポーターでした
- 家重自身は病弱で、公の場に出ることが少なかったと伝えられています
- てんかんのような持病を抱えていた可能性があり、静養を繰り返していました
- 言語障害による意思疎通の難しさが、実権委譲の体制を後押ししました
- 側室・お喜世の方との間に、後の第10代将軍・徳川家治をもうけました
- 家重と家治の間には、安定した政権継承がなされました
- 「うなぎが好き」という逸話は、家重の人柄を伝える面白い一面です
- 死因は明確ではありませんが、重い病による衰弱死と考えられています
- 在任中は大きな戦や騒乱がなく、幕府は一定の安定を保っていました
- 統治の中心には立ちませんでしたが、「穏やかな時代の橋渡し役」として再評価されることもあります
家重は、華々しい実績は少なかったかもしれませんが、混乱のない時代を次代へとつなげるという重要な役割を果たした将軍です。
その静かな功績は、歴史の中でじわじわと見直されつつあるのではないでしょうか。
関連記事



参考サイト
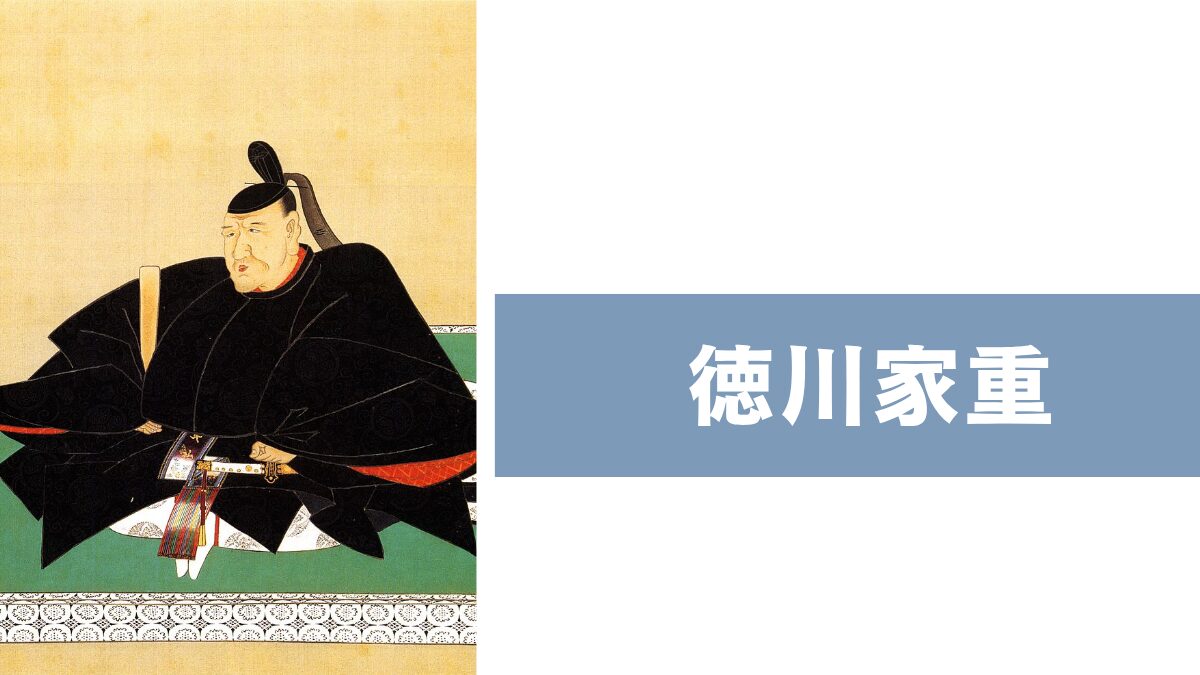

コメント