明治時代の重要な政治論争のひとつ「征韓論」について、教科書では難しく感じたことはありませんか?
いつ起きたのか、なぜ論争になったのか、どっちが正しいのか――そんな疑問を持って「征韓論 わかりやすく」と検索された方に向けて、この記事ではポイントを簡単に整理してご紹介します。
征韓論は、明治政府内で起きた「朝鮮への対応」をめぐる深刻な対立でした。
西郷隆盛をはじめとする賛成派と、大久保利通ら反対派の意見がぶつかり合い、最終的にどうなったのか、その結果や影響は、日本の歴史に大きな転機をもたらしました。
この記事では、征韓論が生まれた背景から反対理由と賛成理由、反対した人と賛成した人の立場の違い、メリットと課題、そして最終的な結末まで、必要なポイントをしっかりおさえて解説しています。
- 征韓論がいつ・なぜ起きたのかの背景
- 賛成派と反対派の人物とその主張の違い
- 論争の結果どうなったかとその後の影響
- 西郷隆盛と征韓論の関係や立場の整理
征韓論をわかりやすく背景から整理

- 征韓論はいつ起きた?時期と年号を確認
- 征韓論が出てきた理由とは?なぜが分かる
- 西郷隆盛と征韓論の関係を簡単に解説
- 反対した人と賛成した人を一覧で整理
- 反対理由と賛成理由をわかりやすく比較
- 征韓論のメリットと当時の狙いを解説
征韓論はいつ起きた?時期と年号を確認
征韓論が本格的に論争となったのは、明治6年(1873年)のことです。
この年に、明治政府内部で朝鮮への対応をめぐって大きな意見の対立が起こりました。
この対立が「征韓論」として歴史に名を残すことになります。
背景として、日本は明治維新から数年が経ち、中央集権的な体制がようやく整い始めた時期でした。
そのような中で、朝鮮との国交交渉がうまくいかず、国内では対応をどうすべきかという議論が続いていました。
そして1873年、海外視察から帰国した岩倉具視、大久保利通、木戸孝允らが「今は国内の整備を優先すべきだ」と主張し、武力による朝鮮開国に反対します。
一方で、西郷隆盛や板垣退助などは「自分が朝鮮に赴き、話し合いによって国交を開かせるべきだ」との立場をとっていました。
この主張の違いが政府内で深刻な対立となり、ついに征韓論をめぐる政争へと発展します。
その結果、1873年10月、西郷ら征韓派が一斉に政府を辞職する「明治六年の政変」が起きました。
この出来事によって、征韓論という言葉が歴史に刻まれたのです。
このように、征韓論が問題として表面化したのは1873年であり、明治6年という年号をおさえることがテスト対策としても重要です。
年表問題で問われることもあるので、数字と出来事をセットで覚えておきましょう。
征韓論が出てきた理由とは?なぜが分かる
征韓論が出てきた背景には、いくつかの複雑な事情が重なっています。
単なる「朝鮮とのトラブル」ではなく、日本の内政・外交の課題、国際情勢、さらには国内の不満のはけ口としての側面もありました。
第一に、朝鮮側が日本との国交を拒否し続けたことが大きなきっかけとなります。
明治政府は、王政復古と新政府樹立を知らせる国書を朝鮮に送りましたが、朝鮮は「皇」「勅」といった用語を理由に、これを拒絶しました。
これは、日本の天皇が清国の皇帝より上の存在と自称しているように見えるため、受け入れられなかったのです。
次に、朝鮮国内で実権を握っていた「大院君」が極めて強硬な鎖国・排日姿勢をとっていたことも緊張を高めました。
「日本人と関わる者は死刑にする」という過激な布告を出したこともあり、日本国内では「このままでは対話は不可能だ」という空気が広がっていきました。
また、日本国内では、士族(旧武士階級)の不満が爆発寸前でした。
明治維新で特権を失った士族たちは行き場のない怒りを抱えており、政府内部でも「不満を外に向けさせる必要がある」と考える者が現れます。
こうして、「朝鮮との衝突」をきっかけにして士族の怒りをそらそうという思惑も含まれるようになったのです。
さらに、欧米列強に対抗するため、アジア諸国と協力して連携を築くべきだという意見もありました。
その第一歩として朝鮮を開国させ、東アジア全体で西欧に対抗できる体制を作ろうという理想が、征韓論の裏にありました。
このように、征韓論が出てきた理由は「外交の失敗」「国内の不満」「国際情勢」など多岐にわたります。
一つの理由で語れないからこそ、問題が深刻化し、政府内での激しい対立へとつながっていきました。
西郷隆盛と征韓論の関係を簡単に解説
西郷隆盛は、征韓論を語る上で絶対に外せない中心人物です。
ただし、誤解されがちなのは「西郷が武力侵攻を主張した」というイメージです。
実は、西郷自身は最初から戦争を望んでいたわけではありません。
西郷の主張は「自分が特使として朝鮮に行き、直接話し合いで解決を目指す」というものでした。
彼は、武力で相手を威圧するよりも、礼節を持った交渉によって朝鮮との関係改善を目指そうと考えていました。
そのため、「武器を持たず、正装で使節として行く」とまで言っています。
一方で、他の征韓派には「朝鮮を討つべきだ」と主張する者も多く、西郷の穏健な立場とはやや異なっていました。
しかし、朝鮮が使節を拒否し続けた場合には、戦争もやむを得ないという姿勢を見せたため、結果として「征韓論=西郷=戦争」といった誤解が広がったのです。
また、西郷がこのような立場をとった背景には、士族たちの不満を外へそらすという現実的な配慮もありました。
内乱を防ぎ、政府を安定させるためにも、外への関心を向ける政策が必要だったのです。
最終的に、西郷の朝鮮派遣計画は、大久保利通らの反対によって却下されます。
この決定に不満を抱いた西郷は、1873年に政府を辞職し、政治の表舞台から退くことになりました。
この一連の動きは「明治六年の政変」と呼ばれ、のちの西南戦争へとつながる重要な分岐点となります。
このように、西郷隆盛は単なる軍事的征服者ではなく、あくまで話し合いによる国交正常化を目指した人物でした。
その姿勢と政府内での対立が、征韓論の象徴として語り継がれているのです。
反対した人と賛成した人を一覧で整理
征韓論では、明治政府の中でも意見が大きく分かれました。
その結果、政府高官たちの間で賛成派と反対派が明確になり、政治の方向性を左右する大論争へと発展していきます。
まず、賛成した人たち(征韓派)には以下のような人物がいます。
- 西郷隆盛(さいごう たかもり):自らが使節として朝鮮に赴くことを提案しました。話し合いによる解決を望んでいましたが、最終的には衝突の可能性も視野に入れていたとされています。
- 板垣退助(いたがき たいすけ):軍隊を派遣して朝鮮を開国させるべきという強硬な姿勢でした。
- 後藤象二郎(ごとう しょうじろう):西郷の提案に賛成し、穏健派ながらも征韓論支持の立場をとっていました。
- 江藤新平(えとう しんぺい):司法制度の整備を進めた功労者でありながら、西郷らと共に征韓論に同意しました。
- 副島種臣(そえじま たねおみ):外交に通じた人物で、西郷の派遣を支持しました。
一方、反対した人たち(反対派)は以下の通りです。
- 大久保利通(おおくぼ としみち):内政優先を主張し、戦争による国力の消耗を避けるべきだと考えていました。
- 岩倉具視(いわくら ともみ):欧米視察を終えて帰国後、征韓論に強く反対しました。国内整備こそ急務と判断したからです。
- 木戸孝允(きど たかよし):岩倉使節団の一員として海外事情を体感し、日本が戦争を起こす段階にないと判断しました。
- 勝海舟(かつ かいしゅう):当時の海軍力では朝鮮との戦争を維持できないと冷静な立場をとりました。
- 伊藤博文(いとう ひろぶみ):近代国家の形成を重視し、戦争より国内制度の整備を優先しました。
このように、征韓論を巡る対立は単なる意見の食い違いではなく、それぞれの人物がもつ国家ビジョンや経験に基づいた深い判断の違いから生まれています。
特に海外経験の有無が、判断を分けた重要な要素だったといえるでしょう。
反対理由と賛成理由をわかりやすく比較
征韓論をめぐる議論では、どちらの主張にも明確な理由がありました。
そのため、単純に「戦争に賛成」「反対」と捉えるのではなく、背景や目的を理解することが大切です。
まず、賛成派の理由は以下の通りです。
- 国交の必要性:朝鮮との国交が成立していない状態では、日本の東アジア外交が進まないと考えられていました。
- 士族の不満解消:明治維新後、特権を失った士族の不満を外へ向けることで、国内の混乱を防ごうという意図がありました。
- アジアの結束を目指す理想論:西郷隆盛など一部の思想家は、日本・朝鮮・清で連携し、西欧列強に対抗する「アジアの連帯」を構想していました。
- 国の威信を保つ:朝鮮の侮辱的な態度に対し、何もせずに黙っていると、日本の立場が弱くなるとする意見もありました。
一方、反対派の理由は以下のように整理できます。
- 国力不足:戦争をするには軍備も経済力も不足しており、国家の負担が大きすぎるという冷静な判断です。
- 国内の整備が優先:教育制度、徴兵令、財政基盤の強化など、やるべき内政課題が山積みでした。
- 外交的リスク:朝鮮の背後には清やロシアといった大国が控えており、下手に戦争を始めれば国際的孤立を招く可能性もありました。
- 条約改正交渉への悪影響:欧米との不平等条約の改正交渉が続く中、日本が好戦的な姿勢を見せれば、国際的信用を失う恐れがありました。
このように、賛成派は「外へ向けて動くべき」派、反対派は「まず内を固めるべき」派といえるでしょう。
どちらの主張にも一理あり、当時の日本がどう舵を切るかで、今後の国の形が大きく変わる岐路に立たされていたのです。
征韓論のメリットと当時の狙いを解説
征韓論には、実行すれば得られると考えられていた複数のメリットがありました。
一方で、その狙いが理想論に偏っていたり、現実とのギャップがあったことも指摘されています。
主なメリットの一つは、東アジアにおける日本の主導権を確立することです。
朝鮮を開国させることで、日本は清やロシアに先んじて影響力を強めることができると考えられていました。
とくに、西郷隆盛らは朝鮮と友好的関係を築いた上で、最終的に清との同盟を視野に入れていました。
この構想が成功すれば、西欧列強に対抗する「アジア連携」が可能になるという見通しもありました。
次に、士族の不満を外へ向けさせるという政治的効果も挙げられます。
維新後の改革で不満を抱えた旧武士たちは、再び武力を行使できる場を求めていました。
これを国内の暴動として爆発させるのではなく、外交問題を通じて昇華しようという意図が、征韓論の中には込められていたのです。
また、当時の日本は、すでに不平等条約の問題や国内改革の課題を抱えており、国威発揚を図るという意味合いもありました。
朝鮮が国書を拒否したことは、ある種の侮辱と捉えられ、対応しなければ国の威信が傷つくと考えた者も少なくありません。
ただし、こうしたメリットには大きなリスクや限界も存在しました。
朝鮮を相手に戦争をすれば、清やロシアとの対立を招く可能性が高く、結果として日本が国際的な孤立を深める危険もありました。
また、国力が整っていない中で戦争に突入すれば、むしろ改革そのものが頓挫してしまう恐れもありました。
こうして見てみると、征韓論の狙いには理想と現実のズレがあり、それをどう乗り越えるかが問われていたのです。
メリットは確かに存在したものの、その実現には多くの障壁があったことも、理解しておくべき点でしょう。
征韓論をわかりやすく結末と影響を解説
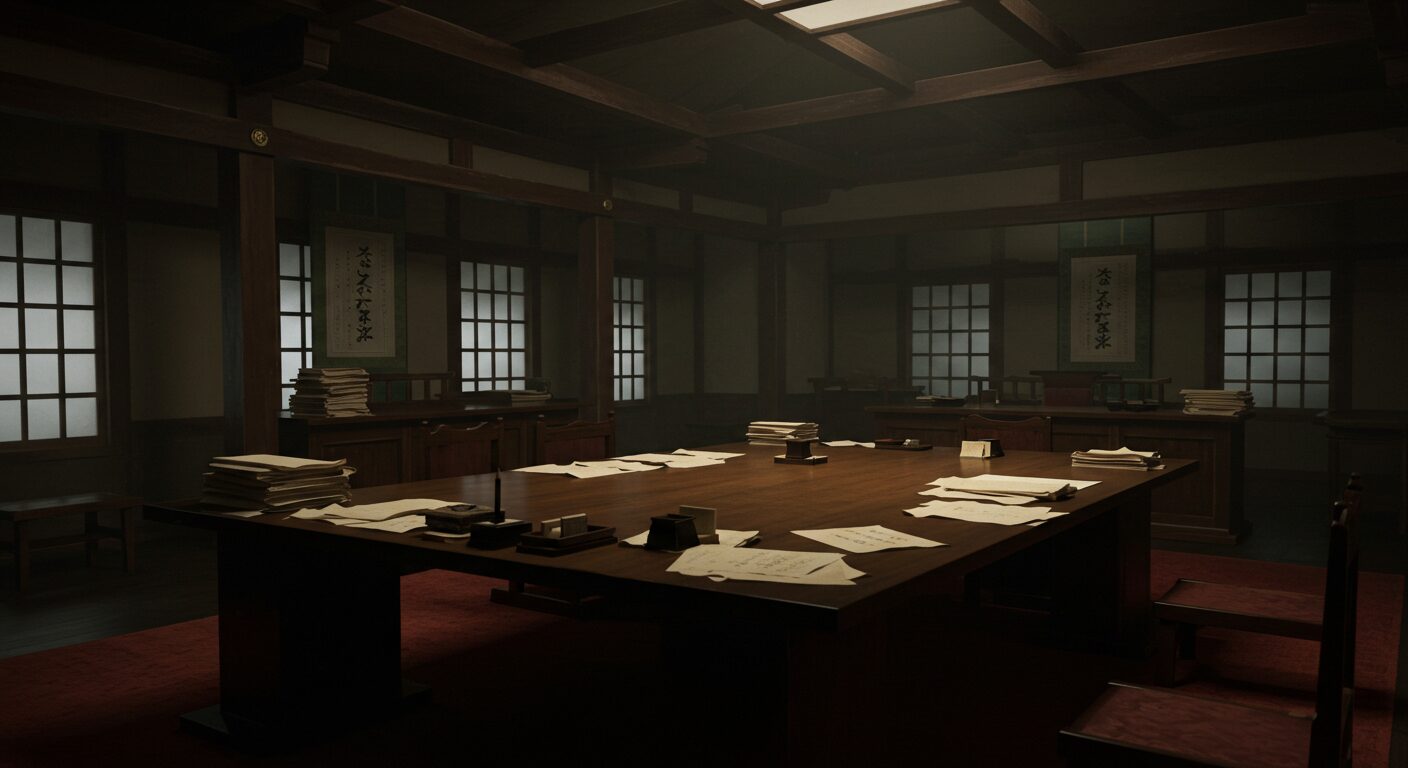
- 論争の結果どうなった?征韓論の結末
- 征韓論と明治六年政変の流れを解説
- 征韓論が西南戦争へつながった理由
- 反対派の主張内容を簡単におさらい
- 外交政策に与えた影響とは?日本の動き
- 征韓論はどっちが正しい?今の視点で考察
論争の結果どうなった?征韓論の結末
征韓論をめぐる激しい議論の末、最終的に政府が出した結論は「征韓論の見送り」でした。
つまり、朝鮮への派兵や西郷隆盛の使節派遣は実現しなかったのです。
当時、政府の中で賛成派と反対派が真っ向から対立していました。
西郷隆盛をはじめとする賛成派は、「話し合いで開国を促す」としながらも、もし拒絶された場合には対処する覚悟を持っていました。
一方で、大久保利通や岩倉具視らの反対派は、「日本はまだ戦争を起こすだけの体力がない」として強く反発しました。
議論が白熱するなかで、太政大臣の三条実美が一時的に西郷の派遣に同意する場面もありました。
しかし、その直後に体調を崩して政務から退いたため、政局は再び混迷します。
最終的に、岩倉具視が太政大臣代理となり、明治天皇に「西郷の派遣は延期すべきだ」と上奏しました。
天皇がこれを受け入れたことで、征韓論は正式に否定される形となります。
この結果、西郷隆盛を含む賛成派の政府高官たちは一斉に辞職。
その中には板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、副島種臣など、明治政府を支えていた中心人物も多く含まれていました。
こうして、征韓論は実行に移されることなく終わりを迎えます。
しかし、この論争によって政府は深く分裂し、以後の政治体制や社会の動きに大きな影響を残すことになります。
征韓論と明治六年政変の流れを解説
征韓論が日本の政治に大きな爪痕を残した出来事、それが「明治六年政変」です。
この政変は、征韓論をめぐる意見対立が最終的に政権内部の分裂へと発展した一大事件です。
まず、事の発端は1873年(明治6年)、日本が朝鮮との国交交渉に行き詰まっていたことにあります。
使節を送っても朝鮮は拒否を続け、朝鮮政府は日本を「野蛮な国」と見なし、国民にも日本人と関わることを禁じていました。
この状況に対して、政府内の「留守政府(西郷・板垣ら)」は朝鮮への対処を強化すべきと判断。
西郷隆盛は自らが使節として朝鮮に赴き、対話を試みたいと申し出ました。
一方、海外視察から帰国した岩倉具視や大久保利通ら「洋行組」は、「日本はまず国内の整備が先」として、西郷の派遣に強く反対します。
一度は太政大臣・三条実美が西郷の使節派遣を内定しましたが、三条が病に倒れたことにより、政局は急展開します。
岩倉具視が太政大臣代理となり、大久保とともに天皇へ「西郷の派遣延期」を進言。
結果として、明治天皇はこの意見を受け入れ、西郷の朝鮮派遣は取りやめとなりました。
これを不服とした西郷隆盛、板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣らは政府を辞職。
当時の参議9名のうち5名が一斉に辞めるという異例の政変となり、「明治六年の政変」と呼ばれるようになりました。
この政変によって、薩摩・土佐・肥前といった旧藩出身者の多くが政治の中心から離れ、以後の政権運営は薩長出身者を中心とした体制へと傾いていきます。
このように、征韓論と明治六年政変は切っても切れない関係にあり、日本の政局を大きく動かす転機となったのです。
征韓論が西南戦争へつながった理由
征韓論が否決されたことは、直接的には朝鮮との戦争を避けたという意味で平和的な判断に見えるかもしれません。
しかしその裏では、征韓論の挫折が国内の重大な内乱、「西南戦争」へとつながっていく火種となっていました。
まず、西郷隆盛が征韓論否決を受けて政府を辞職したことが大きな転換点です。
政府を去った西郷は故郷・鹿児島に戻り、「私学校」という士族教育機関を設立。
この学校には多くの不平士族が集まり、次第に政府への不満を募らせる場へと変化していきました。
当時、日本政府は士族の特権を次々に廃止しており、帯刀の禁止(廃刀令)や俸禄の打ち切り(秩禄処分)などが実施されていました。
これらの改革は近代化のためには必要なものでしたが、武士としての誇りを持っていた士族たちにとっては我慢ならないものでした。
征韓論が実行されていれば、士族たちは「国家のために戦う」という新たな役割を得ていたかもしれません。
しかしそれが否定され、士族は居場所を失ったまま、社会の片隅に追いやられていったのです。
そうした中で、西郷を精神的な支柱とする士族たちは、ついに明治10年(1877年)、政府に対して武装蜂起します。
これが「西南戦争」です。
西郷は初めは慎重でしたが、情勢の流れに抗えず、ついには挙兵に踏み切りました。
つまり、征韓論が否決されたことによって西郷が政府を去り、その後の士族反乱が最終的に西南戦争という大規模な内戦へとつながったのです。
表向きは外交問題であった征韓論が、実は国内の不満と密接に結びついていたことが、この流れからもよく分かります。
反対派の主張内容を簡単におさらい
征韓論に対して明確に反対の立場をとった人たちは、単に戦争を恐れたわけではありません。
彼らの主張には、当時の日本の現実を冷静に見極めた、いくつかの具体的な理由が含まれていました。
ここで、主な反対派の主張を整理しておきましょう。
まず第一に挙げられるのは、「国内の整備が優先である」という考え方です。
明治政府が発足してまだ数年しか経っておらず、教育制度、徴兵制、財政基盤、交通インフラなど、国内の制度改革が始まったばかりでした。
戦争に力を割けば、せっかく始まった近代化が中途半端なまま止まってしまう、という懸念があったのです。
次に重要なのが、「国力不足」への危機感です。
大久保利通や岩倉具視、木戸孝允ら岩倉使節団のメンバーは欧米諸国を視察し、日本がいかに発展途上であるかを実感しました。
兵力や財政面、外交交渉力など、どれをとっても海外に比べて不十分であるという認識が、彼らの反戦姿勢を支えていました。
さらに、「戦争は国際的リスクを高める」という判断も見逃せません。
もし日本が朝鮮を相手に戦争を起こせば、朝鮮の背後にいる清やロシアを刺激し、大きな戦争に発展するおそれがありました。
このような状況は、当時の日本にとって大きな負担であり、むしろ国の存続に関わるとまで考えられていたのです。
また、国内の視点からも反対派の声は理にかなっていました。
戦争になれば当然、財政負担が増加します。
重税や物価高騰を招けば、国民の生活がさらに苦しくなり、内政不安にもつながりかねません。
このように、反対派はただ消極的だったわけではなく、「今の日本にはその余裕がない」という現実的な立場から意見を述べていました。
短期的な感情よりも、長期的な国の安定と発展を重視していた点が特徴です。
外交政策に与えた影響とは?日本の動き
征韓論の否決は、日本の対外政策に大きな影響を与えました。
戦争には至らなかったものの、その後の日本は独自の外交戦略を展開し、最終的には朝鮮との関係にも重大な変化が生まれます。
まず、征韓論を見送った直後の政府は、「平和的な外交方針を優先する」という姿勢を表に出しました。
この方針のもとで進められたのが、国際社会における信頼の回復です。
岩倉使節団の視察で見えてきた日本の課題を受け、政府は近代化を一層加速させ、条約改正や国際的な交渉力の強化を目指します。
しかしその一方で、朝鮮との関係は依然として膠着状態が続いていました。
幾度となく使節を送っても交渉は進まず、朝鮮側の排日姿勢はむしろ強まっていきます。
このような中、政府は1875年、「江華島事件」という強硬手段に出ます。
日本の軍艦が朝鮮沿岸で挑発行動を取り、砲撃を受けたことをきっかけに戦闘が発生。
これに乗じて、日本は日朝修好条規という不平等条約を結ばせ、朝鮮を開国させることに成功しました。
この出来事は、征韓論が直接実現しなかった代わりに、「事実上の武力外交」が取られたことを意味します。
結果として、日本は朝鮮との国交を確立しましたが、それは話し合いではなく、軍事的圧力によるものでした。
その後も日本は、アジア各国への影響力を徐々に拡大させ、最終的には日清戦争・日露戦争へと歩を進めていきます。
こうして見ると、征韓論を否決したからといって日本の対外進出が止まったわけではありません。
むしろ、それは外交戦略を一時的に見直す「転換点」であり、やがてより現実的で強硬な政策へとつながっていきました。
征韓論はどっちが正しい?今の視点で考察
征韓論を振り返ったとき、現代の私たちは「賛成と反対のどちらが正しかったのか」と考えたくなるかもしれません。
しかし、答えは一方的には出せません。
当時の日本がおかれていた内外の状況を踏まえれば、両方に一定の正当性があったことが分かります。
賛成派の主張には、「国交が拒まれているなら、行動に移すべきだ」という現実的な焦りがにじんでいました。
朝鮮の挑発的な態度や、日本に対する敵視的な姿勢は明らかであり、放置すれば国の威信が損なわれると考えられても不思議ではありません。
また、士族の不満を解消する手段としても、外征という選択は一定の説得力を持っていました。
一方で、反対派の意見も極めて合理的でした。
日本はようやく明治維新を経て、近代国家としての第一歩を踏み出したばかり。
軍事力や財政力はまだ未熟で、対外戦争によって国が立ちゆかなくなる可能性も十分にありました。
また、国際情勢において孤立すれば、列強からの圧力を受けかねないという懸念も正当でした。
こうした視点を総合すると、「どちらが絶対に正しい」というよりも、「どのタイミングで何を優先すべきか」の判断の違いであったことが見えてきます。
賛成派は短期的な行動と国威の発揚を意識し、反対派は中長期的な国家の成長と安全を重視していたのです。
現代から見れば、結果として日本は戦争を回避した後も朝鮮に軍事的圧力をかけ、最終的には日清戦争・日露戦争を経て朝鮮を支配下に置きました。
その歴史を踏まえると、「武力によらない対話の選択肢をもっと追求すべきだった」と考える人もいるでしょう。
つまり、どちらが正しいかを問う前に、「どの選択がより多くの人にとって長期的にプラスとなったのか」を見つめることが、歴史を学ぶうえでの本質といえるのではないでしょうか。
征韓論をわかりやすくまとめて総括
この記事では、征韓論について背景から流れ、登場人物の立場やその後の影響まで丁寧に解説してきました。
ここで一度、内容を整理しておきましょう。テスト前の復習やレポート作成にも役立つよう、ポイントを箇条書きでまとめました。
- 征韓論が本格的に問題化したのは明治6年(1873年)です。
- 朝鮮が日本からの国書を拒否したことが対立のきっかけとなりました。
- 明治政府内で、朝鮮への対応をめぐる意見が大きく分かれました。
- 西郷隆盛は「自分が特使として朝鮮に行く」と穏やかな解決策を提案しました。
- 一方、大久保利通や岩倉具視は「国内の近代化が最優先」として反対しました。
- 賛成派には西郷、板垣退助、後藤象二郎らが名を連ねていました。
- 反対派には大久保、岩倉、木戸孝允、勝海舟、伊藤博文らがいました。
- 賛成理由には「国交の確立」「士族の不満解消」「アジアの連携構想」などがありました。
- 反対理由には「国力不足」「内政の未完成」「外交リスク」などがありました。
- 最終的に西郷の派遣案は却下され、賛成派の要人たちは辞職します。
- この政治的な衝突は「明治六年の政変」と呼ばれる出来事につながりました。
- 西郷は鹿児島に戻り、士族とともに私学校を設立しました。
- その後、士族の不満が爆発し、西南戦争が勃発します。
- 征韓論自体は否決されましたが、1875年の江華島事件で朝鮮は実質的に開国させられました。
- つまり、話し合いではなく、結果として武力で道が開かれたともいえる展開でした。
このように、征韓論は単なる外交問題ではなく、日本の政治・社会・外交に深く関わる大きな転機となった出来事です。流れを押さえておけば、今後の学習にもつながりやすくなります。
参考サイト

コメント