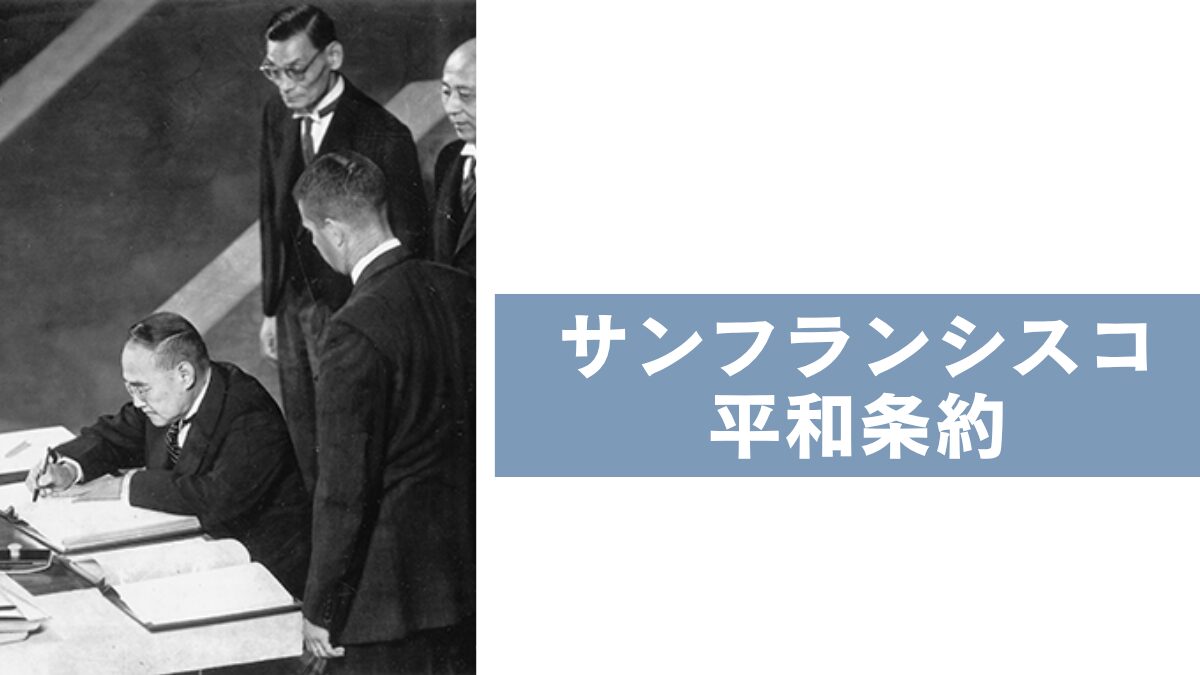「サンフランシスコ平和条約」と聞いて、「日本の独立」を思い浮かべる方は多いと思います。
しかし、なぜこの条約が、70年以上経った今もニュースで聞く領土問題や基地問題の「原点」と呼ばれるのか、具体的に説明するのは少し難しいと感じていませんか?
この記事では、戦後日本が国際社会に復帰するきっかけとなったサンフランシスコ平和条約について、締結が急がれた背景から、日本の独立や領土に関する具体的な内容、そして現代にまで続く影響まで、一つひとつ丁寧にわかりやすく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、以下の点がすっきりと理解できます。
- 条約が結ばれた目的と「冷戦」という背景
- 日本が独立し、放棄した領土の具体的な内容
- なぜソ連や中国が参加しなかったのか
- 現代の領土問題や基地問題にどう繋がるか
サンフランシスコ平和条約をわかりやすく解説

- そもそもどんな条約?目的と概要
- なぜ締結が急がれた?冷戦という背景
- 主な内容① 日本の独立と主権回復
- 主な内容② 放棄を決めた領土
- 賠償金は原則なし?役務賠償とは
そもそもどんな条約?目的と概要
サンフランシスコ平和条約とは、一言でいえば、第二次世界大戦を法的に終わらせるために結ばれた講和条約です。
この条約によって、日本は再び独立した主権国家として国際社会に復帰することが認められました。
1945年8月にポツダム宣言を受け入れて降伏した後、日本は連合国軍総司令部(GHQ)による占領下に置かれていました。
この間、日本の政治や社会はGHQの管理下にあり、独立国としての「主権」(自分の国のことを自分で決める権利)が制限された状態だったのです。
戦争を正式に終結させ、この占領状態を終わらせ、日本が自らの力で国を運営していくためには、日本と戦争をしていた「連合国」との間で、正式な「講和(仲直り)」の取り決めを結ぶ必要がありました。
それが、このサンフランシスコ平和条約だったのです。
この条約の正式名称は「日本国との平和条約(Treaty of Peace with Japan)」と言います。
1951年9月8日、アメリカのサンフランシスコ市にあるオペラハウスで開かれた講和会議において、日本と、アメリカやイギリス、フランスなどを含む連合国48カ国との間で署名されました。
日本の首席全権(代表)は、当時の内閣総理大臣であった吉田茂が務めています。
そして、翌年の1952年4月28日にこの条約は発効(効力を持つこと)しました。
この瞬間をもって、約7年近く続いた連合国軍による日本の占領は終わりを告げ、日本は独立を回復しました。
条約の目的は、大きく二つありました。
一つは、前述の通り、日本と連合国との間の「戦争状態」を法的に完全に終結させることです。
もう一つは、戦争が終わった後の日本のあり方について、国際的なルールを明確に定めることでした。
例えば、日本が独立国として国際社会の一員となることの承認、戦争責任の処理(賠償など)、そして日本の領土の範囲をどこまでにするか、といった戦後処理に関する重要な事柄が、この条約によって決定されたのです。
条約の前文では、日本が国際連合憲章の掲げる義務を受け入れ、世界人権宣言の実現に向けて努力することなども記されており、日本が平和を愛する国際社会の一員として再出発する意志を示すものともなりました。
条約の正文(公式な言語)は、英語、フランス語、スペイン語で作成され、日本語版も「ひとしく正文である」と準ずる扱いになっています。
このように、サンフランシスコ平和条約は、戦後の日本が「独立国」として再スタートを切るための、最も基本的かつ重要な国際条約だと言えます。
なぜ締結が急がれた?冷戦という背景
サンフランシスコ平和条約の締結が1951年という時期に急がれた背景には、当時の世界情勢、特に「冷戦(冷たい戦争)」の激化が大きく関係しています。
第二次世界大戦が終わった後、世界は二つの大きな勢力に分かれて対立することになりました。
一つは、アメリカを中心とする資本主義・自由主義の国々(西側陣営)です。
もう一つは、ソビエト連邦(ソ連)を中心とする社会主義・共産主義の国々(東側陣営)でした。
両陣営は、直接的な戦争(熱い戦争)こそ避けたものの、政治、経済、軍事のあらゆる面で激しく睨み合い、対立を深めていきました。
この状態が「冷戦」と呼ばれています。
戦争が終わった当初、アメリカの日本に対する占領政策は、日本を二度と戦争ができないように非軍事化し、弱体化させることが中心でした。
しかし、冷戦が深刻化するにつれて、アメリカの考えは大きく変わっていきます。
1949年には、広大な中国大陸で内戦に勝利した中国共産党が「中華人民共和国」の成立を宣言し、東側陣営に加わりました。
さらに決定打となったのが、1950年に勃発した「朝鮮戦争」です。
日本のすぐ隣にある朝鮮半島で、ソ連と中国が支援する北朝鮮(社会主義)と、アメリカが支援する韓国(資本主義)との間で、冷戦が実際の戦闘となる「代理戦争」が始まってしまったのです。
アジア全域で社会主義の勢力が急速に拡大することを、アメリカは強く恐れました。
「ドミノ倒し」のように、アジアの国々が次々と社会主義化してしまうのではないかと懸念したのです。
そこでアメリカは、日本に対する政策を180度転換しました。
日本を弱体化させるのではなく、むしろ占領状態から早期に独立させ、西側陣営の強力な同盟国として育て上げることを選んだのです。
日本を「アジアにおける資本主義の砦(とりで)」とし、東側陣営の拡大を防ぐための防波堤にしようと考えました。
このアメリカの方針転換が、サンフランシスコ平和条約の締結を急がせた最大の理由です。
アメリカの特使であったジョン・フォスター・ダレスが中心となって、西側諸国との講和の準備が精力的に進められました。
日本側でも、吉田茂首相は、この国際情勢の変化を日本の独立回復の好機と捉え、アメリカと歩調を合わせる現実的な道を選びました。
もし朝鮮戦争が起こらず、冷戦が激化していなければ、日本の占領はさらに長く続いていた可能性もあります。
このように、サンフランシスコ平和条約は、単に日本の戦争処理という側面だけでなく、冷戦という当時の厳しい国際政治の駆け引きの中で、アメリカの戦略的な思惑と日本の独立への願いが一致した結果、急いで締結されたものだったのです。
主な内容① 日本の独立と主権回復
サンフランシスコ平和条約の中で、日本人にとって最も重要だった内容は、日本の独立と主権の回復を正式に認めた部分です。
これは条約の第一章、第1条に明確に記されています。
まず、第1条(a)で「日本国と各連合国との間の戦争状態は、…効力を生ずる日に終了する」と宣言されました。
これにより、1941年の太平洋戦争開始から続いていた法的な戦争状態が、ようやく終わりを迎えたのです。
そして続く第1条(b)では、「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」と定められました。
この「主権の承認」こそが、独立の核心部分です。
「主権」とは、簡単に言えば「自分の国のことを、他国からの干渉を受けずに、自分たちで最終的に決定できる権利」を指します。
降伏後、日本はGHQの占領下にあり、法律や政策の多くがGHQの指示や許可なしには実行できませんでした。
例えば、新聞や出版物には検閲があり、政府の重要な決定にもGHQの意向が強く反映されるなど、日本の主権は大きく制限されていました。
しかし、この条約が発効した1952年4月28日をもって、GHQによる占領統治は終了し、日本は自らの政府と国会、そして法律に基づいて国を運営する力を取り戻したのです。
この主権回復と関連して、日本の安全保障に関する重要な規定も盛り込まれました。
第5条(c)では、日本が主権国として、国際連合憲章に定められている「個別的自衛権」(自国が攻撃された時に自国を守る権利)と、「集団的自衛権」(同盟国などが攻撃された時に共同で防衛する権利)を持っていることを連合国が承認しました。
当時の日本国憲法は戦争を放棄していましたが、独立国として自らを守る固有の権利(自衛権)自体は持つことが国際的に認められたのです。
さらに、日本が他国と「集団的安全保障取決め」を自発的に結ぶこと、つまり、他国と軍事的な同盟を結ぶことも認められました。
一方で、占領軍の扱いについては第6条(a)で定められました。
条約が発効してから90日以内に、すべての連合国占領軍は日本から撤退しなければならないとされました。
これにより、占領が終わることが明確に示されたのです。
ただし、ここには重要な但し書きがありました。
「一又は二以上の連合国との間で二国間又は多国間の協定が締結された場合」は、その協定に基づいて外国軍隊が日本に駐留し続けることを妨げない、とされたのです。
この一文が、平和条約と同時に締結されることになる「日米安全保障条約」の法的根拠の一つとなり、独立後も米軍が日本に駐留し続ける道を開くことになりました。
このように、この条約は日本の主権回復を高らかに宣言すると同時に、独立後の日本の安全保障のあり方についても方向性を示すものとなりました。
主な内容② 放棄を決めた領土
サンフランシスコ平和条約では、日本が独立を回復する条件として、かつて統治や領有をしていた広範な地域の権利を放棄することが定められました。
これは、日本の降伏条件であったポツダム宣言(カイロ宣言の履行を含む)に基づき、戦前の領土拡大を清算し、戦後の日本の領土範囲を法的に確定させるための規定でした。
具体的には、条約の第2章「領域」に、日本が権利、権原(所有権などの根拠)、請求権を放棄する地域が列挙されています。
放棄が明記された主な地域
まず、第2条(a)で、日本は「朝鮮の独立」を承認し、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利と請求権を放棄しました。
次に、(b)では「台湾及び澎湖諸島」に対するすべての権利と請求権を放棄することが定められました。
さらに、(c)では「千島列島並びに日本が1905年のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太(サハリン)の一部及びこれに近接する諸島」に対するすべての権利と請求権を放棄しました。
このほかにも、(d)で国際連盟の委任統治領であった南洋諸島(パラオ、マーシャル諸島など)、(e)で南極地域、(f)で新南群島(スプラトリー諸島)及び西沙群島(パラセル諸島)に対する権利と請求権の放棄が定められています。
これらの規定により、日本はかつての植民地や占領地、勢力圏の多くを法的に手放すことになりました。
アメリカの施政権下に置かれた地域
上記の「放棄」とは別に、第3章「安全保障」の中の第3条で、特定の島々がアメリカの管理下に置かれることが定められました。
対象となったのは、「北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)」、そして「孀婦(そうふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖の鳥島及び南鳥島」です。
これらの地域について、日本は、アメリカ合衆国を唯一の施政権者とする国際連合の信託統治制度下に置くというアメリカのいかなる提案にも同意するとされました。
事実上、これらの島々は日本の主権は残しつつも、アメリカが統治を行う(施政権を持つ)状態に置かれたのです。
これは「放棄」ではなかったため、後に日本に返還されることになりますが、沖縄は1972年、小笠原諸島は1968年まで、日本本土の独立後もアメリカの統治下に置かれ続けることになりました。
この領土に関する規定は、条文の解釈や、条約に署名しなかった国との関係において、現代まで続く領土問題の火種を残すことにもなりました。
例えば、日本が放棄した「千島列島」の範囲に北方領土が含まれるかどうかで日本とロシアの主張が対立しています。
また、台湾の最終的な帰属先が明記されなかったことも、後の東アジアの国際関係に複雑な影響を与え続けています。
賠償金は原則なし?役務賠償とは
サンフランシスコ平和条約において、戦争責任の取り方、特に「賠償」の問題は非常に重要な焦点の一つでした。
結論から言うと、この条約では、日本が莫大な額の「賠償金」を現金で支払うことは、原則として免除されました。
その代わりとして、「役務(えきむ)賠償」という特殊な形での賠償が認められたのです。
第一次世界大戦後、敗戦国のドイツは巨額の賠償金を課せられ、経済が破綻寸前になりました。
このことが、国民の不満を高め、結果としてナチスの台頭と第二次世界大戦の一因になったという反省がありました。
アメリカは、特に冷戦が激化する中で、日本に同じ轍を踏ませるべきではないと考えました。
日本に重すぎる賠償負担を課せば、経済復興が遅れ、西側陣営の同盟国として期待する役割を果たせなくなってしまうからです。
むしろ、日本の経済的負担を軽くし、早期に復興させることがアメリカの戦略的利益にかなうと判断されました。
このため、条約の第14条(a)では、日本が戦争によって連合国に与えた損害及び苦痛に対して賠償を支払うべきことが承認されつつも、同時に「現在の日本の資源では、完全な賠償を行って経済を維持していくことはできない」ことも認められました。
その上で、現金での賠償ではなく、日本が持つ「役務(サービス)」によって賠償を行う道が示されました。
これが「役務賠償」です。
具体的には、戦争で被害を受けた連合国(希望する国)との間で個別に協定を結び、日本が持つ技術や労働力を提供する、という形を取りました。
例えば、日本の企業が賠償相手国に出向き、ダム、発電所、橋、道路といったインフラ(社会基盤)を建設したり、機械や船舶などの生産物を提供したりしました。
これは、日本にとっては手持ちの外貨(現金)を使わずに賠償義務を果たせるという利点があり、同時に日本の産業の復興や、後の経済進出の足がかりにもなりました。
一方、賠償を受け取る国にとっては、戦争で破壊された国の復興を日本の技術で進められるという利点がありました。
この役務賠償は、フィリピン、インドネシア、ビルマ(現ミャンマー)、南ベトナムとの間で実施されました。
また、第14条(b)では、この条約で決められた以外の連合国のすべての賠償請求権は、日本が放棄することも定められました。
つまり、連合国はこれ以上の賠償を日本に求めない、ということです。
さらに、占領期間中にかかった占領軍の費用についても、日本に請求しないことが決められました。
ちなみに、講和会議の場では、セイロン(現スリランカ)の代表が「憎しみは憎しみによっては消えず、慈愛によってのみ消える」という仏陀の言葉を引用し、日本への賠償請求権を放棄する演説を行い、日本の国際社会復帰を後押しする場面もありました。
このように、日本の賠償問題は「原則無賠償(現金賠償なし)」と「役務賠償」という形で、現実的な解決が図られたのです。
わかりやすいサンフランシスコ平和条約の影響と問題点

- 全面講和ではなかった?片面講和の理由
- 同時に結ばれた日米安全保障条約とは
- 領土問題の火種が残った?
- 不参加国との国交回復はどうした?
- 現代につながる「主権回復の日」
全面講和ではなかった?片面講和の理由
サンフランシスコ平和条約は、日本の独立を回復させた重要な条約ですが、一つの大きな問題を抱えていました。
それは、第二次世界大戦で日本と戦ったすべての国が参加し、署名したわけではなかった、という点です。
本来であれば、戦争に関わったすべての国と同時に講和を結ぶ「全面講和」が理想でした。
しかし、現実にはソビエト連邦(ソ連)や中国といった主要な交戦国が参加しなかったため、この条約は「片面講和」、あるいは「多数講和」と呼ばれることになったのです。
なぜ全面講和が実現しなかったのか、理由は大きく三つあります。
一つ目は、前述の通り「冷戦」の決定的な影響です。
アメリカを中心とする西側陣営は、日本を早期に独立させて自分たちの陣営に組み込むことを最優先しました。
一方、ソ連を中心とする東側陣営は、日本が西側の軍事拠点となることを強く警戒し、講和条約に反対の立場を取りました。
両陣営の思惑が真っ向から対立したため、全員が納得する形での講和は不可能だったのです。
二つ目は、「中国代表権問題」です。
当時、中国には二つの政府が存在していました。
一つは、共産党が率いる「中華人民共和国」(大陸側)、もう一つは、内戦に敗れて台湾に逃れた国民党が率いる「中華民国」(台湾側)です。
アメリカや日本は中華民国を、ソ連やイギリスは中華人民共和国をそれぞれ正統な政府として承認しており、どちらを講和会議に招待するかで連合国間の意見がまとまりませんでした。
この対立を解決できなかった結果、アメリカは苦肉の策として、中華人民共和国と中華民国のどちらも会議に招待しない、という決定を下しました。
日本の戦争において、最も長く、甚大な被害を受けた相手である中国が、講和会議に参加できないという異例の事態となったのです。
三つ目は、ソ連や一部アジア諸国の反対です。
ソ連、そして同じ東側陣営のポーランド、チェコスロバキアは、講和会議自体には参加しました。
しかし、ソ連は、中国が参加していないことや、条約の内容(特に、独立後も米軍が日本に駐留し続けること)に強く反対し、条約への署名を拒否しました。
また、アジアの国々の中でも、インドとビルマ(現ミャンマー)は、中国が排除されたことや、沖縄などがアメリカの統治下に置かれる条約内容は日本の完全な独立とは言えないとして、会議自体に参加しませんでした。
こうした背景から、日本国内でも「全面講和論」と「単独講和論」という大きな論争が起きました。
吉田茂首相ら政府は、ソ連や中国の参加を待っていては独立がいつになるか分からないとして、アメリカなど西側諸国と先に講和を結ぶ「単独講和(多数講和)」を現実的な選択として進めました。
これに対し、多くの学者や野党(日本社会党など)は、ソ連や中国を抜きにした講和は真の平和とは言えず、日本が西側の軍事ブロックに組み込まれて再び戦争に巻き込まれる危険があるとして、「全面講和」を強く主張しました。
結果として、吉田内閣は単独講和の道を選び、サンフランシスコ平和条約が締結されました。
この「片面講和」という形が、その後の日本の外交や安全保障、さらには領土問題にも長く影響を与え続けることになったのです。
同時に結bれた日米安全保障条約とは
サンフランシスコ平和条約が署名された1951年9月8日、同じサンフランシスコ市内で、もう一つの非常に重要な条約が日本とアメリカの間で結ばれました。
それが「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」、一般に「日米安全保障条約(旧安保条約)」と呼ばれるものです。
この二つの条約は、事実上セットで考えられていました。
平和条約によって日本は独立を回復しますが、当時の日本は1947年に施行された日本国憲法のもとで軍隊を持たず、自国を守る力がほとんどない状態でした。
一方で、世界は冷戦の真っ只中にあり、すぐ隣では朝鮮戦争が続いていました。
独立したばかりの無防備な日本が、ソ連や北朝鮮といった東側陣営の脅威にさらされる危険性があったのです。
そこで、日本の安全を確保する手段として、アメリカ軍に独立後も引き続き日本国内に駐留してもらい、日本の防衛を担ってもらう、という取り決めが必要になりました。
これが日米安全保障条約が結ばれた主な理由です。
平和条約の首席全権は吉田茂首相以下6名でしたが、この安保条約には吉田首相が一人で署名しました。
この条約は国内での評判が良くないことを分かっていた吉田氏が、「君たちの経歴に傷をつけたくない」と他の全権に配慮したためだと言われています。
この旧安保条約の主な内容は、以下のようなものでした。
第一に、アメリカ軍が日本国内及びその周辺に駐留する権利を日本が認めることです。
条約の前文では、日本が独自の防衛力を持つまでの暫定的な措置として、アメリカが日本の防衛に協力することがうたわれました。
第二に、日本はアメリカ軍の駐留のために、基地を提供することに同意しました。
これにより、占領軍の基地が、独立後は安保条約に基づく「米軍基地」として存続することになりました。
ただし、この旧安保条約にはいくつかの大きな問題点も含まれていました。
一つは、アメリカ軍の駐留経費の分担などが明確でなかった点です。
もう一つは、アメリカ側には日本を守る明確な「義務」が記されておらず、あくまで「駐留する権利」が中心だったのに対し、日本側には基地提供の義務があるという「片務的(一方的)」な側面が強かった点です。
さらに最も問題視されたのが、アメリカ軍が「日本国政府の明示の要請があつた場合」に、日本国内の大規模な内乱や騒じょうを鎮圧するために出動できる、という規定があったことです。
これはアメリカが日本の内政に干渉する口実になりかねないと、国内から強い批判を受けました。
これら二つの条約、つまりサンフランシスコ平和条約(独立回復)と日米安全保障条約(米軍駐留)によって、戦後日本の基本的なあり方が決定づけられました。
これを「サンフランシスコ体制」と呼びます。
西側陣営の一員として独立し、経済発展を目指す一方で、安全保障はアメリカに依存するという体制です。
この旧安保条約は、前述のような問題点を抱えていたため、1960年に改定され、現在まで続く「新・日米安全保障条約」へと引き継がれていくことになります。
領土問題の火種が残った?
サンフランシスコ平和条約は、日本の領土範囲を法的に画定するという重要な役割を持ちましたが、その条文の解釈や、条約締結のプロセス自体が、現代の日本が抱える領土問題の大きな火種となってしまいました。
問題が残った理由は、主に三つ考えられます。
第一に、条約に署名しなかった国の存在です。
特にソビエト連邦(ソ連)が署名を拒否したことが、北方領土問題に決定的な影響を与えました。
第二に、条文の記述が曖昧だった点です。
条約では、日本が「どこを放棄するか」は記されましたが、「放棄した領土が、最終的にどこの国に帰属するか」までは明記されませんでした。
第三に、条約の起草過程での経緯が、後の解釈の違いを生んだ点です。
具体的に、現在の領土問題とどう関連しているのかを見ていきます。
北方領土問題
条約第2条(c)で、日本は「千島列島」を放棄すると定められました。
しかし、日本政府は、歴史的に日本の固有の領土であり、千島列島には含まれてこなかった「北方四島(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)」は、この条文で放棄した「千島列島」には含まれていない、という立場を一貫して取っています。
ところが、ソ連(現在のロシア)は、北方四島も「千島列島」に含まれると主張し、現在も実効支配を続けています。
もしソ連がこの条約に署名していれば、その時点で「千島列島」の範囲について交渉する余地がありましたが、ソ連が署名を拒否したため、日本とソ連(ロシア)との間では領土の最終的な合意が得られないまま、問題が先送りされてしまいました。
これが、現在も日ロ間で平和条約が締結できない最大の理由となっています。
竹島問題
韓国政府は、講和条約の草案作成の段階で、アメリカに対し、日本が放棄する領土(第2条(a)の朝鮮関連部分)に「独島(竹島)」を含めるよう強く要請しました。
しかし、アメリカ政府は1951年8月の「ラスク書簡」と呼ばれる公式回答で、「我々の情報によれば、独島(竹島)は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にある。この島が朝鮮によって領有権を主張されたという記録はない」として、韓国の要請を明確に拒否しました。
その結果、最終的な条約の条文には、竹島に関する記述は一切含まれませんでした。
日本政府はこれを、竹島が日本の領土であることが認められた証左であると解釈しています。
しかし、韓国は条約が発効する直前の1952年1月、一方的に「李承晩(イ・スンマン)ライン」という海洋主権宣言を行い、竹島をそのラインの内側に取り込み、実効支配を開始しました。
条約で明確にされなかったことが、後の力による現状変更を許す隙を与えたとも言え、現在に至る日韓の対立点となっています。
尖閣諸島問題
条約の第3条では、沖縄(琉球諸島)がアメリカの施政権下に置かれることが定められました。
当時、尖閣諸島は沖縄の一部として扱われており、この第3条に基づきアメリカの施政権下に入りました。
そして、1972年の沖縄返還協定により、尖閣諸島も沖縄と共に日本に返還されました。
日本はこの一連の流れを当然の措置としています。
しかし、中国と台湾は、沖縄返還が近づいた1970年代に入ってから、尖閣諸島の領有権を公式に主張し始めました。
条約策定時やその後の長い期間、異議を唱えてこなかったにもかかわらず、後になって領有権を主張し始めたことが、現在の日中・日台間の深刻な対立の原因となっています。
不参加国との国交回復はどうした?
サンフランシスコ平和条約は「片面講和」であったため、日本は独立を回復した後も、条約に参加しなかったり、署名を拒否したりした国々とは、法的に戦争状態が続いたまま、あるいは国交がない状態のままでした。
独立後の日本政府にとって、これらの国々と個別に交渉し、国交を正常化していくことは、国際社会への完全な復帰を果たすための重要な外交課題となりました。
まず、講和会議に不参加だったアジアの国々との関係改善が急がれました。
会議に招待されなかった中華民国(台湾)とは、サンフランシスコ平和条約が発効したまさにその日、1952年4月28日に「日華平和条約」を締結しました。
これにより、日本は台湾の中華民国政府を中国の正統な政府として承認し、戦争状態を終結させました。
会議への参加を辞退したインドとは、1952年6月に「日印平和条約」を締結します。
インドは日本への賠償請求権を放棄しました。
同じく不参加だったビルマ(現ミャンマー)とも、1954年に「日本ビルマ平和条約及び賠償・経済協力協定」を結び、賠償問題と国交正常化を同時に解決しました。
また、会議には署名したものの、国内の批准(議会の承認)が遅れていたインドネシアとも、1958年に「平和条約」と「賠償協定」を締結しています。
一方、大国であるソ連と中国との国交回復は、冷戦の影響もあり、より複雑な道のりをたどりました。
条約への署名を拒否したソビエト連邦(ソ連)とは、その後も厳しい対立関係が続きました。
しかし、1950年代半ばになると、日本国内での国交回復を求める声や、日本の国連加盟問題(ソ連が拒否権を持っていた)もあり、交渉が本格化します。
1956年、「日ソ共同宣言」が調印されました。
これにより、両国間の戦争状態の終結と国交の回復が合意されました。
ただし、これは正式な「平和条約」ではありませんでした。
北方領土問題が解決しなかったため、「平和条約締結後に歯舞群島と色丹島を引き渡す」という内容にとどまり、領土問題は先送りされたのです。
この宣言により、日本は同年にソ連の支持を得て、念願の国際連合加盟を果たしました。
会議に招待さえされなかった中華人民共和国(中国)との間には、非常に長い間、国交がありませんでした。
日本は台湾の中華民国と国交を結んでいたためです。
しかし、1970年代に入り、アメリカと中国の関係が劇的に改善する(ニクソン訪中)と、日本も中国との国交正常化に踏み切ります。
1972年、田中角栄首相が訪中し、「日中共同声明」が発表されました。
日本は中華人民共和国を「中国の唯一の合法政府」として承認し、国交を正常化しました。
これに伴い、台湾との「日華平和条約」は終了し、断交することになりました。
その後、1978年には「日中平和友好条約」が締結されました。
また、会議に招待されなかった韓国(大韓民国)とは、1951年から交渉が始まりましたが、竹島問題や賠償(請求権)問題、在日朝鮮人の法的地位などをめぐり、交渉は何度も中断し、非常に難航しました。
最終的に、1965年に「日韓基本条約」が結ばれ、ようやく国交が正常化されました。
このように、サンフランシスコ平和条約で残された課題は、独立後の日本が十数年、あるいはそれ以上をかけて一つ一つ解決していく長いプロセスの始まりでもあったのです。
現代につながる「主権回復の日」
「主権回復の日」とは、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本が連合国軍の占領から脱して独立を取り戻した、1952年4月28日を記念する日を指します。
この日は、法的に日本の「主権」が回復した日であり、戦後の日本が国際社会の一員として新たなスタートを切った、非常に象徴的な節目です。
この「4月28日」をどのように捉えるかについては、実は現代の日本においても、様々な議論や複雑な感情が入り混じっています。
2013年4月28日、条約発効から61年を迎えたこの日、当時の第2次安倍晋三内閣は、政府主催による「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」を初めて開催しました。
この式典は、日本の独立の意義を国民全体で再確認し、戦後の歩みを振り返るとともに、未来への決意を新たにする目的で開かれたものです。
この動きは、日本が占領体制から脱却した歴史的な日を正当に評価し、国家としての自覚を促すものだとして、保守層を中心に強く支持されました。
しかし、この「主権回復の日」を政府主催で「祝う」ことに対しては、強い批判や反対の声も上がりました。
その最大の理由は、沖縄の存在です。
1952年4月28日は、日本本土にとっては確かに主権が回復した「喜びの日」だったかもしれません。
しかし、前述の通り、サンフランシスコ平和条約第3条によって、沖縄(および小笠原諸島)はこの日をもって日本本土から切り離され、引き続きアメリカの施政権下に置かれることが決定づけられた日でもあります。
沖縄の人々にとって、この日は独立ではなく、むしろ日本から見捨てられた「屈辱の日」として記憶されているのです。
沖縄が本土に復帰できたのは、それから実に20年後の1972年5月15日でした。
そのため、沖縄県民からは「沖縄の苦難を無視して、本土だけが主権回復を祝うのは受け入れられない」という強い反発の声が上がりました。
2013年の政府式典の際も、沖縄県選出の国会議員の多くが抗議のために欠席する事態となりました。
また、沖縄の問題だけでなく、この日の独立が「片面講和」であったことや、日米安全保障条約によって米軍基地が日本全土に残り続ける「サンフランシスコ体制」が始まった日であることも、祝賀に否定的な見方を生む理由となっています。
反対する人々から見れば、この日はアメリカへの軍事的な従属が確定した日であり、「真の主権回復とは言えない」というわけです。
このように、「主権回復の日」という一つの日付をめぐる認識の違いは、70年以上が経過した現代においても、なお解決されていない「戦後」の問題、特に本土と沖縄の間に横たわる歴史認識の溝や、基地問題のあり方を象徴していると言えます。
サンフランシスコ平和条約を学ぶことは、単なる過去の歴史を知ることではなく、現代の日本社会が抱える課題の「原点」に触れることでもあるのです。
サンフランシスコ平和条約について、わかりやすく総まとめ
ここまでサンフランシスコ平和条約について詳しく見てきましたが、最後に重要なポイントをまとめて振り返ってみましょう。
この条約は、戦後の日本がどのようにして独立を回復し、国際社会に復帰していったのかを理解するための原点とも言えるものです。
- サンフランシスコ平和条約は、第二次世界大戦を法的に終わらせるための「講和条約」です。
- 1951年9月8日に署名され、翌1952年4月28日に発効(効力を持つこと)しました。
- この条約の発効により、約7年間続いたGHQによる占領が終わり、日本は「主権」を回復しました。
- 当時は「冷戦」の真っ只中で、朝鮮戦争も勃発しており、アメリカが日本を西側陣営の同盟国とするため締結を急いだ、という背景があります。
- 日本の独立と主権回復が認められ、同時に国連憲章に基づく自衛権(個別的・集団的)を持つことも承認されました。
- 内容には、朝鮮の独立承認、台湾・澎湖諸島、千島列島、南樺太などの領土を「放棄」することが含まれています。
- 沖縄と小笠原諸島は「放棄」ではありませんでしたが、日本本土から切り離され、アメリカの施政権下に置かれました。
- 戦争賠償については、日本の経済力を考慮し、現金での支払いは原則免除され、「役務賠償」(技術や労働力の提供)という形が取られました。
- ただし、この条約は日本と戦った全ての国が参加した「全面講和」ではありませんでした。
- ソビエト連邦(ソ連)は会議に参加したものの署名を拒否しました。
- また、中国(中華人民共和国・中華民国とも)は会議に招待されませんでした。
- このように主要な国が参加しなかったため、「片面講和(多数講和)」と呼ばれています。
- 条約とまさに同じ日、独立後も米軍が日本に駐留し続ける根拠となる「日米安全保障条約(旧安保)」も結ばれました。
- 領土の範囲に関する条文の解釈などをめぐり、現代まで続く北方領土問題や竹島問題などの「火種」が残る形になりました。
- 条約が発効した4月28日は、本土にとって「主権回復の日」ですが、アメリカ統治下に残された沖縄にとっては「屈辱の日」とも呼ばれています。
このように、サンフランシスコ平和条約は、日本の独立を決定づけると同時に、その後の日本の安全保障や領土問題、沖縄との関係など、現代につながる多くの課題を生み出すきっかけともなった非常に重要な条約です。
参考サイト