高校での日本史の選択科目に「日本史探究」が登場したことで、「これまでの日本史Bと何が違うの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、大学入試や共通テストを見据えて科目選択をする高校生や保護者の方にとって、「どっちが難しいのか」「どちらが進路に合っているのか」はとても気になるポイントです。
この記事では、「日本史探究と日本史Bの違い」をテーマに、授業の内容や教科書の構成の違い、導入された時期(いつから)などをわかりやすくまとめています。
また、科目ごとに向いている学習スタイルや、入試で有利になるパターン、おすすめの参考書なども詳しくご紹介。
暗記量や思考力の違いをふまえて、あなたにとって最適な選び方をお伝えします。
迷いやすい選択だからこそ、ポイントを押さえて納得のいく判断をしたいところ。
この記事を読むことで、日本史探究と日本史Bの違いがクリアになり、自信をもって科目選択ができるようになります。
この記事を読むとわかること
- 日本史探究と日本史Bはどっちが難しいか
- それぞれの教科書や授業の内容の違い
- 共通テストや大学入試で必要となる科目の選び方
- おすすめの参考書や学び方の違い
日本史探究と日本史Bの違いを分かりやすく解説
- 日本史探究と日本史Bはどっちが難しい?
- 日本史探究と日本史Bの授業内容の違い
- 日本史探究と日本史Bの教科書の構成を比較
- 日本史探究と日本史Bの参考書おすすめ比較
- 日本史探究と日本史Bはどっちが暗記量が多い?
日本史探究と日本史Bはどっちが難しい?
一般的に、「日本史探究」のほうが難易度は高いとされています。
ただし、その難しさの種類が「日本史B」とは異なるため、どちらが自分にとって学びやすいかは、学習スタイルや思考の傾向によって変わってきます。
「日本史B」は、時代ごとの出来事や人物、政治制度、文化などを体系的に覚えていく、いわば“知識のインプット型”の学習が中心です。
一方で、「日本史探究」は、知識を前提としたうえで問いを立て、自ら考察し、資料や史料をもとに論理的に結論を導き出すといった“アウトプット型・思考型”の学びが求められます。
例えば、日本史Bでは「明治維新とは何年に起きたか」を問われる場面が多いですが、日本史探究では「明治維新はなぜ必要だったのか」「その変化は民衆にどう影響を与えたのか」といった問いに答える必要があります。
つまり、単なる知識だけでは対応しきれない、論理的思考や読解力、表現力が求められるのです。
さらに、日本史探究では授業内に発表・ディスカッションなどの活動も多く、調べ学習やグループワークなどを通じて理解を深めていくアクティブラーニング型の授業も増えています。
このような授業スタイルに苦手意識がある人にとっては、日本史Bより難しく感じるかもしれません。
逆に、暗記に自信がないけれど考察やディスカッションが得意な人にとっては、日本史探究の方が「やりがいがある」と感じることもあります。
日本史探究と日本史Bの授業内容の違い
「日本史探究」と「日本史B」の授業内容は、学ぶ範囲こそ似ていますが、学び方や重点の置き方に明確な違いがあります。
特に、「日本史探究」は単なる知識習得を超えて、思考力・判断力・表現力を育むことを目的とした授業設計になっています。
まず、日本史Bでは古代から現代までの歴史的事実を系統的に学び、各時代の政治・経済・文化・外交などを詳細に覚えていく授業です。
年表や流れを意識しながら、人物名や出来事の背景などを整理し、知識を広く深く積み上げていくスタイルが中心になります。
それに対して日本史探究は、「歴史総合」の学習を踏まえた上で、あるテーマについて深く考察する授業が展開されます。
例えば「江戸時代の都市文化の形成」「明治期の教育制度とその影響」など、テーマに基づいて問いを設定し、生徒自ら資料を読み解いて考察するというプロセスを重視します。
このような探究的な活動は、単に「知る」だけでなく、「考える」「伝える」学びへとつながっていきます。
また、日本史探究の授業では、地図や図表、風刺画などのビジュアル資料や、当時の一次史料を使って考察を行うことも多くなります。
その結果、授業は一方向的な講義ではなく、生徒同士の意見交換やプレゼン、ディスカッションを含む双方向型の学びになる傾向があります。
日本史探究と日本史Bの教科書の構成を比較
日本史探究と日本史Bの教科書は、構成やアプローチの方法に大きな違いがあります。
両者の目的や学習目標に合わせて、編集方針も異なっているためです。
日本史Bの教科書(例:山川出版社『詳説日本史B』)は、年代順に通史的に構成されています。
「古代」→「中世」→「近世」→「近代」→「現代」と時代を追いながら、政治や文化、外交などの出来事を網羅的に記述していきます。
各節には図表や写真、コラムもありますが、基本は「流れ」を追っていくための参考書としての性格が強く、知識整理に特化した作りです。
一方、日本史探究の教科書(例:山川出版社『日本史探究』)は、テーマ別・課題別の構成になっています。
時代をまたいで「問い」や「課題」を深掘りするユニットが用意され、「なぜその制度が必要だったのか」「どのように社会が変化したのか」といった探究的な視点で進んでいきます。
そのため、章の始めには必ず「探究する問い」が提示され、それに対する資料や情報を読みながら、自分の意見を構築していく構成です。
また、探究の教科書では、本文だけでなく資料の読み取りや考察が求められるコーナーが多く、文章量や史料の種類も多様です。
その分、読みごたえはありますが、読み飛ばしてしまうと理解が浅くなりやすいという側面もあります。
このように、同じ歴史を扱っていても、知識の整理を重視する日本史Bと、考察・発信まで踏み込む日本史探究では、教科書の構成が大きく異なります。
日本史探究と日本史Bの参考書おすすめ比較
日本史探究と日本史Bは学習スタイルが異なるため、それぞれに適した参考書選びが重要です。
目的や使用場面に応じて、選ぶべき書籍も変わってきます。
まず、日本史Bの場合は、暗記や通史の理解に強い参考書が役立ちます。
たとえば『金谷の日本史「なぜ」と「流れがわかる本」』は、講義形式で日本史の流れを丁寧に解説しており、初心者にも読みやすい構成です。
また、山川出版社の『詳説日本史』は教科書としても有名で、難関大志望者にとっては標準的な知識を網羅できる王道の一冊といえます。
一方で、日本史探究では、考察や探究学習に使える教材が求められます。
具体的には『探究日本史ワークブック』や、StudyValleyが提供する「探究ワークシート一式」など、資料分析や思考整理に使えるテンプレート系教材が有効です。
また、『日本史探究 詳説日本史』(山川)は、考察に適した資料や記述が多く、探究活動における調べ学習や論述力強化にも活用できます。
参考書選びのポイントとしては、日本史Bでは「体系的な通史理解と知識の整理」、日本史探究では「資料活用と論理的な思考練習」にフォーカスしたものを選ぶことです。
学習の目的が異なるため、互換性があるように見えて、使い方は大きく変わってくる点に注意しましょう。
日本史探究と日本史Bはどっちが暗記量が多い?
暗記量という視点で比較すると、一般的には「日本史B」の方が暗記すべき情報量は多いとされます。
ただし、日本史探究では知識を活用する力が求められるため、「覚えて終わり」にはなりません。
日本史Bは、古代から現代に至るまでの日本の歴史を網羅的に学ぶことが目的です。
そのため、人物名、年号、出来事、文化財、法令名など細かい用語が大量に登場し、丸暗記しなければ対応できない問題も少なくありません。
特に、共通テストや私立大学の選択問題では、知識を正確に記憶しておくことがスコアに直結するケースが多く見られます。
一方、日本史探究では、知識を前提に「問いを立てて考える」「資料を根拠に意見を述べる」ことが重視されます。
このため、一つひとつの用語を丸暗記するのではなく、その背景や意味、相互の関係性まで理解する必要があります。
覚える量はBに比べて少ないように見えても、その分、知識の深さと活用力が問われるのが特徴です。
また、探究では授業中に自らテーマを設定したり、レポートや発表を行う場面が多く、知識をストックするだけでは対応できません。
たとえ用語数がBより少なくても、「なぜそうなったか」「どう説明するか」を常に考える必要があるため、負担感としては決して軽いわけではないのです。
このように考えると、暗記量そのものは日本史Bの方が多いですが、深い理解と活用力が求められる日本史探究にも、別の意味での“学習負荷”があります。
単に覚えるのが得意な人にとってはBが向いていますが、理解して使いこなす力に自信がある人は探究型の学びにも適応できるでしょう。
日本史探究と日本史Bの違いと選び方のポイント
- 共通テストでは日本史探究と日本史Bどちらが必要?
- 大学入試で有利なのは日本史探究と日本史Bどっち?
- 日本史探究と日本史Bは進路でどう選ぶべき?
- 日本史探究と日本史Bはいつから変わった?
- 探究学習の特徴とアクティブラーニング要素
- 日本史Aからの接続は探究とBでどう違う?
共通テストでは日本史探究と日本史Bどちらが必要?
共通テストで必要とされるのは「日本史B」であるケースがほとんどです。
2025年度の共通テストにおいても、「日本史探究」は選択科目としては設定されていません。
そのため、共通テスト対策として日本史を選ぶ場合は、「日本史B」の履修が前提となります。
これは、大学入試センターが定める共通テストの出題範囲が、旧学習指導要領に基づいた教科をベースとしているためです。
現在の高校3年生が高校に入学した時点では、まだ完全に「探究型カリキュラム」へ移行しておらず、過渡期にあるため、出題内容も旧カリキュラムに準拠しています。
ただし、注意すべき点として、将来的には「日本史探究」が共通テストの対象科目に置き換わる可能性もあります。
特に、2025年度以降の高校入学生については、新学習指導要領に完全対応する形で「探究科目」の学習が主軸となっていくため、状況は徐々に変わっていくと考えられます。
したがって、現時点で共通テスト対策を考えている高校生にとっては、「日本史B」を選択することが、試験制度に適合した選択といえるでしょう。
受験年度や志望校によって要件が変わる可能性もあるため、志望大学の最新情報を確認しながら履修科目を選ぶことが重要です。
大学入試で有利なのは日本史探究と日本史Bどっち?
大学入試での有利・不利を比較する際、「日本史B」が依然として優位である場面が多く見られます。
特に国公立大学の一般入試や共通テストを受ける場合には、日本史Bの知識が直接問われることが多く、その対応力が合否を左右します。
多くの大学はまだ「日本史探究」を一般入試の出題対象科目に指定していないため、探究で学んだ内容だけでは、十分に対応しきれない可能性があります。
たとえば、京都大学や一橋大学などの論述型試験では、知識と論理的思考の両方が求められますが、ベースとなる通史の知識が不足していると、思考力を発揮する以前に問題文を正しく理解できないこともあります。
一方で、推薦入試や総合型選抜では、日本史探究で培った「探究力」や「表現力」が評価されるケースも増えています。
例えば、探究活動を通じて作成したレポートや発表資料を活用し、小論文や面接で自分の関心や学習意欲をアピールできる場合は、探究型学習の経験が大きな強みになります。
つまり、入試方式によって有利になるポイントが異なります。
一般入試や共通テスト対策では「日本史B」が有利ですが、探究的な学びを重視する推薦入試では「日本史探究」が活きる場面もあります。
どの入試方式を目指すかに応じて、科目選択の戦略を考える必要があります。
日本史探究と日本史Bは進路でどう選ぶべき?
進路を考慮して科目を選ぶ場合、「大学進学の有無」と「入試の形式」を軸に判断するのが効果的です。
なぜなら、日本史探究と日本史Bは目的や学習スタイルが大きく異なるため、将来の目標によって適切な選択が変わってくるからです。
まず、大学進学を希望しており、特に国公立大学や私立大学の一般入試を目指している場合は、「日本史B」を選ぶ方が適しています。
通史を網羅的に学び、知識量を蓄積できる日本史Bの内容は、共通テストや大学の個別試験に直結しているため、試験対策としても有効です。
一方で、推薦入試や総合型選抜を視野に入れている生徒、または専門学校・就職を考えている人であれば、「日本史探究」でも問題はありません。
探究では、レポート作成やグループディスカッション、プレゼンなど、アウトプット型の学びが中心となるため、面接や小論文で活用できる実践力が身につきます。
また、理系で日本史を使わない場合や、文理選択後に地歴公民の履修を制限される学校もあります。
このような場合には、学校のカリキュラムや受験の必要性を踏まえて、自分にとって最も合理的な選択をすることが大切です。
つまり、入試に出題されるかどうかだけでなく、自分の進路に合った学び方ができるかどうかという観点から選ぶことが重要です。
「受験に使うからB」「学びを深めたいから探究」といった明確な基準をもとに判断すると、後悔のない選択ができるはずです。
日本史探究と日本史Bはいつから変わった?
「日本史探究」が正式に導入されたのは、2022年度から始まった新しい学習指導要領に基づくカリキュラムからです。
それに伴い、従来の「日本史A」と「日本史B」という分け方から、「歴史総合(共通必履修)」と「日本史探究(選択)」へと再編が行われました。
この改革の背景には、これまでの知識詰め込み型の授業から脱却し、思考力や表現力、主体性を育てる教育への転換があります。
文部科学省が進める教育改革の一環として、「何を学ぶか」だけでなく「どう学ぶか」を重視する方針にシフトしたのです。
2022年度に高校1年生になった世代から、新カリキュラムが全面適用されました。
このため、2022年以降に高校に入学した生徒は、「歴史総合」を1年次に学び、その後「日本史探究」もしくは「世界史探究」などの探究科目を選択する流れになっています。
つまり、「日本史探究」は比較的新しい科目であり、過渡期にある今は学校によって指導内容や教材に差がある場合もあります。
そのため、保護者や受験生が情報収集する際には、学年やカリキュラムの移行時期に注意することが重要です。
探究学習の特徴とアクティブラーニング要素
探究学習の最大の特徴は、「問いを立てて、自ら調べ、考え、発表する」というプロセスに重きを置いている点です。
単に知識を受け取るのではなく、自分で課題を見つけ、その答えを導き出す主体的な学び方が求められます。
この学びの中核にあるのが、アクティブラーニングです。
アクティブラーニングとは、教師の一方的な講義ではなく、生徒が能動的に授業に参加する学習方法を指します。
具体的には、グループワーク、ディスカッション、調べ学習、プレゼンテーション、フィールドワークなどがその例です。
例えば、日本史探究の授業では、「なぜ江戸時代に寺子屋が普及したのか?」といった問いをテーマにして、当時の資料や記録、地図などをもとに考察を深める場面がよくあります。
生徒たちは調査を通じて仮説を立て、意見を発表し、クラスで意見交換を行うことで、多角的な視点から歴史を理解する力を養います。
また、発表の場面では、論理的な話し方や資料の使い方、聞き手を意識した説明力も求められるため、表現力やコミュニケーション能力の向上にもつながります。
このように、探究学習では学力そのものだけでなく、社会に出た後にも役立つスキルを総合的に育むことが可能です。
日本史Aからの接続は探究とBでどう違う?
かつての「日本史A」は、近現代を中心に学ぶ歴史科目として位置づけられていました。
これに対して「日本史B」は古代から現代までを広く深く扱う内容であり、両者は補完的な関係にありました。
現在のカリキュラムでは、「日本史A」に相当する役割を持つのが「歴史総合」です。
これは高校1年生で全員が履修する共通科目で、近現代史を中心に世界と日本の関係を俯瞰的に学ぶ内容になっています。
この「歴史総合」を学んだ上で、「日本史探究」や「世界史探究」などに進む形となります。
「歴史総合」から「日本史探究」への接続では、単なる知識の延長ではなく、「問いを立てる力」や「資料を読み解く力」がより重視されます。
生徒は歴史を一方向的に学ぶのではなく、複数の視点や立場を踏まえながら歴史の解釈を深めていく必要があります。
一方、「歴史総合」から「日本史B」へ進むという流れは、基本的には想定されていません。
なぜなら、日本史Bは旧課程の科目であり、新課程では「日本史探究」に一本化されていく方向にあるためです。
つまり、今後の接続関係としては、「歴史総合→日本史探究」が標準的なルートとなり、「日本史B」は過渡期における選択肢の一つにとどまります。
高校での履修選択に際しては、このカリキュラムの流れをしっかり理解しておくことが大切です。
日本史探究と日本史Bの違いをわかりやすく総括
ここでは「日本史探究」と「日本史B」の違いについて、データAでお伝えした情報をもとに、ポイントを整理してまとめていきます。
どちらを選ぶか迷っている方の判断材料としてお役立てください。
- 「日本史B」は通史中心で、知識を系統的にインプットしていく学び方が中心です。
- 「日本史探究」は、テーマを深掘りして自分なりの考えをアウトプットする力が求められます。
- 暗記量は「日本史B」の方が多めで、年号や人物、出来事を幅広く覚える必要があります。
- 「日本史探究」は暗記の量よりも、資料を読み解いて考察する力が重要になります。
- 授業スタイルとしては、「日本史B」は講義型が多く、「日本史探究」は発表やディスカッションが多く取り入れられています。
- 教科書の構成も異なり、「日本史B」は時系列順、「日本史探究」は課題・テーマ別で展開されます。
- 「日本史探究」では「問いを立てて調べる→考察する→表現する」といった探究活動が多くなります。
- 共通テストでは、現時点では「日本史B」の履修が前提となっています。
- 大学入試の一般選抜では「日本史B」の方が出題対象になることが多く、受験には有利です。
- 一方で、「日本史探究」は推薦入試や総合型選抜でのレポートや面接に活用しやすい傾向があります。
- 「日本史探究」は、アクティブラーニングや探究的学びを通じて、表現力・論理力を育てられるのが特徴です。
- 教材や参考書も異なり、「日本史B」は知識整理型、「日本史探究」は資料読解や記述練習向きのものが向いています。
- カリキュラムの変化により、「日本史探究」は2022年度以降の新課程において正式に導入されました。
- 接続の仕組みとしては、高校1年で「歴史総合」を学び、2年以降に「日本史探究」などの選択科目を履修する流れが基本です。
- 学びのスタイルや進路、試験の目的に応じて、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。
このように、「日本史探究」と「日本史B」は学ぶ目的や方法が大きく異なります。
自分の得意・不得意や将来の進路をよく考えながら、より納得のいく科目選択をしていきましょう。
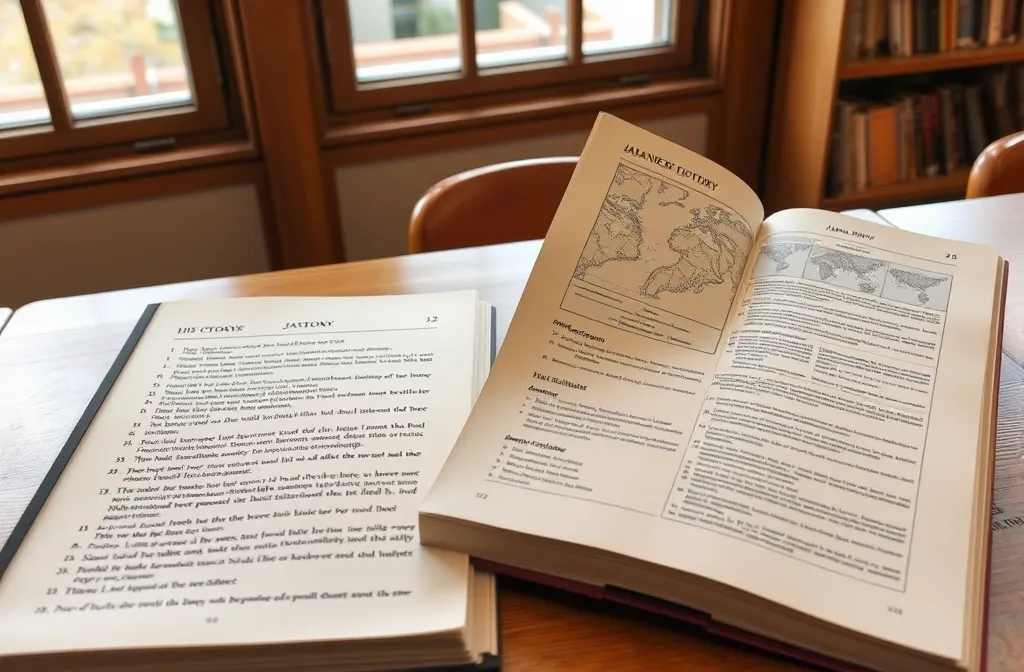
コメント