高校で文系を選んだ多くの方が、一度は悩む「日本史と世界史、どっちがいいの?」という問題。
この記事にたどり着いたあなたは、自分に合った科目を選ばないと後悔するのではないかと感じていませんか?
たしかに、どちらを選ぶかで受験勉強の効率や本番での得点力、さらには将来の進路までも左右される可能性があります。
中には「日本史にすればよかった」「世界史にすればよかった」と選択を間違えたと感じて後悔する声も。
実際、「世界史に向いてない人」や「日本史に向いてない人」には共通する特徴があるため、それを知っておくことは非常に大切です。
また、「どっちが簡単なのか」「楽なのはどっちか」「どっちが難しいか」といった観点も、選ぶ上で気になるポイントですよね。
科目ごとの特性を理解せずに選んでしまうと、学習が思ったよりも“きつい”と感じる原因にもなります。
そこで本記事では、日本史・世界史それぞれの向き不向きを診断しながら、選ぶ際に押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
「どっちがいいか」迷っている方が、自分に合った最適な科目を見つけられるよう、網羅的かつ具体的にまとめました。
この記事を読むと、次の4つのことがわかります
- 日本史と世界史の「向き不向き」の診断ポイント
- 世界史に向いてない人・日本史に向いてない人の特徴
- 「楽なのはどっち?」を含む、各科目の学習負担の比較
- 「どっちが簡単・難しいか」の受験対策としての現実的な判断基準
日本史と世界史の向き不向きを徹底診断

- 診断|あなたが向いている科目はどっち?
- 世界史に向いてない人の特徴とは?
- 日本史に向いてない人の共通点とは?
- 楽なのはどっち?暗記と理解の負担を比較
- どっちが簡単?勉強の始めやすさで判断
- どっちが難しい?共通テスト・二次試験の傾向
診断|あなたが向いている科目はどっち?
高校生が文系進学を決めたとき、まず直面するのが「日本史と世界史、どっちを選ぶべきか?」という悩みです。
選択を誤ると、後々の勉強が苦痛になることもあります。
そこで、まずは自分に合った科目がどちらなのかを診断する視点をいくつか紹介します。
一つ目は「歴史に対する興味の方向性」です。
例えば、戦国時代や幕末に強い興味を持っているなら日本史が向いています。
一方で、ローマ帝国の興亡やフランス革命、冷戦の構造などに興味があるなら、世界史の方が楽しめる可能性が高いです。
興味を持てるかどうかは、勉強を継続するうえで大きなモチベーションになります。
二つ目の診断ポイントは「暗記の得意・不得意」です。
日本史は「狭く深く」が基本で、一国の詳細な出来事や人物を掘り下げて学ぶスタイルです。
そのため、一つひとつを正確に覚えることが求められ、漢字表記の用語も多くなります。
反対に世界史は「広く浅く」で、様々な国の出来事を大まかにおさえることが必要です。
カタカナの用語が中心で、ストーリーとして覚えるのが得意な人に向いています。
また、地理や国際情勢などの背景知識があるかどうかも診断材料のひとつです。
世界史では、時代と地域を横断する学びが求められるため、ヨーロッパやアジア、中東などの国や文化に抵抗がない人が有利です。
日本史は舞台が日本一国に限られるため、地理や国際関係にあまり自信がない人でも学習しやすいといえます。
最後に、試験形式や志望校の入試傾向も含めて判断しましょう。
例えば、私大文系を目指していて基礎から積み上げたいなら日本史。
国公立の論述もあるなら、広範な知識が必要な世界史を選ぶ方が有利なケースもあります。
どちらにも向き不向きがありますが、総合的には「興味がある方」「得意になれそうな方」を選ぶのが成功への近道です。
ぜひ、今回紹介したポイントで自分に合った科目を見つけてみてください。
世界史に向いてない人の特徴とは?
世界史に向いていない人の特徴を理解することで、自分に合った学習科目を選ぶヒントが得られます。
ここでは、具体的にどのような人が世界史に不向きとされるのかを解説していきます。
まず最初に挙げられるのは、「情報を整理するのが苦手な人」です。
世界史では、アジア・ヨーロッパ・アフリカなど多地域の歴史を並行して学びます。
たとえば、同じ19世紀にフランスで革命が起こり、清朝ではアヘン戦争が起きていた、というように時代を超えて各国の流れを整理する力が必要です。
この「ヨコのつながり」が把握できないと、知識が頭の中でバラバラになりがちです。
次に、「カタカナの名前に抵抗がある人」も向いていない傾向があります。
カール5世、アウグスティヌス、ウィルヘルム2世など、カタカナ語が頻出する世界史は、音だけではなく意味や時代背景も一緒に覚えなければなりません。
これが苦手だと、記憶の定着が難しく感じられるでしょう。
さらに、「論理的に物事を積み上げて覚えるのが苦手な人」も注意が必要です。
世界史は単なる出来事の羅列ではなく、宗教改革が産業革命につながり、それが戦争や独立運動へ波及していく…といった因果関係の理解が求められます。
ストーリーとして歴史を捉えられないと、点と点がつながらず暗記効率も落ちてしまいます。
また、「基礎の勉強を早めに終わらせたい人」にとっては不利かもしれません。
世界史は範囲が広く、最初の通史だけでもかなりの時間を要します。
そのため、短期集中型の学習にはやや不向きです。
このように、整理力・カタカナ耐性・論理力・計画性などが世界史学習には必要です。
これらに不安がある人は、他の科目と比較してじっくり検討することが大切です。
日本史に向いてない人の共通点とは?
日本史に不向きな人には、いくつかの共通する特徴があります。
それらを理解しておくと、科目選択の際にミスマッチを防ぎやすくなります。
まず、最も多いのが「漢字が苦手な人」です。
日本史では登場する人物名や用語がすべて漢字で表記されており、記述式の問題では正確な漢字で書けることが前提となります。
「藤原不比等」「聖武天皇」「徳川慶喜」など、読みやすさに比べて書き取りの難易度が高い語句が頻出します。
もし漢字への苦手意識が強い場合、記憶にも時間がかかってしまうでしょう。
次に、「細かい内容を詰めて覚えるのが苦手な人」も注意が必要です。
日本史は「狭く深く」が基本で、同じ幕末でも複数の藩・人物・政策が登場します。
特に近現代史では法改正や政党の変化など、細かい知識の積み重ねが点数に直結します。
こうしたマニアックな情報に抵抗を感じる人にはややハードルが高く感じられるかもしれません。
また、「因果関係よりストーリー性を重視する人」にとっては、日本史はやや退屈に映ることもあります。
というのも、日本史では制度や条文などの記録的な内容も多く、それが続くと飽きてしまう人もいるからです。
映画や小説のような展開を期待している場合は、世界史の方が刺激的かもしれません。
さらに、「中学時代に歴史が嫌いだった人」は一度立ち止まって考える必要があります。
中学校では主に日本史が扱われているため、その時点で苦手だった場合は日本史選択後に後悔する可能性もあります。
このように、日本史は精密な記憶力と集中力、漢字への対応力が求められる科目です。
自分の性格や学習スタイルに合っているかを、しっかり見極めることが大切です。
楽なのはどっち?暗記と理解の負担を比較
日本史と世界史を選ぶうえで、「楽なのはどっち?」と感じるのは当然のことです。
ここでは、暗記量や理解の難しさといった観点から、それぞれの“しんどさ”と“楽さ”を整理して比較していきます。
まず、日本史の特徴として「暗記する内容が細かい」という点が挙げられます。
同じような人物名、年号、政策が多く、特に近代史に入ると内閣の構成や条約の内容、法改正の詳細まで問われます。
また、試験では「細かすぎる問題」が出題されやすく、ちょっとした言葉の違いで正誤が分かれることも珍しくありません。
一方で、日本史は一国に絞った内容であるため、全体の流れを理解するのは比較的簡単です。
中学までの学習内容とも地続きであるため、初学者でもとっつきやすい傾向があります。
つまり、勉強のスタートは楽ですが、深堀りが必要になったときに急にきつくなるのが日本史です。
対して世界史は「広い範囲を浅く学ぶ」スタイルです。
ヨーロッパ、中国、イスラム、アフリカ、アメリカなど、国や文明がバラバラに登場します。
そのため、学習初期は混乱しやすく、「どこの国の話だっけ?」となりがちです。
特にヨコのつながり(同時代に複数の国で何が起こっていたか)を整理する力が必要とされます。
しかし一度この構造に慣れると、世界史は「浅く広く」で済むため、細かい知識に追い詰められることは比較的少なくなります。
また、カタカナ表記が多いぶん、漢字の書き取りに苦労する心配が少ないという点も、気楽に感じられる要素です。
つまり、「最初が楽で後がしんどい」のが日本史、「最初は大変だが後が安定する」のが世界史という傾向があります。
どちらが“楽”かは、自分のペースや学習スタイルに応じて変わるため、始めやすさだけでなく長期的な見通しを立てたうえで選ぶことが大切です。
どっちが簡単?勉強の始めやすさで判断
「どちらが簡単か?」という質問は、実は「勉強を始めやすいのはどちらか?」という問いに置き換えると分かりやすくなります。
その観点で見たとき、日本史は比較的“簡単に感じやすい”科目です。
その理由として、中学校までの歴史教育がほぼ日本史で構成されていることが挙げられます。
弥生時代から江戸時代、明治維新、戦後の復興まで、すでに基礎的なイメージを持っている学生が多いため、復習のような感覚で学習をスタートできます。
加えて、日本語で完結するため、人物や出来事の名前も馴染みがあり、最初の抵抗感が少ないのが特徴です。
一方で、世界史は高校から本格的に学び始める科目です。
知らない国や文化、カタカナの人名、聞き慣れない用語が次々と登場し、最初は混乱する人も少なくありません。
例えば、「ビザンツ帝国」「ムハンマド」「アウグスティヌス」など、名前を聞くだけでとっつきにくさを感じる人も多いでしょう。
さらに、世界史では「時代順に並んでいない」という問題もあります。
地域ごとに学習が進むため、例えば中国史では明代をやっているのに、次のヨーロッパではまだローマ帝国時代、というように時代が前後します。
これを整理できるかどうかが、世界史学習の第一関門になります。
ただし、世界史は慣れてくると一気に学習効率が上がる科目でもあります。
一度通史を終え、全体像を把握できるようになれば、その後の学習はかなりスムーズになります。
こう考えると、「勉強の始めやすさ」に限って言えば日本史に軍配が上がります。
ただし、初期の印象だけで判断するのではなく、最終的にどのくらいのレベルまで学ぶ必要があるのかも考慮して選択するのが賢明です。
どっちが難しい?共通テスト・二次試験の傾向
歴史科目を選ぶ上で、「結局、どっちが難しいのか?」という点は大きな判断材料になります。
ここでは、共通テストと二次試験における傾向と難易度の違いを整理して比較していきます。
まず共通テストについてですが、ここ数年の平均点を見ると、世界史の方がやや高くなる傾向があります。
これは、世界史が比較的「知っていれば解ける」知識問題が多く、読み取りや深い理解を求められる日本史と比べて得点しやすいからです。
一方で、日本史は設問に対して細かい判断が求められるケースが多く、選択肢を見比べる際の精度が問われるため難しさを感じる人が多くなります。
次に、二次試験(特に記述型)での傾向ですが、ここでは逆に日本史の方が厳しい内容になるケースが目立ちます。
難関大学では、日本史において教科書の欄外に書いてあるような事項や、資料集にしか載っていない知識まで出題されることも珍しくありません。
細部への正確な理解が求められるため、「丸暗記だけ」では通用しにくい傾向があります。
一方、世界史の二次試験では、基礎知識をもとに因果関係を述べる記述問題が多くなります。
大まかな流れや構造を理解していれば高得点も狙える反面、論理的に説明できないと得点になりません。
また、資料の読解問題も増加しており、表やグラフを読みながら歴史的背景を説明する力も問われています。
このように、共通テストでは世界史がやや有利、二次試験では世界史も日本史も高難度の出題が想定されますが、特に日本史は深い知識が求められるため、難易度が高く感じられる人も多いようです。
どちらが難しいかは、「どの試験で使うか」「自分がどの程度の理解型か」によって変わります。
難易度だけで選ぶのではなく、自分の得意分野や志望校の出題傾向もあわせて見極めましょう。
日本史と世界史の向き不向きで後悔しない選び方

- 選択を間違えたと感じた人のよくある理由
- 日本史にすればよかったと後悔するケース
- 世界史にすればよかったと後悔する理由とは
- 試験で安定得点できるのはどっちがいい?
- 将来の進路や学部に役立つのはどちらか
- 学校の先生や塾が勧めるのはどちらか
選択を間違えたと感じた人のよくある理由
高校で日本史か世界史を選んだあと、「選択を間違えたかも…」と感じる生徒は少なくありません。
その主な原因は、自分の学習スタイルや理解のタイプと科目の性質が合っていなかったというケースが多く見られます。
まず典型的なのが、「暗記の負担が想像以上に大きかった」というパターンです。
日本史は一つの国の歴史を細かく学ぶ分、1つ1つの出来事について非常に詳細な知識を問われます。
また、似た名前の人物や出来事が多く、混乱しやすいため、「やってもやっても終わらない」と感じる人もいます。
世界史にしても、範囲の広さと各国の複雑な歴史背景を覚えることに圧倒され、「これ全部覚えるのは無理」と途中で後悔する人もいます。
次に多いのが、「自分の興味のない時代や地域が思ったより多かった」というものです。
例えば、幕末や戦国時代に興味があって日本史を選んだものの、縄文時代や平安時代の細かい暗記が苦痛に感じる。
逆に、世界史のローマ帝国に憧れて選んだのに、中東やアフリカの古代史に全く興味が持てず苦しむ、という例もあります。
また、「先生との相性」も無視できない要因です。
授業の進め方や教え方が合わないことで、どんなに好きだった科目でもつまらなく感じてしまうことがあります。
特に世界史では先生の説明力によって理解の深さが変わりやすく、モチベーションに直結します。
加えて、「受験に不利だったと感じる」という声もよく聞かれます。
たとえば、志望校の入試問題が自分の選択した科目よりももう一方の科目の方が解きやすそうだったり、平均点が高かったりすると、選択ミスを意識してしまいます。
これらを総合すると、選択ミスの多くは「自己理解が不十分だった」「情報収集が足りなかった」「指導環境に左右された」の3点に集約できます。
今からでも遅くはありません。
自分の現状を振り返り、必要であれば科目変更も含めた見直しを検討してみましょう。
日本史にすればよかったと後悔するケース
世界史を選んだ生徒の中には、「やっぱり日本史にしておけばよかった」と後悔する人も一定数います。
その背景にはいくつかの共通したパターンがあるため、ここで詳しく紹介しておきます。
まず最も多いのが、「範囲の広さに苦しんだ」というケースです。
世界史はヨーロッパ、中国、アメリカ、中東、アフリカなど、地理的にも文化的にも多様な地域を学ぶ必要があります。
その結果、通史の学習に非常に時間がかかり、テスト範囲が変わるたびに新しい国や文化をゼロから覚えなければならないというプレッシャーに晒されます。
「勉強しても点に結びつかない」と感じるようになると、精神的な負担も大きくなっていきます。
また、「カタカナ用語が多くて混乱した」という声も目立ちます。
たとえば、ルイ14世・ルイ16世のような同じ名前に数字がついた王の区別、イスラム教やキリスト教に関連する専門用語など、耳慣れない言葉が多いことが壁になることがあります。
そうした状況に疲弊し、「日本史の方がまだ覚えやすかったのでは」と感じる生徒も少なくありません。
さらに、「日本文化への理解を深めたかった」という理由で後悔するケースもあります。
日本史は日本人としてのアイデンティティや歴史的背景を知るうえで有意義な科目です。
大学入学後、文学、法学、教育などの分野で日本の近代史が話題に出た際、理解が追いつかず、世界史選択を悔やむという声も聞かれます。
このように、世界史の「情報量の多さ」「用語のとっつきにくさ」「文化的距離感」が原因で後悔するパターンは珍しくありません。
こうした経験を避けるためにも、自分の得意不得意だけでなく、学びたい内容や将来の進路も含めて選択することが大切です。
世界史にすればよかったと後悔する理由とは
日本史を選んだ人の中にも、「やっぱり世界史を選んでおけばよかった…」と感じる場面があります。
こうした後悔には、日本史特有の学習スタイルや受験傾向が関係しています。
一つ目によくあるのが、「あまりにも細かい知識を問われてしんどい」という声です。
特に難関大学を目指す場合、日本史では条文の一部や政策の詳細、マイナーな人物の逸話などが出題されることもあります。
たとえ全体の流れを理解していても、細部の暗記ができていなければ点数に直結しないというフラストレーションが生まれます。
次に挙げられるのが、「思っていたより暗記することが多かった」というケースです。
日本史は範囲が狭い分、逆に深掘りされがちです。
「これも覚えるの?」「この用語、また出たの?」といった細かい反復が求められるため、暗記が得意でない生徒には苦痛に感じることがあります。
また、「グローバルな話題についていけない」という後悔も見られます。
大学進学後、特に国際系の学部や教養科目では、世界史的な知識が当然のように前提として語られることがあります。
たとえば、冷戦の構造やヨーロッパの歴史的背景を知らないと、ディスカッションについていけないこともあります。
「世界史を学んでおけば、もっと理解できたのに…」という声も少なくありません。
加えて、「教科書の構成や資料の選択肢が限られている」という点も後悔の一因です。
日本史は一つの国に特化している分、参考書や資料の種類が偏っていたり、情報のバリエーションが少なく感じることもあります。
世界史のように国ごとの文化や思想を横断的に学べる楽しさに憧れる人も出てきます。
このように、日本史に対する「細かすぎる」「将来に活かしにくい」といった印象から、世界史への再評価が起こることは珍しくありません。
どの科目にも一長一短があることを理解したうえで、自分の学習スタイルや将来の進路と照らし合わせることが後悔を防ぐポイントです。
試験で安定得点できるのはどっちがいい?
受験勉強では、「どれだけ安定して点数が取れるか」がとても重要なポイントです。
知識が身についたとしても、本番でそれを正しくアウトプットできなければ意味がありません。
この視点から、日本史と世界史のどちらがより安定して得点できるかを考えてみましょう。
まず、日本史の特性から見ていきます。
日本史は「縦の流れ」が一貫しており、時代の因果関係が比較的つかみやすい構成になっています。
例えば、鎌倉時代の出来事が室町時代にどう影響したのかなど、連続したストーリーとして記憶しやすいのが強みです。
そのため、一度流れをつかめば、安定的に得点を取れるようになる傾向があります。
ただし、その一方で「重箱の隅をつつくような問題」が出やすいのが日本史の試験です。
細かな政策の違いや人物の詳細、文化史のピンポイントな知識が問われる場面も多く、油断すると失点につながることがあります。
つまり、ミスを減らすには地道な知識の積み重ねと、繰り返しの復習が欠かせません。
一方、世界史は範囲が広く、最初はつまずきやすい科目です。
複数の地域・文明・宗教・民族などを並行して学ぶため、混乱しやすく、知識を横断的に整理する必要があります。
しかし、通史をしっかり終えて全体像をつかめるようになると、設問の傾向が素直であるぶん、点数が安定しやすくなるのが特徴です。
特に共通テストでは、世界史のほうが「資料の読み取り」「正誤判定」などの問題が比較的オーソドックスな傾向にあります。
対して日本史は、細かい文言の違いや設問のひっかけがやや多く、初見の問題で思わぬ失点をするケースがあります。
これらを踏まえると、しっかり準備できる人には日本史が向いており、短期間で確実に点を取りたい人には世界史がやや有利といえるでしょう。
自分の性格や試験に強いタイプを分析したうえで、どちらが「安定的な得点源」になるかを見極めることがポイントです。
将来の進路や学部に役立つのはどちらか
歴史科目の選択は受験対策だけでなく、大学入学後や将来の進路にも影響します。
ここでは、日本史と世界史のそれぞれが将来にどう活かせるのか、進学・就職の観点から考えてみましょう。
まず、日本史が有利に働く場面を挙げてみます。
教育学部、法学部、文学部の中でも特に日本文化や歴史、古典文学などを扱う学科では、日本史の知識が土台になります。
例えば、古文を学ぶ際にその背景となる時代を理解していることで、作品の内容がより深く読み取れるようになります。
また、公務員試験や教員採用試験では、日本史に関する出題がされることも多いため、学んできた知識がそのまま武器になります。
一方で、グローバルな視点を求められる学部や職業に進む場合は、世界史が役立つ場面が増えます。
国際関係学部、外国語学部、経済学部などでは、世界の歴史的背景や文化的相違を知っていることが重要になります。
ビジネスのグローバル化が進むなかで、例えば「なぜフランスとドイツの関係が複雑なのか」や「中東の歴史的対立の根本は何か」といった視点が求められることも少なくありません。
また、社会学や政治学の分野でも、世界史を通して国際的な価値観や宗教観を学んでいることは大きなアドバンテージになります。
最近では「SDGs」や「グローバルシチズンシップ」などが注目される中で、世界史を学んでいる学生はそれに直結する知識を持っていると評価されやすい傾向があります。
このように、日本でのキャリアを重視するなら日本史、国際的な視野を持ちたいなら世界史が活きるケースが多いです。
将来の進路に少しでも見通しがあるなら、それに合った科目選びをすることで、大学以降も学びを有効活用できるでしょう。
学校の先生や塾が勧めるのはどちらか
高校や塾の先生が歴史科目を勧めるとき、実は「どちらか一方を絶対に選ぶべき」と断言することは少ないものです。
それは、どちらの科目にも一長一短があり、生徒のタイプによって合う・合わないがはっきり分かれるからです。
一般的に、高校の先生は「これまでの学習状況」や「得意・不得意の傾向」を見て日本史か世界史をアドバイスします。
例えば、暗記が得意で細かい作業にコツコツ取り組めるタイプの生徒には日本史を勧める傾向があります。
日本史は同じ日本語で学べて馴染みがあり、流れを掴むのが比較的容易なので、短期間でもある程度は得点が狙えます。
一方で、塾の先生や予備校講師の中には「入試対策として世界史を推す」ことが多いのも事実です。
その理由は、世界史のほうが試験問題のパターンが読みやすく、過去問演習との相性が良いため、点数を安定させやすいからです。
また、早慶や難関私大を目指す場合、日本史だと細かい知識勝負になりやすく、知識の差が結果に大きく影響します。
その点、世界史は基礎を固めていれば合格点が取りやすいとされているため、あえて世界史を勧める講師も少なくありません。
加えて、学校のカリキュラムや先生の専門分野にも影響を受けます。
日本史が得意な先生が多い学校では、どうしても日本史の方が手厚く指導されやすくなります。
一方で、世界史を専門とする教師がいる学校では、資料や副教材が充実しており、世界史の授業が楽しく感じられることもあります。
このように、先生がどちらを勧めるかは「生徒のタイプ」「学校の指導体制」「受験校の傾向」によって変わります。
最終的には自分が続けやすいか、興味が持てるかを重視しながら、先生の意見を“参考情報の一つ”として受け止めるのが良い選び方です。
日本史と世界史の向き不向きを総括
日本史と世界史のどちらを選ぶべきか悩んでいる方にとって、「自分に向いているのはどちらか」を判断することは非常に大切です。
ここでは、データAの内容をもとに、日本史と世界史それぞれの向き不向きを総合的に整理しました。
選択ミスを防ぐための15の視点を、箇条書きでまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 歴史に対する興味の方向が、日本の戦国や幕末なら日本史、古代文明や世界の戦争なら世界史が合いやすい。
- 暗記が得意で細かい知識を覚えるのが好きなら日本史向き。
- ストーリーや因果関係で覚えるのが得意なら世界史が合っています。
- カタカナの人物名や地名が苦手な人は、世界史に不向きな傾向があります。
- 漢字の書き取りが苦手な人は、日本史で苦労することが多くなります。
- 複数の国や地域の出来事を同時に整理するのが苦手な人は、世界史は難しく感じやすいです。
- 狭く深く掘り下げるのが好きな人には日本史が向いています。
- 広く浅く多文化を学びたい人には世界史がフィットします。
- 中学の歴史授業に苦手意識がある場合、特に日本史に慎重になる必要があります。
- 勉強のスタートを楽にしたいなら、既に馴染みのある日本史が取りかかりやすいです。
- 勉強の最初は大変でも、後で得点を安定させたい人には世界史が好まれる傾向があります。
- 志望校の入試傾向によっては、論述問題が多い世界史、または詳細知識が問われる日本史の有利・不利が変わります。
- 公務員や教職など、日本の制度を学ぶ進路を目指すなら日本史が活きやすいです。
- 国際関係・外国語系の学部や将来海外で働くことを視野に入れているなら世界史がおすすめです。
- 先生や塾の指導方針や指導体制も選択に影響するため、自分の学習環境も見極めましょう。
このように、日本史と世界史の向き不向きは、「好き・嫌い」だけではなく、興味の方向性、得意不得意、進路、試験傾向など、さまざまな観点で見極めることが重要です。
自分にぴったりの科目を選ぶためにも、これらの視点をひとつずつ照らし合わせてみてください。
関連記事
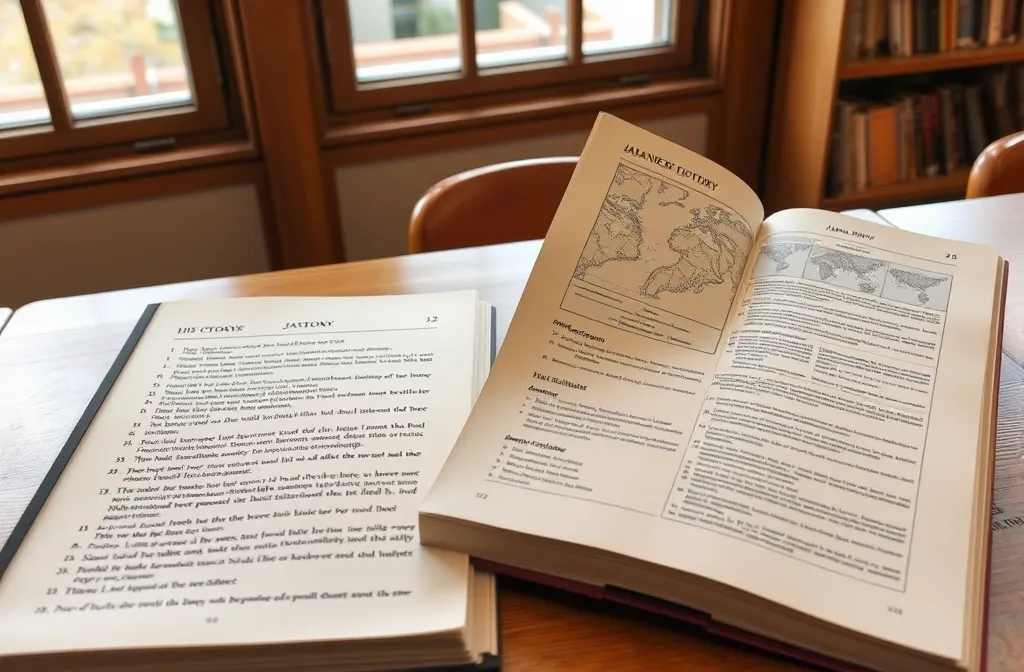
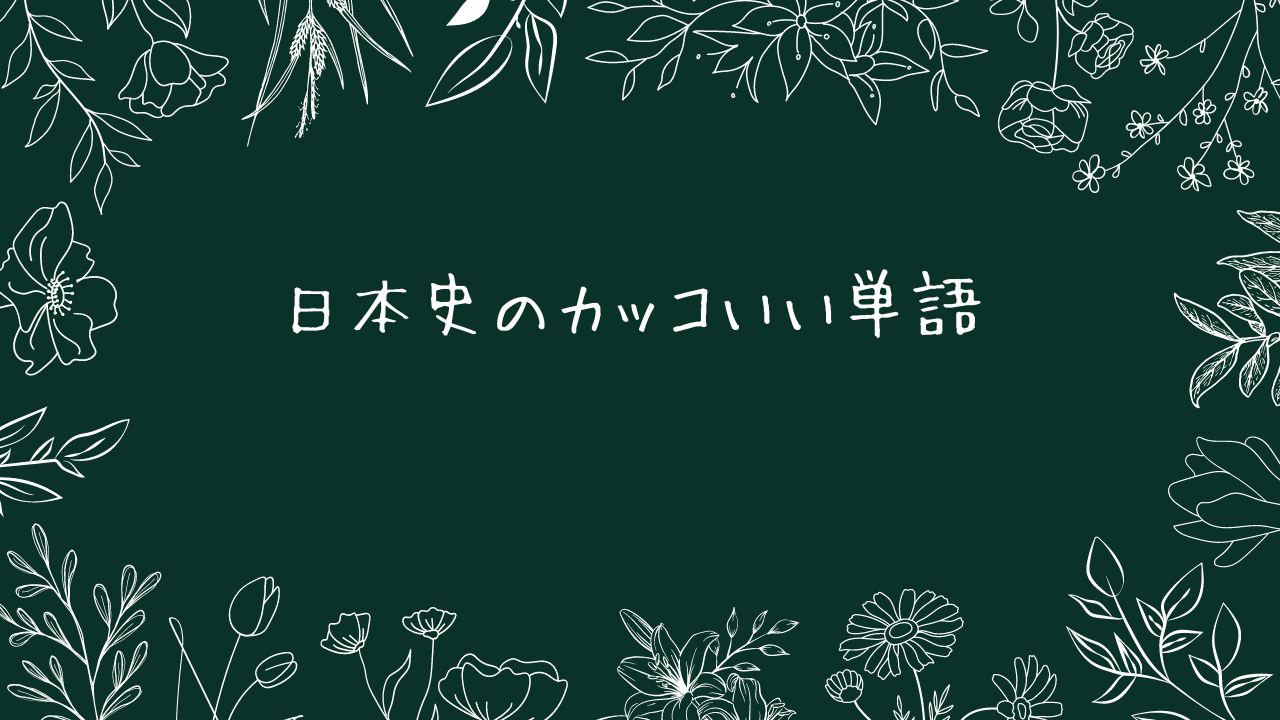
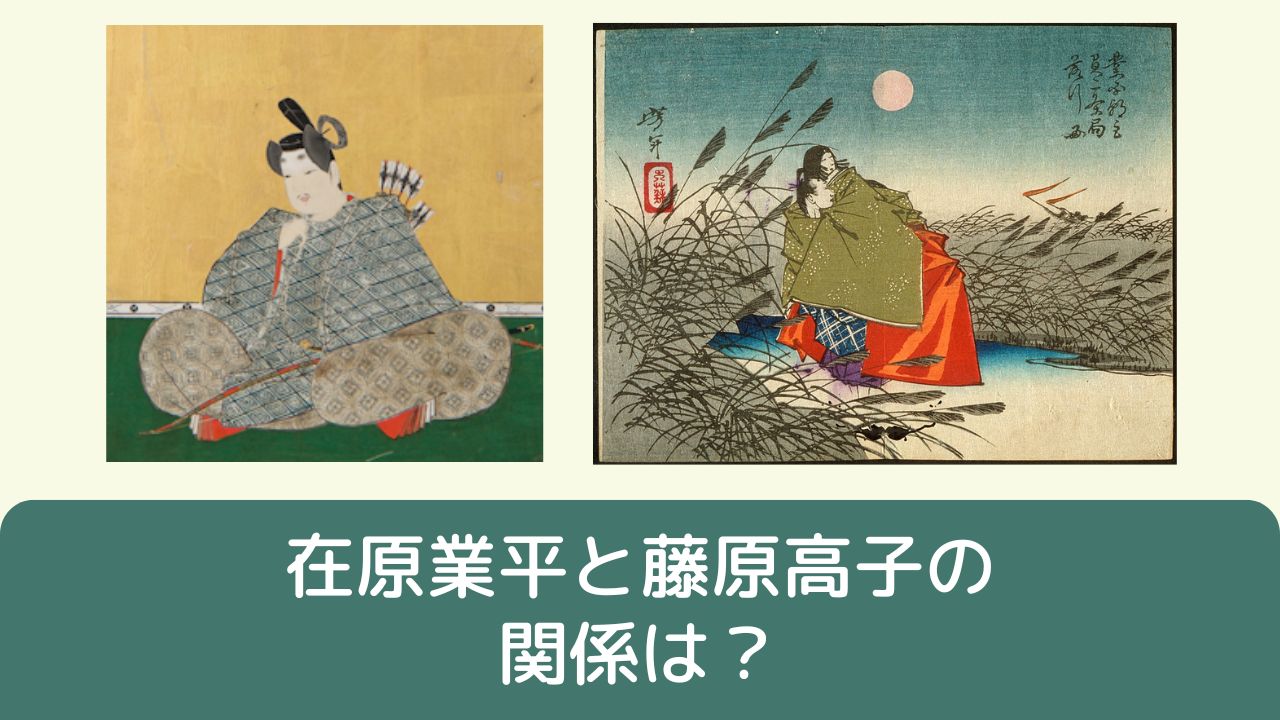
参考サイト


コメント