「中先代の乱」を調べている方の多くは、「結局それってどういう出来事だったの?」と感じているかもしれません。歴史の授業や試験対策では登場するものの、登場人物や背景、なぜ起きたのか、どこで何が起こったのかなど、断片的な情報ばかりで、全体像を簡単に把握するのは意外と難しいものです。
そこで本記事では、「中先代の乱」について歴史に詳しくない方でもスッと理解できるように、流れや背景、結果などを簡単に丁寧にまとめました。北条時行が誰で、足利尊氏とどう関わっていたのか、なぜこの反乱が起き、どのような場所で展開されたのかも一緒に整理しています。
この反乱は、わずか20日ほどの出来事でありながら、のちの南北朝時代や室町幕府の成立にまでつながる重要な転換点でもあります。「誰が起こしたの?」「勝者は誰?」「結果は?」という疑問を持つ方にも役立つ内容を揃えています。
この記事を読むとわかること
- 中先代の乱がなぜ起きたのか
- 北条時行と足利尊氏の関係と立場
- 中先代の乱がどこで起きたのか(場所)
- この乱の結果とその後の影響
中先代の乱をわかりやすく解説する基本情報

- 中先代の乱とは何かを簡単に紹介
- 中先代の乱はなぜ起きたのか?背景を解説
- 中先代の乱は誰が起こした?主導者の狙い
- 北条時行とは?人物像と略歴を簡単に紹介
- 中先代の乱における足利尊氏の動き
中先代の乱とは何かを簡単に紹介
中先代の乱とは、1335年(建武2年)に起こった反乱で、鎌倉幕府を再興しようとした北条時行らが主導した武力蜂起です。わずか20日間ほどの鎌倉支配で終わった短期間の反乱ではありますが、その影響は非常に大きく、のちの南北朝時代の始まりにも関わってきます。
この反乱の舞台は、かつて鎌倉幕府が政治の中心としていた鎌倉地域です。幕府が滅亡した後、新たに始まった「建武の新政」が多くの武士にとって不満の多いものであったため、旧幕府関係者や武士の間には反乱の気運が高まっていました。
その中で登場したのが、北条氏の遺児・北条時行です。彼は信濃国(現在の長野県周辺)で挙兵し、旧幕府関係者の支援を受けながら進軍。鎌倉を守っていた足利尊氏の弟・足利直義の軍を破り、鎌倉を奪還します。
ただし、この支配は長くは続きませんでした。すぐに尊氏自身が大軍を率いて鎌倉に向かい、わずか20日で時行を敗走させます。この短期間の出来事ゆえ、「廿日(はつか)先代の乱」とも呼ばれることがあります。
このように中先代の乱は、短い期間に起きた反乱でありながら、日本の歴史において大きな転換点となった事件です。単なる北条氏の復権を目指しただけではなく、尊氏と朝廷の対立を決定的なものにした点でも注目されます。
つまり、中先代の乱は「旧勢力(北条氏)と新体制(建武政権)」の衝突であり、後の室町幕府成立や南北朝時代の混乱に直接つながる重要な歴史的出来事なのです。
中先代の乱はなぜ起きたのか?背景を解説
中先代の乱が起こった背景には、建武の新政に対する武士の強い不満がありました。鎌倉幕府の滅亡後、後醍醐天皇によって始まったこの新政は、公家主導の政治を目指し、武士たちを軽視する内容が多く含まれていました。
例えば、戦功のあった武士たちへの恩賞が十分に行われなかったり、公家が地方統治に関与したりすることで、現地の武士たちの不満は日に日に高まっていきます。特に、旧鎌倉幕府で重用されていた北条氏の家臣やその関係者にとっては、建武政権は敵そのものでした。
もう一つの要因は、北条氏の残党による復権の動きです。鎌倉幕府の最後の執権・北条高時が滅亡した際、多くの北条一族は自害しましたが、その遺児や弟たちは各地に逃れ、生き延びていました。とくに高時の息子である北条時行は、信濃の諏訪氏に匿われながら、鎌倉再興の機会をうかがっていました。
また、京都では公家の西園寺公宗と北条泰家がクーデターを計画していたことが発覚します。この失敗が、かえって地方の反北朝勢力を刺激する結果となり、信濃の時行らの挙兵につながっていくのです。
これらの背景を踏まえると、中先代の乱は「建武政権に対する抗議」と「北条氏による幕府再興」の両方の性格を持っていたことがわかります。
つまり、新体制に対する旧勢力の反発と、武士社会全体の政治的な不満が重なった結果、爆発的に発生したのがこの中先代の乱だったのです。
中先代の乱は誰が起こした?主導者の狙い
中先代の乱を起こした中心人物は、北条時行という少年武将です。ただし、彼は当時まだ10歳前後であったため、実際に軍の指揮を執ったのは彼を支えた御内人・諏訪頼重でした。
北条時行は、鎌倉幕府の最後の執権・北条高時の子どもです。鎌倉幕府が滅びた後も、時行は信濃の諏訪氏に匿われて生き延びており、北条家の再興を夢見ていました。
諏訪頼重は、信濃国に根を張る武士で、かつて北条氏の家臣でもありました。彼は、北条時行を担いで旧幕府の再興を目指し、建武政権に不満を抱く武士たちを糾合して挙兵します。
彼らの狙いは明確です。かつての政権を再建し、北条氏が再び関東の支配権を握ること。この背景には、建武の新政によって冷遇された旧幕府関係者の怒りや、武士の権益を無視する公家中心の政治への反発があります。
さらに、中央では西園寺公宗らのクーデター計画が露見し、政権の混乱が続いていたため、時行側には「今こそ挙兵の好機」と判断する下地がありました。
このように、中先代の乱を起こした主導者たちは、北条氏の名のもとに勢力を結集し、鎌倉幕府の復興と武士政権の奪還を目指していたのです。
一方で、彼らの行動はあくまで地方に限定されたもので、全国的な支持を得られたわけではありませんでした。そのため、のちに足利尊氏の軍によって短期間で鎮圧される結果となります。
北条時行とは?人物像と略歴を簡単に紹介
北条時行は、鎌倉幕府の最後の執権である北条高時の息子として知られています。1333年に幕府が滅びたとき、まだ幼い年齢だったとされ、多くの一族が自害する中、信濃の諏訪氏によって密かに救われました。
その後、時行は信濃国で成長を続け、1335年に中先代の乱を引き起こす中心人物となります。年齢は諸説ありますが、当時10歳前後だったとされており、実際の指導は諏訪頼重に任されていました。
彼の人物像は、忠誠心が強く、家名を大切にした武家の後継者として描かれます。自ら前線で戦ったという記録は少ないものの、のちに南朝に加わり再び足利氏と戦うなど、執念深く戦い続けた姿が特徴的です。
中先代の乱で鎌倉を一時的に奪還したあとも、逃亡しながら各地で再起を図り、南北朝時代には南朝側の武将として活動します。その後も新田義貞らとともに足利軍と戦いましたが、1352年頃に捕らえられ、翌年処刑されたと伝えられています。
北条時行の生涯は、武士の家に生まれた若武者が滅びゆく一族の誇りを背負い、最後まで戦い続けた物語とも言えます。近年では漫画や書籍などでも再評価され、注目を集める歴史人物の一人です。
中先代の乱における足利尊氏の動き
中先代の乱の中で、足利尊氏は非常に重要な動きを見せました。初めは建武政権の立場に立ちつつも、やがて後醍醐天皇と対立するきっかけを作ってしまう行動へとつながっていきます。
当初、鎌倉を守っていたのは尊氏の弟・足利直義でした。しかし、北条時行の軍が鎌倉へ進軍した際、直義の対応は遅れ、敗北を喫してしまいます。この報告を受けた尊氏は、ただちに出陣を決意します。
尊氏は「総追捕使」と「征夷大将軍」の任命を天皇に求めましたが、拒否されます。それでも尊氏は勅許なしに出陣し、事実上の独断で東へ向かうのです。
この行動が、のちに尊氏が「朝敵」とみなされる大きな理由となります。尊氏は、直義と合流後、相模・駿河・遠江などを転戦しながら進軍し、最終的に中先代の乱を鎮圧。時行の軍を鎌倉から追い出します。
しかし、その後尊氏は、天皇の命令を無視して鎌倉にとどまり、自ら恩賞を与えるなど、独自の政治行動を開始します。これにより、後醍醐天皇との関係は決定的に悪化し、建武政権からの離反、そして南北朝時代へと繋がることになるのです。
このように、中先代の乱における足利尊氏の動きは、単なる反乱の鎮圧にとどまらず、自身の政治的立場を大きく変化させる転機となったものでした。中先代の乱が尊氏の台頭と室町幕府成立の前段階であることは、非常に重要なポイントです。
中先代の乱をわかりやすく時系列で整理

- 中先代の乱の主な戦いと進軍ルート
- 中先代の乱の場所はどこ?現代地名で紹介
- 中先代の乱の勝者と敗者は誰だったのか
- 中先代の乱の結果とその後の影響
- 中先代の乱と建武の新政の関係
- 中先代の乱という名前の意味と由来
- 歴史マンガでも描かれる時代背景とは
中先代の乱の主な戦いと進軍ルート
中先代の乱では、北条時行を中心とする反乱軍が信濃から鎌倉を目指して進軍し、各地で足利方の軍勢と激しい戦いを繰り広げました。時行の軍勢は、諏訪頼重の指導のもと、信濃国から関東に向けて一気に南下していきます。
最初の大きな戦いは、信濃国・青沼(現在の長野県千曲市周辺)で起こりました。ここでは守護である小笠原貞宗の軍と交戦しています。この一戦は時行側にとって序盤の突破口となり、勢いそのままに次々と関東方面へ侵攻しました。
武蔵国に入ると、戦線はさらに拡大します。女影原(現在の埼玉県日高市)では渋川義季らが指揮する鎌倉方の軍を破り、小手指ヶ原(所沢市)では今川範満を撃退。さらに、武蔵府中(東京都府中市)では小山秀朝率いる軍も打ち破られ、足利直義に連なる勢力が次々と敗北していきます。
井出沢(東京都町田市)では、足利直義自身が出陣しますが、ここでも敗北を喫し、直義は成良親王や尊氏の子・義詮と共に鎌倉を退くことになります。この時点で時行側は、鎌倉への道を事実上、制圧した状態になります。
7月25日、ついに北条時行は鎌倉に入城。ここまでの一連の戦いは、信濃から南下して関東の要所を押さえるという、短期間ながらも計画的な進軍ルートによって達成されました。
一方で、8月に入ると形勢は逆転します。足利尊氏が西から出陣し、弟と合流。遠江(現在の静岡県西部)・橋本の戦いを皮切りに、清見関・小夜の中山・箱根・相模川など、各地で戦闘が続きました。これらの戦いで時行軍は次第に劣勢に追い込まれ、8月19日には鎌倉を放棄。ここで中先代の乱は終息します。
このように、中先代の乱は、北から南への進撃と、西からの逆襲という二つの大きな軍事的展開が交差した、短期集中型の戦いでした。
中先代の乱の場所はどこ?現代地名で紹介
中先代の乱は日本の中部から関東南部にかけて広い範囲で展開された反乱であり、現在の地名に照らし合わせることで、より理解しやすくなります。ここでは主な戦場や関連地域を、現代の地名で紹介します。
まず、反乱の出発地点となったのは信濃国、現在の長野県です。とくに諏訪市周辺が中心拠点となっていました。北条時行はここで諏訪頼重らと合流し、挙兵を決断します。
初戦が展開されたのは、長野県千曲市付近の青沼。守護・小笠原貞宗との戦いで勝利を収めたことにより、時行軍は南への進軍を加速させます。
その後、群馬県を抜けて埼玉県に入り、女影原(埼玉県日高市)、小手指ヶ原(所沢市)、府中(東京都府中市)などで戦闘が発生。さらに南下して東京都町田市の井出沢でも激戦が繰り広げられました。
そして、最終目的地である鎌倉(神奈川県鎌倉市)に到達。7月25日、ついに時行軍は鎌倉を奪還します。
反撃に転じた足利尊氏の動きも見ておきましょう。尊氏は京から出発し、途中で三河国(愛知県岡崎市周辺)の矢作宿に拠点を置きました。その後、静岡県湖西市の橋本、掛川市の小夜の中山、さらに駿河区の清見関などで戦闘を行いながら東進します。
尊氏軍と時行軍の最終的な決戦の地は、箱根(神奈川県箱根町)、相模川(厚木市~茅ヶ崎市流域)、辻堂(藤沢市)など。鎌倉周辺での連戦の末、尊氏側が勝利を収めました。
このように、中先代の乱は長野県・埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県など、現代でも人口が多く交通の要衝である地域を舞台にしていたことがわかります。これを踏まえて地図を見ると、歴史の動きがよりリアルに感じられるでしょう。
中先代の乱の勝者と敗者は誰だったのか
中先代の乱の勝者は、最終的に足利尊氏率いる鎌倉将軍府の側でした。敗者はもちろん、北条時行を中心とする旧幕府勢力です。しかしながら、勝者と敗者の構図は単純な「強者が勝った」では語りきれない複雑さも含んでいます。
北条時行軍は序盤、破竹の勢いで信濃から関東を南下し、各地で勝利を重ねて鎌倉を奪還しました。その点では、短期的には時行側が「勝者」に近い結果を出していたとも言えます。特に足利直義を破って鎌倉を支配した20日間は、北条氏の再興に向けた希望が最も膨らんだ時期でした。
しかし、この勝利は長く続きません。尊氏が自ら出陣し、西から東へと急進軍を行ったことで、時行軍は次第に追い詰められます。箱根や相模川での連戦に敗れた時行軍は、鎌倉を放棄し、諏訪頼重をはじめとした主力が自害。これにより、尊氏側が最終的な勝利者となりました。
この戦いを通じて、足利尊氏は武家の支持をさらに集めることに成功し、のちに室町幕府を開くことになります。つまり、軍事的勝利にとどまらず、政治的な影響力でも「勝者」となったわけです。
一方で、北条時行は敗者ではありますが、その後も南朝に属して足利氏と戦い続けました。その意味では、完全に潰された存在とは言い切れず、再起の機会をうかがう粘り強さも見せています。
こう考えると、中先代の乱の勝者は足利尊氏ですが、それ以上に「武士の支持を得た者が政権を握る」という時代の転換点を象徴する結果だったと言えるでしょう。
中先代の乱の結果とその後の影響
中先代の乱がもたらした結果は、単なる反乱の鎮圧にとどまらず、日本の政治体制に大きな変化を与えるものでした。短期的には足利尊氏が勝利し、北条時行の鎌倉再興の夢は潰えましたが、より大きな影響はその後の「南北朝の動乱」につながっていきます。
まず直接的な結果として、建武政権と足利尊氏との関係が決裂します。尊氏は中先代の乱を鎮圧したあと、朝廷の命令に背いて鎌倉に居座り、独自に恩賞を与えるなど、実質的に独立した政権のような振る舞いを見せるようになりました。
これを受けて、後醍醐天皇は尊氏を朝敵と見なし、新田義貞に追討を命じます。これが直接の引き金となって、建武政権と足利氏の全面対決へと発展。結果的に日本の朝廷は南朝と北朝に分裂し、南北朝時代という長期の内乱期が始まることになります。
また、中先代の乱は、旧幕府勢力の反抗の象徴でもありました。北条氏に仕えていた御内人や地方武士たちが、中央の公家政治に不満を持っていたことがはっきりと示されたのです。これは、武士が政治の主導権を求める動きが加速した証拠でもあります。
さらに、乱を通じて足利尊氏の求心力が高まり、武士層におけるリーダーとしての地位が確立されました。これが後の室町幕府設立の土台となったことは間違いありません。
中先代の乱は、鎌倉幕府再興という目標が達成されなかった一方で、結果的に建武政権の限界を露呈させ、次の時代への移行を促す大きな契機となったのです。
中先代の乱と建武の新政の関係
中先代の乱は、建武の新政と深く関わっており、この乱の発生と拡大は、建武政権の政治的な脆弱さを浮き彫りにしました。建武の新政とは、1333年に鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇が始めた新しい政治体制で、公家主導の統治を目指したものでした。
ところが、この体制は当時の武士たちから強い反発を受けていました。なぜなら、倒幕に尽力した多くの武士たちが報われず、恩賞も不公平で、政治の中心からも遠ざけられていたからです。これによって、「せっかく幕府を倒したのに、今のほうがむしろひどい」と感じる武士が続出しました。
このような武士たちの不満は各地で噴出し、特に旧鎌倉幕府の家臣や御内人を中心とした反乱が頻発するようになります。その一つが中先代の乱でした。つまり、この乱は単に北条氏の遺児・時行が幕府を再興しようとしただけではなく、建武政権に不満を持った多くの武士たちの怒りが集まった結果でもあります。
また、建武政権はこの反乱に対しても迅速に対応できず、内部の意思決定の遅さが露呈します。時行の軍が鎌倉に攻め込んでいた時、中央では「京に来る」と誤認していたというエピソードもあり、情報の混乱や判断ミスが目立ちました。
さらに、この中先代の乱をきっかけに、足利尊氏が後醍醐天皇に背き、やがて武家政権を立てる決意を固めていくことになります。尊氏は天皇の命を受けずに出陣し、鎮圧後も鎌倉にとどまったことで、両者の関係は決裂しました。
このように、中先代の乱は、建武の新政の欠陥を突きつけ、武士と公家の溝を決定的に深める要因となりました。そして、この出来事がその後の南北朝時代への移行を促したと言えるのです。
中先代の乱という名前の意味と由来
「中先代の乱」という名称には、非常に独特な意味と背景があります。この名前を理解することで、当時の時代認識や政治的状況も見えてきます。
まず「先代」という言葉は、鎌倉幕府を支配していた北条氏の時代を指しています。幕府が続いた長い期間、北条家が実権を握っており、その時代はまさに「先代の政権」として記憶されていました。
一方、「当代」とは、この乱の後に本格的に権力を握ることになる足利尊氏による室町幕府の時代を意味します。では、その「中」とは何かというと、北条と足利の間に一時的に存在した、北条時行による鎌倉の支配期間を指しています。
つまり「中先代の乱」とは、先代(北条氏)と当代(足利氏)の中間で一時的に鎌倉を支配した出来事であることから名づけられたのです。このネーミングは、非常に短命だった時行の支配が「過渡期的なものであった」という認識を込めているとも言えます。
また、乱の別名として「廿日(はつか)先代の乱」という呼び方もあります。これは、北条時行が鎌倉を支配した期間が約20日間と非常に短かったことに由来します。いかに時行の奪還が劇的だったとしても、その支配は儚く終わったという印象を残す呼び名です。
これらの名称は、単なる史実の呼称というよりも、時代をどう理解し、どのような視点で評価するかを示す象徴でもあります。つまり、「中先代」という言葉は、歴史の移り変わりの狭間に一瞬だけ現れた、旧政権の亡霊のような存在を表しているとも言えるのです。
歴史マンガでも描かれる時代背景とは
中先代の乱が描かれる歴史マンガや小説が注目される背景には、この時代そのものがドラマチックで、登場人物が非常に個性的であることが挙げられます。特に近年では『逃げ上手の若君』のように、北条時行を主人公にした作品が人気を集めています。
この時代は、鎌倉幕府が滅びたばかりの混乱期であり、中央では建武の新政が始まっていたものの、地方では旧幕府の残党や武士たちが次々に蜂起していました。政治体制が不安定で、誰が次の時代の主導者になるのか先が見えないという、不穏かつ希望にも満ちた時代です。
このような背景は、フィクションの題材として非常に魅力的です。若き遺児・北条時行がわずか10歳で反乱軍の象徴として立ち上がり、父の仇を討とうとする姿は、読者の共感を呼びやすいヒーロー像でもあります。
また、敵として立ちはだかる足利尊氏も単なる悪役ではありません。尊氏自身も建武政権に不満を持ち、やがて自らの幕府を作ることになる人物であり、彼の葛藤や行動も物語に厚みを持たせています。
さらに、護良親王や諏訪頼重など、忠誠・裏切り・悲劇に彩られた人物たちが多数登場することで、ストーリーはさらに濃密になります。戦の駆け引き、主従の絆、そして失われた家族との再会など、現代の読者にも響くテーマが多いのも特徴です。
このような時代背景を知っておくことで、マンガやドラマを見る際の理解が深まり、単なる娯楽以上に歴史そのものの面白さにも気づけるようになります。つまり、中先代の乱を知ることは、歴史エンタメをより楽しむための「知的なスパイス」としても役立つのです。
中先代の乱をわかりやすく総括
中先代の乱は、日本の歴史の中でも短期間で終息した出来事ですが、その影響は非常に大きく、後の時代へもつながる重要な反乱です。
ここでは、初めてこの歴史に触れる方にも理解しやすいよう、ポイントを箇条書きでまとめました。
- 中先代の乱は1335年(建武2年)に起こった反乱です。
- 旧鎌倉幕府を再興しようとした北条時行が中心となって挙兵しました。
- 幼い時行を支えたのは、諏訪頼重をはじめとする旧幕府の家臣たちでした。
- 反乱のきっかけは、建武の新政に対する武士たちの不満でした。
- 武士への恩賞が不十分だったことが、各地で反発を生んでいきます。
- 反乱軍は信濃(今の長野県)から関東を目指して進軍しました。
- 女影原、小手指ヶ原、武蔵府中など、各地で足利方と激戦を交えました。
- 足利直義が守っていた鎌倉を時行軍が一時的に奪還します。
- 鎌倉の支配は約20日間だけで、「廿日先代の乱」とも呼ばれています。
- その後、足利尊氏が西から出陣し、反乱を鎮圧しました。
- 尊氏の行動は朝廷の命令を無視したもので、のちに朝敵とされます。
- この反乱を機に、足利尊氏と後醍醐天皇の関係は完全に決裂します。
- 中先代の乱は南北朝時代へと続く、大きな分岐点となりました。
- 「中先代」という名前は、北条と足利の“間”に一時的に存在した政権を意味しています。
- この時代はマンガやドラマでも人気があり、歴史の魅力に触れやすい題材です。
このように、中先代の乱は「ただの反乱」ではなく、旧体制と新体制の激突、そして武士と公家の対立を象徴する出来事でした。歴史の流れをつかむうえで、知っておくと理解が深まる重要なテーマの一つです。
関連記事
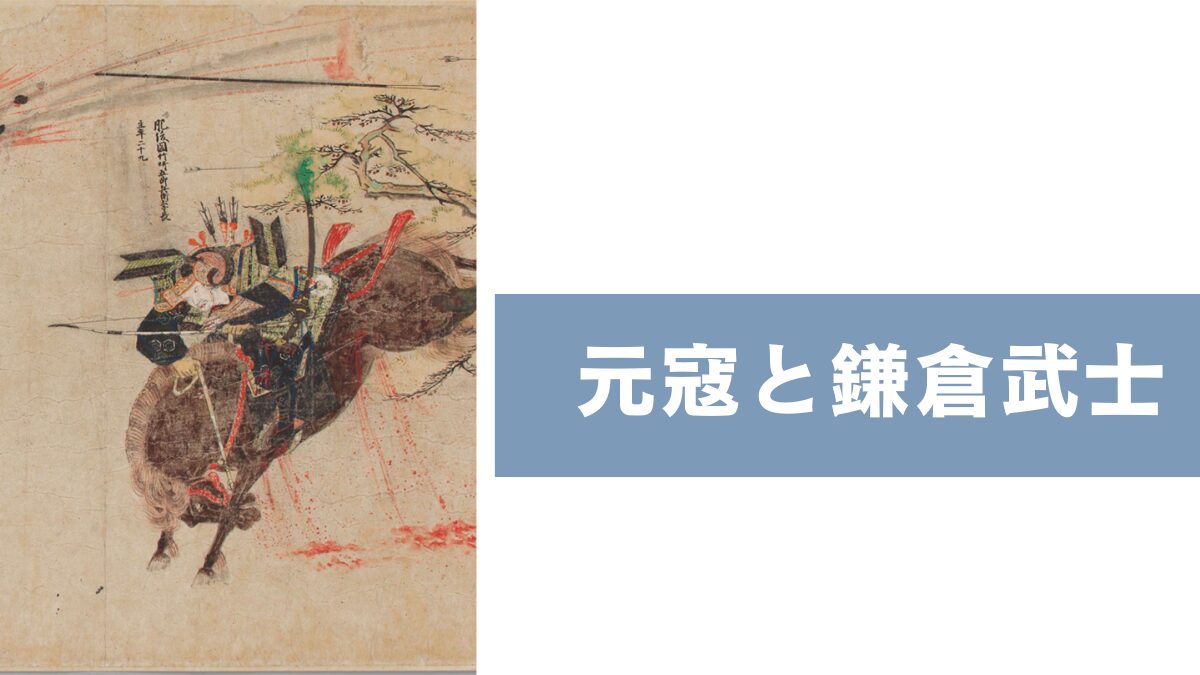
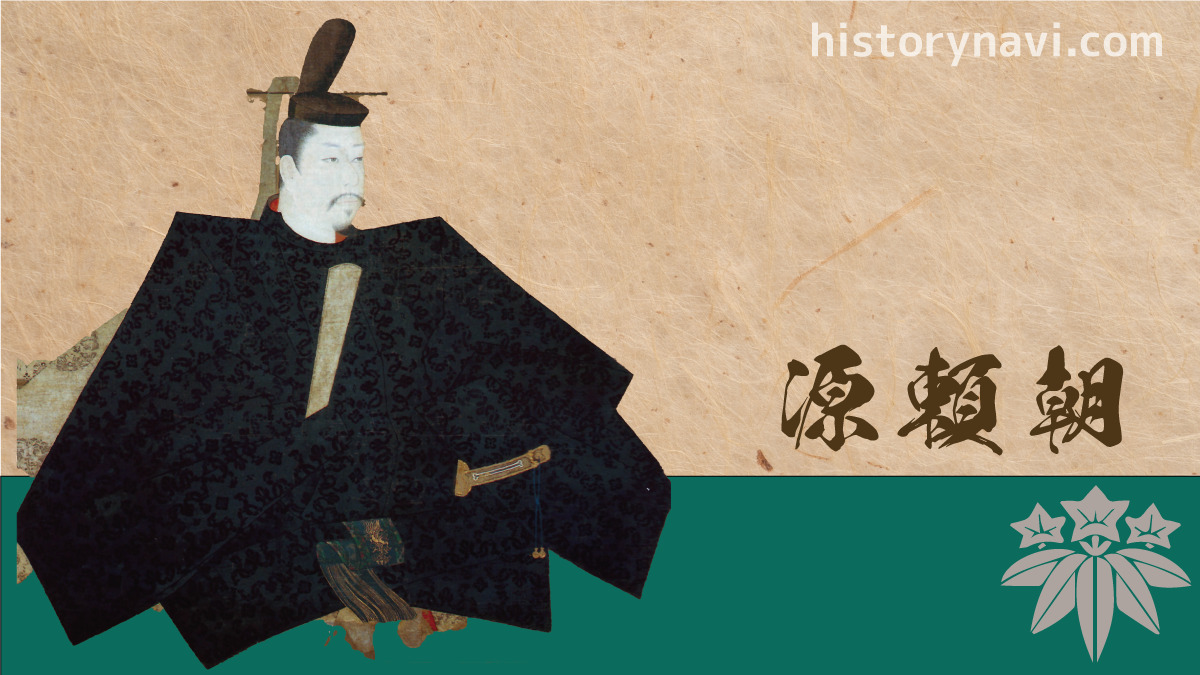
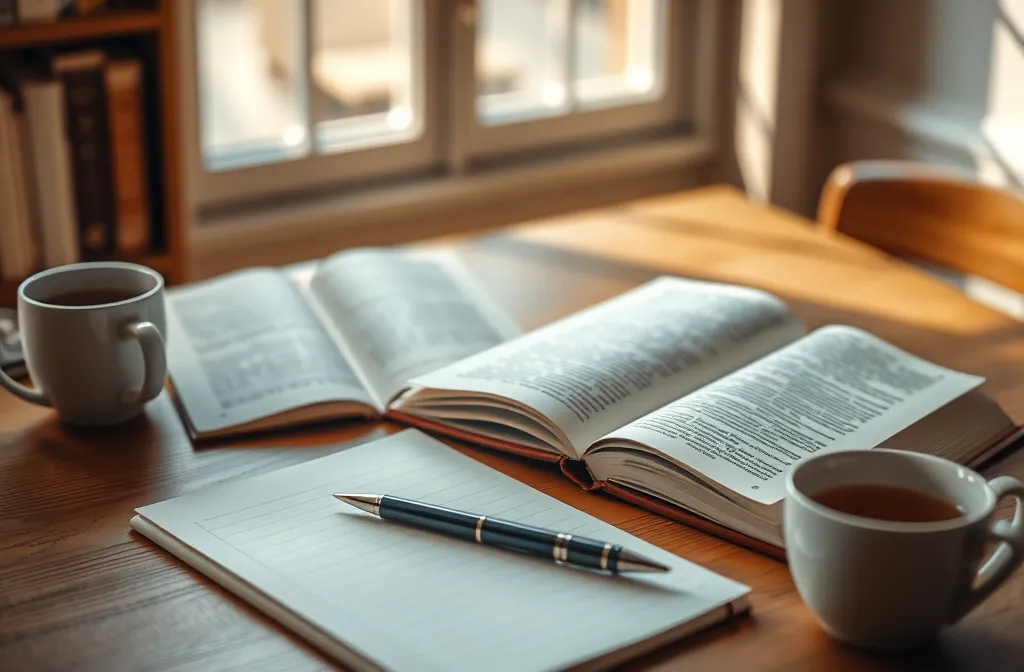
参考サイト
関連書籍
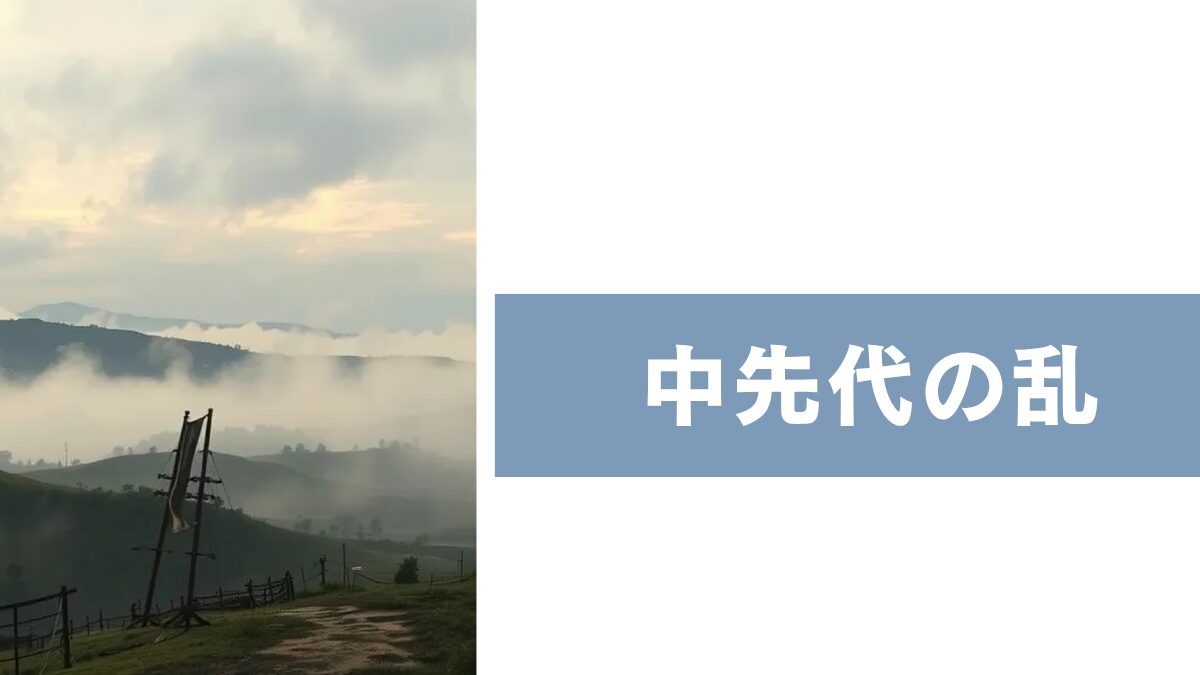

コメント