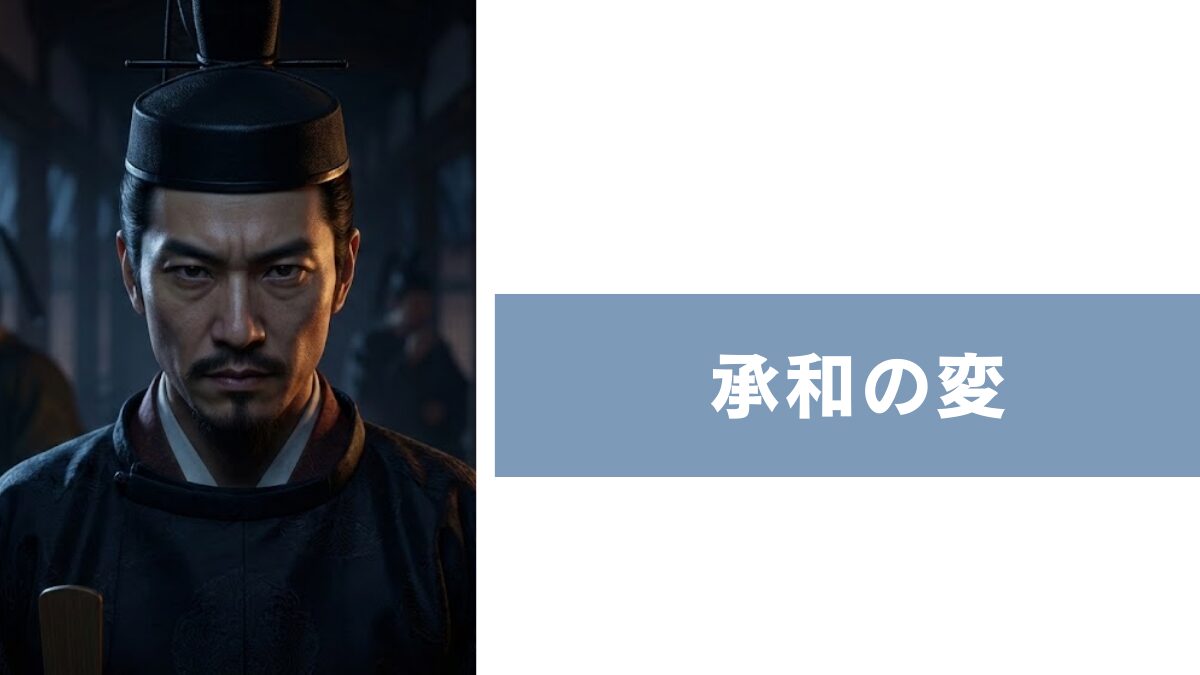平安時代の歴史は似たような事件名が多く、「結局なにが起きたの?」と混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
特に「承和の変(じょうわのへん)」は、名前は知っていても、その重要性や背景まではピンとこないという声もよく聞きます。
実はこの事件、一言で言えば「藤原氏が権力を独占するために仕掛けた、最初のクーデター」なのです。
複雑に見える皇位継承問題や貴族たちの争いも、その裏にある藤原良房の野望を知れば、現代のドラマ顔負けのサスペンスとして理解できるようになります。
本記事では、教科書だけでは見えてこない事件の深層を、歴史初心者の方にも承和の変をわかりやすく、かつドラマチックに解説していきます。
この記事を読むとわかること
- 兄弟で皇位を継ぐシステムが生んだ対立構造
- 藤原良房が仕組んだクーデター計画の全貌
- 伴健岑と橘逸勢がたどった悲劇的な運命
- 摂関政治の始まりと歴史への決定的な影響
承和の変とは?わかりやすく歴史の背景を解説

- 平安初期の政治状況と事件の簡単なあらすじ
- 兄弟で皇位を継ぐシステムが生んだ構造的な歪み
- 藤原良房の台頭と外戚関係をめぐる強い野心
- ターゲットにされた伴健岑と橘逸勢の動向
- 嵯峨上皇の崩御が引き金となったクーデター計画
平安初期の政治状況と事件の簡単なあらすじ
平安時代と聞くと、雅な貴族たちが歌を詠んで暮らしている平和なイメージを持つ人が多いかもしれません。
しかし、実際には水面下で激しい権力争いが繰り広げられていました。
特に平安時代の初期は、奈良時代から続く古い体制から、藤原氏が中心となる新しい政治体制へと移り変わる重要な転換期にあたります。
この時代の流れを決定づけたのが、842年(承和9年)に起きた「承和の変」です。
この事件を一言で説明するならば、「藤原氏がライバルを蹴落とし、自分たちの権力を絶対的なものにするための最初のクーデター」といえます。
当時の天皇であった仁明天皇の時代に、次の天皇候補である皇太子・恒貞親王(つねさだしんのう)が突然廃位されるという衝撃的な出来事が起こりました。
そして、親王に仕えていた伴健岑(とものこわみね)や橘逸勢(たちばなのはやなり)といった有力な貴族たちが、「謀反(国家への反逆)」を企てたという罪で捕まり、都から追放されてしまったのです。
この事件の背景には、天皇の位をめぐる複雑な人間関係がありました。
当時は、今の天皇の家系と、前の天皇の家系とが入り乱れる状況にあり、どちらのグループが主導権を握るかで宮廷内は二つに割れていたのです。
一見すると、皇太子が反乱を企てたことが発覚して処罰されただけの事件に見えるでしょう。
ただ、歴史研究の視点から見ると、これは藤原良房(ふじわらのよしふさ)という野心家が仕組んだ、極めて計画的な陰謀であった可能性が高いとされています。
なぜなら、この事件によって得をしたのが誰かを考えると、答えは明白だからです。
事件の結果、ライバルである伴氏や橘氏は没落し、代わりに藤原良房の甥っ子にあたる道康親王が新しい皇太子になりました。
つまり、この事件は単なる反乱騒ぎではなく、藤原氏が「天皇のおじいちゃん(外戚)」として権力を振るう「摂関政治」の幕開けを告げる合図だったのです。
歴史の教科書では数行で語られることの多い事件ですが、その中身は現代の政治ドラマ顔負けの、スリルと悲劇に満ちた権力闘争でした。
兄弟で皇位を継ぐシステムが生んだ構造的な歪み
承和の変が起きた最大の原因は、当時の特殊な「皇位継承ルール」にありました。
普通、天皇の位というのは「親から子へ」と受け継がれていくのが自然だと考えるでしょう。
しかし、この時期は少し事情が違っていました。
平安京を作った桓武天皇のあと、その子供たちの間で争いが起きないようにと配慮された結果、「兄から弟へ」と皇位を回すシステムが採用されていたのです。
具体的には、52代の嵯峨天皇と、その弟である53代の淳和天皇の間で取り決めがなされました。
嵯峨天皇は弟の淳和に位を譲り、その代わり淳和天皇は自分の息子ではなく、兄(嵯峨)の息子を皇太子にするという約束をしたのです。
さらに、その次はまた淳和の息子(恒貞親王)を皇太子にするという、まるで「たすき掛け」のような複雑な交代制が敷かれました。
これは、兄弟同士の争いを避けるための苦肉の策であり、お互いの顔を立てる平和的な解決策のように見えました。
ここで問題になったのが、実際に政治を行う現場の混乱です。
「今の天皇」のグループと、「次の天皇になる予定の皇太子」のグループ、さらには「引退した上皇」のグループが同時に存在することになります。
特に、嵯峨上皇と淳和上皇という二人の実力者が並び立つ状況は、宮廷の中に「二つの朝廷」があるような状態を作り出してしまいました。
貴族たちも、どちらの派閥につけば将来安泰なのかを見極めるのに必死になります。
このような状況を整理すると、以下のようになります。
| グループ名 | 中心の人物 | 皇位継承の正当性 | 支持勢力 |
|---|---|---|---|
| 嵯峨・仁明派 | 嵯峨上皇・仁明天皇 | 父から子への直系継承を望む | 藤原北家(良房など) |
| 淳和・恒貞派 | 淳和上皇・恒貞親王 | 兄弟間での約束(たすき掛け)を重視 | 伴氏・橘氏などの古参氏族 |
このように、システム自体が構造的な歪みを抱えていました。
嵯峨天皇も淳和天皇も、本心では「自分の可愛い息子に跡を継がせたい」と思っていたはずです。
しかし、兄弟間の義理や約束があるため、それを口に出すことはできません。
この「建前上の平和」と「本音の野望」のズレが、やがて大きな亀裂となって表面化するのは時間の問題でした。
承和の変は、この無理のある継承システムが限界を迎え、崩壊した瞬間だったとも言えるのです。
藤原良房の台頭と外戚関係をめぐる強い野心
この複雑な状況下で、一気に頭角を現したのが藤原北家の藤原良房です。
彼は政治的な才能に恵まれていただけでなく、自分の妹である順子(のぶこ)を仁明天皇の后として送り込んでいました。
そして、二人の間には道康親王(後の文徳天皇)という男の子が生まれます。
良房にとって、この道康親王の存在こそが、権力を掴むための最強のカードとなりました。
もし、当時のルールの通りに、淳和上皇の息子である恒貞親王が次の天皇になってしまったらどうなるでしょうか。
恒貞親王のお母さんは嵯峨上皇の娘である正子内親王ですが、そこに藤原良房の影響力は及びません。
天皇の「母方の親戚」として権力を握ることを「外戚(がいせき)」と言いますが、恒貞親王が即位してしまうと、良房は外戚の地位を得ることができなくなってしまいます。
それは、藤原北家がその他大勢の貴族の一つに成り下がってしまうことを意味していました。
良房が目指したのは、自分の甥っ子である道康親王を何としてでも天皇にすることです。
そのためには、現在皇太子である恒貞親王には、どうしてもその座から降りてもらわなければなりません。
しかし、恒貞親王には何の落ち度もなく、廃位させる正当な理由を見つけるのは困難でした。
そこで良房が必要としたのが、相手を社会的に抹殺できるほどの強力なスキャンダル、すなわち「謀反」の容疑だったのです。
また、当時の仁明天皇自身も、内心では自分の息子(道康親王)に位を譲りたいと考えていました。
良房はこの天皇の親心を利用し、巧みに連携をとりました。
「恒貞親王派が何か怪しい動きをしている」という噂を広めたり、相手の不安を煽ったりすることで、事態を自分に有利な方向へと誘導していったのです。
良房の野心は単なる個人の出世欲にとどまらず、藤原一族全体の繁栄をかけた巨大なプロジェクトでした。
彼はこの目的のためなら、古くからの名門氏族を陥れることも、強引な手段を使うことも厭わない冷徹さを持っていました。
承和の変は、この良房の並外れた執念と政治力が引き起こした事件だったのです。
ターゲットにされた伴健岑と橘逸勢の動向
藤原良房らが着々と包囲網を狭める一方で、追い詰められていたのが恒貞親王の側近たちです。
その中心人物が、伴健岑(とものこわみね)と橘逸勢(たちばなのはやなり)でした。
彼らは立場も性格も全く異なる二人でしたが、「主君である恒貞親王を守りたい」という一点で結びついていました。
伴健岑は、古代からの名門軍事氏族である大伴氏(伴氏)の出身です。
大伴氏といえば、万葉集にも歌われるほど武勇に優れた家柄でしたが、この頃には藤原氏に押され気味でした。
健岑自身も非常に気性が激しく、忠義に厚い人物だったと伝えられています。
彼は、藤原良房が自分の主君である恒貞親王を廃そうと画策していることを敏感に察知していました。
「このままでは親王様の身が危ない」という危機感から、武力を使ってでも状況を打開しようと考えていた節があります。
一方、橘逸勢は全く異なるタイプの人物でした。
彼は「三筆」の一人に数えられるほど書道に優れ、空海や嵯峨天皇とも交流がある当代一流の文化人でした。
政治的な駆け引きよりも、芸術の世界に生きる穏やかな人物だったと思われます。
しかし、彼は皇室とも縁の深い橘氏の出身であり、恒貞親王の教育係のような立場にもありました。
本来であれば政治抗争の矢面に立つような人物ではありませんでしたが、その名声と立場ゆえに、良房にとっては排除すべき邪魔な存在としてマークされてしまったのです。
彼らは日に日に強まる藤原氏からの圧力に焦りを募らせていました。
そして、「いざとなれば京を脱出して、東国(関東地方)へ逃れよう」という計画を話し合っていたとされています。
ただ、これが具体的なクーデター計画だったのか、それとも身の危険を感じた上での単なる逃避行の相談だったのかは、今となっては分かりません。
歴史書には「謀反」と記されていますが、彼らにとっては「正当防衛」のための準備だった可能性も十分にあります。
いずれにしても、彼らが密室で交わした会話や、不安からくる軽率な行動が、結果として良房に「謀反発覚」という絶好の口実を与えてしまうことになりました。
彼らの忠誠心が、皮肉にも主君を窮地に追い込む引き金となってしまったのです。
嵯峨上皇の崩御が引き金となったクーデター計画
承和の変が勃発した直接のきっかけは、政界の重鎮であった嵯峨上皇の死でした。
842年(承和9年)の7月、重い病を患っていた嵯峨上皇がついに崩御しました。
これは単に一人の元天皇が亡くなったというだけでなく、宮廷内のパワーバランスを保っていた巨大な支柱が失われたことを意味していました。
嵯峨上皇は、仁明天皇にとっても恒貞親王にとっても父親や祖父にあたる存在であり、彼の睨みが効いている間は、露骨な争いは抑え込まれていたのです。
上皇の死が決定的になると、伴健岑らはパニック状態に陥りました。
「後ろ盾を失った今、恒貞親王はすぐにでも藤原氏に襲われるかもしれない」という恐怖が彼らを支配したのです。
ここで彼らは致命的なミスを犯してしまいます。
阿保親王(平城天皇の皇子)という人物に、「東国へ逃れる計画」を相談し、協力を求めたのです。
伴健岑としては、同じく皇族である阿保親王なら味方になってくれるだろうという期待があったのかもしれません。
しかし、阿保親王はこの相談内容を、あろうことか敵対勢力側に近い檀林皇后(橘嘉智子)に密告してしまいました。
檀林皇后は橘逸勢の親族ではありましたが、それ以上に「国母」として、自分の息子である仁明天皇と、孫である道康親王の将来を第一に考えていました。
彼女は実家の橘氏を守ることよりも、現在の皇統の安定を選び、この密告情報を仁明天皇と藤原良房に伝えたのです。
これにより、良房側は「待っていました」とばかりに行動を開始します。
彼らにとって、上皇の死による混乱は想定内の事態であり、むしろこのタイミングを狙っていたフシさえあります。
「皇太子の側近たちが、上皇の死に乗じて国家転覆を狙っている」という大義名分を得た良房は、直ちに軍事力を動員しました。
こうして、嵯峨上皇の死からわずか数日のうちに、事態は急展開を迎えることになります。
上皇の喪に服すべき期間に、水面下では冷酷な政治的粛清のシナリオが実行に移されていたのです。
承和の変の結果をわかりやすく!歴史への影響

- 迅速すぎた軍事行動と逃げ道を塞ぐ包囲網
- 謀反の疑いをかけられた人々の過酷な運命
- 強行された皇太子の交代と直系継承への転換
- 藤原氏による他氏排斥の成功モデルとして
- 人臣初の摂政誕生へつながる権力構造の変化
- 悲劇の文化人・橘逸勢と御霊信仰の広がり
迅速すぎた軍事行動と逃げ道を塞ぐ包囲網
嵯峨上皇が亡くなってからわずか2日後の7月17日、藤原良房は電撃的な行動に出ました。
その動きはあまりにも迅速で、周到に準備されていたとしか思えないほどでした。
まず、良房自身が40人の兵士を率いて、恒貞親王の住まいである近衛廐(このえのうまや)を完全に包囲しました。
これは「警護」という名目でしたが、実際には親王を軟禁し、外部との接触を断つための軍事行動でした。
さらに特筆すべきは、京から地方へと続く主要な交通ルートが一斉に封鎖されたことです。
もし伴健岑たちが計画していたように東国へ逃げようとすれば、必ず通らなければならない道や橋がありました。
良房は六衛府(宮中の警備隊)の兵士たちを動員し、以下の重要なポイントを物理的に塞いでしまったのです。
| 封鎖された場所 | 方角・役割 | 目的 |
|---|---|---|
| 宇治橋 | 南方面への出口 | 大和・伊賀方面への逃走阻止 |
| 山崎橋 | 西方面への架橋 | 西国へのルート遮断 |
| 淀の渡し | 水運の要所 | 川を使った移動の封鎖 |
| 大原道 | 北方面への道 | 北陸方面への出口封鎖 |
| 大枝道 | 山陰方面への道 | 山陰道への移動阻止 |
これらの場所は、現代で言えば高速道路のインターチェンジや主要な駅のような場所です。
ここを軍事力で固められてしまっては、伴健岑らが京から脱出することは物理的に不可能でした。
まさに「袋のネズミ」状態です。
この徹底した封鎖作戦は、単に犯人を捕まえるためだけでなく、京の内部で起きている異変を地方に知らせないための情報遮断の意味もありました。
地方にいる伴氏や橘氏の仲間たちが応援に駆けつけるのを防ぐためです。
当時の貴族たちは、このあまりの手回しの良さに戦慄したことでしょう。
事件が発覚してから対策を練ったのではなく、あらかじめ「Xデー」に向けて全ての配置が決められていたことは明らかです。
この軍事的な威圧感の前では、恒貞親王派の貴族たちも抵抗する術はなく、なすすべなく捕らえられるしかありませんでした。
この日の平安京は、厳戒態勢が敷かれた戒厳令下のような物々しい雰囲気に包まれていたはずです。
謀反の疑いをかけられた人々の過酷な運命
軍事的な包囲網が完成すると、次に行われたのは関係者の大量逮捕と厳しい尋問でした。
伴健岑と橘逸勢はもちろんのこと、彼らに近い立場にいた高官たちも次々と呼び出されました。
その中には、藤原愛発(ふじわらのちかなり)や藤原吉野といった、藤原氏でありながら良房とは距離を置いていた人物たちも含まれていました。
良房は、この機会を利用して、他氏族だけでなく身内の政敵までも一掃しようとしたのです。
逮捕された人々を待っていたのは、過酷な取り調べでした。
当時の尋問は、現代のような人権に配慮したものではなく、肉体的な苦痛を与える拷問も辞さない厳しいものでした。
記録によると、伴健岑と橘逸勢は最後まで「自分たちは謀反など企てていない」と無実を主張し続けたと言われています。
特に橘逸勢は高齢であり、筆を持って生きてきた文化人です。
粗暴な兵士たちによる尋問が、彼の老体にどれほどのダメージを与えたかは想像に難くありません。
それでも、朝廷側(実質的には良房側)は彼らの言い分を聞き入れることはありませんでした。
最初から「有罪」という結論ありきで審理が進められたからです。
結果として、彼らは死刑こそ免れましたが、当時の貴族にとっては死にも等しい「流罪(るざい)」を言い渡されます。
主な処罰内容
- 伴健岑:隠岐国(現在の島根県隠岐の島)へ流罪
- 橘逸勢:伊豆国(現在の静岡県伊豆半島)へ流罪
華やかな都での生活から一転して、彼らは罪人として僻地へ送られることになりました。
また、彼らの親族や部下たちも連座して処罰され、長年朝廷に仕えてきた伴氏や橘氏の勢力は、この事件を境に壊滅的な打撃を受けました。
「勝てば官軍、負ければ賊軍」という言葉がありますが、承和の変における敗者の扱いは、あまりにも一方的で悲惨なものでした。
彼らの名誉が回復されるまでには、長い年月と、ある「超自然的な現象」を待たなければなりませんでした。
強行された皇太子の交代と直系継承への転換
伴健岑らの処分が決まると、事件の最大の目的であった皇太子の交代がすぐに実行されました。
恒貞親王は「謀反に関与した責任を取る」という形で皇太子を廃されました。
親王自身は謀反の計画など全く知らなかったとしても、側近が反乱を企てた以上、その監督責任からは逃れられないという理屈です。
恒貞親王はその後、仏教に帰依して出家し、「恒寂(ごうじゃく)」という名前になって政界から完全に身を引きました。
彼は自らの運命を受け入れ、争いを避ける道を選んだのです。
そして、空席となった皇太子の座には、良房の計画通り、仁明天皇の息子である道康親王が就きました。
これは単に人が入れ替わっただけではありません。
日本の皇位継承ルールが、「兄弟で回す方式」から「父から子へ受け継ぐ方式」へと強制的に書き換えられたことを意味します。
これ以降、天皇の位は「現天皇の直系の息子」が継ぐことが原則となりました。
この変更は、藤原氏にとって非常に都合の良いものでした。
なぜなら、自分の娘を天皇に嫁がせ、生まれた男の子を次の天皇にすれば、自分は確実に「天皇のおじいちゃん」になれるからです。
兄弟継承の場合、次の天皇が自分の孫になるとは限りません。
しかし、直系継承であれば、一度外戚の地位を確保してしまえば、その権力を長く維持しやすくなります。
良房は、この「父子直系継承」という新しいルールを確立することで、藤原氏が代々権力を独占できるシステムを作り上げたのです。
このように、承和の変は突発的な事件ではなく、日本の政治構造を根底から変えるための「構造改革」でした。
もちろん、それは藤原氏という特定の氏族のための改革でしたが、結果として皇位継承の不安定さを解消し、政治を安定させたという側面も否定できません。
犠牲になった恒貞親王の無念の上に、平安時代中期の藤原氏の栄華が築かれていったのです。
藤原氏による他氏排斥の成功モデルとして
歴史を学ぶ上で重要なのは、この承和の変が「一回限りの事件」ではなかったということです。
むしろ、藤原氏が得意とする「他氏排斥(たしはいせき)」の勝ちパターンが、ここで完成したと見るべきでしょう。
他氏排斥とは、ライバルとなる有力な氏族に無実の罪を着せたり、些細なミスを大きく取り上げたりして、政治の表舞台から消し去る手法のことです。
承和の変で良房が行った手口を整理すると、次のようなステップが見えてきます。
- ターゲットの選定:自分たちの権力を脅かすライバルを見つける。
- 情報収集と陰謀:相手の不安を煽り、ボロを出させるか、密告を誘導する。
- 迅速な断罪:事件が起きたら間髪入れずに処罰し、反論の機会を与えない。
- 権力の掌握:空いたポストに自分たちの身内を送り込む。
このあまりにも鮮やかな成功体験は、その後の藤原氏の政治手法に決定的な影響を与えました。
実際に、この後も同じような事件が繰り返されています。
866年の「応天門の変」では、伴善男(とものよしお)が放火の罪を着せられて排斥されました。
969年の「安和の変」では、源高明(みなもとのたかあきら)が謀反の疑いで左遷され、これにより藤原氏以外の氏族で高官になれる家はほとんどなくなりました。
いわば、承和の変は「プロトタイプ(試作品)」であり、ここで確立されたノウハウが後の事件でも応用されたのです。
良房が作ったこの冷徹な政治マニュアルは、子孫たちに受け継がれ、藤原氏の独裁体制を磐石なものにしていきました。
歴史の授業でこれらの事件を習うとき、「また藤原氏が誰かを追い出したのか」と思うかもしれません。
しかし、その最初の一歩がこの承和の変であり、ここから全てが始まったのだと理解すると、平安時代の政治史が一本の線でつながって見えてくるはずです。
人臣初の摂政誕生へつながる権力構造の変化
承和の変から得られた果実は、良房個人にとっても計り知れないほど大きなものでした。
この事件で実力を証明した良房は、その後も順調に出世を重ねていきます。
そして事件から16年後の858年、彼が皇太子に押し上げた道康親王(文徳天皇)が亡くなり、その息子である惟仁親王がわずか9歳で即位しました。
これが第56代・清和天皇です。
清和天皇は良房の娘である明子が生んだ子供です。
つまり、良房はついに念願だった「天皇の母方の祖父」になったのです。
幼い天皇に代わって政治を行うため、良房は皇族以外の身分(人臣)として初めて「摂政(せっしょう)」という地位に就きました。
それまで摂政になれるのは皇族だけという決まりがありましたが、良房はその前例を覆したのです。
これこそが、皆さんが歴史の教科書で習う「摂関政治」の始まりです。
承和の変でライバルを排除し、皇位継承を自分の血筋に有利なように変更していなければ、良房が摂政になる未来は絶対に訪れませんでした。
もし恒貞親王が天皇になっていれば、歴史は全く違うルートを辿っていたでしょう。
藤原氏が天皇を補佐するという名目で、実質的な日本の支配者として君臨するスタイルは、この時に確立されました。
この権力構造の変化は、単にトップが変わったというレベルの話ではありません。
天皇個人の能力やカリスマ性で国を治める「天皇親政」の時代が終わり、組織と家柄で政治を動かす「貴族政治」の時代へと完全にシフトしたことを意味します。
良房が切り開いたこの道は、後の藤原道長・頼通の時代に全盛期を迎え、日本の貴族文化が花開く土台となりました。
承和の変は、その壮大な歴史のドラマの第一章として、極めて重要な位置を占めているのです。
悲劇の文化人・橘逸勢と御霊信仰の広がり
最後に、この事件の「敗者」である橘逸勢のその後について触れておきましょう。
彼の運命は、当時の人々に強烈なインパクトと恐怖を与えました。
無実の罪(と多くの人が信じていました)で伊豆への流罪が決まった逸勢ですが、彼は配流地へ向かう旅の途中、遠江国(現在の静岡県西部)で力尽き、亡くなってしまいます。
都での優雅な生活から引き剥がされ、罪人として護送される中での孤独な死でした。
逸勢の死後、都では奇妙なことが次々と起こり始めました。
疫病が流行したり、天災が起きたりと、不吉な出来事が続いたのです。
当時の人々はこれを「無念の死を遂げた逸勢や伴健岑の祟り(たたり)ではないか」と噂しました。
科学が発達していない時代、政治的な恨みを持って死んだ人の霊が、災いをもたらすという考え方は非常にリアルな恐怖でした。
朝廷側もこの噂を無視できなくなりました。
彼らは逸勢の怒りを鎮めるために、死後に位(くらい)を贈って名誉回復を行いました。
さらに、863年には神泉苑という場所で「御霊会(ごりょうえ)」という大規模な儀式を行いました。
これは、政治争いで敗れて死んだ人々の霊を「御霊(ごりょう)」として祀り、慰めるためのものです。
この儀式では、早良親王(崇道天皇)などと共に、橘逸勢も神様のような存在として祀られました。
これは後の菅原道真(天神様)のケースと非常によく似ています。
優れた才能を持ちながら政治の犠牲になった人物が、死後に恐ろしい怨霊となり、やがて神として祀られる。
この「御霊信仰」の流れを作るきっかけの一つが、橘逸勢の悲劇だったのです。
彼は政治家としては敗北しましたが、その死は人々の心に深く刻まれ、日本人の宗教観や死生観に大きな影響を与え続けました。
承和の変は、政治史だけでなく、文化や宗教の面でも忘れられない傷跡を残した事件だったと言えるでしょう。
承和の変をわかりやすく総まとめ:事件のポイントを振り返る
ここまで解説してきた「承和の変」について、複雑な歴史の流れを整理し、重要なポイントをまとめていきましょう。
この事件は、単なる昔の政治トラブルではなく、その後の日本の形を決める大きな転換点でした。
全体の流れをおさらいすると、以下のような要点が見えてきます。
- 事件の発生:842年(承和9年)に平安京で起きた、藤原氏による他氏排斥クーデターです。
- 歴史的な位置づけ:古代から続く古い政治体制から、藤原氏中心の「摂関政治」へ移り変わるきっかけとなりました。
- 根本的な原因:嵯峨天皇と淳和天皇の間で決められた「兄弟で皇位を回す」という無理なルールが、派閥争いを生みました。
- 対立の構図:現天皇の直系継承を望む「嵯峨・仁明派」と、約束通りの兄弟継承を守りたい「淳和・恒貞派」が対立しました。
- 黒幕の野望:藤原良房が、自分の甥(道康親王)を天皇にするため、邪魔な皇太子(恒貞親王)の排斥を計画しました。
- ターゲット:皇太子の側近であり、名門氏族の伴健岑と橘逸勢が「謀反」の容疑者に仕立て上げられました。
- 事件の引き金:両派閥のバランスを保っていた嵯峨上皇の崩御により、良房側が実力行使に出るチャンスが到来しました。
- 致命的なミス:伴健岑らが東国への脱出を阿保親王に相談したところ、その情報が檀林皇后を通じて良房側に漏れてしまいました。
- 迅速な軍事行動:良房は即座に兵を動かし、宇治橋などの主要な交通路を封鎖して、相手の逃げ道を完全に断ちました。
- 過酷な処分:伴健岑と橘逸勢は無実を訴えましたが聞き入れられず、流罪という社会的抹殺を受けました。
- 皇太子の交代:事件の結果、恒貞親王は廃太子となり、良房の望み通り道康親王(文徳天皇)が新たな皇太子となりました。
- ルールの変更:皇位継承が「兄弟間」から「父から子への直系」へと強制的に変更され、外戚の影響力が強まりました。
- 他氏排斥のモデル化:この事件での「陰謀→迅速な処分→権力奪取」という手口は、その後の応天門の変などでも繰り返されました。
- 摂関政治の確立:良房はこの功績により、後に人臣として初めての摂政となり、藤原氏の独裁体制を築き上げました。
- 御霊信仰へ:流罪先で亡くなった橘逸勢は、後にその祟りを恐れられて神として祀られ、御霊信仰の先駆けとなりました。
このように、承和の変は一人の野心家がシステム不全を突き、ライバルを蹴落として頂点に立つまでの完全なサクセスストーリー(敗者にとっては悲劇)だったと言えます。
この15のポイントを押さえておけば、平安時代初期の政治ドラマの核心をしっかりと理解できたことになります。
参考サイト