「後醍醐天皇って、一体何をした人なんだろう?」 「鎌倉幕府を倒したすごい天皇だって聞くけど、建武の新政はなぜすぐに終わっちゃったの?」 「足利尊氏とは、最初は仲間だったはずなのに…」
歴史の教科書に必ず登場する後醍醐天皇。 その名前は知っていても、彼が具体的に「何した」のか、どんな生涯を送ったのか、意外と知らないことが多いかもしれませんね。
この記事では、そんな後醍醐天皇の波乱に満ちた生涯を追いかけながら、彼が理想とした天皇自ら政治を行う「親政」への熱い思い、そして大きな期待とともに始まった「建武の新政」がなぜ短期間で崩壊してしまったのか、その理由を「簡単に」わかりやすく解き明かしていきます。
さらに、絶望的な「島流し」からの奇跡的な復活劇、宿命のライバル「足利尊氏」との激しい対立、そして彼の「息子」たちが辿った運命、知られざる人間味あふれる「エピソード」から、その壮絶な最期と「死因」に至るまで。 後醍醐天皇という人物の「すごい」功績と、時代を動かした強烈な個性に迫ります。
これを読めば、あなたが抱いていた疑問もきっとスッキリするはずです。
この記事を読むとわかること
- 後醍醐天皇が目指した「親政」と鎌倉幕府打倒までの道のり
- 「建武の新政」の具体的な内容と、なぜ短期間で失敗したのか
- 宿敵「足利尊氏」との関係性の変化と、南北朝時代が始まった経緯
- 後醍醐天皇の知られざる「エピソード」や「息子」たち、「死因」まで含めた生涯
後醍醐天皇は何をした?波乱の生涯を簡単に紹介

- 後醍醐天皇の生涯と「何した」か簡単に解説
- 理想とした天皇「親政」と討幕への道筋
- 最初の挫折「正中の変」と隠岐への「島流し」
- 不屈の脱出!鎌倉幕府滅亡への大きな貢献
- 「建武の新政」開始と後醍醐天皇の理想政治
後醍醐天皇の生涯と「何した」か簡単に解説
後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は、日本の歴史において非常に個性的で、大きな変革をもたらした天皇の一人です。
「後醍醐天皇は何をした人物なのか?」この問いに答えるならば、一言で言えば「鎌倉幕府を倒し、天皇中心の新しい政治を試みたものの、武士との対立から南北朝という分裂の時代を招いた天皇」と言えるでしょう。
彼の生涯は、まさに波乱万丈という言葉がふさわしく、強い意志と理想を掲げて行動し続けたことが特徴です。
後醍醐天皇は1288年に第91代後宇多天皇の第二皇子として誕生しました。
当時の皇室は、持明院統(じみょういんとう)と大覚寺統(だいかくじとう)という二つの系統に分かれて皇位を争っており、鎌倉幕府の介入によって交互に天皇を出す「両統迭立(りょうとうてつりつ)」という不安定な状態にありました。
後醍醐天皇は大覚寺統に属し、1318年に31歳で即位しますが、これは兄である後二条天皇の皇子・邦良親王(くによししんのう)が成人するまでの中継ぎとしての立場でした。
しかし、後醍醐天皇自身はこの「中継ぎ」という立場に甘んじることなく、天皇自らが政治を行う「親政(しんせい)」への強い憧れを抱いていました。
それは、かつて醍醐天皇と村上天皇が行った「延喜・天暦の治」という理想的な天皇政治を現代に蘇らせたいという熱い思いがあったからです。
その決意の表れとして、通常は死後に贈られる追号(おくりな)を、生前から自ら「後醍醐」と定めていたほどです。
即位後、父である後宇多上皇の院政を廃止し、親政を開始した後醍醐天皇は、自らの理想を実現するために、鎌倉幕府の打倒を目指します。
しかし、その道のりは険しく、最初の討幕計画である「正中の変」(1324年)は失敗に終わります。
それでも諦めない後醍醐天皇は、再び討幕を企てますが、「元弘の乱」(1331年)で敗れ、隠岐の島へ流されてしまいました。
ところが、後醍醐天皇は不屈の精神で隠岐を脱出し、楠木正成(くすのきまさしげ)や足利高氏(あしかがたかうじ、後の尊氏)といった武士たちの協力を得て、1333年ついに鎌倉幕府を滅亡させるのです。
幕府滅亡後、後醍醐天皇は京都に戻り、天皇中心の新たな政治「建武の新政(けんむのしんせい)」を開始します。
しかし、この新政は公家を重視しすぎたことや、恩賞の不公平などから武士たちの不満を買い、わずか2年半で崩壊してしまいました。
特に、討幕の最大の功労者の一人であった足利尊氏との対立は決定的となり、後醍醐天皇は京都を追われることになります。
そして、奈良の吉野へ逃れた後醍醐天皇は、そこで新たな朝廷(南朝)を開き、京都の北朝と対立する「南北朝時代」が始まるのです。
後醍醐天皇は、吉野で南朝を率いながら京都奪還を目指し続けましたが、その夢は叶うことなく、1339年に52歳で崩御しました。
このように、後醍醐天皇は天皇親政という高い理想を掲げ、時代を大きく動かした一方で、その急進的な改革が新たな混乱を生み出した、光と影を併せ持つ天皇だったと言えるでしょう。
理想とした天皇「親政」と討幕への道筋
後醍醐天皇が目指した政治の中心には、天皇自らが直接国を治める「親政(しんせい)」という強い理想がありました。
彼がなぜこれほどまでに親政にこだわったのか、そして、その実現のために鎌倉幕府の打倒という険しい道を選んだのか、その背景にはいくつかの重要な理由が存在します。
まず、後醍醐天皇が理想としたのは、平安時代中期の醍醐天皇と村上天皇による「延喜・天暦の治(えんぎ・てんりゃくのち)」と称される時代でした。
この時代は、天皇が摂政や関白といった補佐役に頼らず、自ら優れた政治を行い、国が安定し文化が栄えたと後世に伝えられています。
後醍醐天皇は、この理想的な天皇政治を自らの手で再興したいという強い情熱を抱いていました。
その思いは、彼が自らの追号(おくりな)を「後醍醐」と定めたことからも明らかです。
これは、単に過去の栄光を懐かしむのではなく、天皇が国家の中心となり、その権威のもとに秩序ある社会を築き上げたいという強い意志の表れでした。
1321年(元亨元年)には、父である後宇多上皇が行っていた院政(天皇が譲位後に政治を行うこと)を廃止させ、本格的に親政を開始します。
これは、彼が目指す政治体制の第一歩と言えるでしょう。
しかし、その後醍醐天皇の理想を実現する上で、最大の障害となったのが鎌倉幕府の存在でした。
当時の皇位継承は、持明院統(じみょういんとう)と大覚寺統(だいかくじとう)という二つの皇統が、鎌倉幕府の意向を受けながら交互に天皇を出す「両統迭立(りょうとうてつりつ)」という不安定なシステムでした。
後醍醐天皇は大覚寺統の出身であり、このルールに従えば、彼の治世は限られたものとなり、自分の子孫に皇位を継承させることも、上皇として院政を敷くことも難しい状況でした。
天皇の意志ではなく、幕府の都合で皇位継承が左右される現状に対して、後醍醐天皇は強い不満を抱いていました。
天皇主導の政治を実現するためには、皇位継承の問題も含めて、幕府の介入を排除し、天皇の権力を回復する必要があったのです。
そのため、彼は鎌倉幕府から政治の実権を奪還することを決意します。
討幕への具体的な動きとして、後醍醐天皇はまず、自らの理想に共感する近臣たちを集めました。
日野資朝(ひのすけとも)や日野俊基(ひのとしもと)といった人物たちが、その中心となりました。
彼らと共に、後醍醐天皇は密かに討幕の計画を練り始めます。
また、後醍醐天皇は密教に深く傾倒していたことでも知られています。
有名な彼の肖像画には、密教法具を手にし、僧侶の法衣である袈裟(けさ)を身に着けた姿で描かれています。
この密教の力を借りて、幕府を討つための祈祷(きとう)も行っていたと言われています。
表向きは「懐妊のための祈祷」と称しながら、実際には討幕の呪詛(じゅそ)を行っていたという説もあるほどです。
このように、後醍醐天皇は、自身の政治的理想の実現と、皇統の未来を守るために、学問、宗教、そして謀略といったあらゆる手段を駆使して、鎌倉幕府打倒という困難な道へと進んでいったのです。
その強い意志と行動力が、やがて日本の歴史を大きく動かすことになります。
最初の挫折「正中の変」と隠岐への「島流し」
後醍醐天皇が理想とする天皇親政の実現と鎌倉幕府打倒への道は、決して平坦なものではありませんでした。
その最初の大きなつまずきとなったのが、1324年(元亨4年、後に正中元年に改元)に起きた「正中の変(しょうちゅうのへん)」です。
これは、後醍醐天皇とその近臣たちによる討幕計画が、事前に鎌倉幕府に露見し、未遂に終わった事件でした。
後醍醐天皇は、天皇主導の政治を行うため、日野資朝(ひのすけとも)や日野俊基(ひのとしもと)といった信頼できる側近たちと共に、幕府の京都における監視機関である六波羅探題(ろくはらたんだい)を襲撃する計画を立てました。
しかし、この計画は実行に移される前に、幕府側に密告されてしまいます。
結果として、計画の中心人物であった日野資朝や日野俊基らは捕らえられ、処罰されました。
後醍醐天皇自身は、この事件への関与を否定する弁明書を幕府に提出したことで、直接的な処分は免れましたが、計画の失敗は明らかでした。
この事件は、後醍醐天皇の討幕の意志がいかに固いものであったかを示すと同時に、幕府の監視体制がいかに厳しいものであったかを物語っています。
正中の変で一度は挫折を味わった後醍醐天皇でしたが、彼の討幕への情熱が消えることはありませんでした。
むしろ、その意志はより一層強固なものとなり、再び機会をうかがいます。
天皇は、自らの味方となる武士を各地から集めようと試みたり、寺社勢力に対して関東調伏(鎌倉幕府を討つための祈祷)を命じたりするなど、水面下で活動を続けていました。
特に、密教への傾倒を深め、幕府には「中宮の懐妊のための祈祷」と称しながら、実際には討幕の呪詛を行っていたとも言われています。
しかし、1331年(元徳3年、後に元弘元年に改元)、後醍醐天皇の二度目の討幕計画もまた、側近の一人であった吉田定房(よしださだふさ)の密告によって鎌倉幕府の知るところとなります。
身の危険を感じた後醍醐天皇は、三種の神器を携えて京都の御所を脱出し、笠置山(現在の京都府相楽郡笠置町)に立てこもり、幕府に対して兵を挙げました。
これが「元弘の乱(げんこうのらん)」の始まりです。
しかし、幕府は迅速に対応し、後醍醐天皇を廃位させ、持明院統の光厳天皇(こうごんてんのう)を新たに即位させました。
そして、圧倒的な兵力で笠置山を攻撃し、ついに後醍醐天皇は捕らえられてしまいます。
捕虜となった後醍醐天皇は、翌1332年(元弘2年)、謀反人として隠岐の島(現在の島根県隠岐郡)へと流されることになりました。
これは、かつて承久の乱で敗れた後鳥羽上皇が隠岐へ流された先例に倣ったものであり、後醍醐天皇にとっては最大の屈辱であったでしょう。
天皇が島流しにされるという事態は、彼の理想がいかに困難なものであったか、そして幕府の権勢がいかに強大であったかを改めて示す出来事でした。
しかし、この逆境が、彼の不屈の精神をさらに燃え上がらせるきっかけともなるのです。
不屈の脱出!鎌倉幕府滅亡への大きな貢献
隠岐の島への配流という、天皇としては最大の屈辱を味わった後醍醐天皇でしたが、彼の鎌倉幕府打倒と天皇親政への執念は消えるどころか、むしろ逆境の中でさらに強固なものとなっていきました。
そして、その不屈の精神と行動力が、やがて鎌倉幕府滅亡という歴史的な転換点を引き起こす大きな力となるのです。
後醍醐天皇が隠岐に流されている間も、彼に忠誠を誓う勢力は各地で討幕運動を続けていました。
特に、皇子である護良親王(もりよししんのう)や、河内の悪党(あくとう、既存の支配体制に反抗する武士団)として知られた楠木正成(くすのきまさしげ)らは、幕府軍に対して粘り強い抵抗を続け、討幕の気運を全国に広めていきました。
楠木正成が千早城(ちはやじょう)で繰り広げた巧みな籠城戦は、少数の兵で大軍を翻弄し、幕府の権威を揺るがすのに十分な影響力を持ったと言われています。
このような情勢の中、後醍醐天皇は隠岐からの脱出の機会をうかがっていました。
そして1333年(正慶2年、元弘3年)、ついにその機会が訪れます。
後醍醐天皇は、伯耆国(現在の鳥取県)の武将であった名和長年(なわながとし)らの手引きによって、釣り船に身を隠して隠岐の島を脱出することに成功しました。
脱出後、後醍醐天皇は船上山(せんじょうさん、現在の鳥取県東伯郡琴浦町)に行宮(あんぐう、仮の皇居)を築き、再び全国の武士たちに鎌倉幕府打倒のための挙兵を促す綸旨(りんじ、天皇の命令書)を発します。
この後醍醐天皇の不屈の呼びかけと、各地で続く討幕運動の高まりは、ついに鎌倉幕府の屋台骨を揺るがす事態へと発展しました。
幕府は後醍醐天皇追討のために軍を派遣しますが、その討伐軍の有力武将であった足利高氏(あしかがたかうじ、後の尊氏)が、突如として後醍醐天皇方に寝返ったのです。
これは幕府にとって致命的な打撃となりました。
足利高氏は京都の六波羅探題(ろくはらたんだい)を攻め滅ぼし、時を同じくして関東では新田義貞(にったよしさだ)が挙兵し、鎌倉を攻撃して陥落させました。
これにより、約150年続いた鎌倉幕府はついに滅亡し、鎌倉時代は終焉を迎えたのです。
この鎌倉幕府滅亡において、後醍醐天皇の役割は非常に大きかったと言えるでしょう。
彼自身が二度にわたる討幕計画を主導し、島流しという苦難を乗り越えて脱出し、再び討幕の旗頭として立ち上がったその不屈の精神は、多くの武士たちの心を動かしました。
もちろん、護良親王や楠木正成、そして最終的に幕府に反旗を翻した足利高氏や新田義貞といった武士たちの力なくして幕府滅亡はあり得ませんでしたが、彼らを一つにまとめ上げ、討幕へと向かわせたのは、後醍醐天皇の強い意志とカリスマ性であったと言えます。
京都に帰還した後醍醐天皇は、ついに政権を奪還し、自らの理想とする新たな政治の実現へと踏み出すことになるのです。
「建武の新政」開始と後醍醐天皇の理想政治
鎌倉幕府という巨大な武家政権を打ち破り、京都に凱旋した後醍醐天皇は、長年の悲願であった天皇中心の新たな政治体制の構築に着手します。
これが「建武の新政(けんむのしんせい)」と呼ばれる、日本の歴史上でも特筆すべき政治改革の始まりでした。
後醍醐天皇が目指したのは、単に政治の実権を武家から天皇の手に取り戻すだけでなく、彼が理想とする古代の天皇親政、すなわち「延喜・天暦の治」を現代に蘇らせることでした。
建武の新政は、1333年(元弘3年)に後醍醐天皇が京都に帰還した直後から本格的に開始されました。
まず、鎌倉幕府が擁立していた光厳天皇(こうごんてんのう)の即位とその元号であった「正慶」を否定し、自らの正統性を改めて宣言します。
そして、「今の例は昔の新義なり、朕が新儀は未来の先例たるべし」という有名な言葉で、これまでの慣習にとらわれず、自らが新たな時代の規範を作るという強い決意を示しました。
この言葉には、古い秩序を打ち破り、天皇の権威のもとに全く新しい国家体制を築き上げようとする後醍醐天皇の意気込みが込められています。
具体的な政策としては、まず天皇の権力を絶対的なものとするため、これまで政治を補佐してきた摂政・関白の職を事実上廃止しました。
そして、天皇の意思を直接政治に反映させるための新たな中央機関として、「記録所(きろくじょ)」、「恩賞方(おんしょうかた)」、「雑訴決断所(ざっそけつだんしょ)」などを設置しました。
記録所は重要政務の審議や記録、恩賞方は討幕に功績のあった者への恩賞の配分、雑訴決断所は土地などの訴訟処理を担当する機関でした。
これらの機関を通じて、天皇が直接政治の細部にまで関与し、迅速な意思決定を行うことを目指したのです。
また、後醍醐天皇は、公家(くげ)を中心とした貴族層を重視する一方で、武士の力を抑制しようとする姿勢も見せました。
論功行賞においては、討幕に大きな功績のあった武士たちよりも、自分に近い公家を優遇する傾向があり、これが後に武士たちの不満を高める一因となります。
さらに、天皇の権威を視覚的にも高めるため、壮大な大内裏(だいだいり、皇居)の造営を計画したり、新たな貨幣である「乾坤通宝(けんこんつうほう)」の鋳造を試みたりもしました。
これらの政策は、天皇の権威を内外に示し、新たな時代の到来を印象づける狙いがあったと考えられます。
特に、天皇の命令書である「綸旨(りんじ)」が非常に重視され、あらゆる決定が天皇の直接的な指示によって行われることを目指しました。
しかし、この後醍醐天皇の理想とした政治は、あまりにも急進的であり、現実社会との間に大きな摩擦を生じさせることになります。
伝統的な慣習や既得権益を無視した政策は、多くの人々の反感を買い、特に武士階級の不満は急速に高まっていきました。
建武の新政は、天皇親政という高い理想を掲げた壮大な実験でしたが、その理想と現実のギャップが、やがて政権の短命と新たな混乱を招くことになるのです。
それでも、後醍醐天皇が目指した理想の政治の姿は、その後の歴史にも大きな影響を与え続けることになりました。
後醍醐天皇は何をした?新政失敗と南北朝時代

- なぜ?「建武の新政」が短期間で失敗した理由
- 盟友から敵へ「足利尊氏」との対立と戦乱
- 吉野へ逃れ南朝樹立、南北朝時代の幕開け
- 後醍醐天皇の「息子」たちの動向とその運命
- 人間味あふれる後醍醐天皇の意外な「エピソード」
- 後醍醐天皇の「すごい」功績と歴史への影響
- 波乱の生涯の終焉、後醍醐天皇の無念の「死因」
なぜ?「建武の新政」が短期間で失敗した理由
後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒し、鳴り物入りで開始した「建武の新政」でしたが、残念ながらその理想は長続きせず、わずか2年半という短期間で崩壊してしまいました。
これほど早くに新しい政治が頓挫してしまった背景には、いくつかの複合的な要因が絡み合っていました。
最大の理由の一つとして挙げられるのは、後醍醐天皇の政策が、あまりにも理想主義的であり、当時の社会の実情や人々の感情を十分に考慮していなかった点です。
特に、公家を重視し武士を軽視する姿勢は、鎌倉幕府打倒に貢献した武士たちの大きな不満を買いました。
例えば、討幕の功績に対する恩賞の配分において、天皇に近い公家や寺社が優遇される一方で、命をかけて戦った武士たちへの恩賞は不十分であったり、土地の権利(所領安堵)がなかなか認められなかったりするケースが頻発しました。
武士にとって土地は何よりも重要な生活の基盤であり、その不安定さは政権への不信感を募らせるのに十分でした。
「二条河原の落書」という当時の風刺文には、「此頃都ニハヤル物、夜討、強盗、謀綸旨(にせりんじ)、召人(めしうど)、早馬、虚騒動(からさわぎ)、生頸(なまくび)、還俗(げんぞく)、自由出家。俄大名、迷者(まよいもの)。安心(あんじん)、を得たる者もなし」といった世相の混乱ぶりが描かれており、新政に対する人々の失望感がうかがえます。
また、後醍醐天皇は、天皇の権威を絶対的なものにしようと、旧来の慣習や制度を急速に改変しようとしました。
摂政・関白を置かず、天皇の命令書である綸旨(りんじ)一つで全てを決定しようとする独裁的な政治手法は、多くの人々の反発を招きました。
綸旨が乱発された結果、その内容が朝令暮改となることも少なくなく、天皇の命令の権威そのものが低下してしまう事態も起きました。
ひいては、偽物の綸旨が出回るなど、社会の混乱に拍車をかけたのです。
さらに、壮大な大内裏の造営計画や新しい貨幣の鋳造計画などは、戦乱で疲弊した民衆や武士たちにさらなる経済的負担を強いるものであり、現実離れした政策と受け止められました。
土地に関する訴訟も急増しましたが、新設された雑訴決断所などの機関も十分には機能せず、問題解決の遅れが不満を増幅させました。
加えて、後醍醐天皇の側近であった公家たちの中にも、天皇の急進的な改革についていけず、政権運営に協力的な姿勢を見せない者もいました。
例えば、陸奥守として東北地方の統治にあたっていた北畠顕家(きたばたけあきいえ)は、新政の問題点を指摘し、天皇に対して厳しい諫言(かんげん)を記した上奏文を送っています。
その内容は、恩賞の不公平、法令の頻繁な変更、贅沢の禁止、地方分権の必要性など、的確なものでしたが、必ずしも聞き入れられたわけではありませんでした。
これらの要因が複雑に絡み合い、建武の新政は武士だけでなく、公家や民衆からも支持を失い、短期間での崩壊という結末を迎えることになったのです。
理想に燃えた改革でしたが、その進め方があまりにも現実からかけ離れていたことが、大きな敗因と言えるでしょう。
盟友から敵へ「足利尊氏」との対立と戦乱
鎌倉幕府打倒という共通の目的のもと、一時的に強固な協力関係を築いた後醍醐天皇と足利尊氏(あしかがたかうじ)。
しかし、その蜜月は長くは続かず、建武の新政が始まると両者の関係は急速に悪化し、やがて日本を二分する大きな戦乱へと発展していきます。
盟友がなぜ敵対するに至ったのか、その背景には複雑な思いと政治的計算が絡み合っていました。
討幕運動において、足利尊氏は幕府の有力御家人でありながら後醍醐天皇に味方し、京都の六波羅探題を攻略するという大きな功績を上げました。
後醍醐天皇も当初は尊氏を高く評価し、建武の新政下では鎮守府将軍(ちんじゅふしょうぐん)という武士の最高位に近い役職や、自らの諱(いみな)である「尊治(たかはる)」から一字を与えて「尊氏」と名乗らせるなど、破格の厚遇をもって報いました。
この時点では、両者の関係は良好であったように見えます。
しかし、建武の新政が進むにつれて、両者の間に溝が生じ始めます。
後醍醐天皇が目指す天皇中心の公家重視の政治は、武士の棟梁としての立場を自負する尊氏にとって、受け入れがたいものでした。
特に、恩賞問題や土地政策の混乱は、多くの武士たちの不満を高め、その不満の受け皿として尊氏への期待が集まるようになります。
また、後醍醐天皇の皇子である護良親王(もりよししんのう)が失脚し、武士たちの間で人気があった彼が排除されたことも、尊氏の政治的影響力を相対的に高める結果となりました。
後醍醐天皇の側から見れば、日に日に勢力を増していく尊氏の存在は、自らの権威を脅かすものとして警戒心を抱かせるものでした。
決定的な亀裂が生じたのは、1335年(建武2年)に起きた「中先代の乱(なかせんだいのらん)」がきっかけです。
鎌倉幕府の執権であった北条高時の遺児・北条時行(ほうじょうときゆき)が、信濃で幕府再興の兵を挙げ、鎌倉を一時占拠しました。
この時、尊氏は後醍醐天皇の正式な許可(勅許)を得ないまま、弟の足利直義(ただよし)を救うためとして関東へ出兵し、反乱を鎮圧します。
問題はその後でした。
尊氏は鎌倉に留まり、後醍醐天皇の帰京命令に従わず、討伐に参加した武士たちに対して独断で恩賞を与え始めたのです。
これは、天皇の権威を無視し、独自の武家政権を樹立しようとする動きと見なされました。
これに対し、後醍醐天皇は尊氏の行動を反逆とみなし、新田義貞(にったよしさだ)に尊氏追討を命じます。
こうして、かつての盟友同士が刃を交えることになったのです。
緒戦では新田軍が箱根・竹ノ下の戦いで敗れ、尊氏軍は一時京都に迫りますが、楠木正成や北畠顕家らの奮戦により九州へと敗走します。
しかし、尊氏は九州で勢力を立て直し、再び京都へ進軍。
1336年(建武3年)の湊川の戦い(みなとがわのたたかい)で、新田・楠木軍は決定的な敗北を喫し、忠臣・楠木正成は自害して果てました。
この敗北により、後醍醐天皇は京都を追われることとなり、足利尊氏との対立は、日本全土を巻き込む南北朝の動乱へと発展していくのです。
理想を追求する天皇と、武家の現実を代表する武将との間の溝は、ついに埋まることなく、悲劇的な戦乱を生み出してしまいました。
吉野へ逃れ南朝樹立、南北朝時代の幕開け
足利尊氏との戦いに敗れ、京都を追われた後醍醐天皇の次なる一手は、多くの人々を驚かせると同時に、日本の歴史に新たな分裂と混乱の時代をもたらすものでした。
それは、険しい山々に囲まれた大和国吉野(現在の奈良県吉野郡)に逃れ、そこで独自の朝廷、すなわち「南朝(なんちょう)」を樹立するという大胆な決断でした。
これにより、京都には足利尊氏が擁立する持明院統の光明天皇(こうみょうてんのう)による「北朝(ほくちょう)」が、そして吉野には後醍醐天皇の南朝が存在するという、二つの朝廷が並び立つ「南北朝時代」が幕を開けることになります。
湊川の戦いで楠木正成をはじめとする有力な武将を失った後醍醐天皇は、一旦比叡山に逃れて抵抗を試みます。
しかし、戦況は厳しく、足利尊氏が京都を制圧し、持明院統の光明天皇を新たな天皇として擁立すると、後醍醐天皇は窮地に立たされます。
そして、足利尊氏との間で一時的な和睦が成立し、後醍醐天皇は三種の神器を新たな天皇に譲り渡し、京都の花山院(かざんいん)に幽閉されることになりました。
この時点で、多くの者は後醍醐天皇の政治生命は終わったと考えたかもしれません。
しかし、後醍醐天皇は決して諦めませんでした。
天皇としての正統性は自分にあり、武力によってその地位を奪われることは許されないという強い信念が、彼を突き動かしたのです。
幽閉されていた花山院を密かに脱出した後醍醐天皇は、1336年の末、腹心の者たちと共に吉野へと向かいます。
そして、吉野の行宮(あんぐう、仮の皇居)において、驚くべき宣言を行います。
それは、足利方に渡した三種の神器は偽物であり、本物は自分が所持しているというものでした。
これにより、自らが正統な天皇であることを改めて主張し、吉野に新たな朝廷を開いたのです。
なぜ吉野だったのでしょうか。
吉野は、古くから修験道の聖地であり、山深く守りやすい地形であると同時に、中央の政治から距離を置き、再起を図る場所としての歴史的背景も持っていました。
また、楠木正成など、かつて後醍醐天皇を支えた勢力の基盤に近い地域でもありました。
後醍醐天皇は、この地を拠点として、北朝とその背後にいる足利尊氏に対抗し、再び京都を奪還することを目指したのです。
こうして始まった南北朝時代は、その後約57年間にわたって続くことになります。
日本に二人の天皇と二つの朝廷が存在するという前代未聞の事態は、全国の武士や民衆を巻き込み、各地で戦乱が繰り返されることになりました。
後醍醐天皇の吉野への逃亡と南朝樹立は、彼の不屈の精神と、天皇としての強烈な自負心の表れでしたが、同時に日本社会に深い亀裂を生み出し、長い混乱の時代を招く結果となったのです。
後醍醐天皇自身の夢は吉野で潰えることになりますが、彼が灯した南朝の炎は、その後も子孫たちによって受け継がれていくことになります。
後醍醐天皇の「息子」たちの動向とその運命
後醍醐天皇の生涯は波乱に満ちたものでしたが、その激動の時代において、彼の息子たちもまた、父の理想と野望に深く関わり、それぞれが過酷な運命を辿ることになりました。
後醍醐天皇は多くの皇子をもうけましたが、その中でも特に歴史の表舞台で活躍し、あるいは悲劇的な最期を遂げた皇子たちの動向は、当時の混乱した世相を色濃く反映しています。
まず筆頭に挙げられるのが、護良親王(もりよししんのう)です。
彼は元弘の乱において、父である後醍醐天皇の討幕運動にいち早く呼応し、各地でゲリラ戦を展開して幕府軍を苦しめました。
その功績は大きく、建武の新政が始まると征夷大将軍に任じられるなど、一時は武士たちの期待を一身に集める存在でした。
しかし、その強い個性と影響力は、やがて足利尊氏との対立を招き、父である後醍醐天皇からも疎まれるようになります。
結果として失脚し、鎌倉に幽閉された後、中先代の乱の混乱の中で足利直義(尊氏の弟)の命により殺害されるという悲劇的な最期を遂げました。
武勇に優れ、カリスマ性も備えていましたが、政治的な駆け引きの中でその才能を十分に発揮することなく散ったのです。
次に、尊良親王(たかよししんのう)も、父の討幕運動に積極的に参加した皇子の一人です。
建武の新政下でも重用されましたが、足利尊氏との対立が激化すると、新田義貞らと共に北陸へ落ち延び、そこで北朝方と戦い続けました。
しかし、奮戦むなしく、越前国金ヶ崎城(現在の福井県敦賀市)で戦死するという壮絶な最期を遂げます。
皇太子であった恒良親王(つねよししんのう)もまた、父と共に戦乱に巻き込まれました。
一時は北陸で天皇として擁立された(北陸朝廷)とも伝えられますが、その後の消息は定かではなく、戦乱の中で行方不明になった、あるいは若くして亡くなったと考えられています。
弟の成良親王(なりよししんのう)は、一時、鎌倉将軍府の長官や、北朝の光明天皇の皇太子に立てられましたが、こちらも早世しています。
その一方で、後醍醐天皇の遺志を継ぎ、南朝の中心となったのが義良親王(のりよししんのう)、後の後村上天皇です。
父の崩御後、幼くして即位し、北畠親房(きたばたけちかふさ)らの補佐を受けながら、困難な状況の中で南朝を維持し続けました。
彼の粘り強い抵抗が、南北朝の対立を長期化させる一因ともなりました。
また、懐良親王(かねよししんのう、または「かねながしんのう」とも)は、征西大将軍として九州へ派遣され、一時は九州の大部分を制圧するほどの勢力を築き上げました。
明(中国)からは「日本国王良懐」として認められるなど、独自の勢力を保ちましたが、最終的には九州における南朝勢力も衰退していきます。
天台座主(てんだいざす、天台宗の最高の僧職)であった尊澄法親王(そんちょうほっしんのう)は、後に還俗して宗良親王(むねよししんのう)と名乗り、東国の南朝勢力をまとめるために活動したほか、優れた歌人としても知られています。
このように、後醍醐天皇の息子たちは、父の理想を実現するために、あるいはその遺志を継ぐために、それぞれの立場で奮闘しましたが、その多くは戦乱の中で命を落としたり、困難な生涯を送ったりしました。
彼らの運命は、後醍醐天皇が生きた時代の厳しさと、その理想の追求がいかに多くの犠牲を伴ったかを物語っていると言えるでしょう。
人間味あふれる後醍醐天皇の意外な「エピソード」
後醍醐天皇と言えば、鎌倉幕府を倒し、建武の新政を断行した強権的な天皇、あるいは足利尊氏と激しく対立し、南北朝の動乱を引き起こした執念の人物というイメージが強いかもしれません。
しかし、歴史書や文学作品を紐解くと、そうした政治的な側面だけでなく、彼の人間的な魅力や意外な一面を伝えるエピソードも数多く残されています。
これらの逸話は、後醍醐天皇が単なる理想家や権力者ではなく、学問や芸術を愛し、時には大胆な機転を見せ、また家族への深い愛情も持ち合わせていた、多面的な人物であったことを私たちに教えてくれます。
まず、後醍醐天皇は非常に学問熱心な人物でした。
特に中国の宋代に興った新しい儒学である朱子学(宋学)に深い関心を示し、僧侶の玄恵(げんえ)などからその教えを学びました。
また、有職故実(朝廷の儀式や法令、慣習)にも通じており、自ら『建武年中行事』という書物を著しています。
これは、朝廷の儀式を復興させ、天皇の権威を高めようとする彼の意志の表れでもありました。
和歌の才能にも恵まれ、多くの優れた歌を残しており、その作品は勅撰和歌集にも収録されています。
後の室町幕府初代将軍となる足利尊氏の和歌の才能を早くから見抜いていたというエピソードも、彼の文化的な素養の高さを示しています。
芸術面では、琵琶の名手としても知られていました。
皇室に伝わる神器「玄象(げんじょう)」という琵琶を愛用し、その演奏は周囲を魅了したと言われています。
また、当時流行し始めた闘茶(とうちゃ、茶の産地などを飲み当てる遊び)の会を催すなど、新しい文化にも積極的に触れていました。
『太平記』などには、後醍醐天皇が唐物(からもの、中国からの輸入品)を非常に好み、手に入れた貴重な品々を近臣たちに気前よく分け与えたという逸話も残されており、彼の豪放な一面をうかがわせます。
彼の機転と大胆さを示す有名なエピソードとしては、元弘の乱で隠岐の島に流された後の脱出劇があります。
軍記物語である『梅松論(ばいしょうろん)』によれば、追っ手の船が迫る中、後醍醐天皇は船頭に命じて船に積んであった大量のイカを自分の体の上に覆い被せさせ、その下に隠れることで追手の目を欺き、無事に脱出に成功したとされています。
天皇という高貴な身分でありながら、このような奇策を用いる大胆さは、彼の非凡な発想力と執念深さを物語っています。
また、隠岐脱出後に船上山(せんじょうさん)で綸旨(天皇の命令書)を発給する際、正式な奉者(ほうじゃ、文書を発給する役人)が側にいなかったため、側近の千種忠顕(ちぐさただあき)になりすまし、その花押(かおう、サイン)まで真似て自ら綸旨を作成したという話も伝わっています。
これは、形式を重んじる天皇としては異例の行動であり、目的のためには手段を選ばない彼の徹底した一面を示していると言えるでしょう。
一方で、家族に対する深い愛情も持ち合わせていました。
正妃であった西園寺禧子(さいおんじきし)とは非常に仲睦まじく、禧子が病に倒れた際には手厚く看護し、その死を深く悲しんだと伝えられています。
また、皇女である懽子内親王(かんしないしんのう)が伊勢神宮の斎宮(さいぐう)となる儀式(野宮入り)を、討幕計画で緊迫した状況下にもかかわらず、娘のために時間を割いて執り行ったことからも、父親としての愛情がうかがえます。
これらのエピソードは、後醍醐天皇が歴史を動かした偉大な天皇であると同時に、喜怒哀楽を持ち、学問や芸術を愛し、時には大胆な行動も辞さない、一人の人間であったことを私たちに伝えてくれます。
後醍醐天皇の「すごい」功績と歴史への影響
後醍醐天皇の政治改革である「建武の新政」は、わずか2年半で失敗に終わり、その後、南北朝の長い内乱時代を招いたことから、彼の評価はしばしば否定的なものになりがちです。
しかし、その短い治世と波乱に満ちた生涯の中にも、日本の歴史に大きな影響を与えた「すごい」功績や、注目すべき側面がいくつも存在します。
単に幕府を倒したというだけでなく、彼が目指した理想や、その行動が後世に与えた影響を多角的に見ることで、後醍醐天皇の真の重要性が明らかになるでしょう。
まず、最も大きな功績として挙げられるのは、約150年間にわたり日本の実権を握っていた鎌倉幕府を、天皇自らが主導して打倒したことです。
これは、武家政権の支配が盤石と思われていた時代において、天皇の権威を再び高めようとした画期的な試みでした。
二度にわたる討幕計画の失敗と隠岐への配流という苦難を乗り越え、不屈の精神で幕府を滅亡に追い込んだその行動力と執念は、まさに驚嘆に値します。
この成功体験は、その後の武家政権のあり方にも影響を与え、天皇や朝廷の存在意義を改めて人々に意識させるきっかけとなりました。
建武の新政自体は短命でしたが、そこで試みられた政策の中には、後の室町幕府に影響を与えたものも少なくありません。
例えば、土地の所有権を明確にし、その引き渡しに際して国家権力による強制執行を導入しようとした試みは、武士社会の安定に寄与する可能性を秘めていました。
また、それまで武士に与えられることの少なかった朝廷の官位を恩賞として積極的に活用したことは、武士の身分秩序に新たな価値観をもたらしました。
さらに、東北地方に陸奥将軍府(むつしょうぐんふ)を、関東地方に鎌倉将軍府を置くなど、地方統治のあり方についても新たな構想を示しました。
裁判制度においても、事件の種類や地域によって担当を分ける「一番一区制」のような合理的なシステムを導入しようとした点は注目されます。
これらの試みは、必ずしも成功したとは言えませんが、日本の統治システムが中世から近世へと移行していく過程で、重要な布石となったと言えるでしょう。
文化的な側面においても、後醍醐天皇の功績は見逃せません。
彼は学問を奨励し、特に宋学(朱子学)の受容に積極的でした。
また、自らも優れた書家であり、その書風は「宸翰様(しんかんよう)」として後世に伝えられています。
和歌や雅楽(ががく)にも深い造詣を持ち、文化の保護者としての一面も持っていました。
このような文化的な活動は、戦乱の時代にあっても、日本の伝統文化を継承し発展させる上で重要な役割を果たしたと言えます。
さらに、後醍醐天皇の存在は、足利尊氏をはじめとする多くの武士たちに大きな影響を与えました。
敵対関係になったとはいえ、尊氏が生涯を通じて後醍醐天皇に対してある種の敬愛の念を抱き続けたとされることは、後醍醐天皇が単なる政敵ではなく、時代を動かすカリスマ性を持った人物であったことを示唆しています。
南北朝の内乱という大きな混乱を引き起こしたことは事実ですが、その一方で、旧来の秩序を打ち破り、新たな時代への扉を開いたという点において、後醍醐天皇の「すごい」功績と歴史への影響は、多角的に評価されるべきでしょう。
彼の挑戦と挫折は、その後の日本の歴史を考える上で、避けては通れない重要なテーマであり続けています。
波乱の生涯の終焉、後醍醐天皇の無念の「死因」
鎌倉幕府打倒、建武の新政、そして吉野での南朝樹立と、まさに日本の歴史を激しく揺り動かした第96代天皇、後醍醐天皇。
その波乱に満ちた生涯は、自らの理想を追い求めた執念の連続でしたが、ついに京都への帰還という最大の夢を果たすことなく、終わりを迎えます。
彼の最期と「死因」には、志半ばで倒れた英雄の無念さが色濃く漂っています。
後醍醐天皇は、足利尊氏に京都を追われ、1336年末に吉野の山中に入り、南朝を開きました。
しかし、吉野での生活は決して安楽なものではなく、北朝及びそれを支持する足利幕府との間で、絶え間ない戦いが続きました。
南朝方は兵力や物資の面で常に劣勢に立たされており、後醍醐天皇は各地に皇子たちを派遣して勢力の回復を図りますが、戦況が好転することは稀でした。
信頼していた楠木正成や新田義貞といった有力な武将たちは次々と戦死し、皇子たちの中にも戦乱の中で命を落とす者が相次ぎました。
京都奪還という悲願は遠のくばかりで、後醍醐天皇の心労は計り知れないものがあったでしょう。
そして、1339年(延元4年/暦応2年)8月、後醍醐天皇は病に倒れます。
具体的な病名は記録されていませんが、長年にわたる政治的苦闘、度重なる戦乱、そして吉野での厳しい生活が、彼の心身を蝕んでいたことは想像に難くありません。
直接の「死因」は病とされていますが、その背景には、過酷な状況下での心労の積み重ねがあったと言えるでしょう。
自らの病が重いことを悟った後醍醐天皇は、皇子の義良親王(のりよししんのう、後の後村上天皇)に皇位を譲り、そのわずか数日後、吉野の行宮(あんぐう)で崩御しました。
享年52歳。
まさに、理想と執念に生きた英雄の、志半ばでの無念の死でした。
軍記物語である『太平記』には、後醍醐天皇の最期について印象的な記述が残されています。
それによれば、後醍醐天皇は崩御の際に、「玉骨(ぎょっこつ)は縦(たと)ひ南山(なんざん)の苔(こけ)に埋(うず)まるとも、魂魄(こんぱく)は常(つね)に北闕(ほっけつ)の天(てん)を望(のぞ)まん」(私の亡骸はたとえ吉野の山中に埋もれようとも、魂は常に北の都、京都の空を望み続けるであろう)という遺言を残したとされています。
この言葉は、彼の京都回復への執念がいかに強かったかを物語っており、後世の人々に深い感銘を与えました。
実際に、奈良県吉野町にある後醍醐天皇の陵墓「塔尾陵(とうのおのみささぎ)」は、多くの天皇陵が南向きであるのに対し、京都の方角を向いた北向きに作られているという伝承があり、この遺言を反映したものと考えられています。
後醍醐天皇の死後も、南朝は後村上天皇に引き継がれ、南北朝の対立はその後数十年にわたって続くことになります。
彼の死は、一つの時代の終わりであると同時に、新たな混乱の継続をも意味していました。
しかし、彼の不屈の精神と、天皇親政という理想を追い求めた姿は、良くも悪くも日本の歴史に強烈な印象を残し、後の時代にも様々な影響を与え続けることになったのです。
足利尊氏でさえ、後醍醐天皇の死を悼み、その菩提を弔うために京都に天龍寺を建立したことは、彼の存在がいかに大きなものであったかを示していると言えるでしょう。
後醍醐天皇の「死因」は病でしたが、その生涯は、まさに日本の歴史そのものを揺るがすほどの激しいエネルギーに満ちていたのです。
後醍醐天皇は結局のところ何をしたのか?総括
後醍醐天皇の生涯は、まさに日本の歴史が大きく動いた時代そのものでしたね。彼が一体何をしたのか、その足跡を辿ってみましょう。
- 鎌倉時代の終わり頃、皇室が二つに分かれていた複雑な状況の中、後醍醐天皇は「中継ぎ」という立場で天皇の位につきました。
- しかし彼はその立場に満足せず、昔の醍醐天皇や村上天皇が行ったような、天皇が自ら政治を行う「親政」を強く理想としていました。
- 自分の子供たちに皇位を継がせたい、そして幕府の言いなりではない政治を行いたいという思いから、鎌倉幕府を倒すことを決意します。
- 最初の挑戦である「正中の変」(1324年)は、残念ながら計画が事前に幕府に漏れてしまい、失敗に終わってしまいました。
- それでも諦めきれなかった後醍醐天皇は、再び討幕を計画しますが、「元弘の乱」(1331年)で幕府軍に敗れ、遠い隠岐の島へと流されてしまいます。これが「島流し」ですね。
- ところが、ここからが後醍醐天皇のすごいところです。不屈の精神で隠岐の島を脱出し、楠木正成や、後に敵対することになる足利高氏(尊氏)といった武士たちの力を借りて、1333年、ついに鎌倉幕府を滅亡へと追い込みました。
- 幕府を倒した後、後醍醐天皇は天皇が中心となる新しい政治、「建武の新政」を意気揚々と開始します。これが彼の大きな仕事の一つです。
- しかし、この新しい政治は、貴族である公家を重視しすぎたり、武士への恩賞が公平でなかったりしたため、多くの武士から不満の声が上がりました。
- 天皇の命令書である綸旨をたくさん出しすぎたり、急すぎる改革や財政的な問題もあって、建武の新政は残念ながらわずか2年半という短い期間で失敗に終わってしまいます。
- そして、かつて幕府を倒すために協力した足利尊氏との間にも溝が深まり、ついには武力で争う事態にまで発展してしまいました。
- 湊川の戦いで足利尊氏の軍に敗れた後醍醐天皇は、都である京都を追われることになります。
- しかし、それでも彼は諦めませんでした。奈良の吉野へと逃れ、そこで「南朝」という新たな朝廷を開き、京都の「北朝」(足利尊氏が立てた朝廷)と対立する「南北朝時代」がここから始まったのです。
- 後醍醐天皇の息子たち、例えば護良親王や尊良親王、そして後に南朝を継ぐ義良親王(後村上天皇)なども、父である後醍醐天皇の戦いに深く関わり、その多くが厳しい運命を辿りました。
- 政治や戦いだけでなく、後醍醐天皇は学問、特に中国から伝わった宋学を好み、和歌や琵琶などの芸術にも通じた文化人としての一面も持っていました。数々の「エピソード」がその多才ぶりを伝えています。
- 京都へ戻り、再び天下を統一するという夢は叶うことなく、1339年、後醍醐天皇は吉野の地で病のため52歳でその波乱の生涯を閉じました。その「死因」は、長年の心労も大きかったのかもしれません。
関連記事
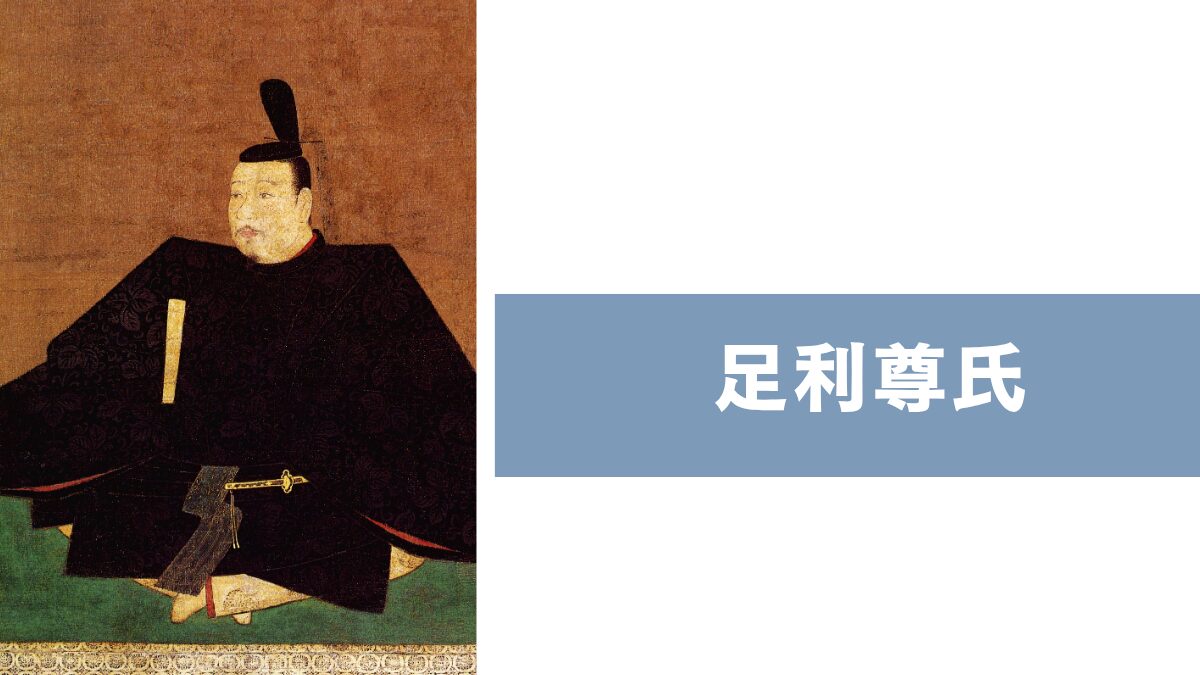
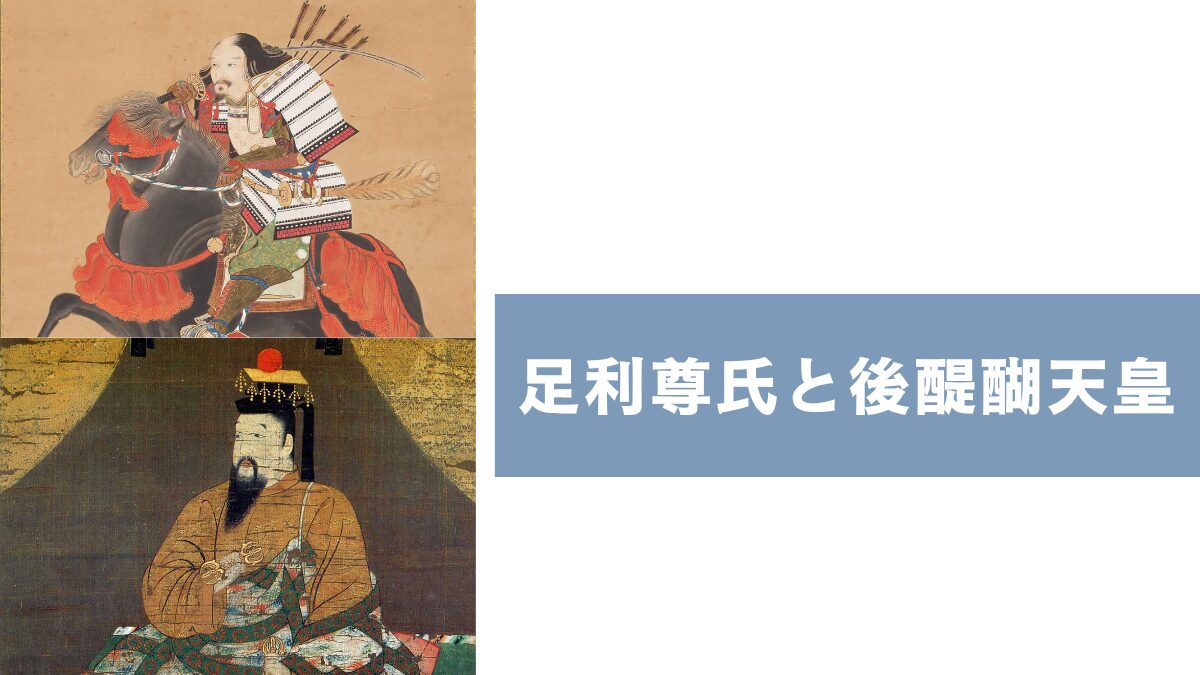
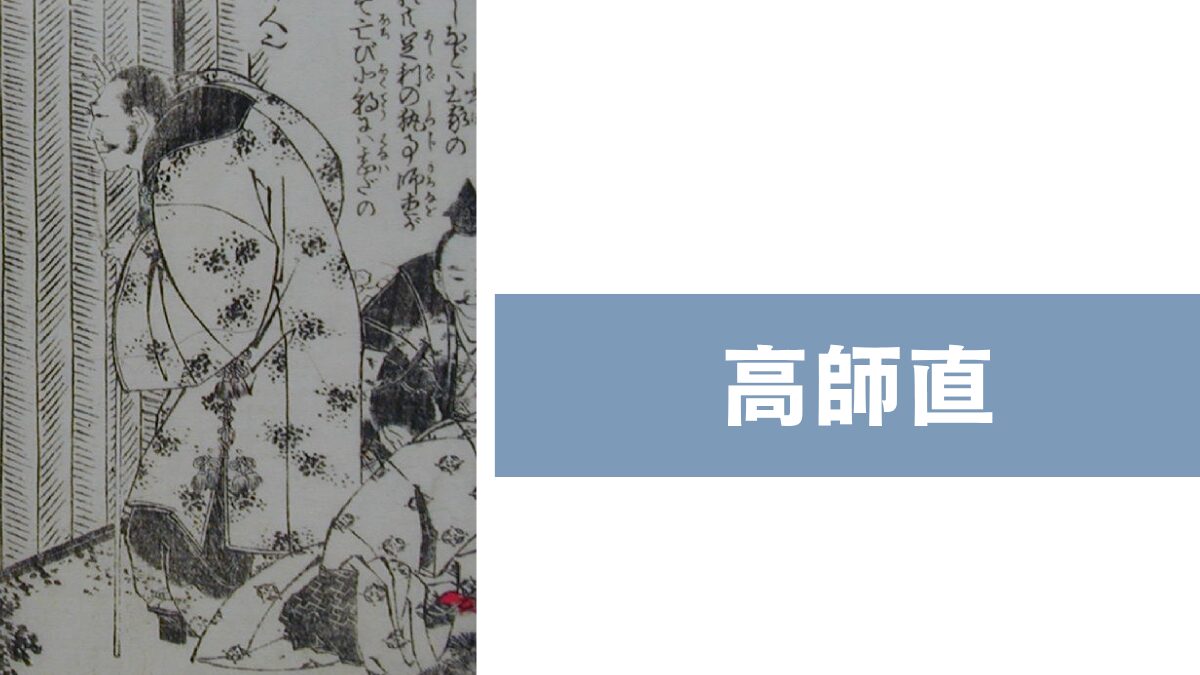
参考サイト
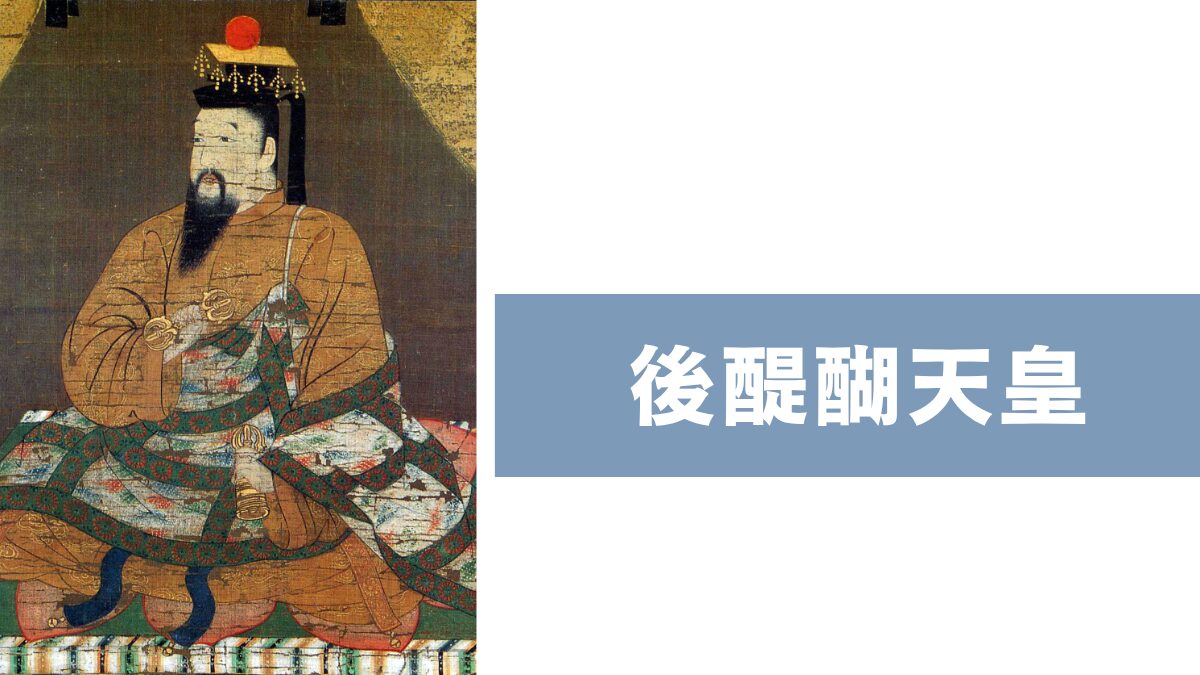

コメント