明治時代の歴史を学んでいると、「廃藩置県」と「版籍奉還」という2つの用語がよく登場しますよね。
名前も似ていて、どちらも江戸時代から明治政府へと移り変わる中で行われた重要な政策のため、違いがよくわからなくなる方も多いのではないでしょうか。
特に「どちらが先に行われたのか」「目的や流れはどうだったのか」など、学校の授業だけでは整理しきれない部分もあると思います。
この記事では、そんな混乱しがちな「廃藩置県と版籍奉還の違い」について、わかりやすく丁寧に解説します。
それぞれの政策が実施された時期(いつ)、中央集権を目指した背景や目的、そしてその結果や影響、さらには地租改正や大政奉還との関係性まで網羅的に紹介していきます。
また、単に用語を暗記するのではなく、「流れ」や「提案した人」「メリット・デメリット」などをセットで理解することで、歴史のつながりが自然と見えてくる構成になっています。
以下のようなことがこの記事を読むとしっかりわかるようになります。
- 廃藩置県と版籍奉還の違いとそれぞれの目的・背景
- どちらが先に行われたか、時系列での流れ
- メリット・デメリットやその結果として起きた社会の変化
- 地租改正や大政奉還との関連性とその意味
廃藩置県と版籍奉還の違いを簡単に解説

- 廃藩置県と版籍奉還はどちらが先か
- 廃藩置県と版籍奉還はいつ行われたのか
- 廃藩置県と版籍奉還の目的をわかりやすく解説
- 廃藩置県と版籍奉還の流れを時系列で紹介
- 廃藩置県と版籍奉還による具体的な変化とは
廃藩置県と版籍奉還はどちらが先か
廃藩置県と版籍奉還のうち、先に行われたのは版籍奉還です。
この二つは似たような名称と目的を持つため、混同されやすいのですが、実際には実施された順番が異なります。制度としての意味や役割も異なるため、順序と併せてその背景も理解しておくと混乱を防げます。
版籍奉還が行われたのは1869年(明治2年)です。
これは明治政府が成立してからまだ間もない時期で、当時の日本は旧幕府体制から新しい中央政府へと大きく移行している過渡期にありました。
一方、廃藩置県が行われたのはその2年後の1871年(明治4年)になります。
この順番が重要なのは、版籍奉還がいわば廃藩置県に向けた「準備段階」であったためです。
具体的には、版籍奉還によって大名が自分の支配していた土地(版)と人民(籍)を天皇に返上しました。
これは大名の権力を形式的に明治政府へ移すことを意味しますが、当初は旧大名が「知藩事」として引き続き自分の藩を治めるという妥協的な体制がとられました。
つまり、見かけ上は土地も人民も政府のものになりましたが、実質的には旧来の藩体制が続いていたのです。
この状況を抜本的に改めるために、明治政府は1871年に廃藩置県を実施します。
ここではすべての藩を廃止し、代わりに「府」や「県」が置かれました。
また、それまでの藩主は知藩事を解任され、中央政府から派遣された県令(現在の知事)が統治を行うようになります。
これにより、地方の行政が完全に中央政府の管理下に置かれ、日本は中央集権国家としての体制を本格的にスタートさせました。
このように、版籍奉還と廃藩置県は密接な関係を持ちつつも、段階的に行われた制度改革です。
どちらが先かを正確に知ることは、明治維新の流れを理解する上でとても重要です。
廃藩置県と版籍奉還はいつ行われたのか
廃藩置県と版籍奉還が行われた年は、それぞれ1871年(明治4年)と1869年(明治2年)です。
この2年の間に、日本の政治体制は大きく様変わりしました。年号を正確におさえることで、明治維新の改革の順序や背景がより明確に見えてきます。
まず、1869年に実施された版籍奉還について見てみましょう。
これは、長州藩や薩摩藩といった倒幕に積極的に関わった有力藩が中心となり、自発的に土地と人民を明治天皇へ返上したことから始まりました。
この年の6月には、明治政府が正式にこの動きを勅命として認め、全国の藩主が次々に従っていきます。
当時の日本は、まだ各藩が独立国家のような体制を取っており、明治政府の実効支配は限定的でした。
そのため、まず形式的にでも全国の土地と人民を政府の下に置く必要がありました。
版籍奉還は、そのための第一段階といえる改革です。
次に、1871年に実施されたのが廃藩置県です。
これは、藩を完全に廃止し、中央政府が派遣する県令による統治体制へと切り替えるものでした。
知藩事として藩を治めていた旧大名たちは解任され、東京へ移住を命じられます。
また、各県に中央の役人が送られ、地方の行政は完全に明治政府の支配下に入りました。
この2つの年号を覚えるコツとしては、語呂合わせが有名です。
版籍奉還(1869年)は「はん(8)せき(6)ほうかん(9)」、廃藩置県(1871年)は「藩(8)は(7)廃(1)止」と覚えるとスムーズです。
こうして、日本は地方分権から中央集権への大転換をわずか数年で成し遂げていったのです。
それぞれの年に何が行われたのかを正確に理解しておくことが、歴史の流れをつかむ第一歩になります。
廃藩置県と版籍奉還の目的をわかりやすく解説
廃藩置県と版籍奉還の目的は、どちらも中央集権体制の確立です。
ただし、その進め方と段階には大きな違いがあります。
それぞれの改革がなぜ必要だったのかを理解することで、日本が近代国家へと進んでいく過程が見えてきます。
まず、版籍奉還の目的は、藩主が支配していた土地(版)と人民(籍)を天皇に返上させ、形式的に全国を国家のものとすることでした。
このとき、各藩主はそのまま知藩事として藩を治めることが認められたため、反発は最小限に抑えられました。
政府にとっては、混乱を避けながら藩主の支配権を取り上げる第一歩となったのです。
一方で、廃藩置県の目的は、そうした表面的な中央集権ではなく、実質的な統治権を政府が掌握することにありました。
つまり、藩という単位を完全に廃止し、中央から役人を派遣することで地方の政治・徴税・軍事すべてを統一的に管理できる体制に移行させたのです。
なぜこのような中央集権が求められたのでしょうか。
背景には、欧米列強との対等な国づくりを目指す明治政府の方針がありました。
当時の日本は、欧米の植民地主義に対抗するには国家としての統一と強固な政府の力が不可欠だと認識していたのです。
さらに、各藩の財政破綻や軍事力のバラつき、独自の法制度なども大きな問題でした。
地方ごとにバラバラな体制では、日本全体として一体的に機能することができず、内乱や反乱のリスクも高まっていました。
こうした背景から、明治政府は段階的に地方の統治権を奪い取り、国家主導の統一を進めていったのです。
このように、版籍奉還と廃藩置県の目的はどちらも「国家の一体化」にありますが、アプローチは異なります。
前者は穏やかな権限の返上、後者は実効的な支配体制の構築という形で、それぞれが役割を果たしていたのです。
廃藩置県と版籍奉還の流れを時系列で紹介
廃藩置県と版籍奉還の流れは、明治維新における中央集権化の過程であり、段階的かつ計画的に進められた一連の改革です。
この流れを時系列で整理することで、それぞれの改革の役割とつながりがより明確になります。
まず、1867年(慶応3年)に「大政奉還」が行われ、徳川慶喜が政権を天皇に返上しました。
ここから幕府体制は事実上終わりを迎えます。
その後、1868年に「王政復古の大号令」が発せられ、明治政府が正式に発足しました。
1869年に入ると、中央集権を目指す明治政府は、旧来の藩主による支配体制を形式的にでも改めるために、版籍奉還を打ち出します。
1月には薩摩・長州・土佐・肥前の4藩が率先して版籍奉還を申し出、6月には勅命として正式に実施されました。
この時点で、大名は知藩事として藩の統治を続けていましたが、徴税や軍事の権限は保持したままでした。
つまり、見た目の改革にとどまり、中央集権の実効性には限界があったのです。
そこで明治政府は、次なる一手として廃藩置県の準備を進めます。
1871年の初夏には、薩摩・長州・土佐から御親兵を集め、万一の反乱に備える体制を構築。
同年7月14日、ついに廃藩置県を断行しました。
この政策により、全国の藩はすべて廃止され、府や県へと置き換えられました。
知藩事は解任され、代わりに中央政府から派遣された県令が地方を統治する体制が整いました。
その後、県の統廃合が進められ、最終的には現在の47都道府県の原型が出来上がっていきます。
このように、明治政府は「大政奉還 → 版籍奉還 → 廃藩置県」という3段階の流れで、封建体制から中央集権国家へと大転換を果たしていきました。
制度の入れ替えだけでなく、その背景や準備も含めて、明治維新は非常に緻密な改革だったと言えます。
廃藩置県と版籍奉還による具体的な変化とは
廃藩置県と版籍奉還がもたらした変化は、日本の政治・社会・軍事の仕組みそのものを根底から変えるものでした。
とくに中央集権体制の確立に向けた制度的・実務的な改革が進んだ点が特徴です。
まず、版籍奉還によって起きた変化を見ていきましょう。
この政策により、全国の藩主が自らの領地と領民を天皇に返上しました。
名目上、日本全国の土地と人民は天皇のものとなり、国家が一体化したかのように見えます。
しかし、実際には旧藩主が知藩事として引き続き藩を治め、税の徴収や軍事力の保持もそのままでした。
つまり、見た目は変わっても中身はほとんど江戸時代と同じというのが実情でした。
次に、廃藩置県が行われると、本格的な変化が訪れます。
まず、藩という単位が消滅し、「府」や「県」という行政区画が新たに設置されました。
これにより、藩ごとの自治的な制度は完全に廃止され、中央政府による直接統治が実現します。
知藩事だった旧藩主は解任され、東京への移住を命じられます。
代わりに政府から派遣された県令が地方を管理するようになり、行政の一元化が進みました。
さらに重要なのが、軍事と財政の統一です。
藩ごとの兵士(藩兵)は解散され、新政府による常備軍が組織されていきます。
また、各藩が独自に徴収していた税も、中央政府が一括して管理する仕組みへと切り替えられました。
これらの変化により、日本は地方分権から中央集権へと大きく舵を切ることになります。
その影響は行政だけにとどまらず、教育、軍事、経済など多方面に及びました。
この中央集権化がなければ、近代国家としての日本の成長はあり得なかったといえるでしょう。
ただし、こうした急速な変革は一部に不満も生みました。
とくに士族層の不満は後の「士族の反乱」へとつながっていきます。
このように、制度改革は成功の一方で、新たな社会的課題も生み出したのです。
廃藩置県と版籍奉還の違いとその背景

- 廃藩置県と版籍奉還のメリット・デメリット
- 廃藩置県と版籍奉還の提案した人は誰?
- 廃藩置県と版籍奉還の結果と影響とは
- 地租改正との関係もあわせて理解しよう
- 大政奉還との違いと関連性を解説
- 現在の都道府県制度との関係を知ろう
廃藩置県と版籍奉還のメリット・デメリット
廃藩置県と版籍奉還は、明治政府が日本を中央集権国家へと転換するために行った大改革です。
そのため、多くのメリットがありましたが、同時にいくつかのデメリットや課題も存在しました。ここでは、両制度のメリットとデメリットを整理して解説します。
まず、版籍奉還のメリットは、封建的な藩主の支配体制に一石を投じるきっかけとなった点です。
形式上とはいえ、大名が自らの領地と人民を明治政府へ返上することで、政府が全国の土地と民を統一的に管理する第一歩を踏み出しました。
これにより「王土王民」という考え方が具体的に現実化し、中央集権への地ならしが行われたといえます。
また、反発を避けるために旧大名を知藩事として任命し、名目上の権力を与えたことで、比較的スムーズに改革が進みました。
一方で、版籍奉還のデメリットは、実質的な改革効果が乏しかった点にあります。
知藩事となった旧大名は、引き続き領地内で税を徴収し、兵を持ち続けていたため、旧来の支配構造はほとんど温存されていました。
そのため、本格的な中央集権の実現には至らず、次の段階である廃藩置県が必要となったのです。
次に、廃藩置県のメリットについて見ていきましょう。
この制度によって、全国の藩が廃止され、府と県という新たな行政単位が設けられました。
知藩事は解任され、中央政府から派遣された県令が地方行政を担当することで、政府の命令が末端まで行き渡る仕組みが整いました。
軍事や税の管理も政府が一元化したことで、国家としての統治能力が飛躍的に向上したのです。
しかし、廃藩置県にもデメリットは存在します。
最大の懸念は、旧藩主や士族層の不満の高まりです。
特に、知藩事の解任や藩兵の解散によって、彼らの既得権が失われたことは大きな反発を生み、一部は後の士族反乱へとつながります。
また、新たに中央から派遣された県令による統治には、地方の実情とのズレや、官僚による強引な運営も見られたという記録があります。
このように、廃藩置県と版籍奉還はいずれも国家の近代化には欠かせない施策でしたが、過渡期特有の課題を抱えた側面も忘れてはならないでしょう。
廃藩置県と版籍奉還の提案した人は誰?
廃藩置県と版籍奉還という重大な政策は、明治政府の中でも特に中心的な役割を果たした人物たちによって提案・実行されました。
いずれも国家の将来を見据えた長期的な視野に基づいたものであり、その発案者たちの先見性がうかがえます。
版籍奉還を最初に提案したとされるのは、大久保利通と木戸孝允です。
彼らは、薩摩藩と長州藩の出身で、いずれも明治維新を推進した中心人物でした。
特に大久保は、中央集権国家を目指す強い意志を持っており、藩主による土地と人民の返上が不可欠であると考えていました。
木戸孝允もまた、諸藩連合的な政府体制では日本が欧米列強に対抗できないと判断し、中央集権の必要性を主張していました。
この構想に最初に応じたのは、長州藩の毛利元徳、薩摩藩の島津忠義、土佐藩の山内豊範、肥前藩の鍋島直大という4藩の藩主たちでした。
いずれも新政府樹立に関わった有力諸侯であり、その協力が他藩への波及を生み出しました。
これを「薩長土肥の版籍奉還」と呼ぶこともあります。
一方、廃藩置県の構想もまた、大久保利通が主導的立場にありました。
さらに西郷隆盛や木戸孝允もこの計画に深く関わっています。
特に西郷は軍事面で重要な役割を担い、薩摩・長州・土佐の3藩から「御親兵」を編成することで、廃藩置県の断行に向けた軍事的支柱を築きました。
また、明治天皇の存在も無視できません。
版籍奉還や廃藩置県はいずれも「勅命」という形をとって発表されました。
これは、政策への正統性と威厳を持たせるための演出であり、明治政府が天皇中心の国家を築こうとしたことの表れでもあります。
このように、これらの政策は一部のリーダーたちの主導によって推し進められました。
彼らは旧体制の権益にとらわれず、時代の要請に応じた果敢な改革を選択したのです。
廃藩置県と版籍奉還の結果と影響とは
廃藩置県と版籍奉還がもたらした結果は、日本の国家体制を根本から変えるものでした。
これらの改革によって、地方分権的な幕藩体制から、中央政府が権力を掌握する中央集権体制への転換が実現したのです。
まず、版籍奉還の結果から見ていきます。
大名が土地と人民を天皇に返還したことで、形式上は日本全国が政府の統治下に置かれました。
旧藩主たちは知藩事に任命され、その地位は一時的に保障されましたが、実際には権限の一部を失った形となりました。
この動きは、中央政府が地方支配に着手するための土台を築いた点で、大きな意味がありました。
ただし、前述の通り、実質的には各藩の軍事力や徴税権は維持されたままで、中央集権としては不完全でした。
そのため、版籍奉還のあとには、より決定的な措置である廃藩置県が実施されます。
廃藩置県の結果、全国の藩が正式に廃止され、「府」と「県」に再編成されました。
知藩事は解任され、中央政府の役人(県令)が地方の統治を担うようになったことで、行政、財政、軍事が一元管理されるようになります。
この制度改革によって得られた最大の効果は、国家運営の効率化と統一的な政策運用の実現です。
地方ごとにバラバラだった法制度や軍制、経済活動が、中央政府の方針に従って整備されていきました。
また、徴兵制度の導入や学制の整備といった、後の近代化政策の基盤もこの改革によって整いました。
地方においても官僚による統治が進み、地域格差の是正やインフラ整備が進んだという報告もあります。
一方で、士族や旧藩主にとっては、既得権を奪われる大きな転機でもありました。
特に士族層の中には、武士としての誇りや収入源を失ったことで不満を募らせる人も多く、後の西南戦争や士族の反乱につながる要因ともなりました。
このように、廃藩置県と版籍奉還は日本の政治体制に多大な変革をもたらし、近代国家としての歩みを本格化させる土台を築いたのです。
地租改正との関係もあわせて理解しよう
廃藩置県と版籍奉還とあわせて理解しておきたいのが、「地租改正(ちそかいせい)」です。
これは1873年に実施された税制の大改革で、中央集権国家の基盤整備に欠かせない制度のひとつでした。
実は、版籍奉還や廃藩置県の延長線上にある政策として位置づけられており、それらと強く関係しています。
まず、版籍奉還によって全国の土地と人民が政府のものとなりました。
しかし、実質的な徴税は依然として各藩主が行っていたため、国家としての財政基盤は弱いままでした。
その後の廃藩置県によって徴税権が中央政府へと移され、土地の管理と税の制度を全国統一する準備が整いました。
このような流れを受けて、地租改正が実施されます。
それまでの税は主に年貢として米で納めるものであり、収穫量や天候に大きく左右されていました。
その不安定さを解消し、現金で一定額を納める「地租(ちそ)」という新しい制度が導入されます。
納税者は土地所有者と定められ、地価に基づいて税額が計算されるようになりました。
この制度のメリットは、政府にとって安定した収入源が確保できることです。
定額で現金収入を得られるため、近代国家として必要な軍備や教育、インフラの整備に予算を充てることが可能となりました。
また、農民にとっても、収穫量に関係なく税額が一定であるという点で、予測と計画がしやすくなりました。
一方で、デメリットも存在しました。
地価の査定が不正確だったために、実情以上の税負担を強いられる農民が多く、不満が噴出しました。
また、不作の年にも一定額の税を納めなければならず、生活が立ち行かなくなる農民も現れました。
これにより、全国各地で一揆や反乱が起こることもありました。
このように、地租改正は廃藩置県と版籍奉還によって得られた中央集権体制を土台として成立した政策です。
財政の安定を図るためには不可欠なものであり、日本の近代化を支えるもう一つの柱と言えるでしょう。
大政奉還との違いと関連性を解説
「大政奉還(たいせいほうかん)」は、版籍奉還や廃藩置県とよく混同されがちな歴史用語です。
しかし、それぞれの意味や背景、影響はまったく異なります。
ここでは、大政奉還との違いをはっきりとさせたうえで、関連性についても丁寧に解説します。
大政奉還が行われたのは、1867年(慶応3年)のことです。
江戸幕府第15代将軍・徳川慶喜が、政権を朝廷(天皇)に返上する形で行われました。
これによって、江戸幕府による長年の支配体制は終わりを迎え、天皇を中心とした新たな政治体制へと移行する準備が整えられました。
一方、版籍奉還(1869年)や廃藩置県(1871年)は、明治政府が実際に全国を統治するための具体的な制度改革です。
つまり、大政奉還は政権の「名義上の返上」であり、版籍奉還と廃藩置県は「統治の仕組みの再構築」と位置づけられます。
大政奉還後も、旧幕府の勢力は一定の影響力を持ち続けていました。
その後、戊辰戦争を経て、旧幕府勢力が完全に排除されると、新政府による中央集権国家の構築が本格化します。
その流れの中で実施されたのが、版籍奉還や廃藩置県というわけです。
また、これらは五箇条の御誓文(1868年)や王政復古の大号令といった政治的スローガンに支えられて実施されました。
新政府は、「公議世論の尊重」「中央集権」「富国強兵」といった理念を掲げ、それを実現する制度として改革を段階的に進めていきます。
このように見てみると、大政奉還は幕府から天皇への政権の移譲という「スタート地点」であり、版籍奉還と廃藩置県はそこから国家体制を実際に作り上げていく「プロセス」の一部です。
相互に密接な関連を持ちつつも、それぞれ果たした役割は異なることを理解しておくと、歴史の流れがより明確になります。
現在の都道府県制度との関係を知ろう
現在の日本における「都道府県制度」は、明治時代に行われた廃藩置県を直接のルーツとしています。
つまり、今私たちが使っている行政区分は、廃藩置県によって確立された仕組みに基づいているのです。
廃藩置県が行われた1871年当初は、全国に「3府302県」という非常に多くの行政単位が設けられました。
これは旧藩をそのまま「県」に置き換えたためであり、飛び地や小規模な地域が乱立している状態でした。
このままでは行政の効率が悪いため、政府は急速に統廃合を進めます。
その後、1871年末には「3府72県」に整理され、さらに再編を重ねて、1888年には現在の「1道3府43県」体制の原型がほぼ完成します。
北海道は「北海道庁」として特別な扱いを受け、東京都は戦後に「都」として制度上区別されるようになりました。
このような経緯を踏まえると、私たちが普段意識する都道府県という枠組みは、明治政府が国家を統一する過程で形づくられたものです。
特に重要なのは、それぞれの地域に「県令(のちの知事)」が配置されるようになった点です。
これによって、すべての地域が中央政府の指示に従って動く仕組みが整いました。
さらに、都道府県制度は戦後の地方自治法によって大きな見直しを受けましたが、根本的な区割りや地方行政の基本形は、今も廃藩置県に由来しています。
この背景を知っておくと、現代の地方行政や選挙制度、地方自治の成り立ちをより深く理解することができます。
都道府県名には旧藩名や地名が残っている場合も多く、地域の歴史的背景を物語っています。
例えば、山口県は旧・長州藩の領地がベースになっており、佐賀県は肥前藩の名残を感じさせます。
このように、廃藩置県は単なる行政改革ではなく、現在の地域社会にも深く関わる重要な歴史的出来事だったのです。
廃藩置県と版籍奉還の違いを総括
ここまで「廃藩置県」と「版籍奉還」の違いについて、時系列や目的、影響などを詳しく見てきました。
最後に、ポイントを整理しながらわかりやすくまとめてみましょう。初めて学ぶ方でも理解しやすいよう、箇条書き形式でお届けします。
- 版籍奉還は、藩主が土地と人民を天皇に返した1869年(明治2年)の出来事です。
- 廃藩置県は、それから2年後の1871年(明治4年)に全国の藩をなくして府と県に置き換えた改革です。
- 名前は似ていますが、版籍奉還が「準備段階」、廃藩置県が「本格的な実行」と言えます。
- 版籍奉還では、旧藩主が「知藩事」として引き続き藩を統治していました。
- 廃藩置県では、知藩事が解任され、中央政府の県令が各地を統治するようになります。
- 両制度の目的は共に「中央集権国家の実現」です。
- 藩主の自主的な協力で行われた版籍奉還は、反発を最小限に抑える効果がありました。
- 廃藩置県は、実質的な支配権を中央政府に集中させる決定的な改革でした。
- これにより徴税権や軍事力も政府に統一され、国家運営の安定につながりました。
- どちらの改革にも大久保利通や木戸孝允、西郷隆盛といった維新の指導者たちが関わっています。
- 明治天皇の名で「勅命」として発せられたことで、改革の正当性が強調されました。
- 1873年の「地租改正」は、これらの改革で整えられた中央集権体制を支える税制でした。
- 大政奉還(1867年)は、政権の名義を天皇に返しただけで、制度面の改革は含みません。
- 現在の47都道府県制度も、廃藩置県の流れを引き継いで形成されています。
- このように、版籍奉還と廃藩置県はセットで理解することで、明治維新の本質がより明確になります。
それぞれの改革は、日本を近代国家へと導くためのステップでした。
制度の中身や順番をきちんと押さえておくことで、歴史の流れが自然とつながって見えてきます。
関連記事

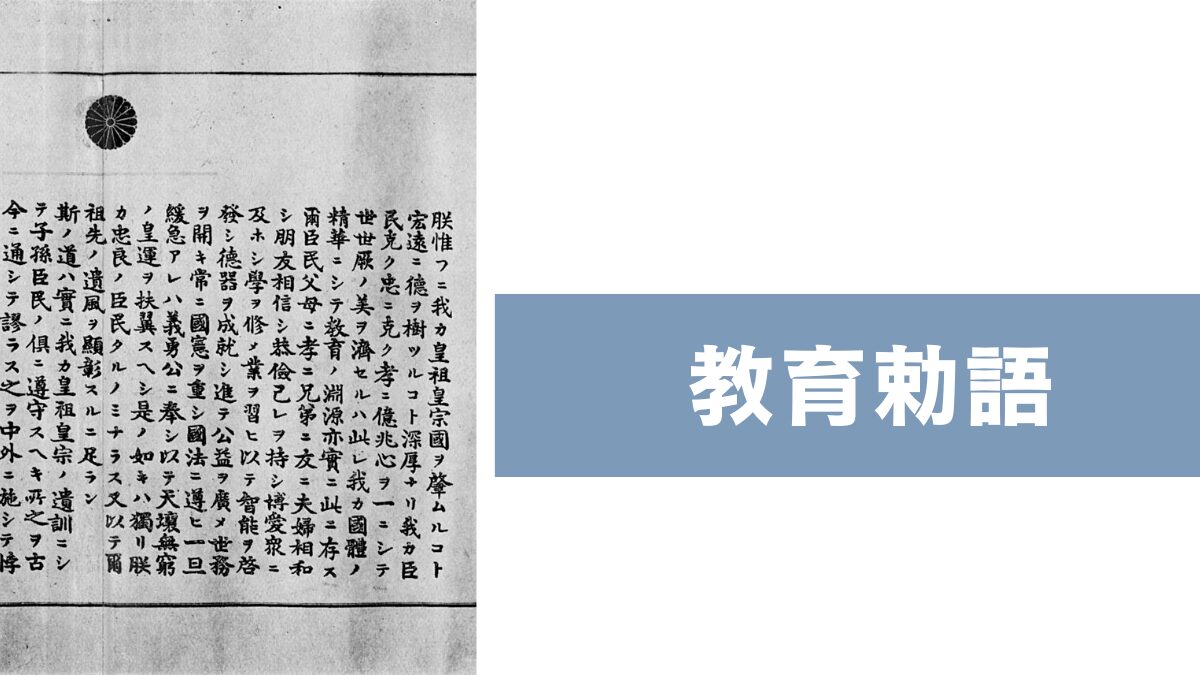
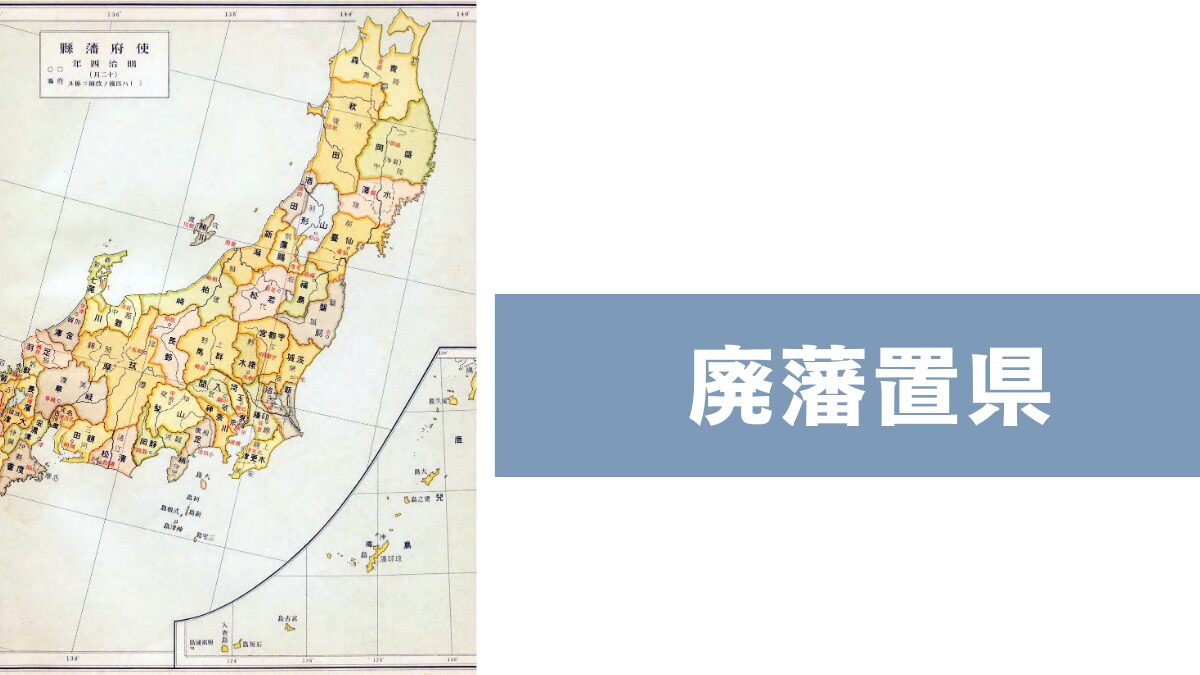
参考サイト

コメント