「クラーク博士って、何をした人なんだろう?」
北海道を訪れたことがある方なら、一度はあの有名な銅像を目にしたことがあるかもしれません。右手で何かを指し示すようなポーズ、そして「Boys, be ambitious(少年よ、大志を抱け)」という名言──この言葉は耳にしたことがあっても、実際にクラーク博士がどんな人物で、日本で何を成し遂げたのか、詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「クラーク博士 何をした人」と気になって検索された方に向けて、その人物像を簡単にわかりやすくご紹介していきます。出身や経歴、日本に来た理由(何人?)、北海道大学との関わり、そして短い滞在期間で築いた功績まで。加えて、名言の続きにまつわる話や、印象的なエピソード、性格・思想、指の先に込められた意味、さらには死因や子孫のことまで、多角的に掘り下げます。
この記事を読むことで、教科書では語られないクラーク博士の「本当の姿」に触れることができるはずです。北海道開拓の父と呼ばれた理由、そしてその精神が今もなお語り継がれる理由を、ぜひ知ってみてください。
この記事でわかること
- クラーク博士が日本で成し遂げた具体的な功績
- 名言「Boys, be ambitious」の本当の意味と続きの話
- 札幌にある銅像のポーズや「指の先」が表す意味
- 教え子たちや子孫を通じて受け継がれたクラーク精神
クラーク博士は何をした人かを簡単に解説

- クラーク博士の出身と経歴を紹介
- クラーク博士は何人?国籍と来日経緯
- 北海道大学の創設に果たした役割とは
- 日本滞在わずか8ヶ月で残した功績
- クラーク博士の教え子たちのその後
クラーク博士の出身と経歴を紹介
クラーク博士ことウィリアム・スミス・クラークは、1826年7月31日、アメリカ・マサチューセッツ州アッシュフィールドで生まれました。父親は医師であり、教育熱心な家庭に育ったことが、彼の学問への興味を早くから育むきっかけとなりました。
その後、彼はウィリストン神学校で学び、18歳で名門アマースト大学に進学します。この大学はアメリカでも屈指のリベラルアーツ・カレッジとして知られていますが、当時のクラークも勉学に励み、成績優秀者の証である「ファイ・ベータ・カッパ」の会員にもなりました。
卒業後はウィリストン神学校で化学を教えたのち、さらに学問を深めるためドイツのゲッティンゲン大学へ留学します。この大学はノーベル賞受賞者を多数輩出する世界有数の研究機関であり、彼はここで化学の博士号を取得しました。
帰国後、彼はアマースト大学の教授に就任し、化学、植物学、動物学など幅広い分野で教鞭を執りました。さらに南北戦争ではマサチューセッツ義勇軍の将校として従軍した経験も持ち、その後は新設されたマサチューセッツ農科大学(現・マサチューセッツ大学アマースト校)の実質的な初代学長を務めました。
教育者としての業績はもちろんのこと、彼の人生は研究者、兵士、行政者と多面的であり、非常にユニークです。その幅広い経験が、後に日本での教育活動にも大きな影響を与えることになります。
彼の人物像を知るうえで重要なのは、「教育を通じて社会に貢献したい」という強い信念を持ち続けていたことです。単に知識を教えるのではなく、人格の形成や道徳の指導にも力を入れていた点が、彼の教育者としての真髄でした。
このような背景を持つクラーク博士は、単なる外国人教師ではなく、明治期の日本にとって極めて重要な意味を持つ存在となったのです。
クラーク博士は何人?国籍と来日経緯
クラーク博士の国籍はアメリカ合衆国です。彼はマサチューセッツ州出身のアメリカ人であり、明治時代の日本に「お雇い外国人」として招かれた教育者の一人です。
では、なぜ彼が日本に招かれたのでしょうか。当時、日本は明治維新を経て近代国家の基盤づくりに奔走しており、特に北海道開拓を成功させるためには、最先端の農業技術とそれを教える教育機関が必要でした。これに応える形で、政府はアメリカに人材派遣を依頼したのです。
その際に推薦されたのが、マサチューセッツ農科大学の学長を務めていたクラーク博士でした。実はこの推薦には、同志社大学の創設者・新島襄の尽力があったとも言われています。新島はアメリカ留学中にクラーク博士の授業を受け、大きな感銘を受けていたことから、明治政府との橋渡し役を果たしました。
こうした経緯を経て、クラーク博士は1876年に日本を訪れます。当初から期間は1年間と決まっており、アメリカでも学長職を休職しての来日でした。彼の日本滞在は結果的に8ヶ月ほどとなりましたが、その短期間での功績は非常に大きく、後に「北海道開拓の父」と称されるまでになりました。
つまり、クラーク博士はアメリカ人でありながら、日本の教育と農業の発展に多大な貢献をした人物です。国境を越えたその行動力と情熱は、現在でも多くの人に尊敬されています。
北海道大学の創設に果たした役割とは
現在の北海道大学の礎を築いた人物として、クラーク博士の名を外すことはできません。彼が来日した目的は、北海道の開拓を担う農業技術者の育成でした。そして、そのために設立されたのが札幌農学校(現在の北海道大学)です。
札幌農学校は1876年に開校しました。当時の日本には、本格的な農学教育機関がほとんど存在しておらず、欧米の先進的な農業技術を直接学べる学校は極めて貴重でした。
クラーク博士はこの学校の初代教頭に就任しますが、実際には「President(校長)」と表記され、校務の全責任を担っていました。開拓使の長官が名目上の校長を兼任していたため、クラーク博士が実質的なトップだったのです。
彼はマサチューセッツ農科大学のカリキュラムを札幌農学校に移植し、英語による講義を導入。農業だけでなく、数学、化学、植物学、動物学、さらにはキリスト教の道徳教育まで幅広く教えました。加えて、実習のための農場「農黌園(のうこうえん)」や、現在の札幌時計台の前身となる演武場の建設も指示し、教育環境の整備にも尽力しました。
このように、クラーク博士は北海道大学の前身校を単なる農業学校ではなく、全人的な教育を行う総合的な学びの場として構築したのです。彼の理念は「Boys, be ambitious(少年よ、大志を抱け)」という名言にも表れており、学生に夢と目標を持って生きることの大切さを教えました。
その影響は現在の北海道大学にも深く根付いています。研究と実践、そして人間形成を重視する姿勢は、クラーク博士の教育方針を今に伝えるものです。
日本滞在わずか8ヶ月で残した功績
クラーク博士の日本滞在は、わずか8ヶ月という短いものでした。しかしその期間に残した功績は非常に大きく、日本の教育史において特筆すべきものとなっています。
彼がまず手がけたのは、札幌農学校の教育環境の整備です。クラーク博士は実践的な教育を重視し、すぐに学生が農作業を体験できる農場「農黌園」を設置しました。これは現在の北海道大学農場の前身にあたります。
また、彼は講義すべてを英語で行い、自然科学の基本から応用までを一貫して教えました。その内容には植物学、動物学、化学、数学、土木工学など多岐にわたる分野が含まれており、当時の日本の教育レベルをはるかに超えるものでした。
さらには、学生にキリスト教の価値観を伝え、人間性や倫理観の育成にも力を入れました。この影響で、多くの学生がキリスト教に関心を持ち、信仰に入るようになります。このように知識だけでなく、人間としての在り方も指導した点は、今でも高く評価されています。
そして忘れてはならないのが、別れの際に生徒へ送った「Boys, be ambitious.」という名言です。この言葉は後に北海道の開拓精神を象徴するメッセージとして語り継がれ、多くの若者の心を動かしました。
クラーク博士は短い滞在期間の中で、教育の形をつくり、生徒の心を育て、地域の未来を切り開いたのです。その実績は、まさに“教育の奇跡”といっても過言ではありません。
クラーク博士の教え子たちのその後
クラーク博士が札幌農学校で教えた学生は、初年度わずか16名でした。しかし、その少数精鋭たちは日本の近代化に大きな貢献を果たしていきます。まさに、彼らこそがクラーク博士の教育理念を受け継ぎ、日本各地に影響を与えた“志ある人材”でした。
代表的な教え子として挙げられるのが、佐藤昌介です。彼は後に北海道帝国大学(現・北海道大学)の総長となり、母校の発展に尽くしました。教育者としても活躍し、多くの後進を育てています。
また、大島正健は言語学者となり、旧制甲府中学校の校長を務めるなど、教育分野でリーダーシップを発揮しました。彼はクラーク博士との別れを詩に綴るなど、深い尊敬の念を持ち続けていた人物でもあります。
さらに、渡瀬寅次郎は農業の分野で活躍し、種苗業を営みながら日本の農業技術の普及に貢献しました。他にも、官吏や企業家として地方行政や経済を支えた人物が多く、各地で指導的な立場を担っています。
これらの教え子たちは、共通して高い志と倫理観を持っていたことが特徴です。これはまさにクラーク博士の教育の賜物であり、学問だけでなく人格の教育がなされていたことを物語っています。
このように、クラーク博士の教え子たちは、彼の精神を実践に移し、日本の発展に大きな足跡を残したのです。短い教育期間でありながらも、その影響力は世代を超えて広がっていきました。
クラーク博士は何をした人かを深掘り解説

- 名言「Boys, be ambitious」の誕生秘話
- 名言の続きはあるの?
- 性格や思想から見る教育哲学
- 心を打つクラーク博士のエピソード集
- クラーク博士の指の先が示すものとは
- 銅像の場所とそれぞれの意味
- クラーク博士の子孫や死因について
名言「Boys, be ambitious」の誕生秘話
「Boys, be ambitious.(少年よ、大志を抱け)」という言葉は、日本でも非常に有名な名言として語り継がれています。札幌農学校の教頭として日本にやってきたクラーク博士が、別れ際に生徒たちに向けて語ったとされるこの言葉には、深い背景があります。
この名言が生まれたのは1877年春、クラーク博士が日本を離れアメリカに帰国する際のことです。彼の任期は1年と決まっており、北海道での滞在はわずか8ヶ月ほどでした。その短い時間の中で、博士は生徒たちに対して熱心な教育を施し、深い信頼関係を築いていました。
帰国の日、クラーク博士は札幌から馬に乗って島松(現在の北広島市)まで移動し、見送りに来た生徒たちと最後の別れを交わしました。このとき、彼は一人ひとりとしっかり握手をし、「時々は手紙を書いてくれ。私はいつも祈っている」と語りかけたと言われています。そして、馬にまたがりながら「Boys, be ambitious!」と叫び、森の中へと去っていったと伝えられています。
この言葉が記録に残ったのは、教え子であった大島正健や安東幾三郎らが後年に語った記録によります。特に安東の証言により、「like this old man(この老人のように)」という続きがあったとも言われており、クラーク博士が自らの姿勢や生き方を手本として語ったことがうかがえます。
この名言は単なる激励の言葉にとどまらず、夢や志を持ち、自分の可能性を信じて進むことの大切さを伝えるものでした。クラーク博士が教えたのは農学や英語だけでなく、生き方そのものだったのです。
名言の続きはあるの?
多くの人に知られている「Boys, be ambitious.」という名言ですが、実はこの言葉には「続き」があるとされる説があります。この説は、クラーク博士の教え子である大島正健や安東幾三郎の証言から広まりました。
「Boys, be ambitious like this old man(少年よ、この老人のように大志を抱け)」というのが、その続きとされる文です。この一文が示すのは、クラーク博士自身が理想を持ち、志に従って生きてきたという強い自負と、それを学生にも受け継いでほしいという願いです。
一方で、別の証言では「Boys, be ambitious in Christ(キリストのうちにあって大志を抱け)」という宗教的な続きが語られることもあります。これは博士がキリスト教信者であり、道徳教育にも重きを置いていたことを反映していると考えられます。
ただし、これらの続きの言葉には公式な文書による裏付けがあるわけではありません。いずれも教え子たちの証言に基づいたものであり、正確な原文は現存していないのが実情です。
それでも、この「続き」の存在が広く知られるようになったのは、単に言葉の意味を拡張するためではなく、クラーク博士が何を伝えたかったのかを後世の人々が深く考え、受け止めようとしたからです。
つまり、続きの有無にかかわらず、名言に込められた核心は「他人のために、社会のために志を持ち、努力を惜しまない生き方を選びなさい」という強いメッセージにあります。
性格や思想から見る教育哲学
クラーク博士は教育者としてだけでなく、人間としても非常に魅力的な人物でした。彼の教育哲学は、その性格や思想に深く根ざしており、単なる知識の伝達にとどまらない教育を実践していました。
彼の性格はとても情熱的で、かつ包容力に富んでいたと言われています。実際、札幌農学校の生徒たちの多くが、彼を「父親のような存在」と慕っていました。それは、彼が一人ひとりの生徒に真剣に向き合い、理解しようと努めていたからです。
また、クラーク博士は「Be gentleman(紳士たれ)」という言葉を校則として提案したエピソードが知られています。これは形式ばった規則よりも、内面的な品格や道徳心を重んじるべきという考え方から来ており、自由と自律を重視する姿勢が見て取れます。
彼の思想にはキリスト教的な価値観も色濃く表れています。生徒たちに聖書を配布し、「イエスを信ずる者の契約」に署名させるなど、道徳教育にも力を入れました。ただし、強制することはなく、信仰や倫理を自発的に考える機会を与えていた点も特徴です。
このような教育哲学は、当時の日本においては非常に革新的でした。従来の詰め込み型の教育とは異なり、学問と人間形成をバランスよく育てる彼の指導は、生徒たちの心に深く根付き、後の人生にも大きな影響を与えました。
クラーク博士の教育は、「大志を抱き、社会のために生きる人間を育てる」というビジョンに貫かれていました。その姿勢は、現代の教育においても大いに学ぶべき点が多いと言えるでしょう。
心を打つクラーク博士のエピソード集
クラーク博士には数々の印象的なエピソードが残されています。中でも特に知られているのが、札幌農学校の生徒に対する親身な指導と温かな人柄に関する逸話です。
授業はすべて英語で行われ、内容も高度でハードなものでしたが、それでも生徒たちが彼に強く惹かれたのは、学問だけでなく人間として尊敬できる存在だったからです。生徒が悩みを抱えていたときには、時間を惜しまずに相談に乗るなど、個別の対応にも真剣でした。
また、別れの直前には一人ひとりと握手を交わし、「健康に気をつけて、祈りを忘れずに」と語りかけたという話は、多くの人の心に残る感動的なエピソードです。このときに発せられた「Boys, be ambitious.」という言葉も、こうした丁寧な人間関係の延長線上にあります。
さらに、彼は教育方針においても実践を重視していました。すぐに農場を設け、学生たちに実地で農業を学ばせたことは、当時としては非常に先進的な教育でした。講義だけでは学べないことを現場で身につけさせるという考え方は、今でも多くの教育現場で受け継がれています。
このようなエピソードを通じてわかるのは、クラーク博士が「信頼」と「実践」を何より大切にしていたということです。だからこそ、生徒たちは学業に励むだけでなく、人格的にも大きく成長することができました。
クラーク博士の指の先が示すものとは
札幌の羊ヶ丘展望台にあるクラーク博士の銅像は、多くの観光客に親しまれています。その最大の特徴といえば、右手を空に掲げた独特のポーズでしょう。この「指の先」には、どのような意味が込められているのでしょうか。
このポーズは「遥か彼方の永遠の真理」を指しているとされています。つまり、ただ物理的に遠くを指しているのではなく、「理想」や「志」、「人として進むべき道」といった抽象的な価値を象徴しているのです。
この銅像は1976年、札幌観光協会の依頼によって彫刻家・坂坦道氏が制作しました。当時、北海道大学構内にある胸像への観光客の殺到が問題となっていたことから、新たな観光スポットとして羊ヶ丘展望台に全身像が建てられたのです。
指をさすポーズは、クラーク博士の名言「Boys, be ambitious.」とセットで語られることが多く、まさに志を持って前に進むべきだというメッセージを視覚的に表現しています。
観光地として人気があるだけでなく、このポーズは多くの若者にとって、自分の未来や理想に目を向けるきっかけにもなっているのです。記念撮影で同じポーズを真似する人が後を絶たないのも、そうした思いを共有したいという気持ちの表れかもしれません。
銅像の場所とそれぞれの意味
クラーク博士の銅像は、実は札幌市内に3箇所存在しています。それぞれの場所には意味があり、見どころも異なります。観光の際には、ぜひその背景を知って訪れることをおすすめします。
最も有名なのが、さっぽろ羊ヶ丘展望台にある全身像です。この像は右手を高く掲げており、「Boys, be ambitious.」という言葉を象徴するポーズとして親しまれています。ここでは、訪れた人が自分の夢を書いて投函できる「大志の誓い」などの企画もあり、観光地としての魅力も高いです。
次に、北海道大学構内にある胸像です。こちらは、クラーク博士が実際に教育を行った札幌農学校(現・北海道大学)の歴史を今に伝えるシンボルとなっています。研究・教育の現場にふさわしく、より静かな雰囲気の中で博士の功績を感じることができます。
もう一つは、北海道大学植物園内にある宮部金吾記念館の像です。この銅像は、現在の全身像の原型とされており、比較的小さめですが、歴史的価値が高いものです。
それぞれの像が立つ場所は、クラーク博士の活動の場や思想と深く結びついています。ただの観光写真スポットではなく、それぞれの背景を知ることで、より深く博士の偉業に触れることができるでしょう。
クラーク博士の子孫や死因について
クラーク博士の家系は現在も続いており、その子孫たちは博士の精神を受け継ぎ、さまざまな分野で活躍しています。代表的な人物の一人が、博士の5代目の子孫であるデブラ・Y・クラーク女史です。彼女は日本のクラーク記念国際高等学校を訪問し、生徒たちと積極的に交流を行っています。
また、博士の玄孫にあたるケイレブ・キンボール・キング博士も、北海道大学を訪れたことがあり、博士の足跡をたどりながら、日米の教育や国際交流について語っています。彼はハーバード大学やマサチューセッツ工科大学で学んだ後、医療や環境工学の分野で活動しており、祖先の志を現代に活かしている人物です。
一方で、クラーク博士の最期は決して幸福なものではありませんでした。札幌での任期を終えた後、彼は鉱山会社を設立するも失敗し、晩年は経済的に困窮しました。心臓病を患い、1886年に59歳で亡くなっています。死の直前、彼は「札幌で過ごした9ヶ月間こそが人生で最も輝いていた」と語ったと伝えられています。
このように、クラーク博士は偉大な功績を残しながらも、波乱に満ちた人生を送りました。彼の死後も、その精神は家族や教育機関を通して今に受け継がれ続けています。
クラーク博士は何をした人かを総括
クラーク博士が「何をした人なのか?」について、これまで紹介してきた内容を整理しながら、わかりやすくまとめてみましょう。
明治期の日本にとって、彼は単なる外国人教師ではなく、国の未来を形づくった教育者でした。
以下のポイントを通じて、彼の功績や人柄を再確認していただければと思います。
- アメリカ・マサチューセッツ州出身の教育者で、化学・植物学・動物学などに精通していました。
- ゲッティンゲン大学で博士号を取得するほどの優れた学者で、後にアマースト大学の教授も務めました。
- 南北戦争に従軍した経験を持つ、行動力と信念に満ちた人物でした。
- 明治政府の要請により「お雇い外国人」として日本に招かれ、札幌農学校の初代教頭に就任しました。
- 現在の北海道大学の基礎を築いた人物で、校務を実質的にすべて任されていました。
- 授業はすべて英語で行い、農学を中心に自然科学全般を教えたことが高く評価されています。
- キリスト教に基づいた道徳教育にも力を入れ、人間性の成長を重視しました。
- 生徒たちと強い信頼関係を築き、「父のような存在」と慕われていました。
- 帰国の際、生徒に向けて「Boys, be ambitious.」という名言を残したことで知られています。
- わずか8ヶ月の滞在で多くの改革と実績を残し、「北海道開拓の父」と称されています。
- 教え子たちは各分野で活躍し、日本の近代化を担う人材となりました。
- 銅像は札幌市内に3か所あり、右手を掲げたポーズは理想と真理を指し示しています。
- 教育理念は「自由と自律」「人格形成」「実学重視」という先進的なものでした。
- 晩年は鉱山事業の失敗や心臓病など困難が続き、59歳で生涯を終えました。
- 彼の子孫たちは現在も活躍し、日本とのつながりを大切に守り続けています。
このように、クラーク博士は教育を通じて北海道だけでなく、日本全体に大きな影響を与えた人物です。今でも彼の精神や教えは、多くの人々の中に息づいています。
関連記事
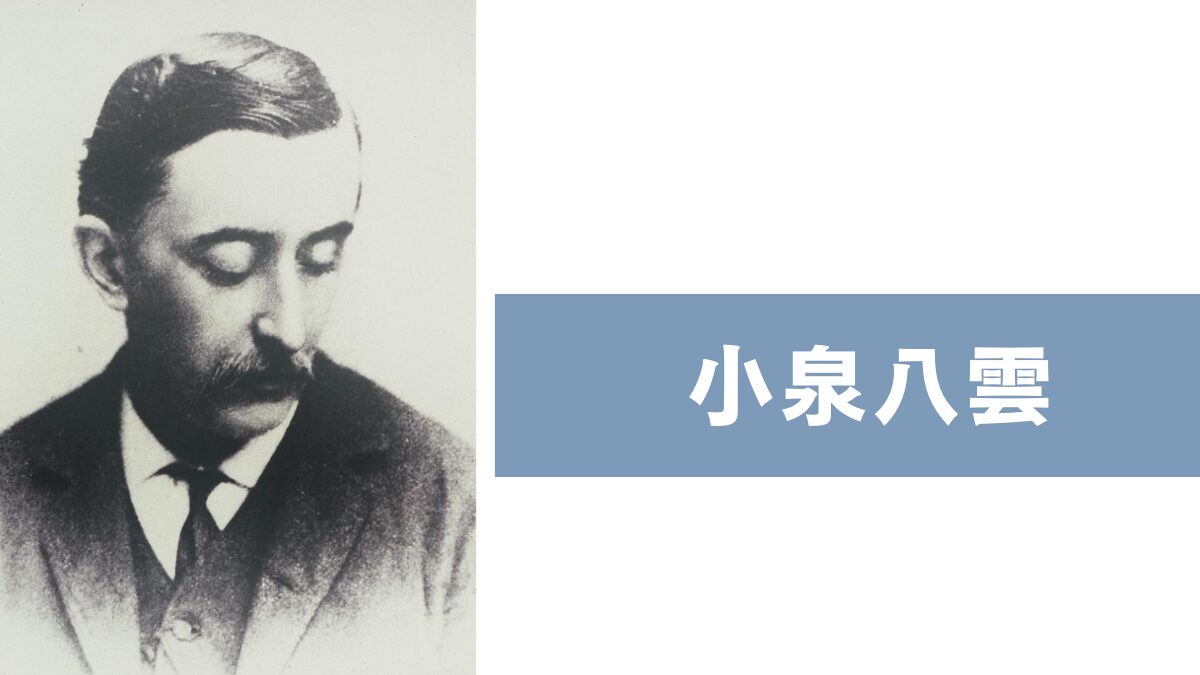

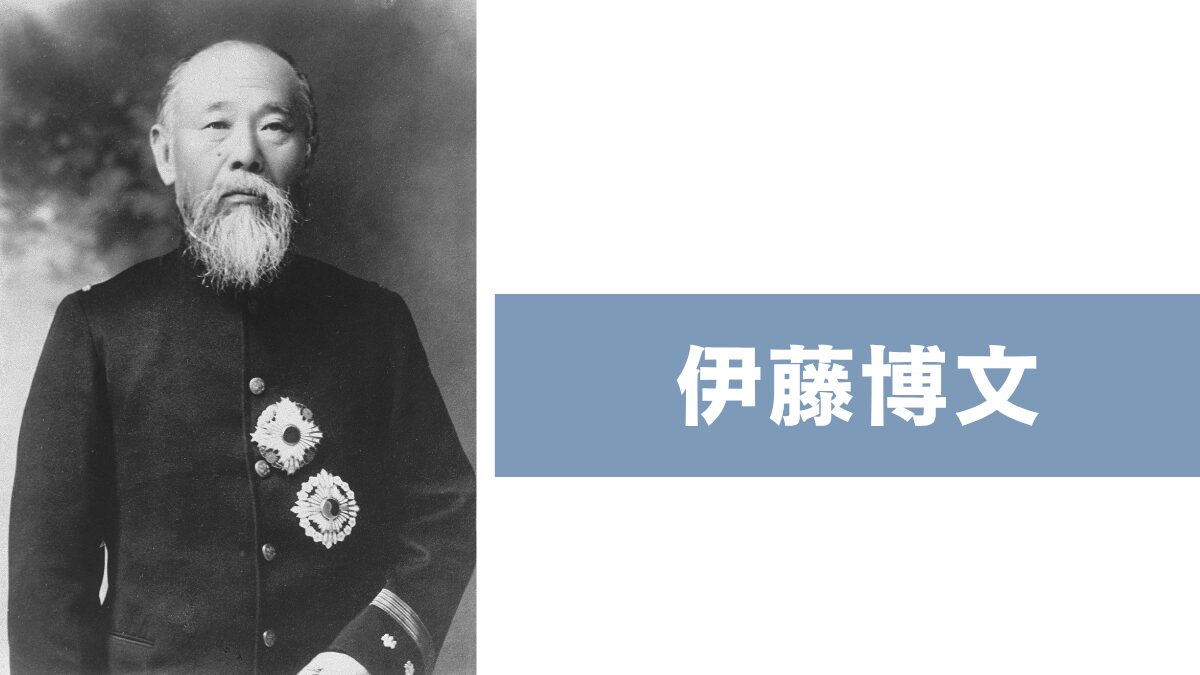
参考サイト
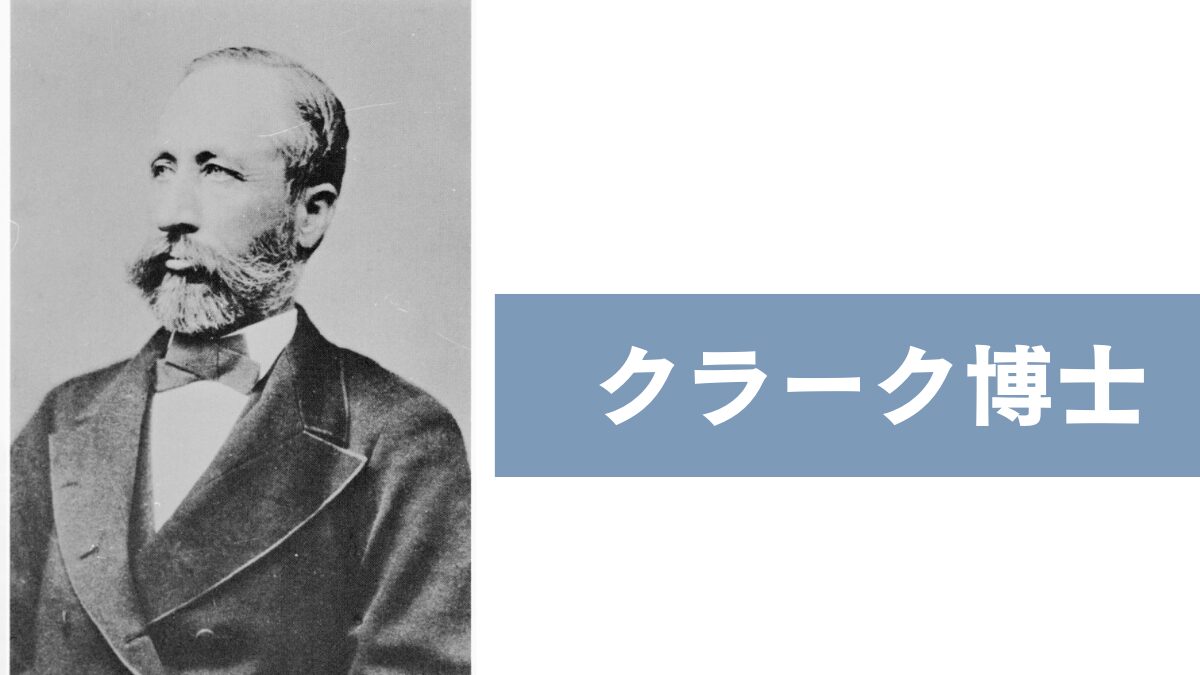

コメント