南極観測の歴史の中でも、多くの人の心に深く刻まれているのが「南極物語で犬が置き去りにされた理由」にまつわる出来事です。
極寒の地に15頭の樺太犬が残され、その中で「タロとジロ」だけがなぜ生き延びたのかという話は、日本中に感動と衝撃を与えました。
一方で、「犬を繋いだまま置き去りにするなんてひどい」といった批判や、「共食いをした」というデマのような情報も拡散され、真相は長く誤解されたままになってきました。
さらに、映画『南極物語』の影響で事実とフィクションが混同されることも多く、撮影中に犬が死亡したという噂が後を絶ちません。
「その後」タロとジロがどのような人生を送ったのか、また彼らが属していた「犬種」の特徴や能力についても、あまり知られていないのが現状です。
置き去りの「期間」や救出できなかった理由など、背景には当時の技術や政治的な事情も深く関わっています。
この記事では、南極に犬を残さざるを得なかった経緯から、タロとジロがなぜ生き延びたのか、そして彼らのその後や歴史的意義まで、一次資料や信頼性の高い証言に基づいて詳しく解説します。
ネット上にあふれる断片的な情報に惑わされず、史実としての「南極物語」を正しく知っていただくための内容になっています。
この記事を読むとわかること
- 犬が置き去りにされた本当の理由と背景
- タロとジロが生き延びた条件や要因
- 共食いデマの真偽と証拠に基づいた見解
- 映画の演出と史実との違い
南極物語で犬が置き去りにされた理由とは

- 観測隊が犬を置いて撤退した経緯
- なぜ犬を再び迎えに行けなかったのか
- 犬を繋いだままにした意図と判断
- 批判された決断が「ひどい」と言われた背景
- 共食いというデマの真偽と実際の証拠
観測隊が犬を置いて撤退した経緯
1958年、第一次南極観測隊と第二次観測隊の交代時に起きた、樺太犬15頭の南極置き去り事件は、日本の観測史における大きな出来事として知られています。
犬たちを置いて撤退するという決断は、無責任な放棄ではなく、さまざまな要因が重なった末のやむを得ない判断でした。
そもそも、1956年に南極観測が始まった当初、日本は敗戦国という背景から国際社会への復帰の一環として、この事業を国家的プロジェクトとして進めていました。
しかしながら、当時の設備や技術、予算は限られており、観測船「宗谷」も老朽船でした。
1958年2月、第2次越冬隊が第1次隊と交代するため、再び昭和基地に向かいましたが、悪天候によって宗谷が岸に接近できず、直接の物資搬入や隊員の移動が極めて困難になります。
このとき、日本はアメリカの砕氷艦「バートン・アイランド号」の支援を受けて、限られた時間と輸送手段で交代作業を行っていました。
空輸に使えた飛行機も小型であり、風速や視界などの条件が悪化すると、再び基地に降りることができなくなる危険が高まりました。
それゆえ、人命を最優先に、第1次隊の11人の隊員をまず宗谷に戻し、次に母犬シロ子と生まれたばかりの8匹の子犬を救出します。
その結果、体重が重くスペースも必要な15頭の成犬を一度に輸送する余裕はなかったのです。
さらに、宗谷自体も氷に閉じ込められかけており、長居は船そのものの遭難にもつながるという判断が求められました。
このような厳しい状況の中で、観測隊はやむを得ず、犬たちを基地に残して撤退するという苦渋の選択をしたのです。
犬たちは完全に放置されたわけではなく、2か月分の食料が与えられ、再び基地に戻る計画も視野に入れていたことから、一時的な措置であるとの認識がありました。
しかし、その後の状況の変化により、結果として「置き去り」という形になってしまったのです。
この撤退は、観測隊員たちにとっても決して軽いものではなく、現地では犬たちの名を叫びながら涙を流す者もいたと言われています。
つまり、犬を置いて撤退する判断は、単なる怠慢や判断ミスではなく、極限の環境下で人命と任務、資源のバランスを考慮した末の、苦しい現実だったのです。
なぜ犬を再び迎えに行けなかったのか
多くの人が疑問に思うのは「一度帰った後、なぜもう一度行って犬を救出できなかったのか」という点でしょう。
確かに、犬を愛する立場から見れば当然の疑問です。ですが、そこには当時ならではの事情がありました。
南極は非常に過酷な環境で、しかも1年のうち上陸可能な期間は限られています。
特に日本が基地としていた昭和基地周辺は氷が厚く、天候も変わりやすいため、安全な再上陸は簡単なことではありません。
第一次越冬隊と第二次越冬隊の交代失敗の際、観測船「宗谷」自体も氷海に閉じ込められる危険性がありました。
その後、天候が回復すれば再進入する予定も立てられていましたが、状況は悪化の一途をたどります。
2月24日には「第二次越冬を断念せよ」という正式な命令が出て、昭和基地からの撤収が確定したのです。
また、技術的にも、当時は現在のような装備や支援体制が整っていませんでした。
ヘリコプターも限定的であり、天候に左右されやすく、再度空輸するには大きなリスクが伴いました。
仮に犬の救出だけのために再進入を強行すれば、犬だけでなく人命も危険にさらす可能性があったのです。
そしてもう一つの側面は、「昭和基地の維持を諦めなかった」という点にあります。
観測隊の計画はあくまで昭和基地での継続観測を前提としていたため、犬たちは次の越冬隊が再び基地を使用する際に再会する、という期待も持たれていました。
つまり、「完全な置き去り」という認識ではなく、「あとで再び使う基地に一時残す」という位置づけだったのです。
いずれにしても、極限の自然環境、装備の制限、時間と資源の問題、そして隊員たち自身の安全確保という事情が重なり、犬だけのために再訪するのは不可能でした。
その結果、実際に再訪できたのは翌1959年、第三次越冬隊が到着した時という形になりました。
犬を繋いだままにした意図と判断
南極の過酷な地に残された15頭の犬たちが、なぜ鎖に繋がれたまま置き去りにされたのかという点も、多くの人が疑問に思うところです。
放しておけば自由に動けるのではないか、と考える方もいるかもしれませんが、そこにも深い理由がありました。
まず第一に、犬たちが「野犬化」することを防ぐ意図がありました。
樺太犬は大型でパワーがあり、野生化した場合、南極の野生動物にとって脅威となる可能性があります。
特に南極ではアザラシやペンギンといった固有種が生息しており、観測隊はこれらの生態系に極力影響を与えないよう求められていました。
次に、犬の管理を前提としていた第二次越冬隊が、到着時に犬を簡単に扱えるようにする意図もありました。
鎖につないだ状態であれば、隊員が到着した際に犬たちの状態をすぐ確認でき、暴走や逃走による混乱を防ぐことができます。
さらに、当時の観測隊員によると、犬たちは非常に力が強く、特に慣れていない隊員にとっては扱いが難しい存在でした。
前述の通り、15頭もの犬を一斉に解放した場合、再び捕獲するのは極めて困難になります。
首輪を緩めることで「もしものときには犬自身が抜け出せるように」との配慮もあり、ただ単に固定して放置したわけではありません。
また、食料も2か月分は用意されていたことから、あくまで短期間の不在を想定しての処置だったとも言えます。
「人間がすぐに戻ってくるはず」と信じていたからこその判断だったのです。
ただし結果として、7頭は鎖につながれたまま餓死し、生き延びたのは鎖を抜けられた2頭だけだったことを考えると、現代の視点では悲劇的な結果になってしまいました。
しかし当時の隊員たちにとって、これは合理性と安全性、生態系保護の観点をふまえた、精一杯の判断だったとも言えるでしょう。
批判された決断が「ひどい」と言われた背景
観測隊が犬を置き去りにしたという事実は、当時の日本社会に大きな衝撃を与えました。
特に「鎖につながれたまま餓死した」という情報が報道されたことで、「ひどい」「非人道的だ」という批判が巻き起こりました。
この批判の背景には、犬という存在に対する日本人の感情的な親しみがありました。
忠犬ハチ公の逸話が全国的に知られていたように、犬は「家族の一員」「忠誠心の象徴」として捉えられることが多かったのです。
そのため、犬をあたかも使い捨ての道具のように扱ったように見える行動には、大きな感情的反発が起こりました。
また、当時は動物愛護の意識が高まり始めていた時代でもありました。
終戦から十数年経ち、国民がようやく生活に余裕を持てるようになったことで、動物の命にも目が向けられるようになったのです。
その中で「命あるものを見殺しにした」という印象を与えたことが、観測隊へのバッシングにつながりました。
実際には、先述したように観測隊員たちは最後まで救出の努力を惜しまず、犬たちを簡単に見捨てたわけではありません。
しかしその苦悩や葛藤は当時の報道ではあまり伝えられず、「置き去りにした」という表面的な情報だけが独り歩きしてしまったのです。
さらに、「外国では安楽死という選択肢もあったはずなのに、日本人は犬をつないだまま見殺しにした」という文化的な比較も、批判を強める要因となりました。
ただ、この「ひどい」という評価には、感情だけでなく、情報不足や誤解が多く含まれていたことも事実です。
結果的に、日本動物愛護協会による慰霊碑の設置や、後年の映画化によって「悲劇の中の奇跡」として語られるようになり、観測隊の決断に対する見方も少しずつ変わっていきました。
共食いというデマの真偽と実際の証拠
「置き去りにされた犬たちは共食いしたのではないか?」という説は、当時からたびたび噂されてきました。
ですが、現在ではこの説はほぼ否定されています。
根拠のない情報や、感情的な推測による部分が大きく、実際の状況とは一致しない点が多くあります。
まず、第三次越冬隊が翌年昭和基地を訪れた際、鎖につながれて餓死していた7頭の犬の遺体は、どれも「きれいな状態」であったと記録されています。
毛や肉をむしられたような痕跡はなく、食べられた形跡もなかったのです。
これは、仮に共食いが起こっていれば、必ず何らかの物理的痕跡が残るはずだという観点から見ても、共食いがなかった証拠とされています。
また、生存していたタロとジロについても、他の犬や野生動物を襲っていたという確証はありません。
実際、彼らが食べていたとされるのは、アザラシの糞や打ち上げられたクジラの死骸、人間の食料の廃棄物などであり、他の犬の死骸を食べた形跡は報告されていません。
この共食い説は、極限環境下での生存本能に基づく可能性として語られがちですが、現場の証言や後年の調査を踏まえると、明確な証拠は一切出てきていません。
むしろ、樺太犬は比較的協調性が高く、極限状態でも仲間を襲う性質は少ないとされています。
もちろん、誰もいない基地内で何があったかを完全に証明することはできません。
ただし、現時点での事実や証言から考えると、共食いは起きなかったという見解が主流です。
したがって、この「共食い」はセンセーショナルに語られたデマである可能性が高く、むしろ生き延びた犬たちが互いに助け合っていた可能性の方が現実に近いとされています。
感情的に過激な噂が、真実をゆがめて伝わってしまった一例だと言えるでしょう。
南極物語で犬を置き去りの理由とその後の真実

- タロとジロはなぜ生き延びたのか
- 犬たちの生死と行方不明の内訳
- リキが果たした可能性のある役割
- タロとジロのその後の生涯と展示先
- 犬種としての樺太犬の特徴と能力
- 映画撮影で犬が死亡したという噂とその真偽
- 史実と映画版の違いと注意点
タロとジロはなぜ生き延びたのか
南極の厳しい自然環境に15頭の樺太犬が置き去りにされる中、生き延びたのはタロとジロの2頭だけでした。
この“奇跡の生還”には、いくつかの条件が重なっていたことがわかっています。
まず、2頭は首輪を抜け出すことができた犬でした。
残された15頭のうち、首輪を抜けられなかった犬たちはその場で鎖につながれたまま命を落としています。
一方、タロとジロは首輪が緩められていたことで自力で抜け出すことができ、自由に行動できる状態だったのです。
そして、タロとジロは若く、当時わずか1歳ほどでした。
これは成犬に比べて体力や柔軟性があり、環境への順応力も高かったと考えられます。
さらに重要なのは、彼らが「基地にとどまった」点です。
多くの犬たちが首輪を抜けて遠くに出て行った結果、雪原で力尽きたとみられるのに対し、タロとジロは昭和基地を“自分の家”と認識して離れなかったため、生存の確率が高まりました。
食料の問題も見逃せません。
当時の記録では、人間用の廃棄食料やアザラシの糞、または打ち上げられたクジラの死骸などを食べていた可能性が指摘されています。
さらに、基地には極寒で傷んだ食料が“天然冷蔵庫”のように残されていたともされ、それを利用して生き延びたとも考えられます。
また、極めて寒さに強い体質を持つ樺太犬の特徴も、彼らの生存を助けた要素です。
毛皮が厚く、皮下脂肪も発達しており、マイナス30度の環境でも雪上で眠れる耐性を持っていました。
こうしてみると、タロとジロが生き延びたのは偶然ではなく、環境・性格・能力・運の全てがそろった結果だったのです。
この事実は、ただの感動話ではなく、極限状況における生物の生存戦略としても非常に興味深いものとなっています。
犬たちの生死と行方不明の内訳
1958年2月、昭和基地に残された15頭の樺太犬たちは、それぞれ異なる運命をたどりました。
第三次越冬隊が約1年後に基地を再訪した際に判明した、彼らの生死や行方不明の内訳は、置き去り事件の真相を知る上で重要なポイントとなります。
具体的には、15頭のうち7頭が鎖につながれたまま死亡しているのが発見されました。
いずれも「きれいな状態」で、外傷や食い荒らされた跡などは見られず、餓死と見られています。
これらの犬たちは、首輪が外れることなく、その場から動けなかったため、食料にありつくこともできなかったと考えられます。
一方、6頭の犬は首輪を抜けて行方不明となっていました。
その後の調査でも痕跡はほとんど見つかっておらず、広大な南極の雪原の中で息絶えた可能性が高いとされています。
唯一、1968年になって、基地周辺の溶けた雪の中から1頭の冷凍遺体が見つかっています。
この犬は毛の色や体格などの特徴から、最年長だったリキではないかと推定されています。
そして残る2頭が、生存を確認されたタロとジロです。
彼らは首輪を抜けて自由になったあとも基地を離れず、基地周辺で生活していたことが報告されています。
このように、15頭の内訳は以下の通りです。
- 生存:2頭(タロ・ジロ)
- 鎖につながれたまま死亡:7頭
- 行方不明:6頭(うち1頭は後に遺体で発見)
こうした事実からも、犬たちの運命は首輪の状態と行動範囲に大きく左右されたことがわかります。
また、行方不明の6頭についてはその後も詳細が不明のままであり、現在でも完全な記録は残っていません。
リキが果たした可能性のある役割
昭和基地に残された15頭の犬のうち、最年長だったのがリキという犬です。
彼は第一次越冬中から犬たちのリーダー的存在として活躍しており、特にタロとジロにとっては「親代わり」のような存在でした。
北村泰一氏(当時の犬係)の証言によると、リキは越冬期間中、まだ幼かったタロとジロに対して非常に面倒見が良く、時には自分の食料を分け与えるような行動も見られたといいます。
そのため、置き去り後の生存にも、リキの存在が大きく影響していたのではないかと考えられています。
実際、1968年に発見された冷凍遺体の特徴から、北村氏はその犬がリキである可能性が高いと指摘しました。
発見場所は昭和基地のごく近くであり、タロとジロが生存していたエリアと重なっています。
このことから、リキもまた基地から離れず、若い2頭と共に行動していたと考えられるのです。
また、南極という極限環境においては、単独で生き延びるのは困難です。
その中で、リキが基地周辺の食料のありかを記憶していたり、他の犬たちを導く能力を持っていた可能性は否定できません。
実際、観測隊が行っていた遠征では、リキがデポ(緊急食料置き場)やクジラの死骸の場所を記憶していたとされる証言もあります。
こうしたことから、リキは単に年長だったというだけでなく、経験と知識を活かして、タロとジロの生存を支えたキーパーソン(キードッグ)だったとも言えるでしょう。
最終的にリキ自身は力尽きてしまったかもしれませんが、その存在がもたらした影響は非常に大きく、影の功労者として再評価されるべき存在です。
タロとジロのその後の生涯と展示先
タロとジロは、置き去りにされた15頭の中で唯一生き残り、1959年1月に第三次越冬隊によってその生存が確認されました。
2頭が駆け寄ってくる姿は、多くの人に感動を与え、日本中が沸き立つほどのニュースになりました。
救出後、ジロはそのまま第四次越冬隊とともに南極にとどまり、翌1960年7月に昭和基地で病死しました。
享年5歳でした。ジロの遺体は日本に持ち帰られ、現在は東京都台東区の国立科学博物館で剥製として展示されています。
一方、タロはジロより長生きし、第五次越冬隊の活動にも貢献した後、1961年に帰国しました。
その後、北海道大学植物園で大切に飼育され、1970年8月11日に14歳で静かに息を引き取りました。
これは大型犬としてはかなりの長寿であり、南極での過酷な体験を乗り越えた生命力の象徴とも言えるでしょう。
タロの剥製は、現在も札幌市の北海道大学植物園で見ることができます。
タロとジロの剥製は、1998年の「タロ・ジロ里帰り特別展」などで一時的に再会する機会もありました。
これは日本中のファンにとって非常に貴重な展示となり、今でも語り継がれています。
彼らの生涯は映画や歌、記念碑などにもなり、日本人の記憶に深く刻まれました。
特に東京タワーに設置された「樺太犬記念像」は、タロとジロをはじめ、命を落とした13頭の犬たちへの慰霊と敬意の象徴として知られています。
このように、タロとジロのその後は、ただの「奇跡の犬」ではなく、国民的なヒーローとして、また科学観測と動物の関係を見直す契機として、大きな意味を持つ存在となったのです。
犬種としての樺太犬の特徴と能力
樺太犬(からふとけん)は、日本の北部や樺太(現在のサハリン)を原産地とする、極寒の地に適応した作業犬です。
現在では純血種としては絶滅したとされますが、かつてはアイヌ民族や現地の人々にとって生活に欠かせない使役犬でした。
その能力と性質は、南極観測においても極めて重要な役割を果たしました。
まず、最大の特徴はその「耐寒性」です。
分厚いダブルコートの被毛と発達した皮下脂肪により、マイナス30度〜40度の環境下でも活動が可能です。
実際、雪の上でそのまま眠ることができるほどの適応力を持っており、他の犬種では到底生きられない環境に耐えることができます。
次に、優れた「牽引力」も大きな魅力です。
体重は30kg前後と大型犬に分類され、雪や氷の上をそりを引いて長距離を移動する能力に長けていました。
世界的な犬ぞりの基準と比較しても、樺太犬は走行距離や耐久力の面で非常に高い評価を受けています。
実際、第一次南極越冬隊においては、雪上車が故障する中、犬ぞりだけで1600km近くを走破したという記録も残されています。
また、性格面でも特筆すべき点があります。
樺太犬は非常に温厚で従順、人間に対する信頼が強く、しっかり訓練すれば高い忠誠心を持ちます。
特に方向感覚や帰巣本能に優れ、見知らぬ場所でも正確に元の場所に戻る能力があったとされます。
これは南極でタロとジロが基地を離れなかった理由のひとつにもなっています。
ただし、デメリットもあります。
暑さに非常に弱く、日本から南極に向かう際には赤道を越えるため、多くの犬が体調を崩しました。
また、飼育にあたっては大量の食料が必要であり、維持費も高かったとされています。
このように、樺太犬は南極という特殊な環境において非常に理想的な犬種でした。
その能力の高さと忠誠心の強さから、現在でも「伝説の犬種」として語り継がれています。
映画撮影で犬が死亡したという噂とその真偽
1983年に公開された映画『南極物語』は、日本映画史上屈指のヒット作として知られています。
そのリアリティの高さや演技力は高く評価されましたが、一方で「撮影中に犬が死亡した」という噂も一部で広まりました。
この点については、いくつかの誤解と混乱があったようです。
まず、この映画で使用された犬は樺太犬ではなく、アラスカン・マラミュートやシベリアン・ハスキーなどの“極地犬種”が代用されました。
これは、すでに純血の樺太犬がほとんど現存していなかったためです。
映画の制作チームは、なるべく実際の体型や毛並みに近い犬を選び、過酷な環境にも耐えられるよう配慮していました。
しかし、撮影は南極ではなく、厳冬期のカナダなどで行われ、自然条件も過酷でした。
その結果、犬が体調を崩したケースがあったのは事実のようです。
ただし、公式に「死亡した」と認められているケースは確認されていません。
関係者によると、すべての犬は獣医師の監督のもとで管理され、極力安全が確保されていたとのことです。
また、噂が拡大した背景には、「映画の中で犬が命を落とすシーン」が強く印象に残ったことも関係していると考えられます。
この感情的なインパクトが、事実とフィクションの境界を曖昧にしてしまったのかもしれません。
一方で、動物愛護の観点からは、いかに安全管理がされていたとしても、極寒の地での長期間の撮影はリスクが大きいという指摘もあります。
現在では、撮影における動物の扱いに関して、より厳格なルールが導入されています。
このように、「犬が死亡した」という話は事実確認のとれていない情報であり、少なくとも公式には否定されています。
とはいえ、動物の命を扱う以上、今後の映像制作においても、さらなる配慮と透明性が求められることに変わりはありません。
史実と映画版の違いと注意点
映画『南極物語』は、多くの人にタロとジロの実話を広く知らしめるきっかけとなりました。
ただし、これはあくまで“映画作品”であり、実際の歴史とは異なる部分も多く含まれています。
観る側としては、その違いを理解した上で鑑賞することが重要です。
まず大きな違いは、「ドラマ性を強調した演出」です。
例えば、映画では人間の隊員が犬たちの死を悔やんで涙を流すシーンや、ジロが力尽きて雪の中で倒れる場面などが描かれていますが、これらは事実を元にした“創作”です。
実際には、誰もいない基地での犬たちの様子は確認されておらず、ドラマチックな展開はあくまで想像に基づいた演出です。
また、登場する犬たちの名前や性格設定も、史実と異なる部分があります。
映画では犬たちに個別のエピソードや性格付けがされていますが、実際の記録ではそこまで詳細な個体識別はされていません。
さらに、観測隊の判断や背景事情についても、映画ではやや単純化されています。
「犬を見捨てた」というような印象を受ける演出がある一方で、史実では燃料不足や悪天候、当時の技術的制限など、やむを得ない事情が複雑に絡み合っていたことが明らかになっています。
そして、タロとジロ以外の13頭の犬たちの扱いについても、映画では断片的にしか描かれていません。
実際には行方不明、餓死、後に発見された個体など、多様な運命がありました。
このように、『南極物語』は史実をベースにした感動作品ですが、あくまで“物語”であることを忘れてはいけません。
事実を知るには、書籍や当時の観測記録、関係者の証言など、一次資料に当たることが大切です。
それでもなお、映画が果たした役割は大きく、動物の命に対する世間の関心を高めた功績は否定できません。
だからこそ、観客としては「物語」と「現実」の線引きをしっかりと意識しながら受け止める必要があるでしょう。
南極物語で犬が置き去りにされた理由を総括
「南極物語で犬が置き去りにされた理由」というテーマについて、ここまでの情報をわかりやすくまとめてみました。
感情的な視点だけでなく、当時の状況や判断の背景を知ることで、より立体的にこの出来事を理解できると思います。
以下は、観測隊の判断や犬たちの運命に関わる重要なポイントを整理したものです。
- 1958年、第一次南極観測隊と第二次隊の交代が悪天候で失敗し、犬たちは南極に残されることになった
- 使用された観測船「宗谷」は老朽船で、氷に閉じ込められる危険が迫っていた
- 犬たちは完全に放棄されたのではなく、2か月分の食料が与えられていた
- 犬を再度救出するための再進入は、天候・装備・燃料の問題から現実的ではなかった
- 鎖につないだままにしたのは野生化を防ぐため、また再訪時に管理しやすくする意図があった
- 首輪は一部緩められており、犬が自力で抜け出せるように配慮されていた
- 結果的に7頭が鎖につながれたまま死亡、6頭は行方不明、2頭(タロとジロ)が生還
- 犬を救えなかった観測隊への批判は「ひどい」とも言われ、感情的な反発が大きかった
- ただし、観測隊員たちは苦渋の選択であり、涙ながらに犬たちを見送ったとの証言もある
- 「共食い」があったという噂は証拠がなく、遺体に食べられた痕跡も確認されていない
- タロとジロは若く、体力や順応性が高かったため基地周辺で生き延びることができた
- 最年長の犬リキがタロ・ジロの生存を助けた可能性があると考えられている
- タロは帰国後に北海道大学で飼育され、ジロは昭和基地で亡くなり、それぞれ剥製として展示されている
- 犬たちの犬種「樺太犬」は極寒に強く、高い牽引力と忠誠心を持つ伝説的な犬種だった
- 映画『南極物語』では事実を元にした創作も多く、史実との違いに注意が必要
このように、「南極物語 犬 置き去り 理由」を掘り下げてみると、当時の極限状況と苦渋の判断、そして奇跡的な生還の背景まで、多くの要素が複雑に絡み合っていたことが見えてきます。
感動だけではなく、事実に基づいた理解が大切だといえるでしょう。
関連記事
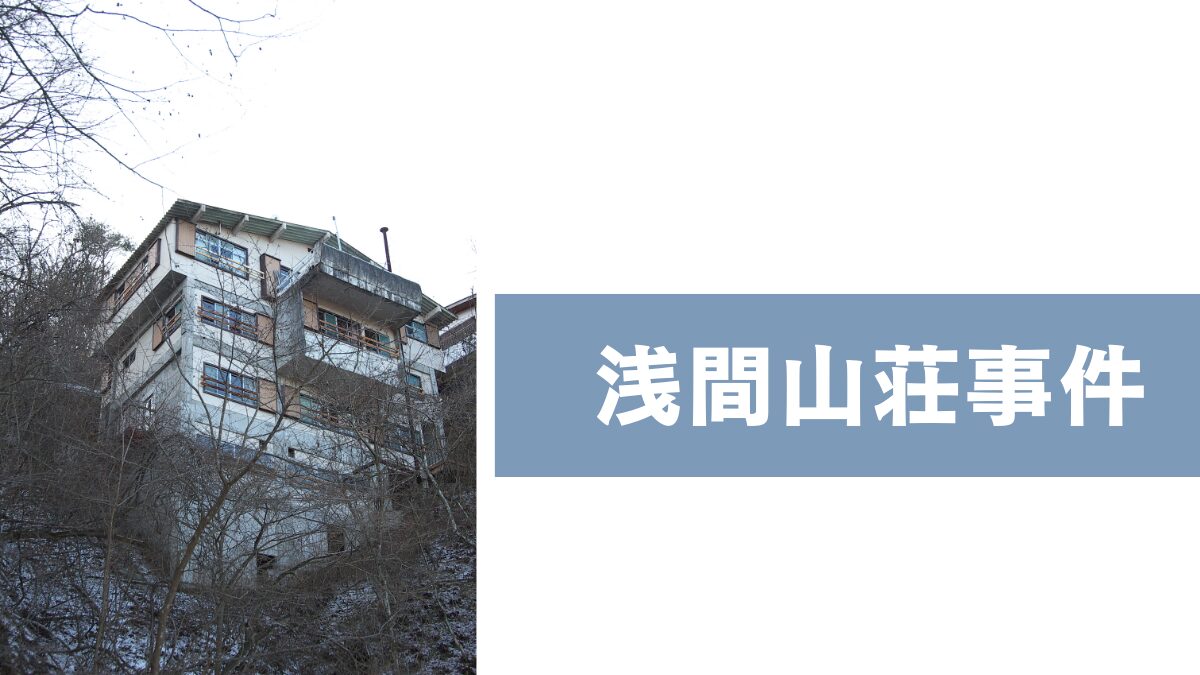
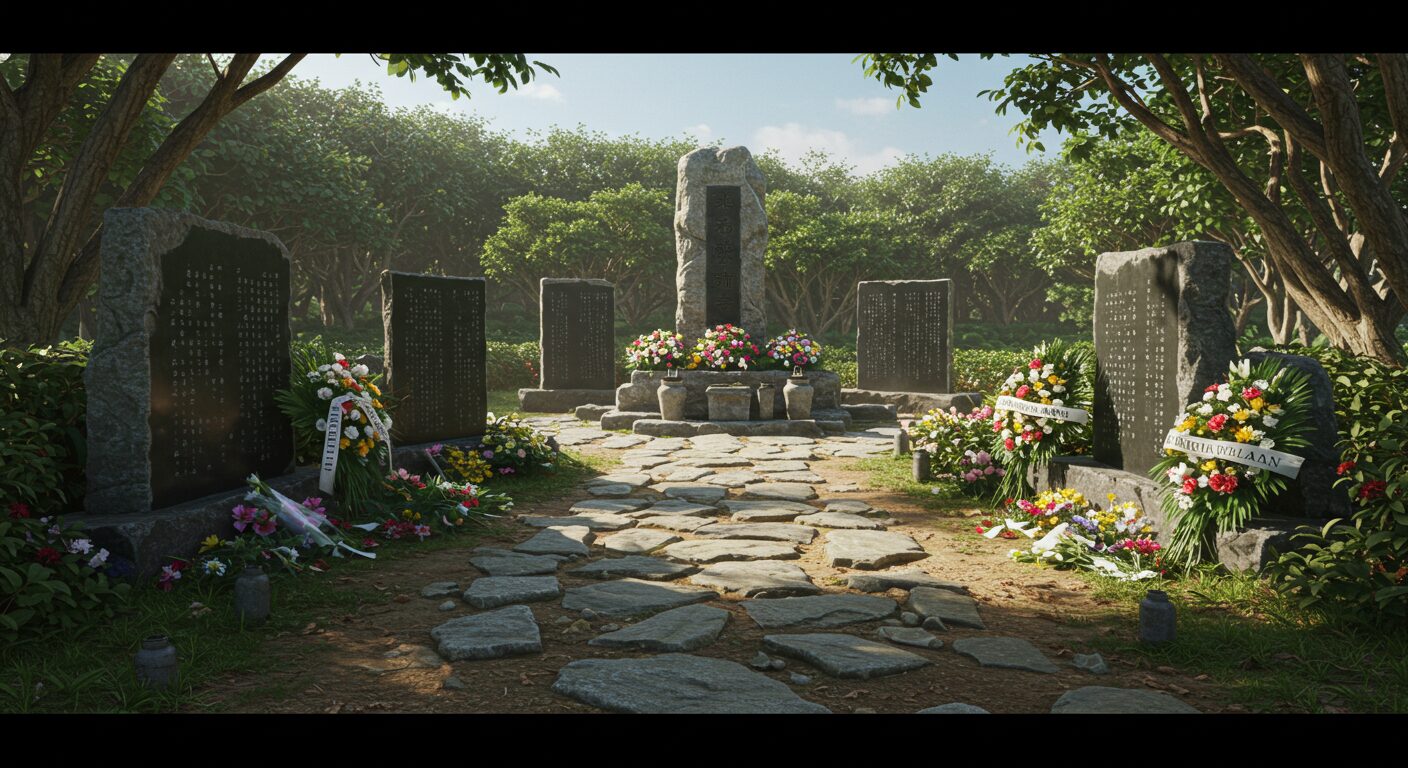

参考サイト
関連書籍



コメント