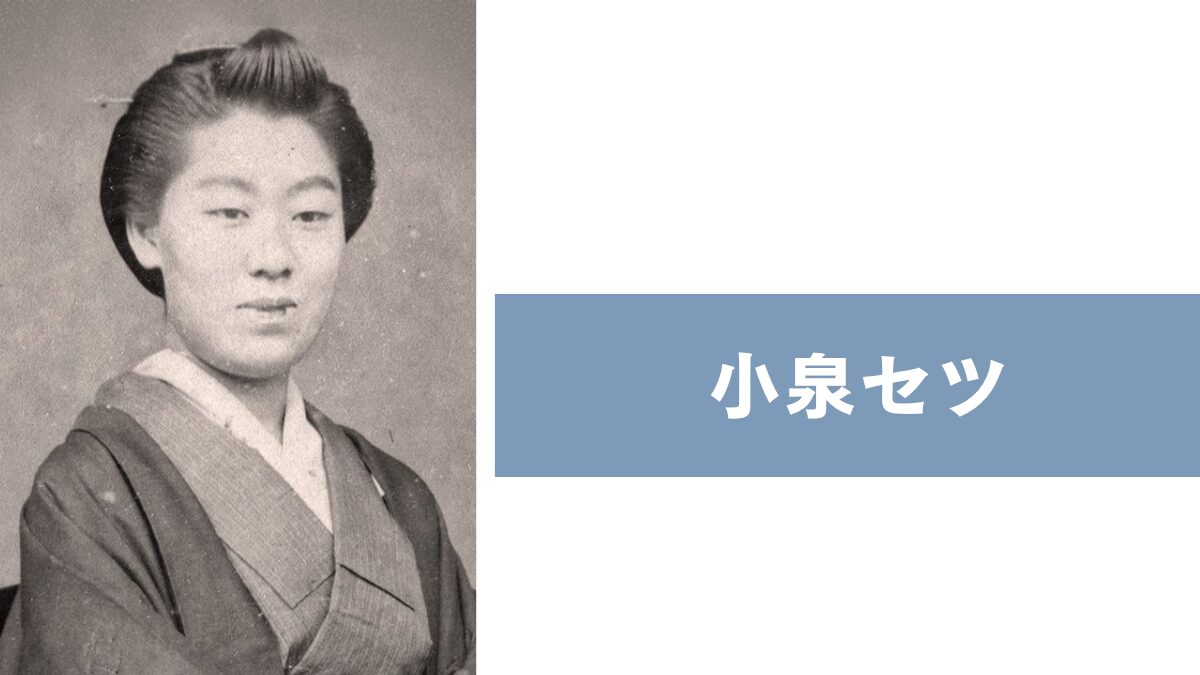2025年秋のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主人公モデルとして、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻・小泉セツが注目されています。
彼女が『怪談』の誕生に深く関わったことは知られつつありますが、「具体的に何をした人なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、セツの生涯は夫ハーンと出会うまで、困窮と苦労の連続でした。
没落士族の娘として生まれ、最初の結婚は夫の出奔という形で破綻します。
しかし、家族を養うために覚悟を決めてハーンの住み込み女中となったことが、彼女の運命を大きく変えました。
この記事では、小泉セツがどのようにして夫の「語り部」となり、その創作活動を支えたのか、波瀾万丈の生涯を詳しく解説します。
この記事を読むとわかること
- 小泉セツの生い立ちと困窮した前半生
- 最初の夫(前夫)との結婚と別れ
- 小泉八雲(ハーン)との出会いと結婚
- 夫の創作を支えた「語り部」としての功績
小泉セツとは何をした人? その生涯

- 小泉セツの生い立ちと育った環境
- 最初の結婚と前夫との別れ
- ラフカディオ・ハーンとの運命的な出会い
- 夫・小泉八雲との結婚
- 夫の創作を支えた「語り部」としての功績
小泉セツの生い立ちと育った環境
小泉セツは、日本の歴史が大きく動いた時代、慶応4年(1868年)2月4日に島根県松江市で生まれました。
この日は節分にあたり、「セツ」と名付けられたと言われています。
彼女が生まれたのは、江戸幕府が終わりを告げ、明治という新しい時代が始まろうとする、まさに激動の時代の幕開けでした。
セツの実家である小泉家は、松江藩に代々仕え、家禄300石の「上士」と呼ばれる由緒ある家柄でした。
父は小泉湊、母はチエといい、セツは6人兄弟の二女として誕生します。
しかし、セツは実の父母のもとで育てられることはありませんでした。
生まれてわずか7日後に、親戚であった稲垣家の養女に出されることになります。
養家となった稲垣家も、小泉家と同じく松江藩に仕える士族でしたが、家禄は100石の「並士」でした。
稲垣家には子供がいなかったため、「小泉家に次に子供が生まれたら養子に迎える」という約束が、セツが生まれる前から交わされていたのです。
養父母となった稲垣金十郎・トミ夫妻は、実家よりも格式高い小泉家から来たセツのことを「オジョ(お嬢)」と呼び、たいへん慈しみ、大切に育てたと言われています。
物語好きだった少女時代
幼い頃のセツは、物語を聞くのが何よりも好きな子供でした。
大人たちを見つけては「お話してごしない(お話ししてちょうだい)」とせがみ、昔話、民話、伝説など、様々な物語に夢中になりました。
特に養母のトミは、出雲大社の神官の家の養女だったこともあり、出雲神話や霊魂にまつわる不思議な話をセツにたくさん語って聞かせました。
この幼少期の体験が、セツの中に「語り部」としての豊かな素養を自然と蓄積させていくことになります。
また、セツが3歳の頃、未来を予感させるような出来事がありました。
当時、松江藩ではフランス人士官のワレットを招き、フランス式の軍事教練を行っていました。
ある日、養母に連れられて見物に行くと、赤い髪の西洋人であるワレットが近づいてきました。
他の子供たちは見慣れない姿に恐れをなして逃げ出しましたが、セツは怖がらずにじっと見つめていました。
ワレットはそんなセツの頭を撫で、小さな虫眼鏡(ルーペ)を手渡してくれたのです。
セツは「顔は怖いが心は優しい」と感じ、この虫眼鏡を生涯の宝物にしました。
後にセツ自身が「この出来事がなければ、ハーンと結婚することは難しかったかもしれない」と語っているように、西洋人への恐怖心を持たなかったこの経験は、彼女の運命に大きく関わってきます。
時代の荒波と困窮
セツが健やかに育つ一方で、日本社会は明治維新によって大きく変わろうとしていました。
武士の時代が終わり、士族は特権も家禄も失い、多くが生活に困窮していきます。
セツの養家・稲垣家も例外ではありませんでした。
養父・金十郎が慣れない商売(士族の商法)に手を出して失敗し、家は没落。
負債を抱え、城下の外れへの転居を余儀なくされます。
セツは学校が大好きで、内中原小学校では優秀な成績を収め、上級学校への進学を強く希望していました。
しかし、家庭の事情がそれを許しませんでした。
養父も養祖父も働こうとせず、養母が縫い物をして得るわずかな収入だけが頼りという状況だったのです。
セツは進学を諦め、義務教育である小学校下等教科を卒業すると、11歳の若さで家計を支えるために働き始めます。
実父・小泉湊が興した織物工場で、織子として機織りの仕事に従事しました。
それでも、実家の小泉家にも出入りし、生け花や茶の湯、謡曲といった良家の子女としての教養も習得しており、これが後に八雲との生活で役立つことになります。
最初の結婚と前夫との別れ
小泉セツは、18歳の時に最初の結婚をします。
明治19年(1886年)のことでした。
相手は鳥取藩士の次男であった前田為二という28歳の男性で、婿養子(入り婿)として稲垣家に迎えられました。
前田家も稲垣家と同様に、明治維新の混乱の中で困窮した士族の家柄でした。
セツは物語好きだったことから、この夫・為二にも物語をせがみ、「鳥取の布団の話」という悲しい話を聞いています。
この話は、後にセツがラフカディオ・ハーンに語り、彼の創作意欲を刺激するきっかけの一つとなります。
しかし、この結婚生活は長くは続きませんでした。
セツが18歳で迎えた夫は、結婚からわずか1年足らずで、セツと家族のもとから去ってしまったのです。
原因は、稲垣家の耐えがたいほどの貧困でした。
養父の事業失敗による負債は重く、セツが機織りなどで懸命に働いても、暮らしは一向に楽になりませんでした。
為二は、そんな生活苦に耐えられなくなり、大阪へと出奔してしまいます。
夫がいなくなった時期と前後して、セツにはさらなる不幸が襲いかかります。
実父の小泉湊が明治20年(1887年)に亡くなり、実父が経営していた織物会社も倒産してしまいました。
これにより、セツは困窮する養家・稲垣家だけでなく、実家である小泉家の生活も支えなければならないという、二重の重圧を背負うことになったのです。
夫を迎えに大阪へ
セツは、夫の為二が大阪にいることを突き止めると、自ら旅費を工面し、夫を連れ戻すために大阪へと向かいます。
当時、若い女性が一人で旅をすることは容易ではありませんでした。
しかし、セツは家族を再建したい一心で、必死の思いで大阪へ向かったのです。
ようやく為二に会うことができたセツは、松江に一緒に帰ってくれるよう懸命に懇願しました。
ところが、為二の決意は固く、セツの願いは冷たい言葉で拒絶されてしまいます。
夫にまで見捨てられたセツは、絶望のあまり、大阪の橋の上から身を投げようとまで思い詰めたと言われています。
しかし、まさにその時、松江で待つ養父母や家族の顔が脳裏をよぎり、なんとか思いとどまりました。
この壮絶な経験を経て、セツは「自分が家族を養っていくしかない」と、改めて強く決意します。
松江に戻ったセツは、夫との婚姻関係を解消する道を選びます。
離婚届は明治23年(1890年)1月に正式に受理され、セツは戸籍上、実家の小泉家に戻ることになりました(復籍)。
この時、セツは22歳。
若くして結婚の破綻と、一家の家計を支えるという重い責任を背負うことになったのです。
この辛い経験は、セツの忍耐強さや、家族を守るという強い意志を形作ったと言えるでしょう。
ラフカディオ・ハーンとの運命的な出会い
最初の夫と別れ、小泉家に復籍したセツでしたが、生活は依然として苦しいままでした。
前述の通り、養家の稲垣家と実家の小泉家、両家の親たちの生活を、セツはほぼ一人で支えなければならなかったのです。
セツの収入だけではどうにもならないほど、両家は困窮していました。
特に明治23年(1890年)から翌年にかけて、松江を記録的な大寒波が襲います。
粗末な家に住むセツたち家族は、凍死の危険さえ感じるほどの寒さと飢えに震えていたと言われています。
セツは、4人の親たちを見捨てるわけにはいかないと、必死に働く道を探していました。
そんな八方塞がりの状況にあったセツに、一つの仕事の話が舞い込みます。
それは、松江に赴任してきた「外国人教師の住み込み女中」の仕事でした。
この外国人教師こそ、のちに小泉八雲となるラフカディオ・ハーン(松江では「ヘルンさん」と呼ばれていました)です。
ハーンは、1890年(明治23年)にアメリカの雑誌社の特派員として来日しました。
若い頃から英訳の『古事記』などを通して日本文化に強い関心を抱いていた彼は、来日後まもなく出版社との契約を解除し、同年8月末から島根県尋常中学校・師範学校の英語教師として松江に赴任していました。
しかし、慣れない日本の生活、特に松江の厳しい冬の寒さで病に倒れてしまいます。
ハーンが当初滞在していた旅館の女中や、勤務先の西田千太郎教頭が、ハーンの身の回りの世話をする人が必要だと考え、世話係を探していました。
そこで白羽の矢が立ったのが、困窮していたセツだったのです。
洋妾(ラシャメン)と呼ばれても
セツにとって、この仕事を引き受けることは、非常に大きな決断でした。
当時の日本では、西洋人の家に住み込みで働く女性は、「洋妾(ラシャメン)」、つまり西洋人の愛人や妾(めかけ)として見られ、世間から非難され、後ろ指を指される可能性が非常に高かったからです。
士族の娘としての誇りもあったセツは、当初、この仕事に強い抵抗を感じていました。
しかし、セツには家族の命がかかっていました。
この仕事を断れば、愛する家族が飢えと寒さで命を落とすかもしれない。
世間体や誇りよりも、家族を守ることを選んだセツは、周囲からどのような目で見られようとも、覚悟を決めてこの仕事を引き受けることにします。
こうして1891年(明治24年)2月頃、セツはラフカディオ・ハーンの住む家に、住み込み女中として働き始めました。
これが、二人の運命的な出会いとなります。
ハーンもまた、セツと同じように、それまでの人生で多くの苦難を経験していました。
ギリシャで生まれ、アイルランドで育ちましたが、幼少期に両親が離婚。
さらに事故で左目を失明するなど、孤独で不幸な少年時代を送っていました。
辛い過去を持つ二人が、遠い異国の地・松江で出会ったのは、まさに運命だったのかもしれません。
セツが家族のために下したこの大きな決断が、彼女自身の人生を、そして日本の近代文学史をも変えることになったのです。
夫・小泉八雲との結婚
小泉セツがラフカディオ・ハーンの家で働き始めてからの二人の関係は、単なる主人と住み込み女中というものではなくなっていきました。
ハーンは、辛い過去を背負いながらも家族のために懸命に働くセツの姿に、次第に惹かれていきます。
セツもまた、西洋人でありながら日本の文化を深く愛し、孤独を抱えるハーンの優しさに触れ、心を開いていきました。
二人が同居を始めて約半年が過ぎた1891年(明治24年)7月、ハーンは同僚の教師と共に、出雲大社近くの稲佐の浜に滞在しました。
しかし、ハーンはわずか2日目には松江からセツを呼び寄せ、その後は二人で仲良く一緒に行動していたと記録されています。
この時点で、ハーンはセツを「住み込み女中」としてではなく、人生のパートナーとして扱っていたことがわかります。
実際に、同年8月11日にハーンが友人に出した手紙の中では、セツとの結婚をはっきりと報告しています。
法的な手続きはまだでしたが、二人は事実上の夫婦として、松江で新たな生活をスタートさせたのです。
同年11月、ハーンは熊本の第五高等中学校(現在の熊本大学)へ転勤となり、セツも彼に従います。
この時、セツは松江から自分の養父母である稲垣夫妻も連れて行きました。
家族を大切にするセツの思いを、ハーンが受け入れた証と言えるでしょう。
その後、神戸、そして東京へと、二人はセツの家族と共に移り住んでいきます。
熊本では長男の一雄が誕生し、二人の絆はさらに深まっていきました。
ヘルンさん言葉による意思疎通
夫婦となった二人ですが、言葉の壁は大きな問題でした。
セツは夫との意思疎通のために英語の勉強を試みます。
彼女が残した『英語覚え書帳』には、「トマール(明日)」や「ワエン(酒)」といった、出雲なまりのカタカナ英語が書き連ねられており、その努力の跡がうかがえます。
しかし、残念ながらセツの英語学習は、ものにはなりませんでした。
一方で、ハーンも日本語を体系的に学ぶことはありませんでした。
しかし、二人の間には、言葉を超えた深い理解と、独自のコミュニケーション手段が生まれていました。
それが「ヘルンさん言葉」と呼ばれる、二人だけの独特な日本語です。
これは、助詞を省略したり、動詞の活用を気にしなかったりする、片言の日本語でした。
例えば、「スタシオンニ タクサン マツノ トキ アリマシタナイ」という言葉は、「駅で待ち時間があまりありませんでした」という意味だそうです。
文法的には正しくありませんが、セツはこの「ヘルンさん言葉」を正確に理解し、ハーンもまた、セツが話すどんな上手な英語よりも、この言葉を心地よく感じていました。
この二人だけの言葉が、夫婦の信頼関係を何よりも強く結びつけたのです。
家族を守るための日本帰化
神戸に在住していた1896年(明治29年)2月、ハーンは人生の大きな決断をします。
日本に帰化し、日本人になることを選んだのです。
当時、ハーンは英国籍でしたが、そのままでは法律上、妻であるセツや長男の一雄に財産を残すことが難しいという問題がありました。
ハーン自身が幼少期に両親の離婚などで法的に不安定な立場に置かれた辛い経験を持っていたため、愛する妻子が同じような苦しみに遭うことを何よりも恐れたのです。
ハーンは、セツの戸籍に入る「外国人入夫結婚」という形を選びました。
これにより、彼は正式に日本国籍を取得し、「小泉八雲」と名乗ることになります。
これは、ただ名前を変えたというだけではなく、ハーンがセツと、彼女の家族である小泉家を生涯守り抜くという、勇気ある決意の表れでした。
この法的な結婚を経て、二人は名実ともに夫婦となり、その後、二男一女(巌、清、寿々子)にも恵まれ、4人の子供を持つ家族となりました。
夫の創作を支えた「語り部」としての功績
小泉セツが果たした最大の功績は、間違いなく、夫である小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の創作活動を、その根幹から支え続けたことです。
八雲は、熊本時代に執筆した『知られぬ日本の面影』が世界的に好評を博して以降、英語教師の仕事と並行して、日本の文化や精神世界に関する著述活動に専念するようになります。
しかし、八雲は来日後も日本語の読み書きを体系的に学んだわけではなく、日本の古典や複雑な物語を自力で読み解くことは困難でした。
ここで、セツの持つ「語り部」としての才能が、八雲の創作にとって不可欠なものとなります。
セツは、夫である八雲の「リテラリー・アシスタント(文学面での助手)」として、八雲の作品世界を構築する上で、決定的に重要な役割を担いました。
『怪談』や『骨董』といった八雲の代表作に収められている「耳なし芳一」や「雪女」などの物語の多くは、セツが八雲に語って聞かせた日本の古い物語が元になっています。
セツがいなければ、これらの有名な作品が世界に知られることはなかったかもしれません。
夫婦の共同作業
セツの功績は、単に物語をハーンに伝えたというだけではありません。
二人の間には、作品を生み出すための独特な共同作業のプロセスがありました。
前述の通り、セツは幼い頃から物語を聞くのが大好きで、養母トミなどから多くの昔話、民話、伝説を記憶していました。
その才能に八雲が気づいたのは、最初の夫から聞いた「鳥取の布団の話」という悲話を、セツが八雲に語った時だったと言われています。
八雲は、セツの語り口と物語の持つ力に深く感動し、「あなたは私の手伝いできる人です」と非常に喜んだそうです。
八雲はセツに対し、本に書かれている物語であっても、本を見ながらそのまま訳すことを望みませんでした。
彼は、セツが一度物語を自分の中に取り込み、内容を完全に理解した上で、セツ自身の言葉で、感情を込めて「語り部」として語ることを要求しました。
セツは、夫の好む怪奇的で不思議な雰囲気の話をよく理解しており、伝承だけでなく、『古今著聞集』などの古典文学や、当時の出版物からも素材を探し出しては読み込みました。
そして、その内容を二人だけの「ヘルンさん言葉」を駆使して、八雲の想像力を刺激するように語り直したのです。
この共同作業は、細部にまで及びました。
例えば、『怪談』の「耳なし芳一」の中で、芳一を迎えに来た侍が門を開けるよう命じる場面の掛け声「Kaimon!」という表現一つをとっても、それがどのような響きを持つべきか、夫婦で熱心に議論して決定されたものだと言われています。
八雲の作品は、まさにセツとの二人三脚、夫婦のコラボレーションによって生み出されたものだったのです。
八雲の感謝とセツの喜び
八雲自身も、妻の貢献の大きさを深く理解していました。
彼は長男の一雄に、「この本、みなあなたのおかげで生まれましたの本です。世界で一番良きママさん」と語り、セツへの深い感謝の気持ちを伝えています。
セツにとっても、夫の好みを知り尽くし、彼の役に立つ素材を探し、語ることが生き甲斐となっていました。
二人の間にあった深い信頼と愛情が、八雲の作品を円熟させ、世界的な評価へと導いたのです。
もちろん、八雲の著作の中には、小学校卒業のセツには理解が難しかったであろう仏教説話なども含まれています。
そのため、フェノロサ夫人や、八雲の同僚であった三成重敬、雨森信成といった、他の協力者の存在も指摘されています。
しかし、彼らが自らの貢献について多くを語らなかったのに対し、セツが八雲の創作活動の最大の功労者であり、その精神的な支柱であったことは、八雲の言葉からも明らかです。
セツは、まさに八雲文学の「育ての親」とも言うべき存在でした。
小泉セツは何をした人か? 夫八雲との日々

- 夫婦の絆「ヘルンさん言葉」とは
- 八雲との間に生まれた子供たち
- 夫の死後、小泉セツは再婚した?
- 晩年の暮らしとセツの死因
夫婦の絆「ヘルンさん言葉」とは
小泉セツと夫のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、どのようにして深い意思疎通を図っていたのか、それは多くの人が疑問に思う点かもしれません。
二人の絆を語る上で欠かせないのが、「ヘルンさん言葉」と呼ばれる、夫婦二人だけのユニークなコミュニケーション手段です。
これは、文法や格好にとらわれない、独特の日本語でした。
二人が出会った当初、もちろん言葉の壁は存在しました。
セツは夫のために英語を学ぼうと努力を重ねています。
彼女が残した『英語覚え書帳』には、出雲なまりが感じられるカタカナで、必死に英単語を書き留めた跡が残っています。
例えば「トマール(Tomorrow=明日)」や「ワエン(Wine=酒)」といった具合です。
しかし、このセツの英語学習は、残念ながら実用レベルには達しませんでした。
一方で、夫のハーンも、日本文化を深く愛していましたが、日本語を体系的に、文法からしっかりと学んだわけではありませんでした。
彼が話す日本語もまた、片言のものでした。
普通であれば、ここで夫婦のコミュニケーションは行き詰まってしまうかもしれません。
しかし、二人はお互いを理解したいという強い思いから、どちらの母国語でもない、二人だけが完璧に理解できる「第三の言葉」を生み出したのです。
それが「ヘルンさん言葉」です。
「ヘルン」とは、ハーンの松江での愛称です。
この言葉の特徴は、日本語の「てにをは」といった助詞を省略したり、動詞や形容詞の活用、文の順序などを気にしなかったりする点にあります。
例えば、「スタシオンニ タクサン マツノ トキ アリマシタナイ」という言葉が残されていますが、これは「駅で待ち時間があまりありませんでした」という意味だそうです。
文法的には正しくありませんが、この言葉をセツは正確に理解できました。
そしてハーンにとっては、この「ヘルンさん言葉」こそが、日本人が話すどんなに流暢な英語よりも、ずっと理解しやすく、心地よいものだったのです。
この「ヘルンさん言葉」の真価は、日常会話だけにとどまりません。
前述の通り、セツは夫の創作活動を支える「語り部」としての重要な役割を担いました。
セツが日本各地の昔話や伝説を収集し、それを八雲に語って聞かせる際、まさにこの「ヘルンさん言葉」が使われました。
セツは、難しい古典の言葉や日本的な情緒を、この二人だけの言葉に“翻訳”し、夫の想像力をかき立てるように語ったのです。
八雲の代表作『怪談』などに収録されている物語の多くは、この「ヘルンさん言葉」というフィルターを通して、セツから八雲へと伝えられ、そして八雲の英文によって世界的な作品へと昇華していきました。
このように、「ヘルンさん言葉」は、単なる片言の日本語ではありません。
言葉の壁に直面した夫婦が、お互いに歩み寄り、努力し、深い信頼関係を築き上げた結果生まれた、愛の結晶とも言えるものです。
この言葉があったからこそ、二人は国籍や文化の違いを超えて深く結びつき、世界に残る文学作品を共に創り上げることができたと言えるでしょう。
八雲との間に生まれた子供たち
小泉セツと小泉八雲は、その結婚生活の中で、三男一女、合計4人の子供たちに恵まれました。
不幸な幼少期を送り、家族の温もりを知らずに育った八雲にとって、セツと共に築いた家庭と子供たちの存在は、何物にも代えがたい喜びであり、彼の人生における大きな精神的支柱となりました。
熊本時代に夫婦となってから、最初の子供が生まれます。
1893年(明治26年)に誕生した長男の一雄(かずお)です。
一雄は、父・八雲の死後、その思い出や小泉家の日常を綴った『父小泉八雲』や『Father and I』といった優れた随筆を数多く残したエッセイストとして知られています。
彼は、母セツと共に「小泉八雲」の名を守り、その功績を後世に伝えるという重要な役割を担いました。
一雄の子供、つまりセツと八雲の孫にあたる小泉時(とき)氏、そして曾孫にあたる小泉凡(ぼん)氏も、民俗学者や随筆家として、八雲に関する研究や紹介を続けています。
熊本、神戸を経て、一家が東京の牛込市谷や西大久保に居を構えてから、さらに3人の子供たちが誕生します。
次男の稲垣巌(いなお)は、母であるセツがかつて養女に入っていた稲垣家を継ぐことになりました。
セツが苦しい時代を過ごした養家ですが、その家名を絶やさないようにという配慮があったのかもしれません。
巌は教師の道に進んだとされています。
三男は清(きよし)と名付けられ、彼は芸術の道に進み、画家として活動しました。
清にも子供たちがおり、セツと八雲の血筋は、芸術の世界にも受け継がれていったことになります。
そして、末っ子として長女の寿々子(すずこ)が生まれました。
三男一女という4人の子供たちに囲まれ、セツと八雲、そしてセツが松江から連れてきた養父母も加わった小泉家の暮らしは、きっと賑やかで愛情に満ちたものだったことでしょう。
八雲が、愛する妻セツと子供たちを守るために、法的な問題を解決しようと奔走し、1896年(明治29年)に日本国籍を取得して「小泉八雲」となったエピソードは、彼の家族への深い愛情を物語っています。
自らが経験したような法的な不安定さや孤独を、愛する家族に決して味わわせたくないという強い意志が、彼を「日本人」になる道へと導きました。
子供たちは、セツにとっても大きな存在でした。 1904年(明治37年)に八雲が急逝し、セツが36歳という若さで未亡人となった時、彼女のそばにはまだ幼い4人の子供たちがいました。
この子供たちを立派に育て上げることが、夫亡き後のセツの生きる大きな支えとなり、彼女が「小泉八雲夫人」としての人生を力強く歩んでいく原動力となったことは間違いありません。
夫の死後、小泉セツは再婚した?
夫である小泉八雲が1904年(明治37年)に心臓発作で急逝した時、妻のセツはまだ36歳という若さでした。
当時はまだ幼い4人の子供たちを抱えており、その後の人生は決して容易なものではなかったはずです。
このような状況から、「セツはその後、再婚したのだろうか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、小泉セツは八雲の死後、再婚することはありませんでした。
彼女は、夫・八雲が亡くなってから1932年(昭和7年)に64歳で亡くなるまでの約27年半という長い期間を、「小泉八雲夫人」として、そして4人の子供たちの母として、独身のまま力強く生き抜きました。
セツが再婚を選ばなかった背景には、いくつかの理由が考えられます。
まず何よりも、夫・八雲への深い愛情と敬意があったことは想像に難くありません。
二人が共に過ごした時間は約13年半と、彼女の生涯から見れば決して長くはありませんが、それはセツの人生において最も輝き、生き甲斐を感じた、かけがえのない時間でした。
八雲との思い出と、彼が残したものを守り抜くことが、彼女の使命となっていたのでしょう。
経済的な側面も、彼女の決断を支えた大きな要因でした。
八雲は生前から、自身の不幸な幼少期の経験を踏まえ、家族が法的に守られるよう配慮していました。
彼は遺言状を作成しており、そこには「遺産はすべて妻に譲る」と明記されていました。
当時としては画期的な内容でしたが、このおかげで、セツと子供たちは八雲の死後に経済的に困窮することを免れます。
西大久保の家や、八雲が愛した書斎、そして多くの蔵書を生前のまま残すことができ、子供たちにも十分な教育を受けさせることができました。
セツは、著作権や印税の管理といった実務もこなし、夫が残した家産をしっかりと守り通したのです。
また、セツの周囲には、八雲の生前からの友人たちがいました。
ミッチェル・マクドナルドやエリザベス・ビスランド、チェンバレンといった人々は、夫を失ったセツと幼い子供たちを放っておかず、親身になって手を差し伸べ、様々な手続きや問題解決を助けました。
このような支援者の存在も、セツが再婚に頼らずとも自立して家庭を守っていく上で、大きな助けとなったはずです。
セツは、単に家庭を守る未亡人であっただけではありません。
「小泉八雲夫人」として、夫に関する著作の出版や東大での講義録の刊行、国内外からの訪問客の接遇、そして自らも八雲との思い出を綴った「思い出の記」を執筆するなど、長男の一雄と共に、八雲の功績を世に伝えるという公的な役割も多忙にこなしていました。
彼女にとって、残りの人生は、夫・小泉八雲の「妻」として生き抜くことそのものに、大きな意味があったのです。
晩年の暮らしとセツの死因
夫・小泉八雲に先立たれた後、小泉セツがどのような晩年を送ったのか、気になる方も多いでしょう。
彼女の人生の前半生は、士族の没落、困窮、最初の結婚の破綻、そして家族を養うための苦労の連続でした。
しかし、八雲の死後の彼女の暮らしは、それまでとは対照的に、比較的穏やかで裕福なものであったと伝えられています。
八雲は、セツと子供たちが将来困らないようにと、全財産をセツに譲るという遺言を残していました。
このおかげで、セツは経済的な心配をすることなく、八雲と暮らした新宿西大久保の家で、4人の子供たちを育て上げることができました。
夫が大切にしていた書斎も生前のままに保存し、夫が好きだったクリーム色の薔薇を霊前に供えることを日課にしていたと言われています。
夫への深い愛情と追慕の念が、彼女の生活の根底には常にありました。
子育てが一段落してからは、セツは自身の時間も大切にするようになります。
趣味として、若い頃に良家の子女として身につけていた茶道や、謡曲(能楽の歌の部分)の稽古に熱心にいそしみました。
これは、ただの気晴らしというよりも、波乱の人生の中で十分にできなかった、自分自身の教養や楽しみを取り戻す時間でもあったのかもしれません。
また、彼女は「小泉八雲夫人」として、非常に多忙な日々を送っていた側面もあります。
八雲の著作権の管理や、夫に関する新たな出版物の監修、国内外からの訪問客の対応など、その役割は多岐にわたりました。
そして、何よりも重要な仕事として、長男・一雄の助けも借りながら、八雲との日々の思い出を綴った「思い出の記」を執筆、出版しました。
この本は、八雲の人物像や夫婦の生活を伝える貴重な資料となっており、セツが晩年に果たした大きな功績の一つです。
このように、夫への追憶と、子供たちや孫たちへの愛情、そして自身の趣味や公的な役割と、セツの晩年は非常に充実していた様子がうかがえます。
しかし、そんな穏やかな生活の中、セツの健康は少しずつ蝕まれていました。
晩年は動脈硬化に苦しんでいたとされています。
そして、1932年(昭和7年)2月18日、小泉セツは、夫・八雲と共に過ごした思い出の詰まった西大久保の自宅で、子や孫たちに見守られながら、64歳の生涯を静かに閉じました。
セツの亡骸は、夫・小泉八雲が眠る雑司ヶ谷霊園の、その傍らに葬られました。
生きていた時の13年8ヶ月という夫婦生活は、彼女の全生涯から見れば短い期間だったかもしれません。
しかし、その後の27年半を「小泉八雲夫人」として生き抜いたセツは、今、愛する夫の隣で静かに眠っています。
「小泉セツは何をした人か」が分かる総まとめ
ここまで小泉セツの生涯について詳しく見てきましたが、改めて「小泉セツが何をした人なのか」を分かりやすく箇条書きでまとめてみます。
- 慶応4年(1868年)、松江藩の由緒ある「上士」の家柄に生まれました。
- しかし生後7日で、親戚である「並士」の稲垣家に養女に出されます。
- 幼い頃から物語を聞くのが大好きで、養母などから多くの話を聞いて育ちました。
- この経験が、後に夫を支える「語り部」としての素養を育みます。
- 明治維新の混乱で養家が没落し、優秀な成績でも進学を諦め、11歳から織子として家計を支えました。
- 18歳の時に婿養子を迎えて結婚しますが、貧困が原因で夫が出奔してしまいます。
- 絶望の中で夫を大阪まで迎えに行きますが拒絶され、22歳で離婚しました。
- 養家と実家の両方の家族を養うため、生活は困窮を極めます。
- 家族を救うため、「洋妾」と非難されることを覚悟の上で、ラフカディオ・ハーン(ヘルン)の住み込み女中となりました。
- これが二人の運命的な出会い(1891年)となります。
- 孤独な過去を持つハーンと、苦労を重ねたセツは次第に惹かれ合い、事実上の夫婦として生活を始めます。
- 言葉の壁を乗り越えるため、二人だけの「ヘルンさん言葉」というコミュニケーション手段を生み出しました。
- 1896年、ハーンはセツと子供たちを守るために日本国籍を取得し、「小泉八雲」としてセツと正式に結婚します。
- 夫・八雲の「リテラリー・アシスタント」として、日本の昔話や怪談を語って聞かせ、創作活動を支えました。
- 『怪談』に代表される八雲の多くの名作は、セツのこの「語り」なしでは生まれなかったと言われています。
参考サイト