足利尊氏と後醍醐天皇の関係は、日本史の中でも特に複雑で、興味深いテーマの一つです。
最初は協力し合って鎌倉幕府の滅亡に貢献したはずの二人が、なぜ激しい対立へと発展していったのでしょうか。
また、その背景にはどのような政治的な思惑や価値観の違いがあったのでしょうか。
この記事では、鎌倉幕府の終焉から南北朝時代の始まりまでの流れを軸に、足利尊氏と後醍醐天皇の関係をわかりやすく解説します。
彼らの対立を決定づけた戦いや、後醍醐天皇の島流し、尊氏による天竜寺の建立など、主要な出来事を一つひとつ丁寧にひもといていきます。
初めてこの時代の歴史に触れる方でも理解しやすいよう、時系列や因果関係を重視して整理しました。
歴史の授業では表面的にしか触れないことの多い足利尊氏と後醍醐天皇の関係。
この記事を読むことで、単なる「対立」だけでなく、その背景にある思想や人間関係までも深く知ることができます。
この記事を読むとわかること
- 足利尊氏と後醍醐天皇の関係の変化と背景
- 鎌倉幕府滅亡における両者の役割
- 両者が関わった主要な戦いとその意味
- 天竜寺や島流しなど象徴的な出来事の意義
足利尊氏と後醍醐天皇の関係を歴史から探る

- 鎌倉幕府滅亡で果たした二人の役割
- 建武の新政と足利尊氏の離反
- 足利尊氏が後醍醐天皇と対立した理由
- 湊川の戦いなどでの両者の争い
- 天竜寺建立に込められた尊氏の意図
鎌倉幕府滅亡で果たした二人の役割
鎌倉幕府の滅亡において、足利尊氏と後醍醐天皇はそれぞれ異なる立場から重要な役割を担っていました。
この時期、日本は武士政権から再び天皇中心の政治に戻るかどうかという歴史的な岐路に立っていたのです。
後醍醐天皇は、鎌倉幕府による幕政に対して強い不満を抱いていました。
当時の幕府は朝廷を軽視し、形だけの権威にとどめていたため、後醍醐天皇は自ら政治を行う「親政」の実現を目指して動き出します。
その一環として企てたのが「元弘の乱」と呼ばれる反幕府活動でした。
一方、足利尊氏は当初、幕府側の有力武将として行動していましたが、後に反旗を翻します。
幕府の命令に反し、後醍醐天皇の味方として六波羅探題を攻略したことで、幕府の支配体制に大きな打撃を与えました。
この行動が決定打となり、1333年、鎌倉幕府はついに滅亡に至ったのです。
このように、後醍醐天皇が理想を掲げて指導し、足利尊氏が実際に武力でそれを支援したことで、長く続いた武家政権を打倒することができました。
ただし、両者の目的には違いがありました。
後醍醐天皇は天皇親政を確立したいと考えており、尊氏は武士による新たな政治のあり方を模索していたのです。
このすれ違いが、後に深刻な対立へと発展する原因となっていきます。
建武の新政と足利尊氏の離反
建武の新政とは、鎌倉幕府の滅亡後に後醍醐天皇が開始した政治体制のことを指します。
これは約140年ぶりに実現した天皇による親政であり、武家中心だった日本の政治構造を大きく変えるものでした。
新政では、恩賞の配分、土地の再分配、税制改革など、幅広い分野で急激な政策が実施されました。
しかし、こうした改革は現実との乖離が大きく、多くの武士たちから不満を買うことになります。
彼らが最も期待していたのは、戦功に応じた領地の恩賞でしたが、後醍醐天皇はこれを公平ではなく朝廷の論功行賞によって裁定しました。
足利尊氏もその一人でした。
彼は幕府打倒に多大な貢献をしたにもかかわらず、十分な恩賞を得られなかったことに加え、朝廷側の政治的対応に不信感を強めていきます。
さらに、尊氏の側近たちも朝廷との関係に不満を募らせていました。
そして1335年、中先代の乱を鎮圧するために尊氏が関東へ出兵したことをきっかけに、朝廷と尊氏の間に深刻な亀裂が生まれます。
尊氏はそのまま独自に行動を始め、朝廷の許可なく東国の支配を進めました。
これが、建武の新政からの明確な離反の始まりです。
こうして、新政はわずか2年余りで瓦解し、尊氏は新たな武家政権の樹立へと動き出していきます。
建武の新政は理念先行で現実の武士社会と乖離していたため、尊氏の離反はある意味で当然の帰結だったとも言えるでしょう。
足利尊氏が後醍醐天皇と対立した理由
足利尊氏と後醍醐天皇の対立は、日本の歴史に大きな影響を与えました。
その主な原因は、両者の政治理念の違いと、それに伴う実利の対立にあります。
後醍醐天皇は、天皇を中心とした政治体制を理想として掲げていました。
この体制では、武士たちの力を抑え、朝廷がすべての権限を握ることを目指していたのです。
一方、足利尊氏は鎌倉幕府の流れをくむ武士出身であり、武士による政治の必要性を強く感じていました。
この思想の違いは、建武の新政の運営にあらわれます。
武士たちは、戦いの功績に応じた領地の分配を求めていましたが、後醍醐天皇は朝廷の伝統的価値観に基づいてそれを判断しました。
その結果、多くの武士が不満を抱き、尊氏もその一人として強く反発するようになります。
さらに、後醍醐天皇は尊氏の権限拡大を警戒し、彼の政治的影響力を抑えようとしました。
尊氏の東国支配や軍事行動に対し、朝廷が制約を課そうとしたことが両者の対立を決定的なものにしていきます。
こうして、両者の信頼関係は崩れ、ついには武力による衝突へと発展していきます。
この対立が後の南北朝時代を生み出すきっかけになったのです。
湊川の戦いなどでの両者の争い
湊川の戦いは、足利尊氏と後醍醐天皇(およびその側近である新田義貞・楠木正成)が直接軍事衝突した重要な戦いです。
この戦いによって、両者の政治的対立は決定的なものとなり、日本は南北朝という分裂した時代へ突入していきます。
1336年、足利尊氏は後醍醐天皇の追討令を受けたにもかかわらず、九州で体制を立て直し、再び東上します。
このとき、迎え撃ったのが楠木正成と新田義貞ら後醍醐天皇の忠臣たちでした。
両軍は摂津国・湊川で激突し、ここでの戦闘が「湊川の戦い」と呼ばれます。
この戦いでは、兵力・戦略において優勢だった足利軍が勝利します。
楠木正成は壮絶な討死を遂げ、新田義貞も後に敗走。
朝廷側は大打撃を受け、事実上、政権の中枢が崩壊しました。
この勝利により、尊氏は自らを正統な政権の担い手として位置づけ、京都に室町幕府を樹立する足がかりを築きました。
ただし、後醍醐天皇はすぐには屈せず、吉野に逃れて南朝を樹立します。
これにより、日本は約60年にも及ぶ南北朝の内乱に突入していくのです。
湊川の戦いは、単なる戦闘ではなく、政治の主導権をめぐる象徴的な争いでした。
この戦いを境に、後醍醐天皇と足利尊氏の間には和解の余地がほとんどなくなったと言えるでしょう。
天竜寺建立に込められた尊氏の意図
天竜寺は、足利尊氏が建立した臨済宗の寺院であり、後醍醐天皇の菩提を弔うための寺でもあります。
この寺には、表向きの宗教的意味を超えた、尊氏の政治的・心理的な意図が色濃く込められていました。
後醍醐天皇は、吉野に逃れて南朝を開いたものの、1339年に崩御します。
このとき、尊氏は表向きには政敵であった後醍醐天皇の死を悼み、その冥福を祈るために天竜寺を建立しました。
一方で、これには政敵に対する「形式的な和解」を示す狙いもあったと考えられます。
南北朝の分裂によって国内は混乱し、尊氏にとっては統一の正統性を示すことが急務でした。
そのため、後醍醐天皇を敵視しすぎず、逆に敬意を示す姿勢をとることで、政権の安定を図ろうとしたのです。
さらに、天竜寺の建立には経済的効果も期待されていました。
尊氏はこの寺の建設費用を捻出するため、「天竜寺船」と呼ばれる貿易船を中国に派遣します。
これにより、日明貿易の礎を築きつつ、幕府の財政基盤を強化しようとしました。
このように、天竜寺はただの供養の場ではなく、尊氏の政治的計算や外交戦略の一環でもありました。
形式の裏に隠された現実的な意図を読み取ることが、歴史を深く理解する手がかりになるでしょう。
対立から南北朝時代へ続く足利尊氏と後醍醐天皇の関係

- 島流しと後醍醐天皇の復権劇
- 南北朝時代の発端と両者の影響
- 吉野へ逃れた後醍醐天皇の思惑
- 征夷大将軍となった尊氏の政治的転換
- 両者の思想の違いと政治理念の対立
- 人物像と性格の違いが招いた歴史の分岐点
島流しと後醍醐天皇の復権劇
後醍醐天皇は、鎌倉幕府に対してたびたび反旗を翻した人物として知られています。
その活動の一環で起こした「元弘の乱」は失敗に終わり、彼は1332年に隠岐島(おきのしま)へ配流されました。
この出来事が「島流し」として有名になった背景には、天皇という存在が流罪になる異例性がありました。
本来、天皇が流刑に処されることは極めてまれであり、それだけ後醍醐天皇の反幕府姿勢が深刻視されていたことを示しています。
しかし、後醍醐天皇はこの窮地に屈することなく、密かに復帰の機会をうかがっていました。
島流し中も、配下の者たちと連絡を取りながら、再起に向けた準備を進めていたとされます。
翌1333年、幕府に不満を抱く有力武士たちが各地で蜂起し、後醍醐天皇の復帰を後押しします。
特に、足利尊氏が幕府に反旗を翻し、六波羅探題を攻撃したこと、そして新田義貞が鎌倉を攻め落としたことで、幕府は崩壊。
後醍醐天皇は再び京都に戻り、悲願の親政を開始することになります。
この一連の流れは、天皇の復権劇として語り継がれています。
ただし、彼の政治体制である建武の新政は短命に終わり、後の混乱を招く結果となりました。
島流しという挫折を乗り越えた復活劇には感動的な側面がありますが、その後の展開を考えると、成功とは言い切れない側面もあったことは否定できません。
南北朝時代の発端と両者の影響
南北朝時代の始まりは、足利尊氏と後醍醐天皇の政治的対立が極限まで進んだ結果と言えます。
この時代は、日本の歴史の中でも特に複雑で、混乱の多い時期とされています。
後醍醐天皇は建武の新政によって親政を実現しましたが、武士たちの支持を十分に得ることはできませんでした。
一方、足利尊氏は武士階級の不満を背景に独自の政権を構想し始めます。
両者の思想や目的が相反していたことから、共存は難しく、最終的に尊氏は後醍醐天皇を京都から追放し、光明天皇を擁立しました。
これにより、日本は「北朝(京都)」と「南朝(吉野)」に分裂し、約60年間にわたる南北朝の時代が始まります。
後醍醐天皇は吉野に移り、自らの正統性を主張し続けました。
尊氏もまた、自らの政権の正当性を保つために天皇を立て、室町幕府の基礎を築いていきます。
この時期、多くの武士たちはどちらの朝廷に味方するかで立場を決めざるを得ませんでした。
そのため、全国的な内乱状態が続き、国土の荒廃や民衆の苦難を招いたのです。
南北朝時代の発端には、両者の個人的な野心や信念だけでなく、当時の社会構造や武士層の不満も大きく関係していました。
その後の歴史にも長く影響を与える重大な転換点であったことは間違いありません。
吉野へ逃れた後醍醐天皇の思惑
後醍醐天皇が吉野へ逃れたのは、足利尊氏によって京都を追われたことが直接のきっかけです。
しかし、単なる逃避行ではなく、そこには政治的な狙いがしっかりと存在していました。
まず、吉野という地は山間部にあり、防御に適した地形です。
後醍醐天皇にとっては、再起を図るための拠点としては理想的でした。
同時に、吉野は天皇家とゆかりのある土地でもあり、精神的な象徴としての意味合いも込められていたと考えられます。
後醍醐天皇の狙いは、京都に擁立された光明天皇を「偽の天皇」と位置づけ、自らこそが正統な君主であると主張することでした。
これにより、日本国内において二つの朝廷が併存する「南北朝」の体制が生まれます。
吉野朝廷は、当初から兵力や資金の面で不利でしたが、後醍醐天皇の強い信念と忠実な家臣たちの支えによって存続しました。
彼は京都奪還を目指し続け、各地で戦いを繰り広げましたが、最終的にはその目標は叶いませんでした。
吉野への逃走は一時的な後退ではなく、国家の正統性を巡る重大な政治的選択だったのです。
その意志の強さは、後世に「南朝の正統性論争」として長く議論されることにもつながっていきます。
征夷大将軍となった尊氏の政治的転換
足利尊氏が征夷大将軍に任命されたのは1338年のことです。
これは、鎌倉幕府の滅亡からわずか5年後の出来事であり、当時の政局がいかに激動していたかを物語っています。
尊氏にとって、征夷大将軍の地位は単なる名誉ではなく、武士政権の正当性を確立するための象徴的な役割を持っていました。
特に、天皇親政を目指した後醍醐天皇に対抗するためには、幕府の再建が不可欠だったのです。
征夷大将軍としての就任は、武士たちの支持を固め、朝廷に対抗する政権として室町幕府を成立させる布石となりました。
このとき、尊氏は北朝の光明天皇を擁立し、自らの政権の正当性を確保しようとしています。
一方で、尊氏の政治は一枚岩ではなく、多くの内紛や反発にも直面しました。
弟・直義との対立や、南朝からの攻撃など、政権は安定せず、尊氏はその対応に追われ続けます。
征夷大将軍という地位は、尊氏にとって自らの理想を実現するための出発点であり、また大きな責任を伴うものでした。
この選択が、以後約240年続く室町幕府の始まりを告げたことは、歴史的に大きな意味を持ちます。
両者の思想の違いと政治理念の対立
足利尊氏と後醍醐天皇の対立は、単なる権力争いではなく、根本的な政治思想の違いによるものでした。
両者の掲げたビジョンが真逆であったことが、対立を避けがたいものにしていたのです。
後醍醐天皇は、古代律令国家に近い中央集権的な政治体制を理想としました。
天皇が自ら政治を行い、貴族や朝廷の官僚たちが国家を統治するという体制です。
これは、建武の新政に色濃く表れています。
一方で、足利尊氏は、武士による現実的な政治運営を志向していました。
戦によって功績を挙げた者が報われる、いわば実力主義の政権です。
そのため、朝廷による一方的な恩賞配分や権力集中には強く反発しました。
このような違いは、制度や法令の運用面でも表面化していきます。
後醍醐天皇は公家優遇の姿勢を取り、武士の不満を招きました。
尊氏はそれに対抗する形で、武士にとって現実的で利益を重視した政権を作ろうとしました。
つまり、両者の対立は、古代的な理想と中世的な現実主義の衝突でもあったのです。
この構造の理解が、なぜ南北朝時代があれほど長引いたかを知る鍵となります。
人物像と性格の違いが招いた歴史の分岐点
足利尊氏と後醍醐天皇は、その性格や人柄にも大きな違いがあったことで知られています。
この個性の違いが、両者の行動や判断に影響を与え、最終的には日本の歴史を大きく動かす分岐点となりました。
後醍醐天皇は、非常に強い意志と理想主義にあふれた人物です。
自らが天皇であることに強い自負を持ち、権力を他者に委ねることを嫌いました。
そのため、武士たちとの妥協を良しとせず、自身の信念を貫こうとする姿勢が際立っていました。
一方で、足利尊氏は慎重で柔軟な人物だったと伝えられています。
一度は幕府に従い、次は朝廷に味方し、そして再び独自の道を歩むなど、その行動は一貫性に欠けるとも言われます。
ただし、それは現実に応じて最善策を選ぼうとする柔軟さの表れでもありました。
両者の違いは、国家運営にも表れました。
後醍醐天皇は理想を追い求めるあまり、現実とのギャップに悩まされました。
尊氏は周囲との協調を優先した結果、内部対立に苦しむことになります。
このように、性格の違いは単なる個性の違いにとどまらず、時代の方向性を大きく左右する要因となったのです。
足利尊氏と後醍醐天皇の関係を総括
足利尊氏と後醍醐天皇の関係は、日本史における大きな転換点の一つでした。
二人の行動や考え方は、時代の潮流を大きく動かし、やがて南北朝時代という激動の時代を生み出します。
ここでは、「データA」の内容をもとに、両者の関係を時系列とテーマごとに整理し、流れをつかみやすいようにまとめました。
- 鎌倉幕府の末期、後醍醐天皇は天皇親政を目指して反幕府活動を始めました。
- その中心的な反乱が「元弘の乱」で、最終的に失敗し、天皇は隠岐島に配流されます。
- 一方で、足利尊氏は当初幕府の側にいましたが、後に後醍醐天皇に呼応して反旗を翻します。
- 尊氏は六波羅探題を攻め落とし、鎌倉幕府の崩壊に大きく貢献しました。
- 後醍醐天皇は復帰後、「建武の新政」を開始し、理想的な天皇親政を進めようとします。
- しかしその政治は武士階層の実情と乖離し、恩賞配分などで大きな不満が生まれました。
- 足利尊氏も恩賞に対する不満を抱え、次第に朝廷との距離を取り始めます。
- 1335年の中先代の乱を機に、尊氏は独自の行動を強め、朝廷からの離反が鮮明になります。
- 1336年、湊川の戦いで尊氏軍が勝利し、後醍醐天皇側の主力を撃破しました。
- 尊氏は光明天皇を立てて北朝を開き、自身は室町幕府の初代将軍となります。
- 後醍醐天皇は吉野へ逃れ、南朝を開いて正統性を主張し続けました。
- こうして「南北朝時代」が始まり、全国が二つの朝廷に分裂して争う長い内乱に突入します。
- 尊氏は1339年に崩御した後醍醐天皇のために天竜寺を建立し、表向きには敬意を示します。
- この寺の建立には政治的意図も含まれており、南朝との融和を示す側面がありました。
- 両者の思想や人物像の違い――理想主義と現実主義――が、分裂の根底にあったことも忘れてはなりません。
このように、足利尊氏と後醍醐天皇の関係は、ただの政敵ではなく、理想と現実、信念と妥協のぶつかり合いによって形作られたものです。
歴史を動かした二人の軌跡を知ることで、南北朝の混乱がなぜ起きたのかが見えてきます。
関連記事
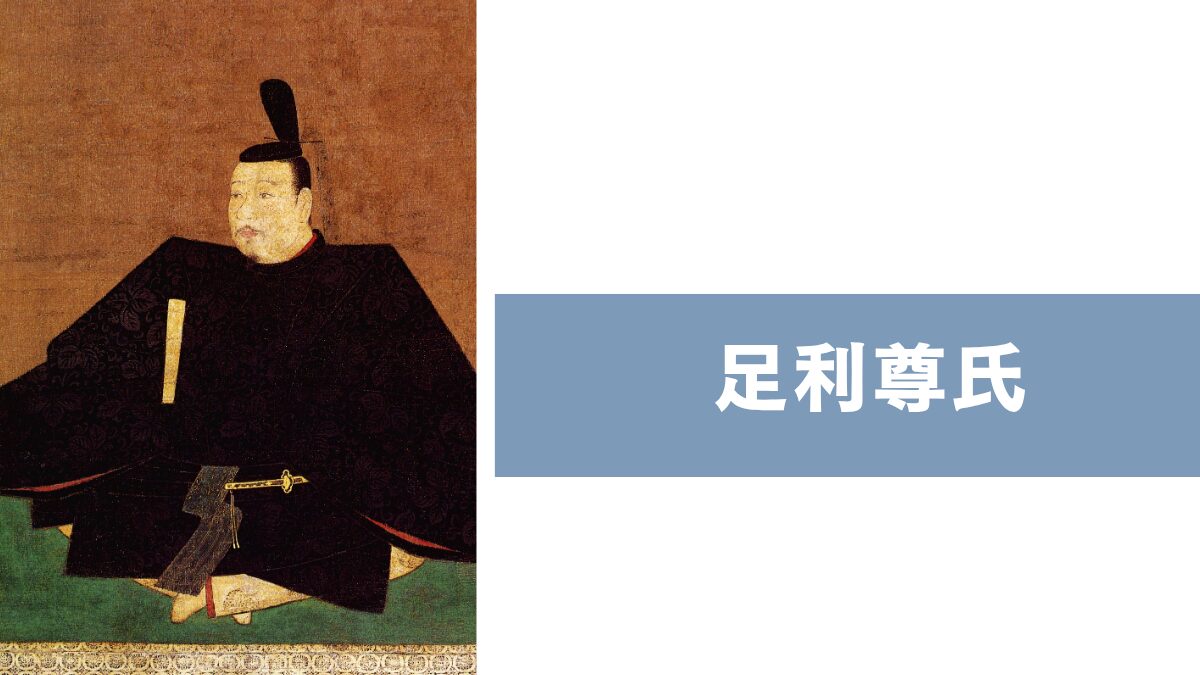
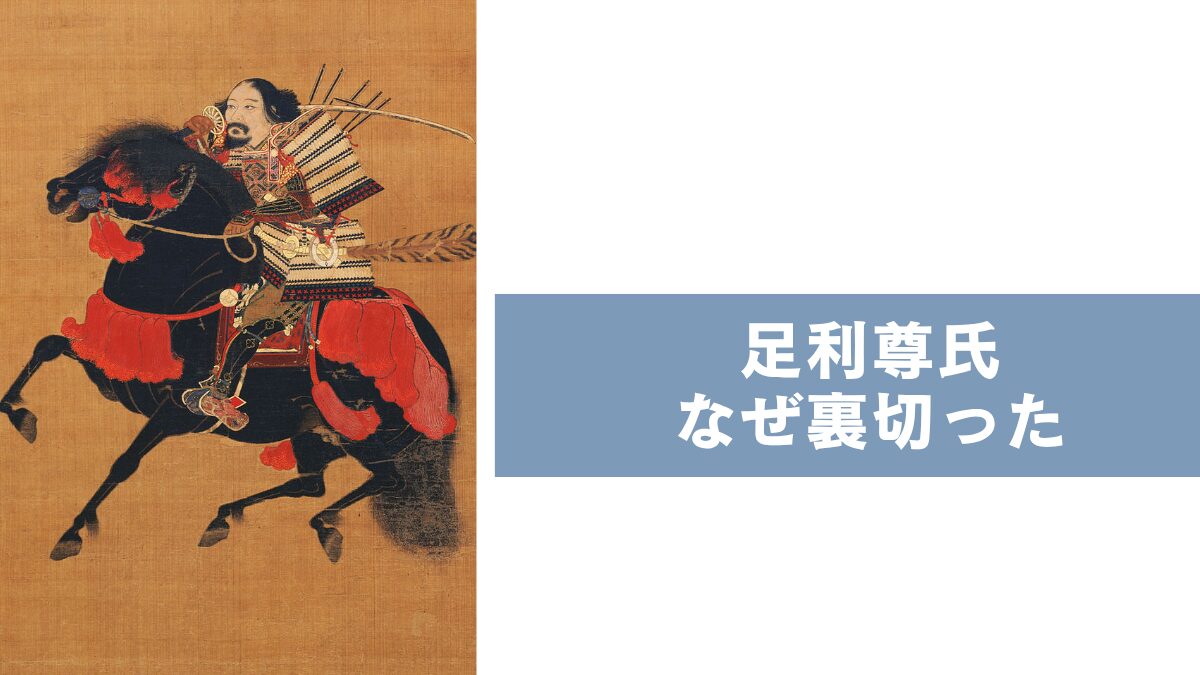
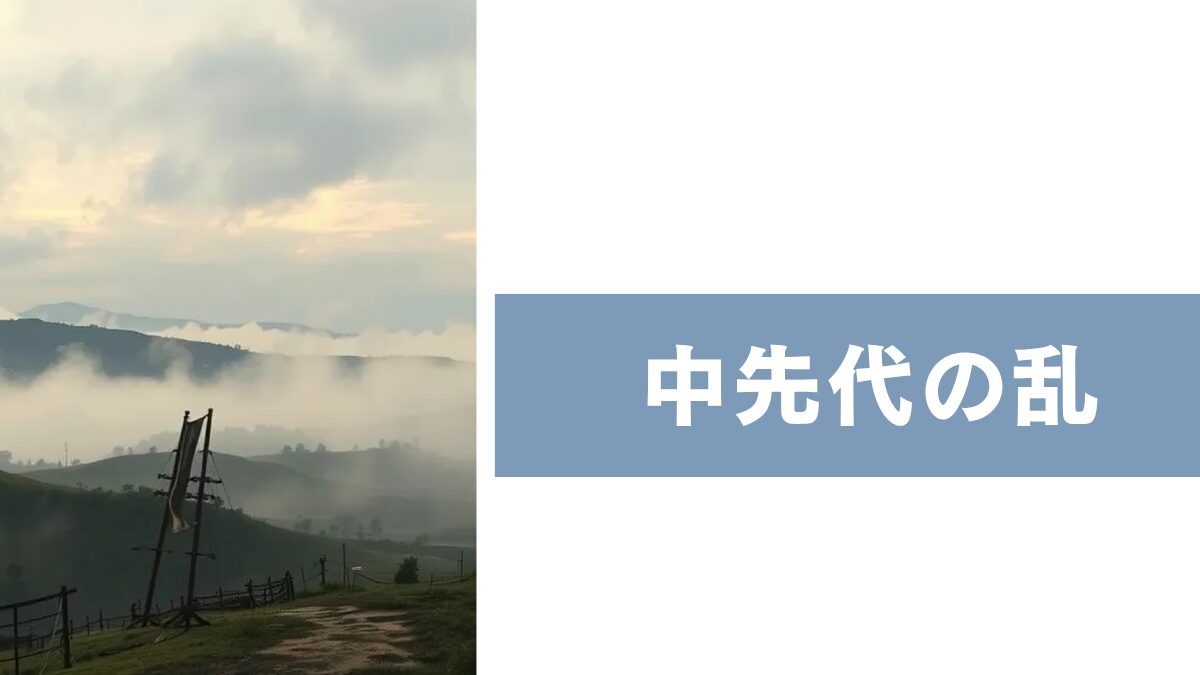
参考サイト
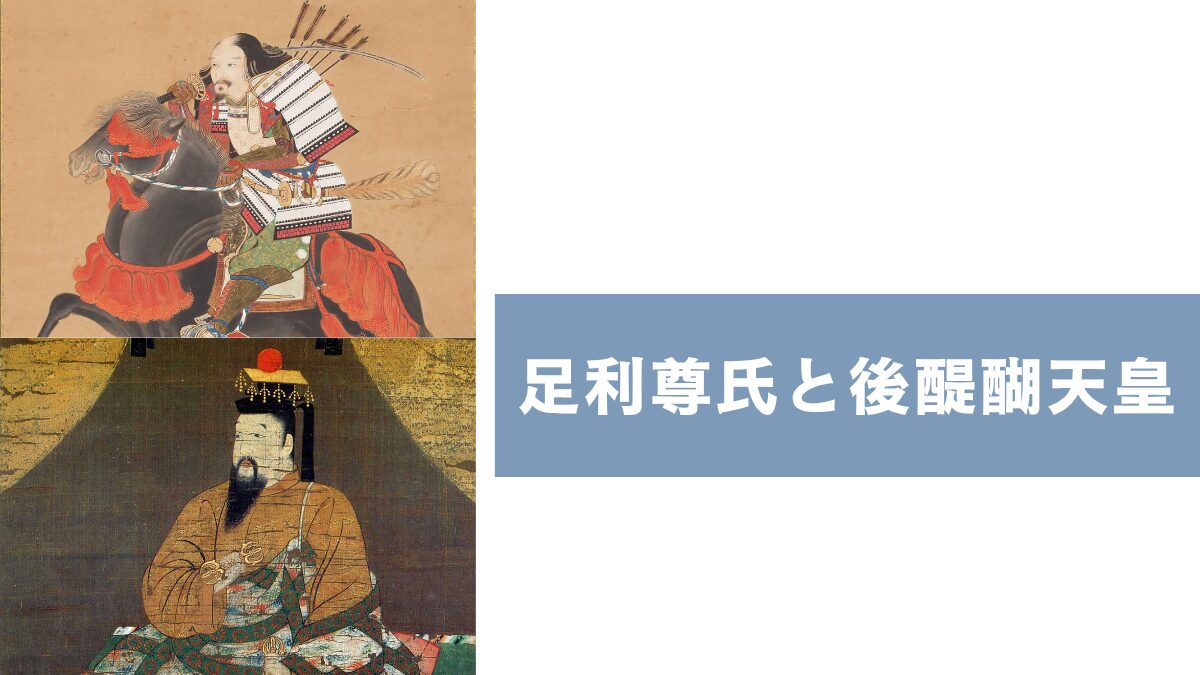

コメント