江戸幕府第10代将軍・徳川家治は、その実績や人物像が分かりにくい将軍のひとりです。
歴史の教科書ではあまり目立たない存在かもしれませんが、実は田沼意次を重用し、幕府の政治や経済に大きな影響を与えた重要な人物でもあります。
一方で、政治よりも趣味に傾倒した姿勢や、権力に固執しない穏やかな性格、さらには「愛妻家」としての一面や「大奥」との関係性など、将軍としては異色のエピソードも多数残されています。
その死因にまつわる不可解な噂も含め、家治という人物には多面的な魅力が詰まっているのです。
この記事では、そんな徳川家治の人物像を簡単にわかりやすくまとめながら、彼が「何をした」のかを深掘りしていきます。
政治的功績はもちろん、田沼意次との関係性や逸話、大奥との関わり、そして最期の様子までを網羅的に解説します。
この記事を読むとわかること
- 徳川家治が将軍として何をしたのかが簡単に理解できる
- 家治と田沼意次の関係と評価のポイント
- 家治の人柄が伝わるエピソードや愛妻家としての一面
- 家治の死因とそれにまつわる真相や噂
徳川家治は何をしたのか簡単に解説
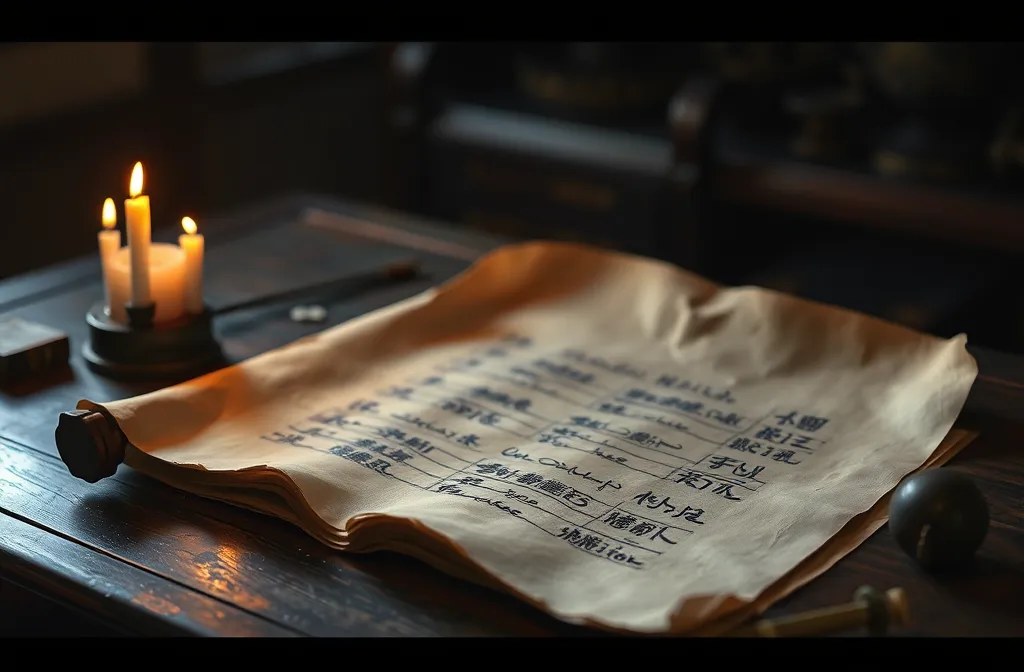
- 徳川家治の治世を年表で振り返る
- 将軍就任と田沼意次の登用理由
- 田沼意次との信頼関係と評価
- 家治が関わった主な政策と功績
- 政治よりも趣味に傾倒した背景
徳川家治の治世を年表で振り返る
徳川家治の将軍在任期間は1760年から1786年までで、約26年間にわたりました。
この期間は、江戸幕府の中でも特に転換期とされる時代であり、商業政策の導入や度重なる天災、さらには政治体制の変化が見られた重要な時期です。
ここでは、徳川家治の治世を主な出来事とともに年表形式で振り返ります。
- 1760年(宝暦10年):父・徳川家重の隠居により、家治が第10代将軍に就任。
- 1767年(明和4年):側用人として田沼意次を登用。ここから田沼の出世が本格化します。
- 1772年(安永元年):江戸で大火災「明和の大火」が発生。田沼意次が老中に昇進。
- 1782年(天明2年):全国的に「天明の大飢饉」が発生し、庶民の生活が逼迫。
- 1783年(天明3年):浅間山が大噴火。農作物への被害が甚大となり、政情不安が加速します。
- 1786年(天明6年):家治が死去(享年50)。これにより田沼意次の立場も急速に悪化します。
このように、家治の治世は大きな災害と政策転換が重なった時代でした。
政治面では田沼意次を中心とした重商主義の導入が目立ちますが、その評価は後年まで分かれています。
ただ、これらの年表を通じて、徳川家治が在位中にどれだけ多くの出来事と直面していたかが分かります。
将軍就任と田沼意次の登用理由
徳川家治が将軍に就任したのは1760年のことです。
このとき、家治はすでに将軍としての素地を祖父・吉宗から徹底的に教え込まれていました。
にもかかわらず、自らが前面に出て政治を主導するより、優れた家臣に政務を任せる姿勢を取ることになります。
その一人が、田沼意次です。
田沼はもともと家治の父・家重の小姓から出世した人物で、家重の遺言として家治に重用されました。
ただし、単なる遺言による登用ではなく、家治自身が田沼の才能を高く評価していたことが複数の記録から明らかです。
田沼はもともと紀州藩(吉宗の出身藩)出身の足軽の子で、実力でここまで登ってきた希少な存在でした。
将軍としての経験が浅い家治にとって、父や祖父に仕えていた人物を側近に置くことは自然な判断だったとも言えます。
また、家治自身が学問や芸術に強い関心を持ち、実務よりも教養を重んじる傾向があったため、政務の実務部分を信頼できる田沼に任せる形になったとも考えられます。
したがって、田沼意次の登用は政治的な便宜だけでなく、家治の人を見る目の鋭さを反映した人事でもあったと言えるでしょう。
田沼意次との信頼関係と評価
徳川家治と田沼意次の関係は、単なる将軍と家臣という関係を超えた強い信頼に支えられていました。
田沼が出世街道を進むなかで、家治の後ろ盾があったことは非常に大きな意味を持ちます。
一例として、田沼意次は1767年に側用人に任じられ、1772年には老中と側用人を兼任するという異例の体制が築かれました。
老中は幕政の中心、側用人は将軍の近習という重要なポジションです。
この2つの役職を同時に任されたのは、当時としても極めて稀であり、家治が田沼に全面的な信頼を置いていた証とも言えます。
さらに、将軍の養子選定という極めて機密性の高い案件も田沼が担当しており、家斉(後の11代将軍)の選出にも深く関与しています。
こうした実績から見ても、家治は田沼の能力をただ評価するだけでなく、幕府の将来を託す存在として考えていたことが分かります。
一方で、田沼の急速な昇進や政策が周囲の反発を招いたのも事実です。
特に、保守的な武士階級からは「身分が低い出自」「賄賂の噂」などで激しく攻撃されました。
そのため、家治の信頼が田沼を支えた一方で、同時に田沼に対する批判が家治に向かう要因にもなったのです。
家治が関わった主な政策と功績
徳川家治は、直接的な政治活動は多くないものの、信頼する田沼意次を通じて多くの政策を実現させています。
とくに、経済政策の面で当時としては革新的な試みが多数行われました。
代表的なのは、商業を重視した「重商主義政策」です。
この政策では、幕府が「株仲間」を公認し、商工業者から公認料(冥加金)や運上金を徴収しました。
これにより幕府は安定した財政収入を得ることができたほか、商工業者の実態把握が可能となり、政策の実行にも役立てられました。
また、「南鐐二朱銀」という貨幣を導入し、東西で異なっていた金銀流通の不便さを改善しました。
加えて、蝦夷地の調査・開発計画も進められ、のちの北海道開拓の先駆けとされています。
さらに、大奥の経費を3割削減するなど、質素倹約の実践も功績の一つです。
将軍としての生活を節制しつつ、財政への影響にも配慮した判断でした。
ただし、これらの政策はすべてが成功したわけではなく、実施タイミングが天災と重なったことで、一部は期待された効果を発揮できなかった側面もあります。
しかし、将来を見据えた長期的な政策を許容し、実行させた家治の姿勢は、決して無為ではなかったと言えるでしょう。
政治よりも趣味に傾倒した背景
徳川家治は将軍でありながら、政治よりも趣味に重きを置いていたことで知られています。
その理由には、個人的な性格や時代背景の両方が関係していたと考えられます。
まず、家治は幼少期から文武に秀で、特に教養・芸術分野に強い関心を持っていました。
将棋、囲碁、絵画、詩文などに熱中し、とりわけ将棋では「御撰象棊攷格(ごせんしょうぎこうかく)」という詰将棋集を自ら制作するほどの情熱を注いでいます。
また、将軍の政治参加が徐々に形骸化していたという制度的背景も見逃せません。
幕府の官僚体制が成熟するにつれて、将軍は象徴的存在としての役割が強くなり、実務は老中や側用人に委ねる傾向が進んでいました。
そのため、家治が積極的に政務に関わらなかったこと自体、当時の一般的な傾向とも一致していたのです。
もちろん、政治に無関心だったわけではありません。
信頼できる人材に仕事を任せ、自身は文化・教養面に力を入れたという解釈も可能です。
とはいえ、趣味に傾倒しすぎた結果、庶民の苦しみに対する対応が遅れた面があることも否定できません。
この点は、将軍としての評価を分ける一因にもなっています。
徳川家治は何をした人物なのか考察

- 人柄が伝わる徳川家治の逸話とエピソード
- 愛妻家として知られる家治の家庭事情
- 大奥との関係と生活ぶりについて
- 徳川家治の死因とその真相
- 徳川家治の評価は暗君か名君か
- 家治の治世が後世に与えた影響とは
- 同時代の田沼意次・松平定信との比較
人柄が伝わる徳川家治の逸話とエピソード
徳川家治の人柄は、いくつかの逸話から非常に穏やかで思慮深く、そして他人に対して気遣いを欠かさない人物だったことがうかがえます。
その一方で、将軍という立場にあっても驕らず、周囲への配慮を常に忘れなかった姿勢が、多くの記録に残されています。
たとえば、将軍としては異例とも言えるほど、朝早く起きてしまったときには、周囲を起こさないように音を立てずに静かに過ごしていたという話があります。
厠(かわや)に行く際にも、当番の者を起こさぬよう、そっと廊下を歩いたとされます。
これは、将軍という権威ある立場にいる人間が、下の者にまで気を配っていたことを示す印象的なエピソードです。
また、ある日、近習が大雨の日に溜息をついていたのを見かけた家治が、その理由を問いただしたところ、実家の屋根から雨漏りしているのを心配していることが分かります。
その話を聞いた家治は、近習に「孝を尽くせ」と言い、修理代として100両を渡したと伝えられています。
当時、100両という金額は非常に大きなものであり、この行為は家治の優しさと判断力を物語っています。
このような逸話から、徳川家治は権力者でありながらも庶民的な感覚を持ち、人としての器の大きさを感じさせる将軍だったことが伝わってきます。
愛妻家として知られる家治の家庭事情
徳川家治は、江戸幕府の将軍の中では珍しく「愛妻家」として知られている人物です。
その家庭事情は、単なる家族の話にとどまらず、家治の人間性や価値観を理解するうえでも非常に興味深いものがあります。
家治の正室は、五十宮倫子(いそのみやともこ)という高貴な出自の女性でした。
彼女との間には2人の娘が生まれましたが、いずれも幼くして亡くなっています。
当時の慣例では、男子がいない将軍は側室を持ち、跡継ぎをもうけることが当然とされていました。
しかし家治は、側室を迎えることに強く抵抗していたといいます。
家臣たちが側室を勧めてもなかなか首を縦に振らず、最終的には田沼意次に「あなたが側室を持つなら」と条件を付けてようやく了承したという逸話も残っています。
実際、側室を迎えたのちは男子(家基)が誕生しますが、家治はその後ほとんど側室のもとへ通うことはありませんでした。
さらに、家基の養育は正室・倫子に任せています。
これは、実子であっても側室の子という壁を取り払い、家族として倫子を信頼していた証と見られます。
このように、形式に流されることなく、妻との絆を大切にしようとした家治の姿は、現代の感覚から見ても誠実で深い愛情を感じさせるものです。
大奥との関係と生活ぶりについて
大奥とは、江戸城内にある将軍の正室や側室、およびその女中たちが暮らす区域のことを指します。
幕府の財政にも大きな影響を与える存在であり、将軍の性格や関心によってその在り方は大きく変わります。
徳川家治の場合、大奥との関係は極めて控えめで、質素倹約の精神が強く反映されたものでした。
徳川吉宗を祖父に持つ家治は、吉宗の質素倹約方針を深く尊重しており、それをさらに徹底したとも言われています。
吉宗の時代にすでに大奥の経費は削減されていましたが、家治はそれをさらに3割も減らしたと記録にあります。
これは一時的な経費削減ではなく、生活全体の見直しによる本格的な改革でした。
ただし、削減と言っても「ケチ」とは異なります。
必要な支出にはきちんと応じていたことが、多くの逸話からもうかがえます。
家臣や近習に対しても、必要なときには気前よく援助を行っていたことから、単なる財政的圧縮ではなく、無駄を排除するための合理的判断だったと考えられます。
大奥の規模や華美な暮らしぶりが権力の象徴であった時代に、これだけの倹約を実行できたのは、家治の信念と実行力があってこそです。
徳川家治の死因とその真相
徳川家治は1786年、50歳という比較的若さで亡くなりました。
その死因については「脚気衝心」、つまり脚気が進行した結果、心臓にまで影響が及んだとされています。
脚気は、当時の上流階級に多かった白米中心の食生活によるビタミンB1欠乏が原因です。
一方で、家治の死に関しては不可解な点も多く、死後すぐには発表されず、一定期間隠されたという記録もあります。
これにより、家治の死には政治的な陰謀が関与していたのではないかという憶測も生まれました。
とくに疑われたのが、田沼意次の関与です。
家治の病が悪化した直後、田沼が推薦した町医者が登城し、その後に急変したことから、「毒を盛られたのでは」という噂が一部で流れました。
しかし、田沼が家治の死によって政治的に不利な立場に追い込まれたことを考えると、あえてそのような行動に出る必然性は薄く、信憑性には疑問が残ります。
これらの情報を総合すると、家治の死因は病死であった可能性が高いと考えられますが、当時の政治情勢の中で、その死が不自然に扱われたことは事実です。
それが家治の死をめぐる憶測を助長する結果となったのでしょう。
徳川家治の評価は暗君か名君か
徳川家治についての評価は、歴史的に分かれています。
一部では「田沼意次を重用し、政治を任せきりにした暗君」と見られますが、別の見方をすれば「有能な人材を見抜き、適切に権限を委ねた名君」とも捉えられます。
家治自身は文武両道に優れ、特に教養面では将軍の中でも屈指の才能を持っていた人物でした。
しかし、政治の表舞台にはあまり登場せず、実務は田沼意次に任せる形となります。
この点が「無責任」とも、「適材適所を実行した」とも受け取られているのです。
田沼意次の政策には功罪がありましたが、重商主義を基礎にした近代的な経済政策を先取りしていた点は、現代の研究でも高く評価されています。
つまり、田沼を信じて任せた家治の判断も、必ずしも間違いだったとは言い切れません。
また、家治は質素倹約や大奥改革、家臣への思いやりなど、人格面での評価が非常に高い将軍でもあります。
政治家としての主導権を握らなかった点は評価の分かれるところですが、それが即ち「暗君」と結びつくかどうかは、見方によって変わる問題です。
家治の治世が後世に与えた影響とは
徳川家治の時代は、江戸幕府の方向性に大きな転換をもたらした時期でもありました。
直接的な施策よりも、彼が容認・支援した政策や人物が、後の日本社会に影響を残すことになります。
代表的な例が田沼意次による「重商主義政策」です。
それまでの「重農主義」によって成り立っていた幕府財政を、商業・流通を基盤とした経済に切り替えようとするこの動きは、のちの近代経済政策の前触れとも言えます。
また、蝦夷地の開拓や長崎貿易の活性化など、外交・領土政策の面でも新たな試みが進められました。
これらの多くは当時実現に至らなかったものの、後の幕政や明治政府に引き継がれていきます。
さらに、家治の死後に実権を握った松平定信が、田沼政治を真っ向から否定し、再び農本主義に回帰したことからも、家治の時代がいかに異色で挑戦的であったかがわかります。
つまり、家治の治世は改革と保守の分岐点であり、その方向性が後の幕府政策や近代国家形成の素地に少なからず影響を与えたと考えられます。
同時代の田沼意次・松平定信との比較
徳川家治と関わりの深い人物として、田沼意次と松平定信がいます。
この2人の違いを比較することで、家治の政治判断や幕政の方向性がより明確になります。
田沼意次は、商業活動を推進し、株仲間の公認や専売制、貨幣政策などを通じて幕府財政の安定化を図りました。
一方で、商人との癒着や賄賂の噂が絶えず、特に天災による不況がその批判に拍車をかけました。
それに対して、松平定信は家治の死後に実権を握り、「寛政の改革」を実施。
倹約・農業重視の政策で田沼政治を全面否定し、再び保守的な幕政へと舵を切ります。
しかし、その成果は限定的で、民衆の支持を得るには至りませんでした。
この比較から分かるのは、家治が田沼のような革新的な人物を選び、あえて変化を許容したという点です。
結果的に批判も招きましたが、保守と改革の間で揺れる幕府において、どちらの方向が正しかったのかは今でも議論が続いています。
家治はこの二人の間に立つようにして、自身は大きく動かず、しかし時代の可能性を広げる判断を下した存在だったとも言えるでしょう。
徳川家治は何をした人物だったのかを総括
ここでは、徳川家治が将軍としてどのような行動を取り、何を実現したのかを簡潔に振り返ってみましょう。
複雑に思われがちな江戸幕府の政治ですが、家治の人物像や政策を知ると、当時の社会が少し見えてきます。
- 1760年に第10代将軍として就任し、26年間にわたって江戸幕府を統治しました
- 幼少期から祖父・徳川吉宗の薫陶を受け、文武に優れた将軍でした
- 父・徳川家重の遺言もあって、田沼意次を重用したことが大きな特徴です
- 田沼意次を側用人から老中にまで引き上げ、異例の権限を与えました
- 重商主義に基づいた経済政策を支持し、商業を活性化させようとしました
- 株仲間の公認によって、商人の統制と財政収入の確保を進めました
- 「南鐐二朱銀」の導入で、金銀両替の不便さを改善しました
- 蝦夷地の調査を命じ、後の北海道開発への足がかりを築きました
- 質素倹約を実行し、大奥の経費を3割削減するなど無駄を排除しました
- 政治の表舞台にはあまり立たず、田沼に政務を任せていたのも特徴です
- 一方で、教養や趣味に優れ、将棋や絵画に並々ならぬ熱意を注ぎました
- 将軍でありながら謙虚な振る舞いが多く、部下や周囲への配慮も忘れませんでした
- 愛妻家としても知られ、正室との絆を大切にし、側室にはあまり通いませんでした
- 晩年には病に倒れ、脚気衝心と見られる症状で50歳で死去しました
- 家治の治世は、のちの田沼時代・寛政の改革への大きな分岐点となりました
このように徳川家治は、決して派手な将軍ではありませんが、時代を静かに動かす判断を重ねた人物でした。
田沼意次という異才を信じて支えた姿勢は、現代から見ると先見の明とも言えるでしょう。
関連記事

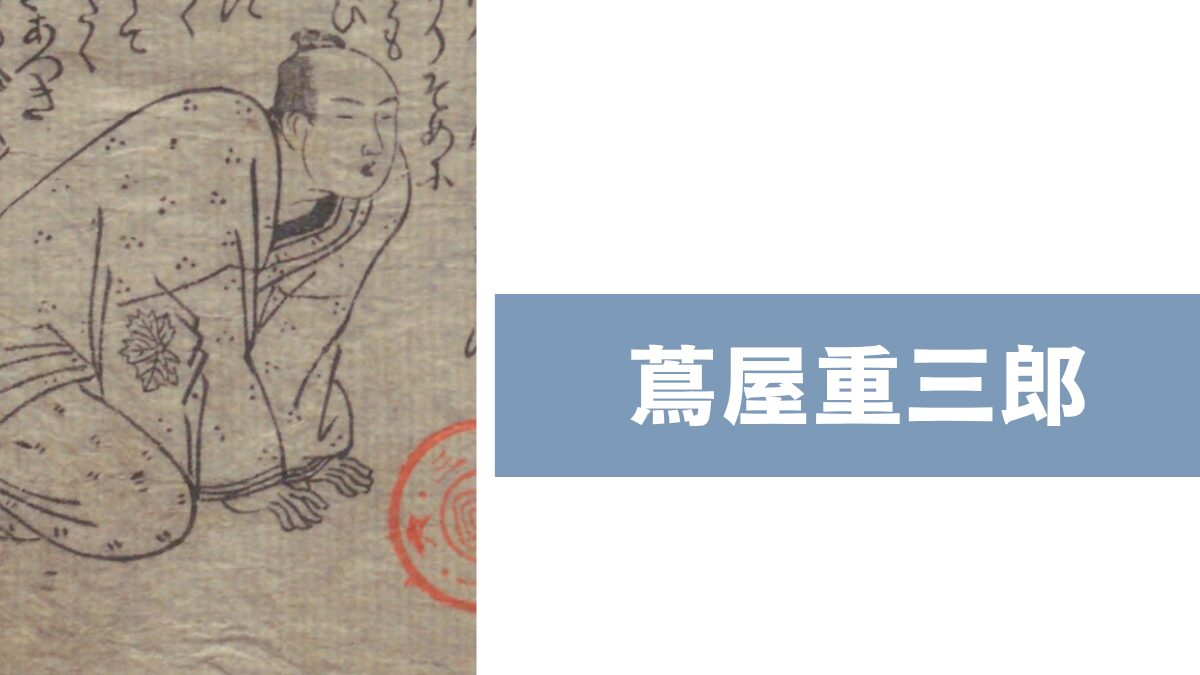

参考サイト
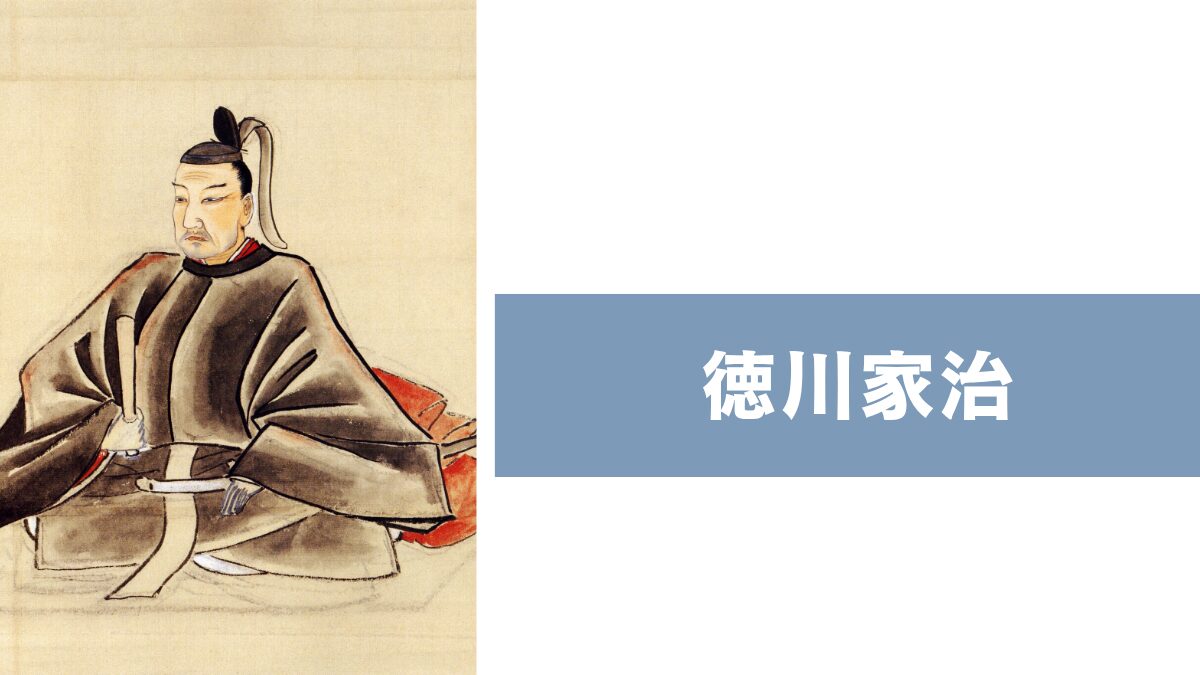

コメント